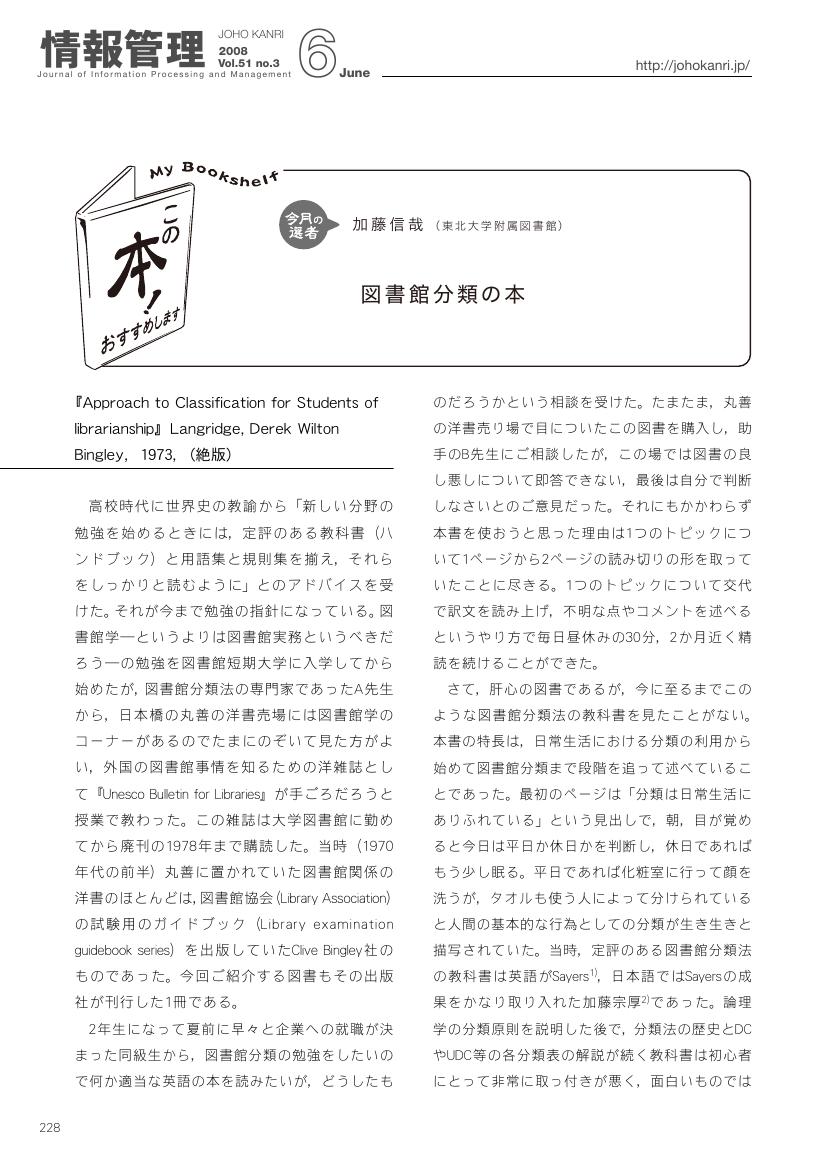- 著者
- Takayuki Arai
- 出版者
- ACOUSTICAL SOCIETY OF JAPAN
- 雑誌
- Acoustical Science and Technology (ISSN:13463969)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.2, pp.188-190, 2008-03-01 (Released:2008-03-01)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 3 3
- 著者
- Satoru Fujita Jianwu Dang Noriko Suzuki Kiyoshi Honda
- 出版者
- Japanese Stomatological Society
- 雑誌
- Oral Science International (ISSN:13488643)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.2, pp.97-109, 2007 (Released:2007-12-21)
- 参考文献数
- 21
The tongue possesses a complex muscular structure, and its motor functions are also intricate. Therefore, it would be beneficial to use a computational physiological model of the tongue to examine its vital functions in normal and pathological conditions. Thus far, the studies of tongue models have focused on symmetric movements for normal speech. For clinical purposes, it is necessary to develop a physiological model to deal with daily vital activities such as mastication and swallowing. To do so, we constructed a full 3D physiological model of the tongue based on MRI data from a normal subject, and verified the basic functions of the model based on anatomic and physiological knowledge. In this study, the model was applied to clinical issues: prediction and verification of the changes in movements of the tongue with a tumor before and after partial glossectomy, respectively. Tongue protrusion and lateral bending motion were examined for the prediction and verification. The simulation results were consistent with the observations for a patient with a tumor in the tongue. Comparisons of the simulation and observation in the clinical case showed that the model could predict potential effects of the glossectomy on the tongue movements. It is suggested that the model is a useful tool for pre-operative planning of glossectomy.
1 0 0 0 OA 電子顕微鏡による断面・界面観察の新たな世界
- 著者
- 清水 健一 立花 繁明 三谷 智明 幅崎 浩樹
- 出版者
- 一般社団法人 表面技術協会
- 雑誌
- 表面技術 (ISSN:09151869)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.9, pp.622, 2006 (Released:2007-03-23)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 5 3
- 著者
- Kenta Saito Kentaro Kobayashi Tomomi Tani Takeharu Nagai
- 出版者
- Japan Society for Cell Biology
- 雑誌
- Cell Structure and Function (ISSN:03867196)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1, pp.133-141, 2008 (Released:2008-09-05)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 4 4
Multi-point scanning confocal microscopy using a Nipkow disk enables the acquisition of fluorescent images with high spatial and temporal resolutions. Like other single-point scanning confocal systems that use Galvano meter mirrors, a commercially available Nipkow spinning disk confocal unit, Yokogawa CSU10, requires lasers as the excitation light source. The choice of fluorescent dyes is strongly restricted, however, because only a limited number of laser lines can be introduced into a single confocal system. To overcome this problem, we developed an illumination system in which light from a mercury arc lamp is scrambled to make homogeneous light by passing it through a multi-mode optical fiber. This illumination system provides incoherent light with continuous wavelengths, enabling the observation of a wide range of fluorophores. Using this optical system, we demonstrate both the high-speed imaging (up to 100 Hz) of intracellular Ca2+ propagation, and the multi-color imaging of Ca2+ and PKC-γ dynamics in living cells.
1 0 0 0 OA 図書館分類の本
- 著者
- 加藤 信哉
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.3, pp.228-229, 2008 (Released:2008-06-01)
- 参考文献数
- 6
1 0 0 0 OA 産学連携における大学内記録情報管理の実践
- 著者
- 古川 勝彦 阿世知 昌弘 八木 信幸 小林 幸治
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.6, pp.398-407, 2008 (Released:2008-09-01)
- 参考文献数
- 4
研究開発に関わる情報は企業にとって経営の根幹ともなる機密情報である。大学にとって,産学連携は重要な取り組みであるが,これまで大学ではこうした研究情報の管理体制が脆弱(ぜいじゃく)であり,それが産学連携の推進を妨げる要因ともなっていた。本論文では,記録情報管理システムを取り入れることによって研究情報の管理体制を強化した九州大学知的財産本部の産学連携に関する情報管理の現況を報告した。目録管理と所在管理が適切に行われるような仕組みを作ることが重要であり,文書種類別に機密度を設定するなど,実践しやすさを心がけている。その実践の上で,産学連携をさらに発展させるために必要となる要件を整理し,今後情報管理に求められる課題について展望した。
1 0 0 0 OA 脳内埋め込み電極と体内埋設型刺激デバイスを用いた不随意運動の治療
- 著者
- 片山 容一 深谷 親
- 出版者
- 一般社団法人 日本めまい平衡医学会
- 雑誌
- Equilibrium Research (ISSN:03855716)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.1, pp.65-71, 2008 (Released:2008-05-02)
- 参考文献数
- 20
In an attempt to control hypokinetic and hyperkinetic movement disorders, deep brain stimulation (DBS) has been developed during the last two decades by several investigators. In 1987, Benabid and his colleagues suggested the usefulness of high-frequency stimulation of the ventral intermediate nucleus of the thalamus for treating drug-resistant tremors and avoiding the adverse effects of thalamotomy. Since then, DBS has been used as an alternative to functional neurosurgery for movement disorders, and more recently, it has been applied to the treatment of epilepsy, obsessive-compulsive disorders and cluster headache, in addition to other applications in experimental models. In regard to the treatment of movement disorders, recent clinical studies have demonstrated that DBS affords great benefits in terms of improvement of the activities of daily living in patients with Parkinson's disease (PD), essential tremor, dystonia and poststroke hyperkinetic movement disorders. We have treated patients with movement disorders by DBS of the thalamic nuclei ventralis oralis (Voa/Vop) et intermedius (Vim), globus pallidus internus (GPi), and subthalamic nucleus (STN). The site of permanent electrode placement was identified using magnetic resonance imaging and multiunit extracellular recording. The implantable pulse generator was internalized after postoperative test stimulation for one week. The stimulation parameters were modified by physicians at each follow-up visit on the basis of the findings on neurological examination, as well as the patient's report concerning the activities of daily living. The advantages of DBS include reversibility and controllability of stimulation. In addition, DBS carries a smaller risk of side effects, particularly when employed bilaterally. Thalamic DBS is useful for controlling tremor that is unresponsive to medication. DBS of the STN and GPi improves the motor functions in PD patients, mainly during the off-period. Moreover, STN-DBS attenuates levodopa-induced dyskinesia through reducing the requirement of DOPA, whereas GPi-DBS directly attenuates DOPA-induced dyskinesia. In addition, GPi-DBS is very useful for controlling the symptoms of idiopatic generalized dystonia. According to reports, DBS is associated with few serious adverse effects associated with DBS. In general, the operative mortality is less than 1%. The incidences of hemorrhage are in the range of about 1-6%, and the incidences of device-related complications, such as infection or skin erosion, are in the range of 3-26%. DBS is clinically effective in well-selected patients and should be considered as a treatment option for patients with medically refractory movement disorders. Despite its clinical usefulness, the mechanism underlying the efficacy of DBS is still unclear. There is no proof currently that long-term DBS can reset neural networks or induce profound modifications of functional organization. Several researchers have proposed hypotheses concerning the mechanism underlying the efficacy of DBS, including 1) jamming of neural transmission, 2) direct inhibition of spike initiation at the level of the membrane that may be due to the activation of inhibitory terminals, 3) functional changes due to a decrease or increase in the amount of neurotransmitter released, and 4) retrograde activation of upstream neural structures. From the viewpoint of basic neuroscience, the development of DBS is intriguing. Investigation regarding the mechanism underlying the efficacy of DBS may provide clues for further clarification of various processes in the central nervous system.
1 0 0 0 OA 学術情報流通における出版社のユーザー・コミュニケーション展望 エルゼビア社副会長に聞く
- 著者
- CHI Youngsuk インタビューと翻訳:熊谷玲美
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.6, pp.379-388, 2008 (Released:2008-09-01)
- 著者
- 松浦 智佳子 小河 邦雄
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.6, pp.408-417, 2008 (Released:2008-09-01)
- 参考文献数
- 5
Web of Scienceは,引用文献の検索や分析ができるデータベースとして有名であるが,2004年にその競合製品であるScopusが発表された。それぞれ特徴を持った機能を有しているが,実際にどのような違いがあるのかを評価した情報は少ない。今回,2社で共同評価を行い,両データベースの基本的な機能の比較,検索システムの特性などについて考察した。前編では,ライフサイエンス系のキーワードで実際に検索を行い,その結果を分析する。
- 著者
- 森田 歌子
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.6, pp.418-419, 2008 (Released:2008-09-01)
1 0 0 0 OA パーソナリティ特性およびネガティブ・ライフイベンツが思春期の抑うつに及ぼす影響
- 著者
- 田中 麻未
- 出版者
- 日本パーソナリティ心理学会
- 雑誌
- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.2, pp.149-160, 2006 (Released:2006-03-31)
- 参考文献数
- 36
- 被引用文献数
- 5 3 6
本研究は,個人内要因である身体的発達および,パーソナリティ特性と心理社会的要因であるネガティブ・ライフイベンツが,思春期の抑うつに及ぼす影響について検討した.中学生518名を対象にして身体的発達,パーソナリティ特性,そしてネガティブ・ライフイベンツからなる質問紙に回答してもらった.階層的重回帰分析の結果,Cloningerのパーソナリティ理論の気質因子である損害回避と友人問題に関するネガティブ・ライフイベンツの嫌悪感が,抑うつを高めることが明らかとなった.さらに,損害回避とネガティブ・ライフイベンツの嫌悪感との間に交互作用が見られた.この結果から,ネガティブ・ライフイベンツの嫌悪感が増加すると,損害回避の高い中学生は,損害回避の低い中学生よりも抑うつが高まることが示唆された.また,女子では,身体的発達と抑うつとの間に正の相関関係が示された.
1 0 0 0 OA 複雑な相互作用ネットワークを導入した人工市場シミュレーション
- 著者
- 内田 誠 白山 晋
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会論文誌 (ISSN:13460714)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.6, pp.485-493, 2008 (Released:2008-08-26)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 1
We investigate a factor of the `network effect' that affects on communication service markets by a multi-agent based simulation approach. The network effect is one of a market characteristic, whereby the benefit of a service or a product increase with use. So far, the network effect has been studied in terms of macroscopic metrics, and interaction patterns of consumers in the market were often ignored. To investigate an infulence of structures of the interaction patterns, we propose a multi-agent based model for a communication serivce market, in which embedded complex network structures are considered as an interaction pattern of agents. Using several complex network models as the interaction patterns, we study the dynamics of a market in which two providers are competing. By a series of simulations, we show that the structural properties of the complex networks, such as the clustering coefficient and degree correlations, are the major factors of the network effect. We also discuss an adequate model of the interaction pattern for reproducing the market dynamics in the real world by performing simulations exploiting with a real data of social network.
1 0 0 0 OA GPS携帯電話を用いたマルチベンダ対応チャットと共有スケジューラの実装
- 著者
- 携帯電話アプリケーション 作成プロジェクト 新美 礼彦 高木 剛 小西 修 宮本 衛市 高橋 修
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第20回全国大会(2006)
- 巻号頁・発行日
- pp.111, 2006 (Released:2006-12-07)
GPS携帯電話を用いたマルチベンダ対応アプリケーションを開発した。GPS機能を用いて、グループメンバの現在位置を地図上に表示し、チャットによりコミュニケーションがとれるシステムを実装した。また、グループメンバで共有できるオンラインスケジューラを実装した。今後、両機能を実装したアプリケーションを開発する予定である。
1 0 0 0 OA ダイカストの歩み
- 著者
- 西 直美
- 出版者
- 一般社団法人 軽金属学会
- 雑誌
- 軽金属 (ISSN:04515994)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.4, pp.163-170, 2007 (Released:2007-07-30)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 4 2
1 0 0 0 OA リスクアセスメントの現状と展望
- 著者
- 長尾 美奈子 日本環境変異原学会臨時委員会
- 出版者
- 日本環境変異原学会
- 雑誌
- 環境変異原研究 (ISSN:09100865)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.193-198, 2004 (Released:2005-12-21)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 2 2
Kojic acid (KA) , belonging to existing food additives for which compositions or usages are not clarified, had been used for prevention of enzymatic browning. In 1995, the food sanitation law was largely revised to harmonize with JECFA, OECD and FDA. Under the new law, reevaluation of existing food additives was required. In 1998, it was found that KA induced tumors in the thyroid and liver of mice. KA also showed genotoxicities; gene mutations in S. typhimurium, chromosome aberrations in CHO-K1 and CHL/IU cells in vitro, and micronuclei in the liver of mice and hematopoietic cells in rats. Although it has not been clarified whether liver or thyroid tumors were induced by genotoxic effects of KA or not, use of KA as a food additive was banned in 2003, based on the fact that KA was not used in any country at that time. The ad hoc committee which was set-up for a three-year task from 2003-2005 considered that KA was an appropriate model compound to re-evaluate the strategies presently used to detect genotoxicity in vitro and in vivo, and to re-evaluate the regulatory rules (use of genotoxic carcinogens as food additives should be totally avoided; genotoxic non-carcinogens in rodents can be used as food additives). First of all, we confirmed the genotoxicity of KA; we demonstrated that genotoxicity in S. typhimurium was due to KA itself, but not due to contaminants, KA induced TK mutations, micronuclei and DNA damage (Comet) in human lymphoblastoid cells, TK6 and WTK-1. These results support the finding that KA is genotoxic in vivo, although it is not clear yet whether KA induces tumors by its genotoxicity or not. Speculating that liver tumors induced by KA were due to its genotoxicity, human risks to KA to which humans are exposed by taking fermented food products was calculated to be 2×10-7 by the linearized multistage model.
1 0 0 0 OA HTSの現状と今後の展望
- 著者
- 植木 智一
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.129, no.4, pp.276-280, 2007 (Released:2007-04-13)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 3
1990年代に欧米の製薬企業で相次いで導入された高速大量スクリーニング(HTS)は,標的分子に親和性を有する化合物の探索の重要な手段として利用されている.その規模は,現在百万化合物を超える化合物ライブラリーを対象にしたスクリーニングに達している.このようなスクリーニング規模に到達した要因として測定技術をはじめとする多くの分野での技術革新が挙げられる.また,HTSの技術利用は,従来の創薬研究の初期段階である「新薬候補化合物の探索」からリード化合物選定に重要な安全動態分野である肝代謝試験,変異原性試験等へ拡大しており,創薬研究の重要な基盤技術となっている.一方,このように応用範囲が拡大するにつれて,予想外な課題や問題点も浮き彫りになってきた.この重要な創薬基盤と位置づけられる高速大量スクリーニングの現状と今後の展望について紹介する.
- 著者
- 森田 歌子
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.4, pp.282-283, 2008 (Released:2008-07-01)
- 被引用文献数
- 1 1 1
1 0 0 0 OA ベクトル空間法とファジィ推論を用いたWEB検索結果自動分類システム
- 著者
- 城市 広大 三好 力
- 出版者
- 日本知能情報ファジィ学会
- 雑誌
- 知能と情報 (ISSN:13477986)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.2, pp.184-195, 2006 (Released:2007-04-20)
- 参考文献数
- 12
インターネット上のWEBページを検索するには検索エンジンを利用するのが一般的であるが, 検索結果の中にユーザーの求める情報を持つページが高い順位で表示されない問題が指摘されている. この理由の一つとして, ユーザーが入力した検索語を含むページを, 検索エンジンが単純に選択していることが挙げられる. 言葉には意味的な多義性や曖昧性があるため, ユーザーがある検索意図を持って検索語を入力しても, 使用した検索語によっては意図と異なる種類のページが混在した状態の検索結果になりやすい.この様な検索結果を改善する方法として, 検索結果に出力されたページ群を内容別に自動分類する手法が研究されており, その一手法としてベクトル空間法を用いるのが一般的である. ベクトル空間法はページ内容の類似性を, 使用単語を次元としたベクトル空間により求める手法であるが, ベクトル空間法をそのままWEBページ分類に適用した場合, 2つの問題点が挙げられる. 1つはページ中に1回でも使用された単語全てを用いるので次元数が大きくなり, 計算コストが大きくなってしまうこと, もう1つはページ間の類似性だけを計算するのでグループの内容を示す言葉を抽出することができず, ページ分類後に各グループの名前もしくは基準をユーザー側に提示できないことである.我々はこの問題点に着目し, 改善を加えることで検索結果のWEBページ群を内容別に自動分類するシステムを提案した. 次元数が大きくなる問題に対しては, ファジィ推論を用いてベクトル空間に使用する単語を一定数だけ選択することで解決を図る. ページ全体での単語の使用傾向をファジィルールに当てはめることで, 重要な単語とそうでない単語との判別が可能であると考えた. もうひとつの問題である, ユーザーに提示するグループの基準については単語の共起頻度を用いることでグループ名を自動作成し, それを基にグループの代表となるページを選択する手法をとった. また, システムについての実験を行い, 選択する単語の総数が200のときが計算コストと分類精度の点から見て最適であること, システムによる分類結果から人間の感覚に近いWEBページの分類が行われることを確認した.
1 0 0 0 OA 英文作成支援ツールとしての用例文検索システムESCORT
- 著者
- 松原 茂樹 加藤 芳秀 江川 誠二
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.4, pp.251-259, 2008 (Released:2008-07-01)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 3
英文作成支援を目的に開発された英文検索システムESCORTについて述べる。ESCORTは,キーワード系列を入力とし,キーワード間に構文的な関係が存在する英文を出力する。単にキーワードを含む文を出力する従来システムと異なり,ユーザの検索意図に合致した用例が検索結果として提示されるため,精度の高い英文検索を遂行できる。また,提示される英文は,キーワード間の関係の種類に応じてグループ化されるため,検索作業を効率的に遂行できる。ESCORTは,英文論文から取り出された文を格納しており,研究者が英語で論文を作成する場面で,参照するにふさわしい用例を提示する。現在,約71万文を対象とする用例検索を実現しており,英文論文作成のためのツールとして活用されている。
1 0 0 0 OA ポリスチレン系粒子
- 著者
- 笠井 澄
- 出版者
- 社団法人 繊維学会
- 雑誌
- 繊維学会誌 (ISSN:00379875)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.7, pp.P_367-P_370, 2004 (Released:2005-12-15)