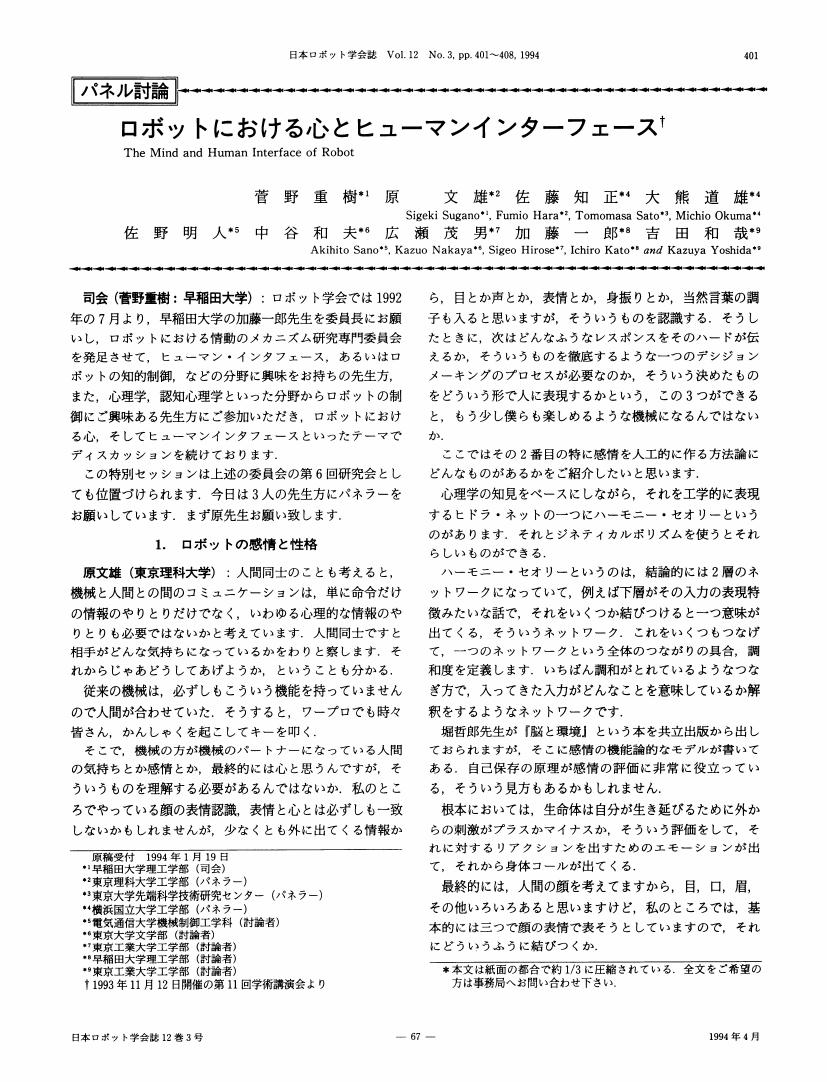- 著者
- 多田隈 建二郎 多田隈 理一郎 木下 宏晃 永谷 圭司 吉田 和哉 Iagnemma Karl
- 出版者
- 一般社団法人日本機械学会
- 雑誌
- ロボティクス・メカトロニクス講演会講演概要集
- 巻号頁・発行日
- vol.2008, pp."2P1-C14(1)"-"2P1-C14(4)", 2008-06-06
In this paper, a novel crawler mechanism for sideways motion is presented. The crawler mechanism is of circular cross-section and has active rolling axes at the center of the circles. Conventional Crawler mechanisms can support massive loads, but cannot produce sideways motion. Additionally, previous crawler edges sink undesirably on soft ground, particularly when the vehicle body is subject to a sideways tilt. The proposed design solves these drawbacks by adopting a circular cross-section crawler. A prototype has been developed to illustrate the concept. Motion experiments confirm the novel properties of this mechanism: sideways motion and robustness against edge-sink. Motion experiments, with a test vehicle are also presented.
- 著者
- 多田隈 建二郎 多田隈 理一郎 永谷 圭司 吉田 和哉 Iagnemma Karl
- 出版者
- 一般社団法人日本機械学会
- 雑誌
- ロボティクス・メカトロニクス講演会講演概要集
- 巻号頁・発行日
- vol.2008, pp."2P1-C15(1)"-"2P1-C15(4)", 2008-06-06
In this paper, the tetrahedral mobile robot as a throwable robot for search and rescue mission is presented. Especially, the tetrahedral mobile robot with the central rotational axis as a expanding mechanism has been developed to illustrate the concept. Motion experiments confirm the novel properties and function of this central axis: Motion experiments, with a test model are also presented.
- 著者
- 大石 千種 多田隈 建二郎 多田隈 理一郎 永谷 圭司 吉田 和哉 明 愛国 下条 誠
- 出版者
- 一般社団法人日本機械学会
- 雑誌
- ロボティクス・メカトロニクス講演会講演概要集
- 巻号頁・発行日
- vol.2009, pp."1A2-G18(1)"-"1A2-G18(4)", 2009-05-25
This paper describes the connected two unit crawlers to realize various configurations. By changing the configuration of two connected vehicle units in relative positions, the robot with this mechanism can automatically adapt to the surface obstacles in the field, including such complicated structures like debris after disasters. In addition we analyzed the effect of the each axis arrangement in order to realized switching function to compose the four basic configurations more easily, and developed an actual prototype model.
- 著者
- 中西 洋喜 加藤 治久 渡辺 敏暢 石上 玄也 西牧 洋一 丸木 武志 吉田 和哉
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. SAT, 衛星通信 (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, no.655, pp.45-51, 2002-02-15
流星は,彗星を起源とする塵が大気圏に突入して発光する現象であり,この塵には生命の起源となった有機物が含まれている可能性が示唆されている.本論文では,しし座流星群をはじめとする様々な流星群を,大気圏外から観測を行い,イメージおよび分光データを取得する小型衛星,LEOLEO(Leonid-Meteor Observer in Low Earth Orbit)-IIを提案する.本衛星には,I.I.CCDカメラ及び分光器が搭載される.これにより地上からでは大気の影響で観測が極めて困難であった,流星の紫外線領域での分光観測が可能となり,これまで得ることができなかった貴重なデータを得ることが期待できる.
1 0 0 0 OA ロボットにおける心とヒューマンインターフェース
- 著者
- 岡田 知之 仲山 英樹 吉田 和哉
- 出版者
- 公益社団法人日本生物工学会
- 雑誌
- 日本生物工学会大会講演要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.20, 2008-07-11
1 0 0 0 月桂冠株式会社総合研究所から : ≪ラボ&オフィス関西≫
- 著者
- 川戸 章嗣 吉田 和哉
- 出版者
- 公益社団法人日本生物工学会
- 雑誌
- 生物工学会誌 : seibutsu-kogaku kaishi (ISSN:09193758)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.9, pp.403-405, 1998-09-25
- 著者
- 永谷 圭司 大木 健 Britton Nathan 佐藤 毅一 野寄 敬博 高橋 悠輔 山内 元貴 秋山 健 吉田 和哉
- 出版者
- 日本惑星科学会
- 雑誌
- 遊・星・人 : 日本惑星科学会誌 (ISSN:0918273X)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.121-129, 2012-06-25
火山噴火時には,その噴火の規模によって定められる危険区域に人が立ち入ることはできない。そのため,噴火予測や住民の避難計画の策定を目指した遠隔操作型の不整地移動探査ロボットによる火山定点観察,移動観察の実現が求められている。ただし,これを実現するためには,不整地環境における高い走行性能,高い位置推定精度,遠隔操作のための長距離通信,長時間活動を支えるための電源といった,様々な技術課題が存在する.これらの課題は,月・惑星における移動探査を行う探査ローバーの技術課題にオーバーラップする部分が少なくない.そこで,本研究では,不整地軟弱土壌における走行性能ならびに,不整地環境におけるロボットの高精度な自己位置推定の実現を目指し,車輪型/クローラ型不整地移動ロボット4台の走行試験を,伊豆大島裏砂漠ならびに,三原山で実施した.本稿では,各走行試験の概要ならびにロボットを紹介すると共に,火山観察ならびに月・惑星探査ロボットに今後必要となる技術課題について考察する.
- 著者
- 中西 洋喜 小笠原 克久 沼田 亜紀子 野口 新 吉田 和哉
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. SANE, 宇宙・航行エレクトロニクス (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.100, no.637, pp.9-15, 2001-02-16
- 被引用文献数
- 1
軌道環境保全という観点から, 故障衛星がスペースデブリとなって漂いつづけるという問題は今後ますます深刻になっていくと考えられ, これらを回収する技術が求められている.ロボットアームを搭載した無人衛星によって、故障した衛星を回収・軌道外投薬することが議論されている。この場合, ターゲットが協力的(姿勢安定, グラプルフィクスチャー装備)であることが要求されるが, 故障衛星にそのようなことを望むことはできない。本論文では, 非協力衛星を協力化させる衛星回収システム"The TAKO-Flyer"を提案する.The TAKO-Flyerはターゲットに多関節グリッパー"TAKO-Gripper"を用いてソフトに抱きつき, その姿勢を安定化させ, ロボット衛星により回収が可能となるような機能を提供する.
宇宙基地と科学実験衛星などの間を往復し、実験機材や機器の搬送、取付け、調整などの作業を行なうためのマニピュレ-タ付き軌道作業衛星の運動は、地上のロボットマニピュレ-タのそれと基本的に異なる点が多く、その制御については未知の部分が多い。本研究はこのロボット衛星の基本モデルとして、一本の多関節マニピュレ-タをもつ衛星が、近くを浮遊する目標物体を捕捉するケ-スをとり上げ、その運動をエアスライドテ-ブルの上でハ-ドウェアモデルによって行なわせ、同時にその時間経過を光学的に追跡して、ソフトウェア的にグラフィックシミュレ-ションによって検証するという手段を採用した。本年度の研究は、一本のマニピュレ-タを持つ軌道作業衛星がその近傍を浮遊する物体を捕捉する作業の制御問題を中心課題にして、以下のような研究成果を得た。すなわち目標の相対速度レベル、大きさ、形状を定義し、それを捕捉する制御問題に拡張した。移動対象物体の捕捉にあたって、以下の三つの制御法をグラフィックシミュレ-ションを理論的に検討し、その有効性を確かめた。(1)最適軌道および保証作業領域を考慮した目標先端速度設定法によるオンライン分解速度制御。(2)直線軌道および保証作業領域を考慮した目標先端速度設定法によるオンライン分解速度制御。(3)直線軌道および等時刻直線到達領域を考慮した目標先端速度設定法によるオフライン分解速度制御。また上記のアルゴリズムに関して、以下の捕捉動作上の特徴を見出した。(1)の制御法に関しては、捕獲の段階で位置偏差をゼロにでき、ソフトな捕獲が可能である。(2)の制御法は捕獲の対象物の位置偏差をゼロにするだけであり、捕獲合体の際の衝撃は大きい。(3)の制御法は、(2)と同様に捕獲の際の速度偏差をゼロにすることは考慮に入れていないので、捕獲の際の衝撃力は大きい。
1 0 0 0 OA 宇宙用ロボット・マニピュレータの運動制御
- 著者
- 吉田和哉 [著]
- 巻号頁・発行日
- 1990
- 著者
- 國森 裕生 竹中 秀樹 布施 哲治 後藤 忠広 久保岡 俊宏 豊嶋 守生 吉田 和哉 桑原 聡文
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. SANE, 宇宙・航行エレクトロニクス (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.112, no.107, pp.99-104, 2012-06-21
東北大が計画している小型衛星「ほどよし21」別名RISESATに光通信ミッションのレーザ送信機器コンポーネントを搭載し、先進的宇宙実証をおこなう計画を述べる。ミッション名VSOTA(Very Small Optical Transmitter for component validation)の目的と仕様、リンク計算、衛星インタフェースと実験とその評価方法の概要を述べる。
1 0 0 0 1A1-B04 月・惑星探査ローバーのすべり制御
- 著者
- 吉田 和哉 濱野 博史 渡辺 敏暢
- 出版者
- 一般社団法人日本機械学会
- 雑誌
- ロボティクス・メカトロニクス講演会講演概要集
- 巻号頁・発行日
- vol.2002, 2002
不整地走行する月・惑星探査ローバーにおいて, 走行中のすべり率を小さく保ち踏破性能の高い制御法を提案する。特に月面環境では地表は細かな砂(レゴリス)で覆われており, 車輪の空転によって穴を掘ってしまい, その場から動けなくなってしまう。このような状況を避けるため, 常にタイヤのすべり率を推定しつつ空転を回避する制御法を示す。また, 各車輪の荷重配分に応じた駆動制御を行うことにより, さらに踏破性能を向上させることができる。これらの制御法について, シミュレーション解析およびテストベッド実験結果について示す。
- 著者
- 中西 洋喜 加藤 治久 渡辺 敏暢 石上 玄也 西牧 洋一 丸木 武志 吉田 和哉
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. SANE, 宇宙・航行エレクトロニクス (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, no.654, pp.45-51, 2002-02-15
流星は,彗星を起源とする塵が大気圏に突入して発光する現象であり,この塵には生命の起源となった有機物が含まれている可能性が示唆されている.本論文では,しし座流星群をはじめとする様々な流星群を,大気圏外から観測を行い,イメージおよび分光データを取得する小型衛星,LEOLEO(Leonid-Meteor Observer in Low Earth Orbit)-IIを提案する.本衛星には,I.I. CCDカメラ及び分光器が搭載される.これにより地上からでは大気の影響で観測が極めて困難であった,流星の紫外線領域での分光観測が可能となり,これまで得ることができなかった貴重なデータを得ることが期待できる.
1 0 0 0 気球搭載望遠鏡による惑星大気・プラズマの研究
惑星大気・プラズマの光学的リモートセンシングを目的とした気球搭載望遠鏡システムを開発した。アルミ角材で構成されるゴンドラを設計・製作した。望遠鏡、太陽電池パネル、PC及び高圧電源を収納する気密容器、ジャイロ(CMG)を収納する防水容器、デカップリング機構がゴンドラに取り付けられる。CMGとデカップリング機構の制御によって、目標精度である約0.2°でゴンドラの姿勢を制御できることが確認された。望遠鏡の光路を波長帯で分け、中心波長400nm及び900nmのバンドパスフィルターを通して別々のCCDビデオカメラで撮像する。経緯台制御によって星像を約0.01°の精度で追尾できることを実験で確認した。望遠鏡視野に天体を捉えたのちは、星像位置検出用光電子増倍管からの出力をフィードバックして2軸可動ミラーマウントを制御することで、星像を視野中心に安定化できることを確認した。追尾性能向上のため、サンセンサーの視野をやや広くし、ガイド鏡の視野をやや狭くする改良を施した。ゴンドラ重量は約300kgとなった。電源は太陽電池から約250Wを供給するが、ニッケル水素充電池でノミナル消費電力を2時間まで供給することが可能である。ニッケル水素充電池の低温特性を測定し、性能に問題ないことを確認した。太陽電池と組み合わせた充放電回路を設計・製作した。熱真空試験を実施し、成層圏環境下で問題なく動作することを確認した。将来、北極で本格的な実験を実施するための調査として、ESRANGEの気球実験担当者と打ち合わせた。10月には実際にスウェーデン・キルナにある気球実験フィールドを視察した。これまでの開発成果を国際学会や国内学会・シンポジウムで発表した。また成果をまとめてAdv.Geosci.誌に投稿し受理された。