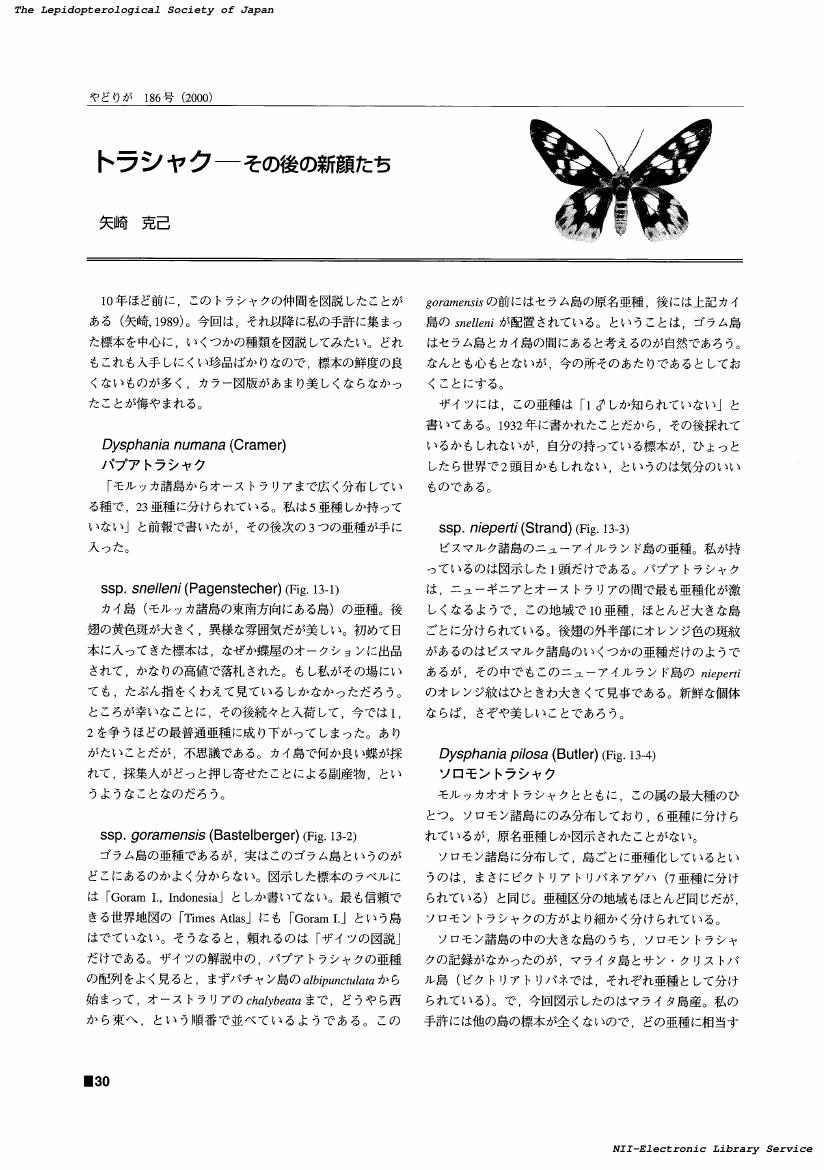1 0 0 0 OA 近世自然法と國家權力の問題
- 著者
- 矢崎 光圀
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.1953PartI, pp.93-135, 1953-09-30 (Released:2009-02-12)
- 参考文献数
- 110
1 0 0 0 OA トラシャク : その後の新顔たち
- 著者
- 矢崎 克己
- 出版者
- 日本鱗翅学会
- 雑誌
- やどりが (ISSN:0513417X)
- 巻号頁・発行日
- vol.2000, no.186, pp.30-31, 2000-09-30 (Released:2017-08-19)
- 参考文献数
- 2
1 0 0 0 OA 副交感神経遮断薬を用いた乳牛の第四胃右方変位および右方捻転の診断と治療
- 著者
- 矢崎 薫 沼津 敬治 一條 俊浩 佐々木 弘志 佐藤 繁
- 出版者
- 日本家畜臨床学会
- 雑誌
- 東北家畜臨床研究会報 (ISSN:09147497)
- 巻号頁・発行日
- vol.1988, no.11, pp.17-21, 1988-12-02 (Released:2009-04-22)
- 参考文献数
- 12
第四胃右方変位の診断を速やかにするため、臨床症状と打・聴診法による右側肋・〓部における金属性有響音の聴取に加え、異なる薬効を有する臭化プリフィニウム製剤とメトクロプラミド製剤を時間差併用投与した。その結果、投与後の臨床症状の変化は同じ部位で金属性有響音を聴取する第四胃アトニー、腸管疾患では改善され、第四胃右方変位および右方捻転では改善されないことから、それらの疾患の鑑別が可能であることが示唆され、その後の処置を施したところ良好な治療効果が認められた。
- 著者
- 矢崎 精二
- 出版者
- 日経BP社 ; 2002-
- 雑誌
- 日経ビジネスassocie (ISSN:13472844)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.7, pp.28-30, 2015-06
低迷を続けていた"ファミレス"の中で、今、一番元気なのがロイヤルホスト。15年連続売り上げ減という危機を救った社長、矢崎精二さんのコミュニケーション術を聞いた。
- 著者
- 矢崎 光圀
- 出版者
- 成城大学
- 雑誌
- 成城法学 (ISSN:03865711)
- 巻号頁・発行日
- no.27, pp.p1-19, 1988-03
1 0 0 0 19世紀末の日本人たちは西洋法思想をどう受けとめたのか
- 著者
- 矢崎 光圀
- 出版者
- 成城大学
- 雑誌
- 成城法学 (ISSN:03865711)
- 巻号頁・発行日
- no.44, pp.p1-13, 1993-09
1 0 0 0 人間の生きることと法思想--変わらない法思想なんてあるだろうか
- 著者
- 矢崎 光圀
- 出版者
- 成城大学
- 雑誌
- 成城法学 (ISSN:03865711)
- 巻号頁・発行日
- no.46, pp.p1-20, 1994-03
1 0 0 0 東西美術略史-〔1〕-
- 著者
- 安藤 更生 矢崎 美盛
- 出版者
- 美術出版社
- 雑誌
- 美術手帖 (ISSN:02872218)
- 巻号頁・発行日
- no.53, pp.66-80, 1952-02
1 0 0 0 八重山諸島における回復期リハビリテーション病棟の現状と課題
- 著者
- 伊能 良紀 崎山 加奈 本間 昌大 西原 美樹 比嘉 育子 長尾 浩志 清水 かつみ 矢崎 真一 波照間 光茂
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2007, pp.E1650, 2008
【はじめに】当院は、平成18年10月に八重山諸島唯一の回復期リハビリテーション(以下、リハ)病棟28床を開設した。八重山諸島は、周囲を海に囲まれ、石垣島を中心に大小8の有人島からなり、沖縄本島から約400km離れている。この地域は、医療・介護保険下のリハサービスの量が不足しており、また退院後の生活をサポートする環境が十分ではない。今回、このような地域での回復期リハ病棟の現状及び課題について報告する。<BR>【対象】平成18年10月1日から平成19年9月30日までの1年間に当院回復期リハ病棟を退院した患者104名(男性31名、女性73名)を対象とした。平均年齢は、79.4±12.4歳(男性72.4±14.9歳、女性82.7±9.8歳)であった。<BR>【現状】当院回復期リハ病棟は、専従医師1名、専従PT3名、専従OT1名、ST1名で行っている。発症から入院するまでに要した日数は37.0±13.4日、平均在院日数は87.5±42.2日であった。紹介元は石垣島内の急性期病院が87.5%と多く、沖縄本島の急性期病院からの紹介もあった。対象疾患別では骨折等49.0%、脳血管疾患等39.4%、廃用症候群10.6%、靭帯損傷等1.0%であった。退院先は、自宅51.0%、施設21.2%、療養病床13.5%であり、その他は急変等であった。ADL評価はBarthel Index(以下、BI)を用いた。退院時BIは、自宅退院群70.9±25.5、施設退院群39.3±34.3であった。<BR>【問題点・課題】最大の問題点は、自宅復帰率が低いことである。自宅復帰には患者の能力や認知症の有無等様々な要因に影響されるが、家族環境にも影響される。親族(二親等内の介護が可能な者)の石垣島在住者数をみると、自宅復帰群の退院時BI40以下(7名)は5.3±2.0人、一方施設退院群のBI85以上(4名)は3.7±1.2人であった。統計的な優位差はなかったが、親族が患者の身近にいる事で自宅復帰しやすい傾向にあるといえる。特に八重山諸島は他の地域と陸続きではないため、沖縄本島や本土にいる親族が介護のために八重山諸島へ帰るという事は経済的負担が大きいので難しい。よって地域内に親族が多い事が、自宅復帰の大きな要素の1つと考える。また、退院後の自宅生活を支援するサービスの量が圧倒的に不足している。昨年報告したようにPT/OT/STの人員不足と、通所リハでは一事業所あたりの利用者が、八重山諸島では26名(全国:9.6名)と多いことなど、サービス面の不足があげられる。これに加えてさらに、低い平均所得、高い物価、高い共働き率、地域の施設依存心もこの地域の在宅復帰率を下げる要因となっている。<BR>【終わりに】この地域では、家族環境や高い共働き率による介護力の低さ、高い施設依存心という問題点を抱えている。今後の課題として、自宅復帰率を増加していくために、早期から家族及びケアマネージャーと連携し自宅復帰を意識させたり、少ないサービスや介護力を有効に使い自宅復帰可能な環境設定を提供していく必要がある。
1 0 0 0 OA 広背筋の筋動作学的研究
- 著者
- 伊東 元 岩崎 富子 山田 道廣 矢崎 潔 田中 繁 飯田 勝
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 臨床理学療法 (ISSN:02870827)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, pp.23-36, 1976-10-31 (Released:2018-07-25)
- 被引用文献数
- 1
The electormyographic study of right latissimus dorsi muscle was performed in 19 men (10 healthy and 9 paraplegic) with the surface electrodes to clarify the functional difference of the 6 parts of the muscle. The 26 kinds of movements were employed for the experiments as followed; extension, adduction and internal rotation of the shoulder joint, lateral tilting of the pelvis, push up exercise and transfer (wheelchair-bed), etc…. The location of the electrodes on each part of the muscle was determined with the anatomical remarks. The electromyographic signals were processed through the rectifying and smoothing net work for the quantitative study and compared after standerization. It was found that two parts, namely upper and lower part of latissimus dorsi muscle have apparent functional difference each other; the former showed marked activities in hyper extension, the latter in lateral tilting of the pelvis; and it was also found that the characteristics of activities were similar on the healthy and the paraplegic subjects.
1 0 0 0 OA P-1-G16 重症心身障害児(者)に対する視覚機能評価の試み
- 著者
- 山際 英男 甲斐 結城 松木 友美 矢崎 有希 小町 祐子 軍司 敦子 山本 晃子 加我 牧子 益山 龍雄 荒井 康裕 本澤 志方 太田 秀臣 立岡 祐司 野口 ひとみ 高木 真理子 真野 ちひろ
- 出版者
- 日本重症心身障害学会
- 雑誌
- 日本重症心身障害学会誌 (ISSN:13431439)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.2, pp.262, 2017 (Released:2019-06-01)
はじめに 重症心身障害児(者)(以下、重症児者)は視覚刺激に対する応答がきわめて乏しい者があり、環境情報取得の制限から周囲の人や物との相互作用が乏しくなりがちである。何をどのように知覚しているのかの視覚認知機能評価は、療育上きわめて重要であり、自覚応答に頼らない視覚機能検査により、視覚情報提供の際の注意点を明らかにするため検討を行った。 対象 重症児者施設長期入所利用者50名(平均年齢37歳、男性26名、女性24名)、大島分類1:39名、2:4名、3:2名、4:3名、5:1名、9:1名。 方法 小町ら(日本重症心身障害学会誌、2013)の方法に準じて検討し、評価した。定性的視覚機能評価は対光反射、光覚反応、回避反応、視覚性反射性瞬目、睫毛反射、視運動性眼振(OKN)、注視、追視、瞥見視野)を調べ、反応状態により、反応あり、条件付き反応、反応無しの3段階の順序尺度で評価し、追視、瞥見視野は角度も測定した。注視・追視可能な者は縞視力測定を行った。機能の有無は評価に参加したセラピスト2/3以上の同意をもって判定した。 結果 各項目の反応出現率は睫毛反射94%、対光反射94%、光覚反応84%、視覚性反射性瞬目68%、注視66%、追視54%、瞥見視野52%、OKN58%、縞視力34%、回避反応40%であった。追視、瞥見視野の結果は個人差が大きく、かつ方向・範囲の制約がみられた。 考察 以上より対象者のうち、94%は情報取得手段として視覚を何らかの形で利用できる可能性があり、追視と瞥見視野の結果は刺激提示場所としてどの位置に提示すれば視覚応答が得られやすいかが示され、個別に考慮、対応すべきことが確認された。重症児者の多くは適切な視野を確保するための自動的な頭部コントロールが困難なことが多いため、「見える位置・距離」に対象を提示することが、残存視力を活かし豊かな相互作用につながると考えられる。
1 0 0 0 OA 社会としての芸術 : 芸術の自律化と制度化についての芸術社会学
- 著者
- 矢崎 慶太郎
- 出版者
- 専修大学人間科学学会
- 雑誌
- 専修人間科学論集. 社会学篇 (ISSN:21863156)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.137-148, 2014-03-15
本論では、芸術についての社会学理論を概観するために、基本的なアプローチを4つに区分して考察する。まず第一に芸術を道徳や経済などの「社会の反映」として示すコント、マルクス、第二に、芸術を社会と対立する関係にあるものと見なし、「社会の外側」にあるものとして扱うアドルノおよびゲーレン。第三に、芸術は社会的な反映ではないが、政治や経済と同様に、社会制度のひとつであり、「社会の内側」に属するものとして扱うベッカー(アート・ワールド)、ブルデュー(芸術場)、ルーマン(芸術システム)。第四に、芸術そのものを社会の原型として見るジンメル、および芸術がどのように他の社会領域に影響を与えているのか、という視点から芸術と経済との関係を研究するアプローチを取り上げる。これらの4つのアプローチを取り上げながら、芸術をどのように社会的な現象として扱うことができるのか、および芸術の社会学的研究にはどのような意義があるのかについて明らかにする。
1 0 0 0 OA 橋血管腫の一例
- 著者
- 山本 信二郎 中村 晋 矢崎 敏夫 橋本 誠二
- 出版者
- 金沢大学十全医学会
- 雑誌
- 金沢大学十全医学会雑誌 (ISSN:00227226)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.5, pp.661-665, 1959-05-20
1 0 0 0 OA 熱音響現象の理解と応用を目指して(非線形波動の数理と応用)
- 著者
- 矢崎 太一
- 出版者
- 京都大学数理解析研究所
- 雑誌
- 数理解析研究所講究録 (ISSN:18802818)
- 巻号頁・発行日
- vol.1483, pp.100-111, 2006-04
1 0 0 0 OA 多倍長乗算回路の構成と評価に関する研究
- 著者
- 矢崎 俊志 Syunji Yazaki
- 出版者
- 電気通信大学
- 巻号頁・発行日
- 2006-03-23
本論文は,一般的な汎用プロセッサのビット長を大きく上回る多倍長数の乗算をハードウェアで実現する方法について述べる.多倍長数の演算は高精度の数値計算や素数判定,カオス計算,暗号計算など,多様なアプリケーションに利用されている.多倍長演算はその性質から,多くの時間を必要とする.特に,頻繁に利用される乗算は演算のボトルネックとなり得る.多倍長乗算においてはO(n^2^) の筆算式乗算よりも効率よく乗算を行う様々なアルゴリズムが存在する.代表的なものとして,O(n^1.58^) のKaratsuba 2-way 法,O(n^1.465^) のKaratsuba 3-way 法,O(n^1.404^) のKaratsuba 4-way 法,O(n^1.365^) のKaratsuba 5-way 法,O(n^1.63^) の法算法,O(n log n log log n) の高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform, FFT) 法がある.これらの中で,オーダの上で最も高速なのはFFT 法である.しかし,FFT 法は,複素数演算のオーバヘッドが大きく数百から数万ビットの演算における実質的な性能はKaratsuba 法よりも低い.このことから,現在もっとも利用されているアルゴリズムはKaratsuba 法である.ただし,数百万桁の乗算においてはFFT 法の方が高速である.現在,これらの多倍長乗算はソフトウェアによって実現されている.一方,多倍長乗算のハードウェア実装に関する研究としては,ガロア体上の乗算を行うものが多く報告されているが,整数の乗算に関するものはごくわずかである.特にFFT 乗算のハードウェア実装に関する研究は知られていない.本研究の目的は,FFT 法を用いた比較的大きな桁数の多倍長乗算とKaratsuba法を用いた比較的小さな桁数の多倍長乗算をそれぞれハードウェア実装し,ソフトウェアとの比較を行うことでその性能やコストを明らかにすることである. FFT 法のハードウェア実装においては,最大値どうしの乗算が最大の誤差をあたえることに着目し,乗算に必要な精度を求め,それを保証するデータ長でFFT 乗算器をCMOS 0.18μm テクノロジを用いて構成した.その結果,16 進数2^13^ 桁の乗算において,IEEE754 の64 ビット浮動小数点表現を用いた場合と比較して面積を60%,最大遅延時間を26% 削減したFFT 乗算器を実装することができた.さらに最適なパイプライン化を行った結果,同世代のテクロノジで設計されたPentium4 1.7GHz 上で実行したFFT 乗算と比較して16 進数2^5^ から2^13^ の範囲で,19.7倍から34.3 倍,平均で25.7 倍の性能を実現することができた.この時の面積は9.05mm^2^ であった.また,FFT 乗算とKaratsuba 乗算の性能が逆転する16 進数2^21^ 桁の乗算においては35 倍の性能を実現した.この時の面積は16.1mm^2^ であった.実際に,16 進数2 桁のFFT 乗算器を2.8mm 角のカスタムチップで試作し,その結果から,より大きな桁のFFT 乗算器も現実に実装可能であることを示した. Karatsuba 乗算器の実装においては2 つの設計選択肢として組み合わせ回路で行うRKM (Recursive Karatsuba Multiplier) と順序回路で行うIKM (Iterative Karatsuba Multiplier) を構成した.CMOS 0.18μm テクノロジを用いてこれらを実装した結果,2^9^ ビット以上の乗算においてRKM の面積は標準的な乗算回路であるWallace Tree 乗算器(Wallace Tree Multiplier, WTM) より小さくなることがわかった.2^9^ ビットにおける面積は30mm^2^ であった.また,最大遅延時間は常に WTM の方が短かった.このことから,性能コスト比においてRKM よりWTMの方が優れていることがわかった.したがって,IKM で用いる基本乗算器としてはWTM を用いる方が良い.IKM に関しては,再帰の回数をそれぞれ1,2,3 としたR1IKM,R2IKM,R3IKM を実装した.さらにそれぞれについて,基本乗算器のビット長(基本ビット長) を4 から128 ビットとするIKM を実装し,その性能,面積,電力を評価した.その結果,基本ビット長を32,64,128 ビットにしたIKMは,ソフトウェア実装exflib と比較してそれぞれ約5,10,30 倍の性能を実現できることを示した.この時,最も大きい面積は,基本ビット長を128 ビットにしたR3IKM の10.9mm^2^ であった.同じR3IKM について消費エネルギーを評価したところ汎用プロセッサと比較して1/600 であることがわかった.全体を通して,ハードウェアとソフトウェアいずれにおいても,FFT 乗算とKaratsuba 乗算は2 進2^23^ 桁(16 進数2^21^) 付近で性能が逆転することがわかった. 2 進2^23^ 桁においてハードウェア実装とソフトウェア実装の性能比はいずれのアルゴリズムについても約30 倍であった.またこのとき,面積はそれぞれ2^12^mm^2^ と16mm^2^ であった.ただし,FFT 乗算器の面積に外部メモリは含まれていない.これらの結果から,FFT 法とKaratsuba 法の両ハードウェア実装おいて,パラメータに応じた性能コスト比の変化と適用範囲が明らかになった.本論文は,広い桁範囲における多倍長乗算のハードウェア化に関する詳細な研究結果を述べた唯一のものであり,多倍長乗算を用いたアプリケーションやシステムの実現において有益な指標となる.また,多倍長演算に関する実装技術の研究や開発,およびアプリケーションシステムの利用促進に大きく寄与すると考えられる.
- 著者
- 平尾 篤利 坂谷内 寿明 矢崎 敬人 疋田 光孝
- 出版者
- 公益社団法人 日本工学教育協会
- 雑誌
- 工学教育研究講演会講演論文集 (ISSN:21898928)
- 巻号頁・発行日
- vol.2014, pp.614-615, 2014
1 0 0 0 IR 橋川文三における「歴史意識」論の展開
- 著者
- 飛矢崎 貴規
- 出版者
- 明治大学大学院
- 雑誌
- 文学研究論集 (ISSN:13409174)
- 巻号頁・発行日
- no.51, pp.249-268, 2019-09-06