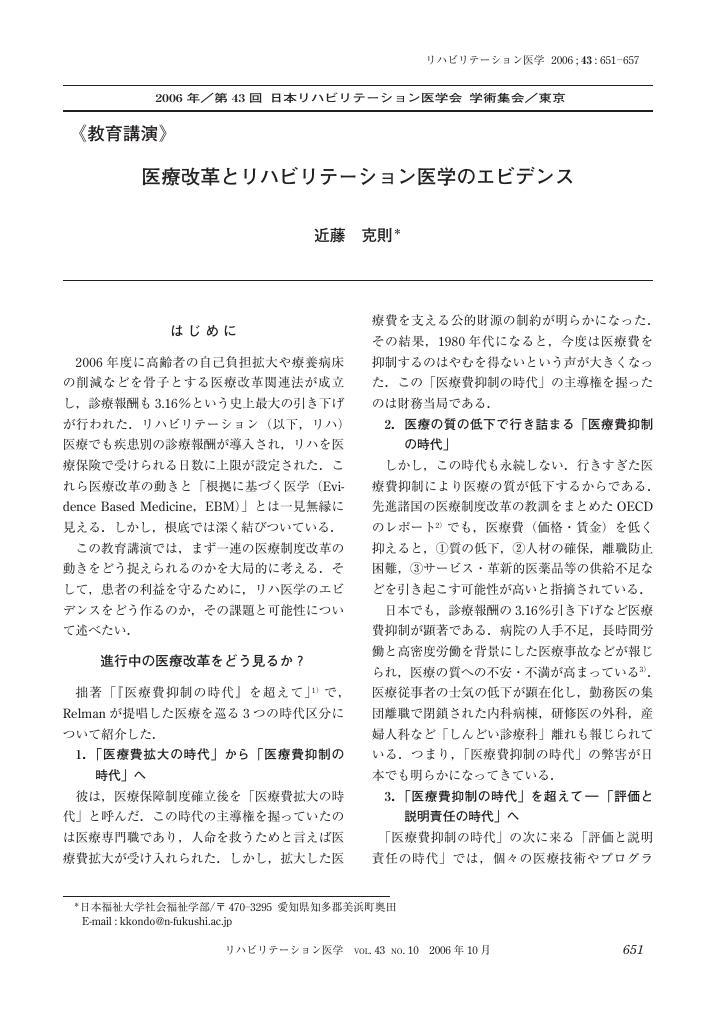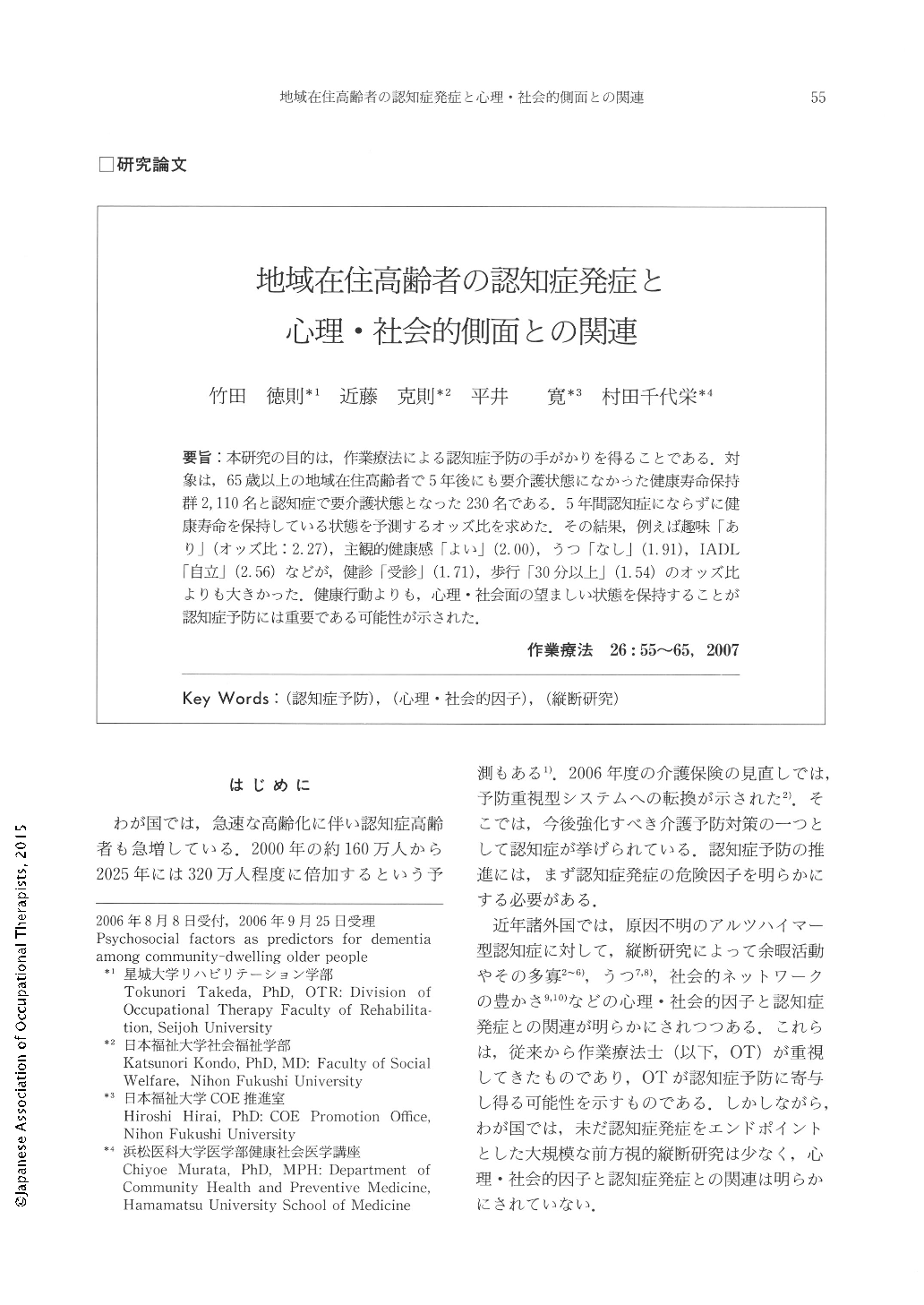1 0 0 0 OA 医療改革とリハビリテーション医学のエビデンス
- 著者
- 近藤 克則
- 出版者
- 社団法人 日本リハビリテーション医学会
- 雑誌
- リハビリテーション医学 (ISSN:0034351X)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.10, pp.651-657, 2006 (Released:2006-11-07)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 5 4
- 著者
- 高杉 友 近藤 克則
- 出版者
- 日本老年社会科学会
- 雑誌
- 老年社会科学 (ISSN:03882446)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.3, pp.173-187, 2020-10-20 (Released:2021-10-25)
- 参考文献数
- 50
- 被引用文献数
- 2
日本の高齢者を対象にした認知症関連リスク要因を検証した研究をシステマティックレビューし,研究の到達点と今後の課題を提示することを目的とした.医学中央雑誌及びPubMed文献データベース検索とハンドサーチにより,2007年以降に発表された34編の論文が抽出された.全体の8割が縦断研究であった.残存歯数,日本食,歩行時間等の生物学要因にとどまらず,うつなし等の心理要因,社会参加,ソーシャルサポート等の社会的要因と認知症リスクとの関連が示唆された.海外での研究に比した独自性は社会的な結びつきに関連する研究が豊富なこと,認知症リスク評価スコア研究や災害地域における研究などと思われた. 今後は個人レベルの要因にとどまらず,認知症対策の新たな戦略・社会政策を検討するためのエビデンスとして,より広い地域や社会,異なる時代の社会・環境要因を明らかにしていく社会科学的研究が必要と考えられた.
1 0 0 0 OA 回復期リハビリテーション医療におけるエビデンス構築に向けて ―データベース構築と活用―
- 著者
- 白石 成明 近藤 克則
- 出版者
- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会
- 雑誌
- The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine (ISSN:18813526)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.4, pp.286-291, 2018-04-18 (Released:2018-05-21)
- 参考文献数
- 19
リハビリテーション医療にもエビデンスに基づく医療(EBM)の提供が求められている.EBMには無作為比較試験(RCT)などの質の高いエビデンスが必要とされるが,RCTはリハビリテーション医療では実施しにくい場合が多い.そこで,RCTに代わるエビデンス蓄積の方法として大規模データベースがある.回復期リハビリテーション医療では,DPCのような大規模なデータベースは存在していないが,日本リハビリテーション・データベースなどがすでに構築されており,これらに基づく優れた研究も発表されている.リハビリテーション医療の質向上と,それに寄与するエビデンスの蓄積,蓄積されたエビデンスの利用のために,大規模データベースの構築とそれを活用した研究の蓄積が望まれる.
1 0 0 0 OA リハビリテーション患者データベースの二次分析 —プロセス,可能性と限界—
- 著者
- 近藤 克則
- 出版者
- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会
- 雑誌
- The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine (ISSN:18813526)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.3, pp.142-148, 2012-03-18 (Released:2012-03-28)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 13 8
The Japanese Association of Rehabilitation Medicine (JARM) is developing a Rehabilitation Patient Database (DB). The accumulated number of registered patients exceeded 10000 by March, 2011. The purposes of this article are to describe the process and procedures of secondary analysis and to consider potentials and limitations of the DB to promote the research activities of JARM members. JARM Members who submitted patient data or cooperate with JARM in the secondary analysis are regarded as eligible to use the combined data submitted by many hospitals. A suitable patient dataset should be derived from the DB including stroke, hip fracture, and spinal cord injury, and also patient data from the acute to recovery phase of rehabilitation. Additionally, before paper drafts can be submitted, a reviewing process is needed. The DB holds much potential, because the sample size is large and data were submitted from many hospitals. Since there are inherent limitations in all observational research, many issues such as endogeneities and confounders should be considered carefully to ensure high quality evidence is obtained with validity and reliability using the DB.
1 0 0 0 OA 会員の声へのお答え
1 0 0 0 OA 社会的フレイルの指標に関する文献レビューと内容的妥当性の検証
- 著者
- 阿部 紀之 井手 一茂 渡邉 良太 辻 大士 斉藤 雅茂 近藤 克則
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.1, pp.24-35, 2021-01-25 (Released:2021-02-25)
- 参考文献数
- 49
- 被引用文献数
- 1
目的:社会的フレイルはリスク因子として重要だが,評価法が統一されていない.本研究の目的は専門家の評価による内容的妥当性のある社会的フレイルの要素を明らかにすることである.方法:PubMedで検索し入手した社会的フレイル関連26論文から抽出した要素のうち,7名中5名以上の評価者が4条件(負のアウトカム予知因子,可逆性,加齢変化,客観性)を満たすと評価した要素を抽出し分類した.結果:4条件を満たす要素は経済的状況(①経済的困難),居住形態(②独居),社会的サポート(③生活サポート者の有無,④社会的サポート授受),社会的ネットワーク(⑤誰かと話す機会,⑥友人に会いに行く,⑦家族や近隣者との接触),社会的活動・参加(⑧外出頻度,⑨社会交流,⑩社会活動,⑪社会との接触)の5分類11要素が抽出された.結論:先行研究で用いられている社会的フレイル22要素のうち,内容的妥当性が示唆された要素は11要素であった.
1 0 0 0 OA 外出頻度を尋ねる際の外出の定義の有無により生じる「閉じこもり」群の要介護リスクの違い
- 著者
- 平井 寛 近藤 克則
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.7, pp.505-516, 2022-07-15 (Released:2022-07-13)
- 参考文献数
- 28
目的 介護予防の重点分野の1つ「閉じこもり」は,外出頻度が週に1回未満の者とされることが多い。しかし質問文に外出の定義がない場合,外出しても外出と認識せず,頻度を少なく回答し閉じこもりと判定される可能性がある。本研究では,高齢者対象の質問紙調査において,外出の定義の有無による閉じこもり割合,要介護リスクの違いを明らかにする。また,目的別の外出頻度を用いて,週1回以上外出しているにもかかわらず閉じこもりとなる「外出頻度回答の矛盾」に外出の定義の有無が関連しているかどうかを検討した。方法 愛知県の4介護保険者A~D在住の自立高齢者に対し2006~2007年に行った自記式調査の回答者10,802人を対象とした。全般的な外出頻度を尋ねる際,保険者Dのみ「屋外に出れば外出とします」という定義を示した。また全4保険者で,買い物等5種類の目的別外出頻度を尋ねた。全般的な外出頻度で週1回未満の者を「全般的閉じこもり」,目的別外出頻度いずれかで週1回以上の者を「目的別非閉じこもり」とした。「全般的閉じこもり」について,約10年間の要介護認定ハザード比(Hazard Ratio, HR)の違いを検討した。「目的別非閉じこもり」かつ「全般的閉じこもり」の者を「外出頻度回答に矛盾がある者」とし,発生割合,発生に関連する要因のPrevalence Ratio(PR)を算出した。結果 全般的閉じこもりの粗割合は保険者ABCでは11.7%であったのに対し,定義を示した保険者Dでは2.8%であった。保険者ABCに対し,保険者Dの全般的閉じこもりは要介護認定を受けるHRが有意に高かった(HR=1.56)。目的別非閉じこもりであるにもかかわらず全般的閉じこもりという矛盾回答は保険者ABCで10.2%,保険者Dで2.2%みられた。矛盾回答の発生に正の関連を示したのは女性,高い年齢,配偶者・子世代との同居,教育年数が短いこと,主観的健康感がよくないこと,うつ,島嶼部の居住者であることであった。外出の定義を示した保険者Dでは有意に矛盾が発生しにくかった(PR=0.29)。結論 外出の定義の有無により閉じこもり割合,要介護リスクに違いがみられた。外出の定義がないことは外出頻度回答の矛盾発生に有意に関連していた。閉じこもりを把握するために外出頻度を尋ねる際には外出の定義を示すことが望ましい。
- 著者
- 田村 元樹 服部 真治 辻 大士 近藤 克則 花里 真道 坂巻 弘之
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- pp.21-014, (Released:2021-10-22)
- 参考文献数
- 38
目的 本研究は,うつ発症リスク予防に効果が期待される65歳以上の高齢者のボランティアグループ参加頻度の最適な閾値を傾向スコアマッチング法を用いて明らかにすることを目的とした。方法 日本老年学的評価研究(JAGES)が24市町村に在住する要介護認定を受けていない65歳以上を対象に実施した,2013年と2016年の2時点の縦断データを用いた。また,2013年にうつ(Geriatric Depression Scale(GDS-15)で5点以上)でない人を3年間追跡し2013年のボランティアグループに年1回以上,月1回以上もしくは週1回以上の参加頻度別に,2016年に新たなうつ発症のオッズ比(OR)を,傾向スコアマッチング法とt検定などを用いて求めた。結果 参加群は,年1回以上で9,722人(25.0%),月1回以上で6,026人(15.5%),週1回以上で2,735人(7.0%)であった。3年間のうつの新規発症は4,043人(10.5%)であった。傾向スコアを用いたマッチングでボランティアグループ参加群と非参加群の属性のバランスを取って比較した結果,月1回以上の頻度では参加群は非参加群に比べて,Odds比[OR]0.82(95%信頼区間:0.72, 0.93)と,うつ発症リスクは有意に低かった。年1回以上の参加群ではORが0.92(0.83, 1.02),および週1回以上では0.82(0.68, 1.00)であった。結論 高齢者のボランティアグループ参加は,月1回以上の頻度で3年後のうつ発症リスクを抑制する効果があることが示唆された。高齢者が月1回でもボランティアとして関わることができる機会や場所を地域に増やすことが,うつ発症予防対策となる可能性が示唆された。
- 著者
- 田近 敦子 井手 一茂 飯塚 玄明 辻 大士 横山 芽衣子 尾島 俊之 近藤 克則
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.2, pp.136-145, 2022-02-15 (Released:2022-03-02)
- 参考文献数
- 33
目的 厚生労働省は2014年の介護保険法改正を通じて,本人を取り巻く環境へのアプローチも含めた取組も進めるとし,通いの場づくりを中心とした一般介護予防事業を設けた。しかし,通いの場への参加による介護予防の効果を複数の市町を対象に検証した報告は少ない。本研究の目的は通いの場参加による要支援・要介護リスクの抑制効果を10道県24市町のデータを用い検証することである。方法 日本老年学的評価研究(JAGES)が10道県24市町在住の要介護認定を受けていない65歳以上を対象に実施した,2013・2016年度の2時点の自記式郵送調査データを用いた。目的変数は要支援・要介護リスク評価尺度(Tsuji, et al., 2018)の合計点数(以下,要介護リスク点数)5点以上の悪化とし,説明変数は通いの場参加の有無とした。調整変数は2013年度の教育歴,等価所得,うつ,喫煙,飲酒,手段的日常生活動作,2013年度の要介護リスク点数(性・年齢を含む),さらに独居と就業状況を加えた9変数とした。統計学的分析は全対象者,および前期・後期高齢者で層別化したポアソン回帰分析(有意水準5%)を行った。感度分析として,要介護リスク点数を3点,7点以上の悪化とする分析も行った。結果 対象者3,760名のうち参加者は全体で472人(前期高齢者316人,後期高齢者156人),12.6%(11.8%,14.5%)であった。参加なしに対して参加あり群における要介護リスク点数5点以上の悪化の発生率比は全対象者で0.88(95%信頼区間:0.65-1.18),前期高齢者で1.13(0.80-1.60),後期高齢者で0.54(0.30-0.96)となり,後期高齢者で有意であった。また,要介護リスク点数3点や7点以上の悪化を目的変数とした感度分析でも同様の結果であった。結論 非参加者と比較し,通いの場参加者において,要介護リスク点数5点以上の悪化は,後期高齢者で46%抑制されていた。とくに後期高齢者が多い地域に対して通いの場づくりを進め参加者を増やすことが,介護予防を推進する上で有効である可能性が示唆された。
- 著者
- 田村 元樹 服部 真治 辻 大士 近藤 克則 花里 真道 坂巻 弘之
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.12, pp.899-913, 2021-12-15 (Released:2021-12-24)
- 参考文献数
- 38
目的 本研究は,うつ発症リスク予防に効果が期待される65歳以上の高齢者のボランティアグループ参加頻度の最適な閾値を傾向スコアマッチング法を用いて明らかにすることを目的とした。方法 日本老年学的評価研究(JAGES)が24市町村に在住する要介護認定を受けていない65歳以上を対象に実施した,2013年と2016年の2時点の縦断データを用いた。また,2013年にうつ(Geriatric Depression Scale(GDS-15)で5点以上)でない人を3年間追跡し2013年のボランティアグループに年1回以上,月1回以上もしくは週1回以上の参加頻度別に,2016年に新たなうつ発症のオッズ比(OR)を,傾向スコアマッチング法とt検定などを用いて求めた。結果 参加群は,年1回以上で9,722人(25.0%),月1回以上で6,026人(15.5%),週1回以上で2,735人(7.0%)であった。3年間のうつの新規発症は4,043人(10.5%)であった。傾向スコアを用いたマッチングでボランティアグループ参加群と非参加群の属性のバランスを取って比較した結果,月1回以上の頻度では参加群は非参加群に比べて,Odds比[OR]0.82(95%信頼区間:0.72, 0.93)と,うつ発症リスクは有意に低かった。年1回以上の参加群ではORが0.92(0.83, 1.02),および週1回以上では0.82(0.68, 1.00)であった。結論 高齢者のボランティアグループ参加は,月1回以上の頻度で3年後のうつ発症リスクを抑制する効果があることが示唆された。高齢者が月1回でもボランティアとして関わることができる機会や場所を地域に増やすことが,うつ発症予防対策となる可能性が示唆された。
1 0 0 0 OA 訂正:高齢者の趣味の種類および数と認知症発症:JAGES 6年縦断研究
- 著者
- LINGLING 辻 大士 長嶺 由衣子 宮國 康弘 近藤 克則
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.12, pp.925, 2021-12-15 (Released:2021-12-24)
第67巻第11号(2020年11月15日発行)「LINGLING,他.高齢者の趣味の種類および数と認知症発症:JAGES 6年縦断研究」において,以下の箇所に誤りがありました。お詫びとともに下記のとおり訂正いたします。P800 筆者•共著者の所属•責任著者連絡先の修正 下線部が訂正箇所誤Ling LING∗,辻 大士2∗,長嶺由衣子2∗,3∗,宮國 康弘4∗,5∗,近藤 克則2∗,4∗ ∗千葉大学大学院医薬学府先進予防医学共同専攻博士課程 2∗筑波大学体育系 3∗東京医科歯科大学医学部付属病院総合診療科 4∗国立長寿医療研究センター老年学•社会科学研究センター老年学評価研究部 5∗医療経済研究機構研究部責任著者連絡先:〒260-8670 千葉市中央区亥鼻1-8-1 千葉大学大学院医薬学府Ling LING正LINGLING∗,辻 大士2∗,長嶺由衣子3∗,6∗,宮國 康弘4∗,5∗,近藤 克則4∗,6∗ ∗千葉大学大学院医学薬学府先進予防医学共同専攻博士課程 2∗筑波大学体育系 3∗東京医科歯科大学医学部付属病院総合診療科 4∗国立長寿医療研究センター老年学•社会科学研究センター老年学評価研究部 5∗医療経済研究機構研究部 6∗千葉大学予防医学センター責任著者連絡先:〒263-8522 千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33 千葉大学大学院医学薬学府LINGLINGP810 筆者•共著者の所属 下線部が訂正箇所WrongLing LING∗, Taishi TSUJI2∗, Yuiko NAGAMINE2∗,3∗, Yasuhiro MIYAGUNI4∗,5∗, Katsunori KONDO2∗,4∗ ∗Docter Course in Graduate School of Medical and Pharmaceutical Sciences, Chiba University 2∗Faculty of Health and Sport Sciences, University of Tsukuba 3∗Department of Family Medicine, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental University 4∗Department of Gerontological Evaluation, Center for Gerontology and Social Science, National Center for Geriatrics and Gerontology 5∗Research Department, Institute for Health Economics and PolicyCorrectLINGLING∗, Taishi TSUJI2∗, Yuiko NAGAMINE3∗,6∗, Yasuhiro MIYAGUNI4∗,5∗, Katsunori KONDO4∗,6∗ ∗Doctor Course in Graduate School of Medical and Pharmaceutical Sciences, Chiba University 2∗Faculty of Health and Sport Sciences, University of Tsukuba 3∗Department of Family Medicine, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental University 4∗Department of Gerontological Evaluation, Center for Gerontology and Social Science, National Center for Geriatrics and Gerontology 5∗Research Department, Institute for Health Economics and Policy 6∗Center for Preventive Medical Sciences, Chiba University
- 著者
- 斉藤 雅茂 辻 大士 藤田 欽也 近藤 尚己 相田 潤 尾島 俊之 近藤 克則
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.11, pp.743-752, 2021-11-15 (Released:2021-12-04)
- 参考文献数
- 28
目的 介護予防事業推進による財政効果を評価する際の基礎資料を得るために,介護予防・日常生活圏域ニーズ調査で把握可能な要支援・要介護リスク評価尺度点数別の介護サービス給付費の6年間累積額を分析した。方法 日本老年学的評価研究(Japan Gerontological Evaluation Study:JAGES)の一環で,2010年に実施された要介護認定を受けていない高齢者を対象にした質問紙調査の一部をベースラインにした(全国12自治体を対象。回収率:64.7%)。その後,行政が保有する介護保険給付実績情報と突合し,46,616人について2016年11月まで(最長76か月間)に利用した介護サービス給付費を把握した。要支援・要介護リスクについては,性・年齢を含む12項目で構成される要支援・要介護リスク評価尺度・全国版(0-48点)を用いた。ベースライン時の基本属性等を調整した重回帰モデルに加えて,従属変数の分布を考慮したトービットモデルおよび多重代入法による欠損値補完後の重回帰モデルを行った。結果 追跡期間中に7,348人(15.8%)が新たに介護保険サービス利用に至っていた。要支援・要介護リスク評価尺度点数が高いほど,6年間の要支援・要介護認定者および要介護2以上認定者割合,累積介護サービス給付費が高く,介護サービスの利用期間は長く,いずれも下に凸の曲線状に増えていた。ベースライン時の諸特性を統計的に考慮したうえでも,リスク評価点数が1点高いほど,6年間累積介護サービス給付費は1人あたり3.16(95%信頼区間:2.83-3.50)万円高い傾向にあった。リスク評価点数が低い群(16点以下)では1点あたり0.89(95%信頼区間:0.65-1.13)万円,高い群(17点以上)では1点あたり7.53(95%信頼区間:6.74-8.31)万円高い傾向にあった。推計モデルによる大きな違いは確認されなかった。結論 ある時点での集団のリスク評価尺度点数からその後6年間の累積介護サービス給付費の算出が可能であることが示された。外出頻度などリスク点数を構成する可変的な要素への介入が保険者単位でみると無視できない財政的なインパクトになりうることが示唆された。
- 著者
- 東馬場 要 井手 一茂 渡邉 良太 飯塚 玄明 近藤 克則
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 総合リハビリテーション (ISSN:03869822)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.9, pp.897-904, 2021-09
1 0 0 0 OA 心身医学と社会疫学
- 著者
- 近藤 克則
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.4, pp.294-301, 2019 (Released:2019-05-01)
- 参考文献数
- 34
心身医学は, 患者を心理・社会・環境面も含めて全人的にみていこうとする. 社会疫学は 「健康格差社会」 を生み出す社会的決定要因を疫学的なアプローチで明らかにする研究分野である. つまり社会疫学は 「広義の心身医学」 の一部であることを意味する. 本稿では, 第1に健康格差の生成プロセスについて解明されてきた到達点をレビューする. 第2に 「健康格差社会への処方箋」 として使える対策を概観する. 第3に地域づくり方法や効果, そして臨床現場で今後の普及が期待される社会的処方について紹介する.
- 著者
- 斎藤 民 近藤 克則 村田 千代栄 鄭 丞媛 鈴木 佳代 近藤 尚己 JAGES グループ
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.10, pp.596-608, 2015
<b>目的</b> 生きがいや社会的活動参加の促進を通じた高齢者の健康づくりには性差や地域差への考慮が重要とされる。しかしこれらの活動における性差や地域差の現状は十分明らかとはいえない。本研究では高齢者の外出行動と社会的・余暇的活動の性差と地域差を検討した。<br/><b>方法</b> Japan Gerontological Evaluation Study (JAGES)プロジェクトが2010年~2012年に実施した,全国31自治体の要介護認定非該当65歳以上男女への郵送自記式質問紙調査データから103,621人を分析対象とした。分析項目は,週 1 日以上の外出有無,就労有無,団体・会への参加有無および月 1 回以上の参加有無,友人・知人との交流有無および月 1 回以上の交流有無,趣味の有無を測定した。性,年齢階級(65歳以上75歳未満,75歳以上),および地域特性として都市度(大都市地域,都市的地域,郡部的地域)を用いた。年齢階級別の性差および地域差の分析にはカイ二乗検定を実施した。さらに実年齢や就学年数,抑うつ傾向等の影響を調整するロジスティック回帰分析を行った(有意水準 1%)。また趣味や参加する団体・会についてはその具体的内容を記述的に示した。<br/><b>結果</b> 年齢階級別の多変量解析の結果,男性は有意に週 1 回以上の外出や就労,趣味活動が多く,団体・会への参加や友人・知人との交流は少なかった。ほとんどの活動項目で都市度間に有意差が認められ,郡部的地域と比較して大都市地域では週 1 回以上外出のオッズ比が約2.3と高い一方,友人との交流のオッズ比は後期高齢者で約0.4,前期高齢者で約0.5であった。性や都市度に共通して趣味の会の加入は多い一方,前期高齢者では町内会,後期高齢者では老人クラブの都市度差が大きく,実施割合に30%程度の差がみられた。趣味についても同様に散歩・ジョギングや園芸は性や都市度によらず実施割合が高いが,パソコンや体操・太極拳は性差が大きく,作物の栽培は地域差が大きかった。<br/><b>結論</b> 本研究から,①外出行動や社会的・余暇的活動のほとんどに性差や都市度差が観察され,それらのパターンが活動の種類によって異なること,②参加する団体・会や趣味の内容には男女や都市度に共通するものと,性差や都市度差の大きいものがあることが明らかになった。以上の特徴を踏まえた高齢者の活動推進のための具体的手法開発が重要であることが示唆された。
- 著者
- 藤原 聡子 辻 大士 近藤 克則
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.11, pp.828, 2020-11-15 (Released:2020-12-23)
第67巻第10号(2020年10月15日発行)「藤原聡子,他.ウォーキングによる健康ポイント事業が高齢者の歩行時間,運動機能,うつに及ぼす効果:傾向スコアを用いた逆確率重み付け法による検証」において,以下の箇所に誤りがありました。お詫びとともに下記のとおり訂正いたします。P744 Methods 7∼11行目 下線部が訂正箇所誤Changes in walking time, physical function, and depression were designated as independent variables, and participation status in the YWP was designated as the dependent variable in the multiple regression analysis with inverse probability of treatment weighting (IPTW), after adjusting for demographic variables, socioeconomic status, health status, and behavior.正Changes in walking time, physical function, and depression were designated as dependent variables, and participation status in the YWP was designated as the independent variable in the multiple regression analysis with inverse probability of treatment weighting (IPTW), after adjusting for demographic variables, socioeconomic status, health status, and behavior.
1 0 0 0 地域在住高齢者の認知症発症と心理・社会的側面との関連
要旨:本研究の目的は,作業療法による認知症予防の手がかりを得ることである.対象は,65歳以上の地域在住高齢者で5年後にも要介護状態になかった健康寿命保持群2,110名と認知症で要介護状態となった230名である.5年間認知症にならずに健康寿命を保持している状態を予測するオッズ比を求めた.その結果,例えば趣味「あり」(オッズ比:2.27),主観的健康感「よい」(2.00),うつ「なし」(1.91),IADL「自立」(2.56)などが,健診「受診」(1.71),歩行「30分以上」(1.54)のオッズ比よりも大きかった.健康行動よりも,心理・社会面の望ましい状態を保持することが認知症予防には重要である可能性が示された.
1 0 0 0 OA 新型コロナウイルス感染症流行下での高齢者の生活への示唆:JAGES研究の知見から
- 著者
- 木村 美也子 尾島 俊之 近藤 克則
- 出版者
- 一般財団法人 日本健康開発財団
- 雑誌
- 日本健康開発雑誌 (ISSN:2432602X)
- 巻号頁・発行日
- pp.20200602, (Released:2020-06-02)
- 参考文献数
- 51
背景・目的 新型コロナウイルス感染症がパンデミック(世界的な大流行)となり,外出や人との交流が難しくなっている.こうした状況の長期化は,閉じこもりや社会的孤立の増加につながりうるが,それによる健康への弊害にはどのようなものが予想されるであろうか.本稿では,日本老年学的評価研究(Japan Gerontological Evaluation Study: JAGES)で蓄積されてきた研究から,高齢者の社会的行動と健康に関する知見を概括し,新型コロナウイルス感染症流行時の高齢者の健康の維持・向上に望ましい生活への示唆を得ることを目的とした.方法 JAGESによる研究の中から,高齢者の社会的行動と健康の関連を示した46件の論文(2009年~2020年発表)を抽出し,その知見を概括し,新型コロナウイルス感染症流行時に可能な健康対策について考察した.結果 介護,認知症,転倒,うつなどを予防し,高齢者の健康を維持・向上するためには,外出や他者との交流,運動や社会参加が重要であることが示された.それらの機会が制限されることで,要介護,認知症,早期死亡へのリスクが高まり,また要介護状態も重症化することが予測された.考察 社会的行動制限は感染リスクを抑えるために必要なことではあるものの,健康を損なうデメリットもあるため,感染リスクを抑えつつ,人との交流,社会参加の機会を設ける必要があると考えられた.密閉,密接,密集を回避しつつ,他者との交流を続けることで,感染リスクと将来の健康リスクが減じ得るだろう.
1 0 0 0 OA 冠動脈疾患と社会経済的要因 —メカニズムと予防の視点から—
- 著者
- 坪井 宏仁 近藤 克則 金子 宏 山本 纊子
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.1-7, 2011 (Released:2014-07-03)
- 参考文献数
- 46
心疾患は、本邦では悪性新生物に次ぐ死因の第2位を占め、その多くが「冠動脈疾患(coronary heart disease, CHD)」である。CHDのリスクファクターとして、高血圧・高脂血症・糖尿病など生活習慣に基づくものが一般に知られているが、心理的・社会的・経済的因子も無視できない。多くの欧米諸国では長年にわたり心疾患が死因の第1位であるため、その原因と予防に関する研究も多く、CHDと心理的社会的因子や社会経済的因子に関する研究結果が多く得られている。わが国でもライフスタイルの変化により動脈硬化病変がさらに増加し、CHD罹患率やそれによる死亡率の上昇することが予測される。その予防において、個人の生活習慣以外にCHDの重要なリスクファクターである社会経済的要因を把握することも重要であろう。わが国は、高度成長時代を経て平等と言われる社会を築いてきたが、1990年代後半以降は個人間の社会経済的格差が広がっている。その変化の長短は視点によって異なるところであろうが、社会経済的格差が健康に影響を及ぼすのであれば、格差の変革が疾病予防にもつながるはずである。そこで本稿では、CHDと社会経済的状況(socioeconomic status, SES)の関係について、まず両者の関係を述べ、次に両者をつなぐメカニズムを主に心理社会的側面から触れ、最後にCHD予防の可能性を社会的側面から考察した。CHDは、冠動脈壁に経年的に形成される内膜の肥厚病変とその破裂により発生し、原因は酸化・炎症や交感神経系の亢進などである。一方、SESは収入・教育歴・職業(職の有無、職場での立場も含む)などから成り、さまざまな経路でCHDに影響すると考えられる。健康行動はSESによって差があり、高SES層ほど健康によい行動を取る傾向にある。その差が、健康増進資源・医療へのアクセスの違いにつながり、CHDの発症および予後に影響する。次に、心理社会的経路であるが、この経路では、心理的・社会的特性の差異が自律神経・内分泌・免疫系を介してCHDの成因に影響する。低SES層には、慢性ストレスやライフイベントが多く、抑うつ傾向・怒り・攻撃性・社会的孤立などが認められる一方、高SES層ではコントロール感や自己実現感が高い。このような差違が、視床下部-下垂体-副腎皮質(hypothalamic-pituitary-adrenal, HPA)系または交感神経-副腎髄質(sympathetic-adrenal-medullar, SAM)系を介し、炎症・酸化・血糖の上昇・交感神経系の亢進に影響し、長年の間にCHDイベントのリスクが高まる。また、両親および幼少期のSESが、HPA系およびSAM系の反応を脆弱にしたり、成人後の行動的・心理社会的リスクファクター(喫煙・運動不足・攻撃性・職場での緊張・不健康な心理状態など)に影響を与え、CHDに影響を及ぼす可能性も示唆されている。さて、CHDの予防は、生活習慣予防として特定健康診査・特定保健指導により個人および職場レベルで2008年より行われている。しかしSESとCHDの関連性を考慮すると、社会レベルでの予防策も必要であろう。WHOは、健康を決定する社会的要因として「社会経済環境」「物理環境」「個人の特性と行動」を挙げている。このうち、社会経済環境を整備することがCHD予防につがなる可能性を示した。教育による介入、社会保障制度の整備、人生の節目でのサポートなどが有効であろうことが海外の研究で示されている。SESを改善しCHDを予防する戦略には、エビデンスに基づいた社会疫学的研究が必要であろう。
- 著者
- 杉山 統哉 田中 宏太佳 鄭 丞媛 松本 大輔 近藤 克則
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2009, pp.B3O2093, 2010
【目的】<BR> 脳卒中後の機能回復の予後において社会的サポートのレベルが高いほどActivities of Daily Living (以下ADL)点数が高くなるという報告がある.社会的サポートとは周囲の人々から得られる有形・無形の援助のことであり,家族介護者は社会的サポートの主な提供者の1つである.そこで介護力の有無により自宅退院率だけではなく,脳卒中後の機能回復に影響があるのかどうかを明らかにすることを目的とした.<BR> 日々の臨床においてもリハビリテーション(以下リハ)の対象となる患者は,関わる人が多い場合,帰結が良くなるという印象がある.仮説として特に家族介護者の関わりが多い方がより早く治したい,動けるようになりたいという感情が強くなり,帰結に影響を及ぼしているのではないかと考えた.しかし脳卒中後リハ対象患者において人の関わりがADLにどう影響を及ぼしているかを検討した報告はほとんどない.そこで多施設参加型データベースであるリハビリテーション患者データバンク(リハDB)に登録されている脳卒中患者のデータを使用し,検討したので報告する.<BR>【方法】<BR> 2009年5月までにリハビリテーション患者データバンク(以下リハDB)に登録された3,930名(30病院)のうち入院病棟区分が「一般病棟」の2,238名(19病院)から今回の検討するデータが入力されている9病院から入院時歩行不可である618名(男性365名,女性253名)を対象にした.患者選択基準は「発症前modified Rankin Scale(以下mRS)0~3」,「入院時mRS4・5 」,「55歳以上84歳以下」,「在院日数8日以上60日以下」,「発症後リハビリ開始病日21日以下」,「発症後入院病日7日以下」,以上の基準を満たすものを分析対象とした.対象の内訳は年齢72.4±7.9歳,発症から入院までの日数1.3±0.7日,発症後リハ開始病日2.8±2.8日,在院日数29.1±12.3日,リハ期間26.0±12.3日,1日あたりのリハ単位数(保険請求分)4.0±2.3単位であった.今回の検討は転・退院時の歩行状態が自立か非自立を帰結にした.そこで対象を転・退院時歩行自立294名と歩行非自立324名に分類した.転・退院時の歩行の自立・非自立の定義は入院時のFunctional Independence Measure(以下FIM)とmRSを掛け合わせることで設定した.リハDBのデータ項目の中から転・退院時の歩行状態を予測する因子として性別,年齢,確定脳卒中診断分類(脳梗塞,脳出血,くも膜下出血),在院日数,糖尿病の有無,高血圧の有無,合併症の有無,脳卒中既往歴,発病前mRS,発症後リハ開始病日,認知症の有無,意識レベル,下肢運動,入院時半側空間無視の有無,入院時感覚障害の有無,入院時FIM運動項目合計,入院時FIM認知項目合計,介護力の有無,装具処方の有無,リハ専門医の関与の有無,カンファレンスの実施状況,休日・付加的な訓練の有無,1日あたりのリハ単位数を選択した.上記の項目を独立変数とし,転・退院時の歩行自立・非自立を従属変数としてSPSSver12.0を用いてロジスティック回帰分析を行った.また,有意水準は5%未満とした.<BR>【説明と同意】<BR> 本研究において用いたデータは,リハDBについて説明の上同意した協力施設から,匿名化処理をし個人情報を削除したデータの提供を受けた.<BR>【結果】<BR> 選択した各変数の単変量解析(χ2検定)を行った結果,糖尿病の有無,高血圧の有無,発症後リハ開始病日,装具の処方の有無,カンファレンスの実施状況,1日あたりリハ単位数以外は有意確率0.05以下であった.<BR> ロジスティック回帰分析の結果は性別が「男」,脳卒中確定診断分類のうち「脳梗塞」,脳卒中既往歴「なし」,発症後リハ開始病日が「3日以内」,下肢運動「正常」,感覚障害「正常」,入院時運動・認知項目合計得点が高い,介護力「0~1人」「1人以上」,リハ専門医の関与「あり」が転・退院時の歩行自立が多い因子(p<0.05)であった.判別的中率は87.3%,HosmerとLemeshowの検定ではχ2=4.485(p=0.811)であった.今回の検討項目である介護力の有無に関してのオッズ比は歩行非自立を「1」としたとき,介護力「なし」に対して「0~1人」が7.142(95%信頼区間:1.846~27.625),「1人以上」が7.448(95%信頼区間:1.799~30.832)であった.<BR>【考察】<BR> 入院時の他の条件が同じ患者でも介護力が大きい人ほど歩行自立する確立が高いことが示された.1993年StrokeのGlassらによると高いレベルの社会的サポートは脳卒中後の機能回復に関連し,重要な予後因子であるかもしれないと報告している.今回の結果においても介護力の有無が脳卒中患者における歩行自立の重要な予後因子であるかもしれないということが示唆された.<BR>【理学療法学研究としての意義】<BR> 本研究の結果から,急性期脳卒中患者において集約的合理的にリハを行う・予後予測する一助になると考えられる.