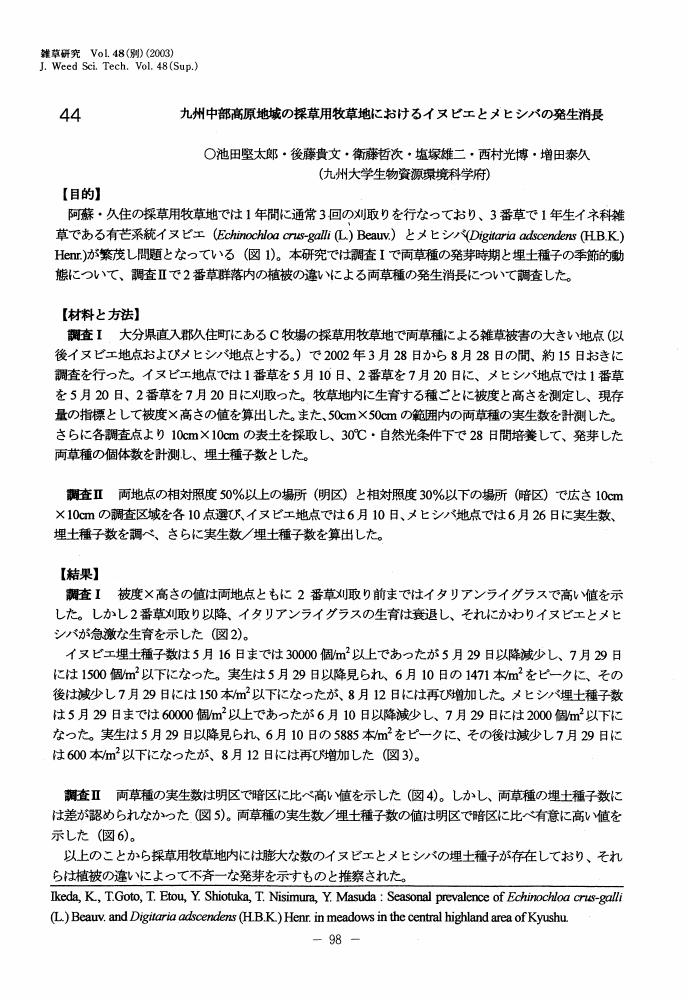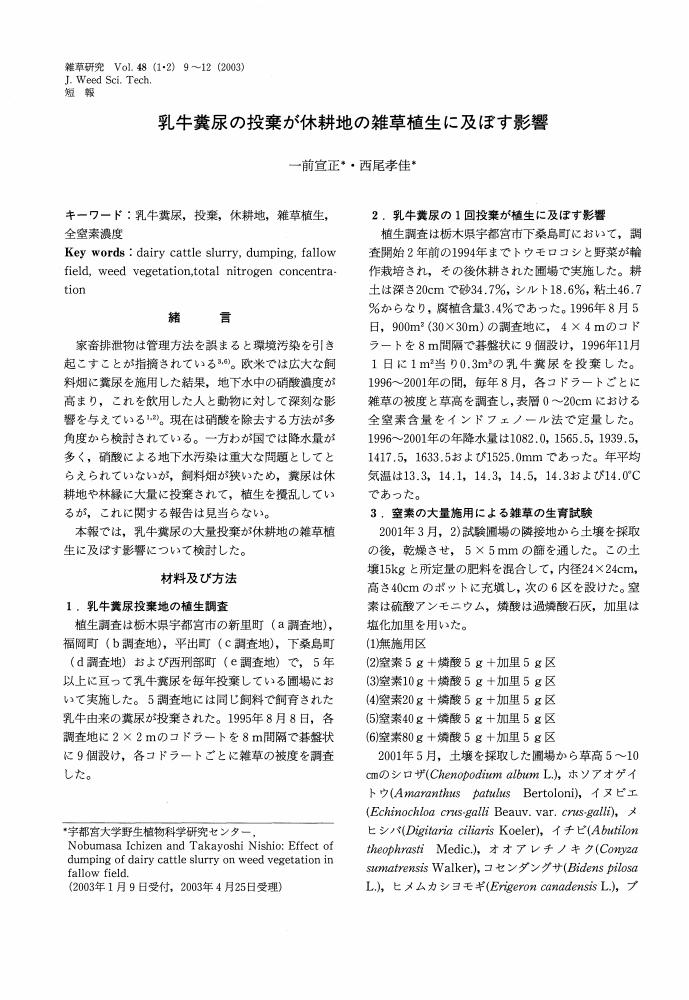1 0 0 0 OA 100 茨城北部および上信越地域における畦畔・農道の形状と植生について
- 著者
- 土田 邦夫 濱村 謙史朗 竹下 孝史 渡邊 泰
- 出版者
- 日本雑草学会
- 雑誌
- 雑草研究. 別号, 講演会講演要旨 (ISSN:0372798X)
- 巻号頁・発行日
- no.36, pp.210-211, 1997-04-17
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 放牧草地におけるエゾノギシギシの乾物消化率, 含有成分とその問題点
- 著者
- 梨木 守 須山 哲男 目黒 良平 加藤 忠司
- 出版者
- 日本雑草学会
- 雑誌
- 雑草研究 (ISSN:0372798X)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.2, pp.118-125, 1991-09-02 (Released:2009-12-17)
- 参考文献数
- 42
放牧草地におけるエゾノギシギシ植物体内の含有成分からみた問題点を明らかにするたあに, 季節ごとのエゾノギシギシの乾物消化率と含有成分 (粗蛋白質, 繊維成分, 無機成分およびNO3-N) を同一草地から採取した牧草 (トールフェスク, シロクローバ) および草地雑草 (メヒシバ, イヌビエ, ウシハコベおよびイヌタデ) と比較した。1) エゾノギシギシの消化率は他の雑草, 牧草と比べて生育ステージに関係なく低かった。このことは高消化性物質の (OCC+Oa) の低含量と低消化性物質のADLの高含量により裏付けられていた。粗蛋白質含量は6月の開花・結実期を除いてトールフェスクや他の雑草より高く推移し, 平均で28%であった。2) エゾノギシギシの無機成分はとくにK, Mgが高含量で推移し, いずれの生育ステージにおいてもトールフェスクや他の雑草と比較して高い傾向を示した。Naを除く他の無機成分の含量も高いが, 一定の傾向は認められなかった。栄養成分比のCa/P比は高く, K/(Ca+Mg) 当量比は低く, さらに反栄養成分のNO3-N は高かった。3) しかし, エゾノギシギシは家畜の嗜好性が低く消化性も低いため, 高含量の粗蛋白質や無機成分は家畜に利用されず, 草地の単位面積当たりの飼料的栄養収量の低下を招く。また, 繁茂が続けば無機成分に対する牧草との競争が強まり, 肥料成分の無効化が懸念される。さらに, 一部のミネラル比の不良や NO3-Nの高含量については, 通常家畜の利用が低いために問題化は少ないと思われるが, 飼料成分的には好ましくない。より高い栄養価の牧草生産を目的とする草地管理の立場からは, エゾノギシギシの存在はその含有成分からみても障害となる。
1 0 0 0 OA 雑草種子の熱による死滅と熱水土壌消毒の抑草効果
- 著者
- 藤井 義晴 大前 義男
- 出版者
- The Weed Science Society of Japan
- 雑誌
- 雑草研究 (ISSN:0372798X)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, pp.114-115, 2001
1 0 0 0 OA ディッシュパック法による植物体から放出される揮発性他感物質の分析・同定
1 0 0 0 サンドイッチ法による雑草および薬用植物のアレロパシー活性の検索
- 著者
- 猪谷 富雄 平井 健一郎 藤井 義晴 神田 博史 玉置 雅彦
- 出版者
- 日本雑草学会
- 雑誌
- 雑草研究 (ISSN:0372798X)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.3, pp.258-266, 1998-10-30
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 7
サンドイッチ法は寒天培地中に包埋した供試植物の乾燥葉から浸出する物質のアレロパシー活性を, 寒天培地上に播種した検定植物の種子根等の伸長抑制程度から判定する方法である。この方法によって, 広島県立大学キャンパスおよび広島大学医学部薬用植物園内で採取した雑草・薬用植物計152種のレタスに対するアレロパシー活性を検定した。その結果, カタバミ, ヒメスイバ, イシミカワ, ヤブラン, メギ, ショウジョウパカマがレタス根長の伸長程度(対照区比)10〜20%と強いアレロパシー活性を示した。上記のような強いアレロパシー活性の認められたもの23種を供試植物とし, 検定植物としてレタスの他にアカクローバー, キュウリおよびイネの4種を用い, サンドイッチ法によって供試植物のアレロパシー活性を検討した。得られたデータの主成分分析の結果, 50%の寄与率を持つ第1主成分は4種の検定植物が共通して示すアレロパシーに対する感受性を表し, かつ検定植物中レタスで最も高い第1主成分の因子負荷量が得られた。これより, サンドイッチ法の検定植物として従来用いられているレタスが適当であることが示唆された。また, 26%の寄与率をもつ第2主成分は, 検定植物のレタス・アカクローバーとキュウリ・イネとで同一物質に対して異なる感受性の方向を示すと考えられた。このことから検定植物間で選択性をもつアレロパシー物質の存在が推定された。
1 0 0 0 OA ショウガ科アルピニア属のチューニングとドメスティケーション
- 著者
- 梅本 信也
- 出版者
- 日本雑草学会
- 雑誌
- 雑草研究 (ISSN:0372798X)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.Supplement, pp.180-181, 2002-04-13 (Released:2009-12-17)
- 著者
- 岡林 哲也
- 出版者
- 日本雑草学会
- 雑誌
- 雑草研究 (ISSN:0372798X)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.49-51, 1980-06-25
1 0 0 0 OA 管理条件の違いが谷戸地形における水田周辺の雑草群落に及ぼす影響
- 著者
- 根本 正之 大塚 広夫
- 出版者
- 日本雑草学会
- 雑誌
- 雑草研究 (ISSN:0372798X)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.3, pp.184-192, 2004-09-30
- 被引用文献数
- 3 4
谷戸地形での雑草群落の構造的な特性とそれを維持してきた管理手法との関係を明らかにするため,同一谷戸内にある農道,畦畔および放棄水田内に発生した雑草の生態的特性と種間相互関係について比較検討した。132地点の方形区から得られた119種のサンプルをTWINSPANによって分類した結果,シバ,チガヤ,オギによって特徴づけられるスタンドがそれぞれ農道,畦畔,放棄水田に対応していることがわかった。地上部が頻繁に破壊される農道は陣地拡大型小型雑草のシバ,シロツメクサの他,木本類や大型雑草の芽生えもあり,不安定なスタンドであった。また年一回の刈取りが行われた畦畔には多くの種が含まれるものの,チガヤが超優占種となり,他種の現存量はヨモギとセイタカアワダチソウを除けば非常に小さかった。一方,放棄水田内ではオギが優占し,それとセリ,スギナやツル性雑草が空間をすみ分けて共存していた。雑草種の潜在的な草丈に基づく植生状態指数(IVC)は雑草群落の持続安定性の指標となるが,本調査地においてはその値は多様性指数と呼応していないことがわかった。
1 0 0 0 OA タイヌビエ種子の休眠と発芽 : 呼吸および呼吸関連酵素活性の変動
- 著者
- 山末 祐二 植木 邦和 千坂 英雄
- 出版者
- 日本雑草学会
- 雑誌
- 雑草研究 (ISSN:0372798X)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.3, pp.188-197, 1987-10-30
- 被引用文献数
- 4
タイヌビエ種子の休眠・発芽における生態的挙動に対する生理・生化学的機構(physiological ecology or ecophy siology)を解明しようとする研究の第一歩として、休眠および休眠覚醒種子の生理的特徴を呼吸およびその関連酵素の活性から検討した。供試種子は農研センター鴻巣試験地由来のタイヌビェから採集したもので、休眠種子は採種後-21℃に貯蔵してその休眠性を維持させ、またこの一部の種子を4℃土壌埋没処理によって休眠覚醒種子を得た(Figure 1)。測定項目は30℃、明条件の発芽床に置床したときのCO_2/0_2交換、エタノール生成、呼吸関連酵素(G6PDH、 6PGDH、 ADH、 ICDH、 cytochrome c oxidase、 polyphenol oxidase、 catalase、 peroxidase)活性の変動であった。休眠種子は置床全期間を通じてCO_2/O_2交換量、すべての酵素活性においてほとんど変動がたく、呼吸代謝的にも全く静止状態にあると考えられた。また、RQ値が1.0付近に維持され、cytochrome c oxidase活性も低いレベルで存在することから(Figures 3,4)、休眠種子は通常の電子伝達系で僅かだから好気呼吸していることが示唆された。しかし、測定された酵素の活性(Figures 4,6)、とくにADH活性は休眠覚醒種子の置床0 hrに比べ比較的大きく、休眠種子内では酵素活性そのものが制限要因でなく、何らかの機作で酵素反応が静止しているものと考えられた。しかし、休眠覚醒種子においては、置床直後からRQ値、ADH活性などが急激に増大し(Figures 3,4)、多量のエタノールが生成されるが(Figure 5)、その後鞘葉、根鞘の突出によって外被が破られ外部酸素が利用可能とたるとADH活性は低下し、代ってcytochrome c oxidase活性が増大し始め、RQ値も1.0に近づいた(Figures 3,4)。したがって、休眠覚醒種子は花被、果皮などを含む外被によって胚に対する酸素の供給が制限されており、置床後から鞘葉だとの突出までの幼芽の生長に必要なエネルギーはアルコール発酵系によって獲得されることが示唆され、この置床初期におけるADH活性の急激な増減は発芽の肉眼的観察以前におこる重要な生理的形質と考えられた。
1 0 0 0 OA セイタカアワダチソウに関する生態学的研究
- 著者
- 榎本 敬 中川 恭二郎
- 出版者
- 日本雑草学会
- 雑誌
- 雑草研究 (ISSN:0372798X)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.4, pp.202-208, 1977-12-25 (Released:2009-12-17)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 1
実験圃場において, セイタカアワダチソウを種子より2年余りにわたって無競争下で生育させた。器官別現存量, 枯死量, 葉面積, 草丈, ロゼット数などを, 個体別に, 期間中20回にわたって測定し, 生産構造, 純生産量などを求めた。その結果, 以下のようなことがわかった。1) 種子より生長を始めた場合は, まず葉と根の生長に重点がおかれ, 次に茎, 花, 地下茎の生長が起こっていることが, 純生産の分配率からわかった。またT/R比, F/W比が大きくて, 1年生草本の値に近く, 茎の伸長速度は小さかった。2) 地下茎から生長を始めた場合は, まず茎への分配率が高くなり, 次いで葉と地下茎への分配率が高くなった。T/R比, F/W比は小さくなり, 年間純生産の地下茎への分配率が高まり, それらは, 完成した群落で得られている値に近づいている。春における茎の伸長速度は極めて大きかった。3) 同化産物は夏から秋にかけて地下茎に蓄えられるが, 冬の間にも茎からの転流が起こっていると考えられ, 春先に地上部へ転流することによって, 急速に地上部が完成された。4) ロゼットは10月に地表に現れ, 春まで数が増加したが, 春から初夏にかけて急激に減少した。この自然間引きは, 草丈の低いものに集中して起こった。5) 同一個体でも, 種子から生長を始めた場合と2年目以後の地下茎からの生長とでは適応戦略が異なっており, このことが本種の定着やその後の生長と繁殖に重要な意味を持っていると考えられる。
- 著者
- 中 精一
- 出版者
- 日本雑草学会
- 雑誌
- 雑草研究 (ISSN:0372798X)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.51-54, 1974-03-25
畑雑草の防除の効率化をはかるために,牽引型除草機の作業条件と作業体系とを組合わせて,機械除草の限界と雑草の種類組成ならびに大豆の生育・収量に及ぼす影響について検討した。1)雑草本数は効果的な条件を連続して適用すると経時的に減少するが,除草効果を高めるには,初期に作用の大きい条件を適用する方式と経時的に作用を増す方式があることが判った。2)ホー除草に比べて機械除草区の雑草本数は0.7〜4.9倍,雑草重は1.8〜16.2倍であり,除草爪の作用深さが増すにしたがって雑草量は減少した。最適作業条件は「作用位置5.cm-作用深さ8cm-連続3回掛け」の条件である。3)除草作用は播種25,45日後の作業で大であり,作業前に比較して雑草本数はそれぞれ68〜81%,43〜84%に減少した。4)作業前の雑草の種類組成は,本数でメヒシバが74%を占めたが,作業回数が増し,雑草総本数が減少するにしたがってメヒシバの占める割合が減少し,ツユクサ,タデ,ヒエの割合が増加した。5)大豆の収量はホー除草に比べて若干低収の傾向があるが,作業条件の間では明確な傾向は認められなかった。
1 0 0 0 OA ナプロアニリドの除草活性の変動と水田土壌の特性
- 著者
- 田中 俊実 小山田 正美
- 出版者
- 日本雑草学会
- 雑誌
- 雑草研究 (ISSN:0372798X)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.2, pp.171-175, 1991-09-02
- 被引用文献数
- 1
全国35地点の水田土壌を採集し、ナプロアニリドの除草活性の変動要因と考えられる土壌特性との関連性について検討した。 1) ナプロアニリドのイヌホタルイに対する除草活性I_<90>値は、35地点の土壌のうち29地点は0.5〜2.0 ppmの範囲にあったが、北海道(南幌)、栃木(宇都宮)、茨城(牛久)、神奈川(藤沢)の土壌で除草活性の低下が認められた。4地点の土壌に共通する特徴は、炭素含有率が高く、ナプロアニリドやNOPに対して強い土壌吸着を示した。 2)土壌特性のうち、炭素含有量、窒素含有量、ナプロアニリドおよびNOPの土壌吸着係数の各要因とナプロアニリドの除草活性との問に高い相関が認められた。 3) ナプロアニリドの除草活性は土色の明度、色相b、彩度との問にも高い相関があり、これらの特性はナプロアニリドおよびNOPの土壌吸着係数との問にも相関が認められた。 4)以上の結果から土壌有機物を多く含む水田土壌では、ナプロアニリドおよびNOPが強く吸着されるため除草活性が低下すると考えられる。また、除草活性の変動を知る方法として土色の識別が利用できる可能性が示された。
- 著者
- 山本 泰由 大庭 寅雄
- 出版者
- The Weed Science Society of Japan
- 雑誌
- 雑草研究 (ISSN:0372798X)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1, pp.33-38, 1977
- 被引用文献数
- 1
主要な畑雑草14種を供試し, 3段階の土壌水分条件下での発生相を調査した。<br>1) 冬雑草では, 高土壌水分区での発生が早い時期から多かった。また, 各草種の発生量は低土壌水分区より高土壌水分区で多かった。<br>2) タデ科雑草では, 発生パターンは3土壌水分区とも大差なかったが, 発生量は高土壌水分区で多かった。<br>3) 夏雑草では, メヒシバ, ザクロソウは高土壌水分区での発生が早い時期から多かった。オヒシバ, スベリヒユは種子埋土直後の発生が, 高土壌水分区ほど多かった。ホナガイヌビユ, コゴメガヤツリは土壌水分によって発生パターンはほとんど変らず, 発生盛期には高土壌水分区ほど発生が多かった。
- 著者
- 内田 成 荒木 順一 青山 良一 西 静雄
- 出版者
- 日本雑草学会
- 雑誌
- 雑草研究 (ISSN:0372798X)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.4, pp.300-306, 1998-12-28
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 1
グリホサートによるスギナ防除に及ぼす生育ステージの影響を検討するため, 1/5000a ポットに生育させたスギナを供試して, グロースチャンバー内で実験を行った。栄養茎の生育初期(草丈3〜13cm・分枝前〜分枝始期), 栄養茎の生育盛期(草丈15〜25cm・分枝盛期), 栄養茎の衰退期(草丈15〜30cm・自然壊死始期)の3時期にグリホサートを処理した結果, スギナ防除には生育盛期の処理が最も有効であった。次に, グリホサートによるスギナ防除に及ぼす土壌水分ストレスの影響を検討するため, 土壌を乾燥させて栄養茎の先端部分が萎凋するまでストレスを与えた試験区と, 通常に灌水を行って土壌を常時適湿状態に保った試験区を設定してグリホサートを処理した結果, ストレスを与えたスギナよりも通常に灌水を行ったスギナの方がグリホサートの影響を強く受けた。
- 著者
- 尹 旻洙 舘内 憲子 〓 凡 與語 靖洋
- 出版者
- The Weed Science Society of Japan
- 雑誌
- 雑草研究 (ISSN:0372798X)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, pp.228-229, 2001
- 被引用文献数
- 2
1 0 0 0 OA 九州中部高原地域の採草用牧草地におけるイヌビエとメヒシバの発生消長
1 0 0 0 OA 乳牛糞尿の投棄が休耕地の雑草植生に及ぼす影響
1 0 0 0 OA シュウ酸を多く含む植物のアレロバシー活性の検索
- 著者
- 猪谷 富雄 藤田 琢也 玉置 雅彦 黒柳 正典 藤井 義晴
- 出版者
- 日本雑草学会
- 雑誌
- 雑草研究 (ISSN:0372798X)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.4, pp.316-323, 1999-12-28 (Released:2009-12-17)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 2 2 2
タデ科, カタバミ科, アカザ科, シュウカイドウ科, バショウ科の体内に比較的高濃度のシュウ酸塩を含むことが知られている植物種 (以後, 本論文ではシュウ酸植物と記す) 計53種を供試し, それらの乾燥葉から滲出する物質のレタス初期生育に対するアレロパシー活性をサンドイッチ (SW) 法によって検定した。SW法では供試植物乾燥葉を0.5%寒天中に包埋後, 検定植物の種子をその上に播種し,20℃で3日後の幼根長と下胚軸長を測定し, その伸長程度 (対照区比) によって供試植物のアレロパシー活性を評価した。その結果, ショウ酸植物にはアレロパシー活性に関して大きな種間差異がみられ, 特にカタバミ科とシュウカイドウ科 Begonia 属において最も活性が強く, ほとんどの種で乾燥葉からの滲出物がレタスの幼根伸長を90%以上抑制した。次に, アレロパシー検定に供試したシュウ酸植物のうち18種の総シュウ酸含量 (水溶性および不溶性を含む) を測定し, 上記SW法における幼根長の対照区比との関係を検討した。その結果, シュウ酸植物の総シュウ酸含量には大きな種間差異が存在し, かつほとんどの植物種については総シュウ酸含量とそのレタスの幼根伸長の対照区比との間には有意な負の相関が認められた。従ってシュウ酸植物の示すアレロパシー活性の一因は体内のシュウ酸であることが示唆された。一方, 数種のシュウ酸植物については上記の相関関係から逸脱するものも存在したので, これら植物のアレコパシー活性には, 植物体中の総シュウ酸の化学的形態の違いや他の抑制物質が関与している可能性が推察された。