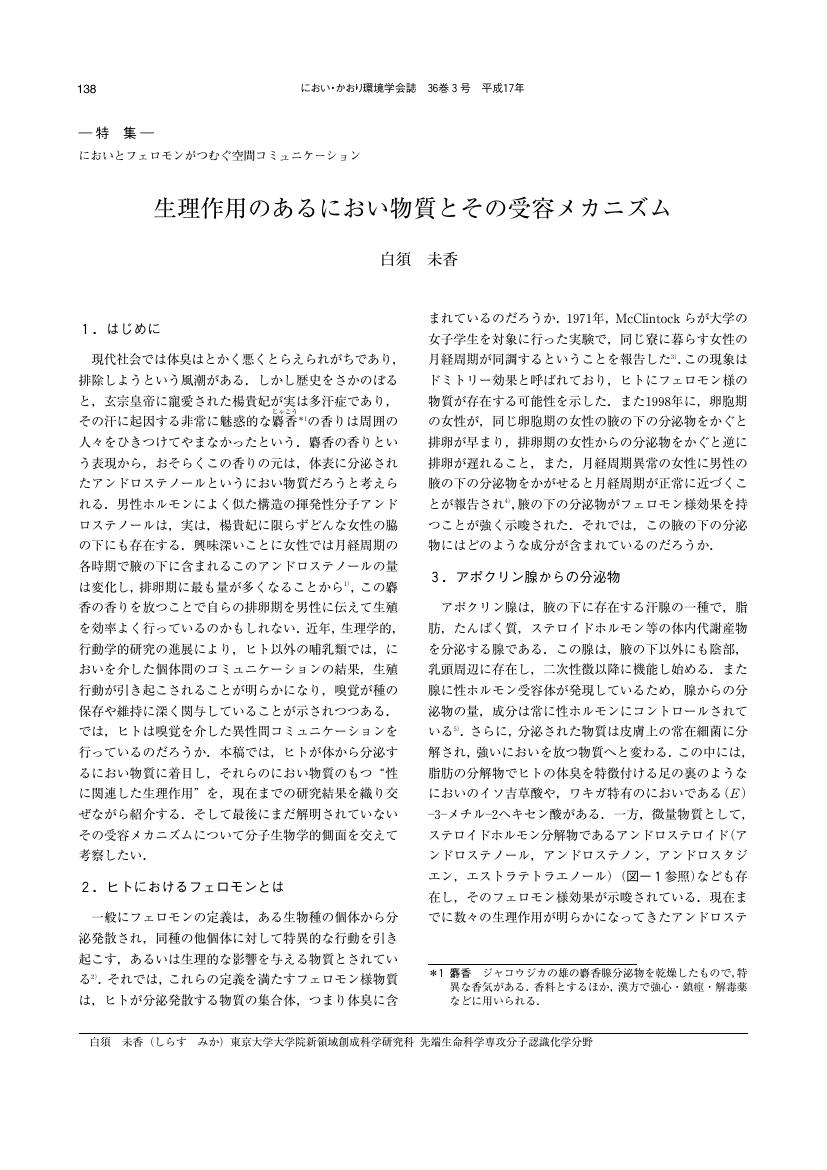314 0 0 0 OA におい嗅ぎガスクロマトグラフィーを用いたハウスダスト中マイクロカプセル化香料の検索
- 著者
- 松元 美里 古賀 夕貴 樋口 汰樹 松本 英顕 西牟田 昂 龍田 典子 上野 大介
- 出版者
- 公益社団法人におい・かおり環境協会
- 雑誌
- におい・かおり環境学会誌 (ISSN:13482904)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.5, pp.319-322, 2020-09-25 (Released:2021-11-14)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 5 3
近年,残香性を高めることを目的としたマイクロカプセル化香料の使用が一般化している.本研究ではハウスダストから甘いにおいを感じることに着目し,におい嗅ぎガスクロマトグラフィー(GC-O)を利用した“におい物質”の検索を試みた.分析の結果,ハウスダストと柔軟剤から共通したにおい物質が検出され,香料がマイクロカプセル化されたことでハウスダストに比較的長期間残留する可能性が示された.
110 0 0 0 OA 感冒後嗅覚障害
- 著者
- 近藤 健二
- 出版者
- 社団法人 におい・かおり環境協会
- 雑誌
- におい・かおり環境学会誌 (ISSN:13482904)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.4, pp.271-277, 2014-07-25 (Released:2018-02-13)
- 参考文献数
- 54
- 被引用文献数
- 1
感冒後嗅覚障害は,上気道のウィルス感染罹患後に上気道炎症状が消失したあとも嗅覚障害が持続する状態である.発症は中高年齢の女性に多く,嗅神経上皮および中枢嗅覚伝導路の傷害による神経性嗅覚障害と考えられている.内視鏡検査,画像検査では異常を認めず,上気道炎罹患後に嗅覚低下を自覚したという病歴が本疾患の診断の決め手となる.基準嗅力検査では中等症以上が大半で高度低下,脱失例が半分以上を占める.治療は本邦では亜鉛製剤,漢方製剤,ステロイド点鼻および内服,ビタミン製剤,代謝改善剤などが使用されている.また嗅覚トレーニングが回復に有効との報告もある.機能回復には長期間(1年以上)かかることが多い.
54 0 0 0 OA 生理作用のあるにおい物質とその受容メカニズム
- 著者
- 白須 未香
- 出版者
- 社団法人 におい・かおり環境協会
- 雑誌
- におい・かおり環境学会誌 (ISSN:13482904)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.3, pp.138-140, 2005 (Released:2005-08-31)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1
20 0 0 0 脊椎動物の嗅覚系の進化的起源と多様化
- 著者
- 大井 雄介 鈴木 大地
- 出版者
- 公益社団法人におい・かおり環境協会
- 雑誌
- におい・かおり環境学会誌 (ISSN:13482904)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.117-126, 2023-03-25 (Released:2023-03-15)
- 参考文献数
- 51
脊椎動物の嗅覚系は,いつ,どのように進化したのだろうか.脊椎動物に最も近縁な無脊椎動物であるホヤやナメクジウオには明確な嗅覚器が認められないため,脊椎動物の嗅覚系は脊椎動物の系統で独自に発達したと考えられる.ヤツメウナギとヌタウナギからなる円口類は,脊椎動物において初期に分岐した系統の生き残りであり,脊椎動物の初期進化を理解するうえで重要な動物群である.嗅覚受容体や嗅細胞,嗅覚回路の比較を通して,円口類と他の脊椎動物の嗅覚系の共通点と相違点が明らかとなり,ここから嗅覚系の起源と多様化が見えてくる.
17 0 0 0 OA 芳香消臭剤の香りの変遷
- 著者
- 矢田 英樹
- 出版者
- 社団法人 におい・かおり環境協会
- 雑誌
- におい・かおり環境学会誌 (ISSN:13482904)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.6, pp.382-389, 2015-11-25 (Released:2019-02-20)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 2
日本で芳香消臭剤が使われ始めて60年あまり,現在では家庭での手軽なにおい対策商品として,また香りを積極的に楽しむ商品として多くの人に認知され多数使用されるようになっている.芳香消臭剤で使用されている香りは時代と共に大きく変化し,1980年頃までは香りには消臭という機能的価値が求められていた.1990年頃以降は機能的価値に加えて香りを楽しむといった情緒的価値も求められるようになってきた.使用される香りの種類も時代と共に大きく変化しており,当初の比較的シンプルな香りから,最近では上質で高級志向の香りが多く使用されるようになってきている.
17 0 0 0 OA 嗅覚が他の感覚知覚に及ぼす影響
- 著者
- 庄司 健
- 出版者
- 社団法人 におい・かおり環境協会
- 雑誌
- におい・かおり環境学会誌 (ISSN:13482904)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.6, pp.424-430, 2006 (Released:2007-09-06)
- 参考文献数
- 13
香りの情報が同時に取り込んだ他の感覚の判断に与える影響についてまとめた.香りの違いによりモノの重さや温冷の判断,日常使用されている化粧クリームの使用感や肌実感にも違いがみられることが,実験により明らかになってきた.香りの質的な特徴が,こうした香りの働きを生み出すことに影響していると考えられた.本研究で検討した感覚の判断を変化させる香りの働きを活用することで,より豊かで満足感の高い生活に役立てることが出来るのではないかと考えている.
16 0 0 0 OA 紅茶キャラクターホイールの作成と紅茶特徴の可視化
- 著者
- 大野 敦子
- 出版者
- 公益社団法人におい・かおり環境協会
- 雑誌
- におい・かおり環境学会誌 (ISSN:13482904)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.5, pp.344-350, 2014-09-25 (Released:2018-02-13)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 3
紅茶の特徴は香り・味・水色の3つの要素から成る.その多彩な特徴の捉え方や伝え方は人によって様々であり,特に香りや味を言葉で表現し,多くの人に伝えることは非常に難しい.よって,紅茶の複雑であいまいな特徴を,製品開発や品質検査においても的確に評価するために,紅茶の特徴を明確に表す評価用語を作成した.また,日本の消費者に紅茶の特徴をわかりやすく伝えるためのツールとして有用である.我々は,紅茶の香り・味・水色の特徴について,より多くの人と共有し,伝達するためのコミュニケーションツールとしての紅茶キャラクターホイールを作成し,その効果を示した.また,紅茶キャラクターホイールに基づいて紅茶の特徴を可視化した.
16 0 0 0 OA 茶の香り
- 著者
- 澤井 祐典
- 出版者
- 社団法人 におい・かおり環境協会
- 雑誌
- におい・かおり環境学会誌 (ISSN:13482904)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.3, pp.179-186, 2007 (Released:2008-03-22)
- 参考文献数
- 17
茶の香気は主に3つの要素から成り立っている.(Z)-3-ヘキセノール,(E)-2-ヘキセノール,ノナナール,(Z)-3-ヘキセニルヘキサノエートなどは若葉の青臭の原因成分であり,2,5-ジメチルピラジン(ピラジン類)などは香ばしい焙煎香の原因成分である.紅茶やウーロン茶に多く含まれるリナロール,ゲラニオール(テルペンアルコール)は花や果実の香りの成分である.このほか,玉露やてん茶には特別にジメチルスルフィドが多く含まれており,おおい香(葭簀などで遮光して育成することにより発生する)の海苔様の香りの原因成分である.
13 0 0 0 OA 他の感覚が嗅覚知覚に及ぼす影響
- 著者
- 坂井 信之
- 出版者
- 社団法人 におい・かおり環境協会
- 雑誌
- におい・かおり環境学会誌 (ISSN:13482904)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.6, pp.431-436, 2006 (Released:2007-09-06)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 1
本稿では,まず,においを溶かした溶液の色やにおい源をイメージさせる写真などの視覚情報が,嗅覚情報処理にどのような影響を与えるかということを調べた研究を紹介した.さらに,これらの影響について,視覚と嗅覚の連合学習,視覚による事物の認知と嗅覚に対するトップダウン処理,視覚による認知の誘導とそれと一致するにおいの側面の強調という3つの考え方から解釈した.最後に,視覚以外の感覚がにおいの知覚や認知に与える影響を調べた研究を紹介し,人間のにおい認知が非常に複雑に行われている過程を理解することによって,におい世界の個人差の理解へつながる可能性を示した.
11 0 0 0 OA ワインの香りの評価用語
- 著者
- 後藤 奈美
- 出版者
- 公益社団法人におい・かおり環境協会
- 雑誌
- におい・かおり環境学会誌 (ISSN:13482904)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.6, pp.390-396, 2013-11-25 (Released:2017-10-11)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 2
ワインには非常に多くの種類がある.多彩なワインの特徴を消費者に伝えたり,専門家が品質を評価したりするには,様々な評価用語が使用される.有名なワインのアロマホイールは,ワインの香りを認識し,表現するための標準的な用語を提供することを目的としている.一方,品質評価用語では,その原因を示す用語が多いことが特徴と言える.ワインの香りは,原料ブドウ,発酵,貯蔵・熟成など,種々の要因の影響を受ける.ワインの香りにはまだ解明されていない点が多くあるが,これまでに明らかにされている成分についても紹介する.
11 0 0 0 OA 呼気中の水素・メタン —消化管の活動を診る—
- 著者
- 瓜田 純久 杉本 元信 三木 一正
- 出版者
- 公益社団法人におい・かおり環境協会
- 雑誌
- におい・かおり環境学会誌 (ISSN:13482904)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.2, pp.99-104, 2006 (Released:2006-10-27)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 1 1
現代の医療では非侵襲的に多くの情報を得ることが求められている.採血さえも不要な呼気試験は,検査方法を工夫すると,多くの消化管情報を得ることができるが,その中心は水素・メタンガスの測定である.空腹時の呼気中水素は消化管発酵反応の指標と考えられているが,その再現性は低く,解釈は難しい.そこで,試験食を負荷して呼気中水素・メタンガスの経時的な変化から病態を評価する方法が一般的である.非吸収型の炭水化物,食物繊維などは小腸で吸収されず,大部分が大腸へ到達し,腸内細菌の発酵反応で分解される.この際発生する水素・メタンガスの時間,量からガス発生部位を推定し,消化管通過時間,細菌の異常増殖を診断することができる.発酵生成物が腹部症状を惹起する場合もあり,消化管での発酵の程度を把握することは重要である.今回,臨床現場における水素・メタンガス測定の実際を述べる.
8 0 0 0 OA においを介した植物間コミュニケーション
- 著者
- 細川 聡子
- 出版者
- 社団法人 におい・かおり環境協会
- 雑誌
- におい・かおり環境学会誌 (ISSN:13482904)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.3, pp.153-155, 2005 (Released:2005-08-31)
- 参考文献数
- 20
8 0 0 0 OA 生物そのものを利用したバイオセンサ—線虫嗅覚によるがん診断—
- 著者
- 広津 崇亮
- 出版者
- 社団法人 におい・かおり環境協会
- 雑誌
- におい・かおり環境学会誌 (ISSN:13482904)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.3, pp.191-199, 2015-05-25 (Released:2019-02-20)
- 参考文献数
- 48
微量のにおい物質の検知には,従来は物理・化学的手法が用いられてきたが,感度,選択性を追求すると大型化,高コスト化を招く問題があった.そこで近年注目されているのが,生物の嗅覚の高感度性,高選択性を生かしたバイオセンサである.その中には,生物の嗅覚機構を模倣するセンサ,生物の機構や設計思想を活用するセンサが含まれるが,本稿では生物そのものを利用するセンサについて紹介する.最近線虫C. elegansががんのにおいを高精度に識別できることが発見された.線虫嗅覚を用いたがん診断技術(n-nose)は,高感度,低コスト,非侵襲性,簡便,早期がんを発見できるなど,これまでのがん検査システムを変える可能性を秘めている.
7 0 0 0 OA ビールのオフフレーバーに関する近年の知見
- 著者
- 岸本 徹
- 出版者
- 社団法人 におい・かおり環境協会
- 雑誌
- におい・かおり環境学会誌 (ISSN:13482904)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.1, pp.13-20, 2013-01-15 (Released:2017-10-11)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 1 2
ビールの製造工程,および製造後の酸化によってビール中に生成するオフフレーバーについて解説した.ビールのオフフレーバーには原料,水に由来するもの,仕込工程,発酵工程中に生成してくるもの,缶やビンに詰めた後の保存後に生成してくる酸化劣化臭がある.それらの中にはSH基をもつ低閾値化合物のように,ビール中にng/L程度しか含まれない微量成分もあるが,近年では分析機器が発達し,定量することも可能となった.ビールのオフレーバーとして過去から近年,着目されている化合物について述べた.
7 0 0 0 OA 化粧と感情の心理学的研究概観
- 著者
- 阿部 恒之 高野 ルリ子
- 出版者
- 社団法人 におい・かおり環境協会
- 雑誌
- におい・かおり環境学会誌 (ISSN:13482904)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.5, pp.338-343, 2011-09-25 (Released:2016-04-01)
- 参考文献数
- 38
- 被引用文献数
- 1 2
化粧に関する心理学的研究は,1980年代から盛んになってきた.化粧は慈しむ化粧(スキンケア)と飾る化粧(メーキャップ・フレグランス)に大別されるが,感情に及ぼす影響に関する研究は,そのいずれもが高揚と鎮静をめぐるものであった. 喩えるなら,メーキャップによって心を固く結んで「公」の顔をつくって社会に飛び出し,帰宅後にはメーキャップを落とし,スキンケアをすることで心の結び目を解いて「私」の顔に戻るのである.すなわち,化粧は日常生活に組み込まれた感情調節装置である.
7 0 0 0 OA 生活空間に存在するリスク低減を目指した可視光応答型光触媒の開発
- 著者
- 砂田 香矢乃 橋本 和仁 宮内 雅浩
- 出版者
- 公益社団法人におい・かおり環境協会
- 雑誌
- におい・かおり環境学会誌 (ISSN:13482904)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.3, pp.174-183, 2013-05-25 (Released:2017-10-11)
- 参考文献数
- 13
紫外光しか吸収しない酸化チタンをベースに,その表面に銅イオンや鉄イオンからなるアモルファス状のクラスター助触媒を担持することで,室内光下でも十分な光触媒活性を発揮する新規な可視光応答型光触媒材料を創製した.それらの材料は,可視光下で空気浄化や抗菌・抗ウイルス,セルフクリーニングなど多機能な性能を示した.抗菌・抗ウイルス効果を中心に病院や空港で製品に近い材料で実証試験を行うなど,光触媒製品のマーケット拡大をめざした取組みについても紹介する.
6 0 0 0 OA 香り作りの材料を知る
- 著者
- 堀内 哲嗣郎
- 出版者
- 社団法人 におい・かおり環境協会
- 雑誌
- におい・かおり環境学会誌 (ISSN:13482904)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.4, pp.187-192, 2005 (Released:2005-10-07)
- 参考文献数
- 3
6 0 0 0 OA 放屁モニター -消化管活動の指標としてのおなら-
- 著者
- 寺井 岳三 植田 秀雄 行岡 秀和
- 出版者
- 社団法人 におい・かおり環境協会
- 雑誌
- におい・かおり環境学会誌 (ISSN:13482904)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.5, pp.275-279, 2005 (Released:2005-11-25)
- 参考文献数
- 10
放屁の有無の測定は,腸管運動の機能の評価において重要である.とくに手術後の患者では,腸管の動きが抑制されるため,放屁の出現は,腸管の運動が回復したことを正確に示し,経口摂取開始の指標となる.放屁を客観的に評価する放屁モニターの,指標として用いることができるガスは,大気中にほとんど含まれず,放屁中に必ず存在する事が必要条件であり,炭酸ガス(CO2)と水素(H2)が適する.CO2は呼気に5%含まれるため,部屋の換気や部屋にいる人数により大気中のCO2は変動するが,H2は,呼気中に含まれる濃度がCO2に比べるとはるかに少ないため,測定に影響が少ない.H2を指標とした小型で,簡便な放屁モニターを試作し,CO2アナライザーと比較した結果,信頼性が高く,CO2アナライザーより優れていた.今後,H2を指標とした放屁モニターの臨床での実用化が期待される.
6 0 0 0 OA 日本酒の成分と香味
- 著者
- 小川 治雄
- 出版者
- 社団法人 におい・かおり環境協会
- 雑誌
- におい・かおり環境学会誌 (ISSN:13482904)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.5, pp.330-339, 2015-09-25 (Released:2019-02-20)
- 参考文献数
- 36
- 被引用文献数
- 1
日本酒の香りや旨みについて概説した.多種の日本酒,すなわち精米歩合や酵母種,醸造法,醸成期間などの醸造工程の異なるタイプの日本酒が対象となった.日本酒の成分と日本酒の持つ特有の香りや旨味の特徴との関わりをまとめた.酸度やアルコール類,カルボニル類,エステル類,アミノ酸,フルフラールの定量値などにより,それぞれのタイプの香味を伴った日本酒が特徴づけられた.アルコール成分と健康についても触れた.試飲からも日本酒の成分とその特徴が確認された.
6 0 0 0 OA 哺乳動物の嗅覚コミュニケーション
- 著者
- 宮崎 雅雄
- 出版者
- 公益社団法人におい・かおり環境協会
- 雑誌
- におい・かおり環境学会誌 (ISSN:13482904)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.1, pp.25-33, 2016-01-25 (Released:2020-09-01)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 1
多くの動物は,生活環境に自分のにおいを残して縄張りを主張する.一方,自分以外の動物に残されたにおいを嗅ぎつけた動物は,におい主の種や性,年齢,個体情報を識別する.これはにおい主の情報が自身の生存や種の存続に必要不可欠だからである.例えばにおい主が敵のものであれば忌避することで自身の生存につながり,同種の異性で繁殖適期の個体であると分かれば,近隣を探すことで子孫を残すためのパートナーが見つかり,種が存続する.また動物個体から分泌されるある種の化学物質は,同種の仲間に特定の行動を誘起したり内分泌系を変化させる生理活性を有し,フェロモンと称される.においやフェロモンは自分が不在の時も生活空間に残すことが可能で自己の情報を相手に伝える媒体として利用できる.このように動物の嗅覚は,種間,異種間コミュニケーションにとても重要である.本稿では,哺乳動物のにおい,フェロモンの受容機構から筆者らが研究しているネコの嗅覚コミュニケーションについて紹介する.