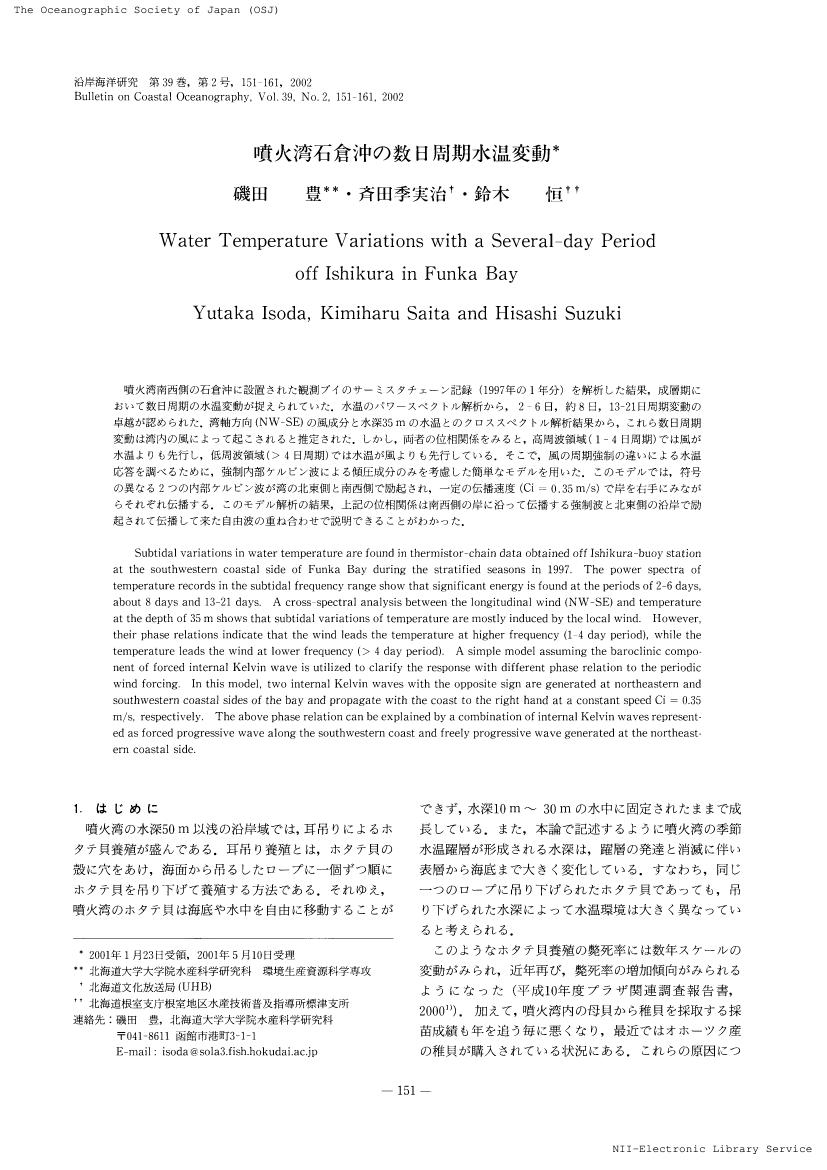47 0 0 0 OA 漂着鯨類の情報収集・蓄積と社会的活用
- 著者
- 石川 創
- 出版者
- 日本海洋学会 沿岸海洋研究会
- 雑誌
- 沿岸海洋研究 (ISSN:13422758)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.2, pp.85-90, 2008 (Released:2020-02-12)
- 著者
- 門谷 茂
- 出版者
- 日本海洋学会
- 雑誌
- 沿岸海洋研究 (ISSN:13422758)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.2, pp.151-155, 2006-02-28
瀬戸内海では,他の人口集中沿岸海域と同様に1950年代以降,流入する河川の栄養塩濃度(とりわけ,リン・窒素)は,上昇を続けその結果として,海域の栄養塩濃度を急上昇させた.とりわけ,60年代後半から赤潮の発生が頻繁に起こるようになり,1976年には年間299回を数えるまでになった.富栄養化は基礎生産の増大をもたらすだけでなく,光合成によって作られた膨大な有機物の多くが水柱内で消費されることなく海底に沈積し,そこで微生物分解されることにより溶存酸素濃度を減少させ,貧酸素水塊を作り出すことにも繋がった.この間の瀬戸内海における富栄養化を進行させてきたのは,陸からもたらされた窒素やリンであることは種々の環境モニター結果から明らかである.瀬戸内海の生物過程において決定的な役割を演じているのは,やはり陸上からの栄養塩負荷であった.一方,近年重要視されてきた外洋起源と言われる窒素やリンが,瀬戸内海の生物生産にどのように寄与しているかについての答えを得ることは,今後の環境行政を考える上でも,沿岸域の生物生産構造を理解する上でも極めて重要である.今後は,溶存無機態の窒素やリンがどのようなタイミングでどこからどれだけ流入しているのかについて,詳細に明らかにする必要がある.
20 0 0 0 OA 噴火湾 石倉沖の 数 日周期水温 変動
- 著者
- 磯田 豊 斉田 希実治 鈴木 恒
- 出版者
- 日本海洋学会 沿岸海洋研究会
- 雑誌
- 沿岸海洋研究 (ISSN:13422758)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.2, pp.151-161, 2002 (Released:2020-02-12)
- 被引用文献数
- 1
12 0 0 0 OA 三陸の沿岸漁業を支えるブルーインフラの大津波後の復興過程*
- 著者
- 小松 輝久 大瀧 敬由 佐々 修司 澤山 周平 阪本 真吾 サラ ゴンザル 浅田 みなみ 濱名 正泰 村田 裕樹 田中 潔
- 出版者
- 日本海洋学会 沿岸海洋研究会
- 雑誌
- 沿岸海洋研究 (ISSN:13422758)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.117-127, 2017 (Released:2020-02-12)
- 参考文献数
- 41
2011年3月11日の東日本大震災は,東北地方の沿岸に甚大なる被害を与えた.津波は,沿岸漁業の社会的インフラである,港,市場,漁船,養殖筏はもちろんのこと,魚介類の再生産の基盤である沿岸のエコトーンであり自然的インフラである藻場など(本論文ではブルーインフラと定義)にも被害を及ぼした可能性があった.そこで,岩手県大槌湾および宮城県志津川湾において,藻場の被害状況とその後の変化を調べた.海藻藻場の被害は大きくなかったが,2014年からは震災後に加入したウニによる磯焼けが生じており,積極的な駆除を行う必要がある.砂地に生育するアマモでは,津波の波高が大きくなったために壊滅的な被害を受けた湾奥部では,2011年6月に埋土種子から実生に生長しており,アマモ場の回復が始まっていた.また,地形的に津波による被害を受けにくい湾央や湾口にあるアマモ場は残っていた.これらのアマモ場は種子供給源になるため,次の大津波に備えて保護することが望ましい.津波と地盤沈下により埋め立てで失われていた塩性湿地や干潟というブルーインフラは再生したが,復旧の埋立や巨大防潮堤などの工事で消滅した.繰り返される将来の大津波に備え,次世代のために持続的で健全な海洋環境および社会を育む沿岸域を実現するという視点から,ブルーインフラの回復を織り込んだグランドデザインを平時につくる必要がある.
- 著者
- 西 隆一郎
- 出版者
- 日本海洋学会
- 雑誌
- 沿岸海洋研究 (ISSN:13422758)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.2, pp.97-103, 2008-02-29
一般の海域利用者は,漂着物ゴミのない綺麗で健康的な海岸を良い海岸環境と評価しがちである.筆者も良好な海岸環境を求めて10年間以上海岸清掃を続け,その知見に基づいて海岸廃棄物の定性的な考察だけを行ったことがある(西ほか,1996).しかし,漂着物(ゴミ)の管理を行うには,定量的な解析法が必要である.そこで,本論文では沿岸域の漂着物に関する問題のうち,特に陸起源漂着物の定量的評価法について考察する.つまり,陸起源物質の移動経路である山地〜河川〜河口〜沿岸域に渡る水系でのゴミ移動を取り扱う手法を提案する.ただし,漂着物収集に携わる一般市民レベルでも使いやすい解析手法とするために,土木工学で用いられる流砂系・漂砂系での土砂収支と言われる巨視的なアプローチを適用する.なお,本数値解析手法は,山地,河川,沿岸領域で収集されたゴミデータに基づいて有効性が検証されるべきであるが,この点に関しては,実際に陸起源漂着物(ゴミ)を調査している研究者の応用に委ねることにする.
2 0 0 0 OA 沿岸海洋学との58年-潮汐残差流から里海まで-
- 著者
- 柳 哲雄
- 出版者
- 日本海洋学会 沿岸海洋研究会
- 雑誌
- 沿岸海洋研究 (ISSN:13422758)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.2, pp.111-115, 2014 (Released:2020-02-12)
- 参考文献数
- 15
小学校1年生で「荒神川の潮の研究」を始めてから現在まで58年間,自分の沿岸海洋学との関わりを振り返る.
2 0 0 0 OA 瀬戸内海東部海域の栄養塩低下とその低次生物生産過程への影響
- 著者
- 多田 邦尚 西川 哲也 樽谷 賢治 山本 圭吾 一見 和彦 山口 一岩 本城 凡夫
- 出版者
- 日本海洋学会 沿岸海洋研究会
- 雑誌
- 沿岸海洋研究 (ISSN:13422758)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.1, pp.39-47, 2014 (Released:2020-02-12)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 6
瀬戸内海東部海域における過去40年間の海水中の栄養塩濃度減少の検証とその低次生物生産過程への影響について,著者らのグループが得た知見を総合して考察した.瀬戸内海では過去,高度経済成長期には著しく富栄養化が進行していたが,1973年に施行された瀬戸内法により,P の発生負荷量は1980年以降,N は1990年後半以降削減された.しかし,播磨灘東部海域の海水中のTN,TP 濃度には直接反映されていない.一方,栄養塩濃度は1970年以降確実に低下しており,特にDIN 濃度は1990年以降も減少傾向にある.これは,主には瀬戸内法の効果と考えられるが,それだけでは説明できない.おそらく,海底堆積物からの栄養塩の溶出量の減少が大きく関与している可能性が考えられた.この栄養塩濃度減少に対する植物プランクトン群集の応答については,その生物量の低下傾向は認められないが,その種組成の変化が認められた.
- 著者
- 堀口 敏宏 趙 顯書 白石 寛明 柴田 康行 森田 昌敏 清水 誠 陸 明 山崎 素直
- 出版者
- 日本海洋学会沿岸海洋研究部会
- 雑誌
- 沿岸海洋研究 (ISSN:13422758)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.2, pp.7-13, 2000-02
- 被引用文献数
- 6
船底塗料などとして使用されてきた有機スズ化合物(トリブチルスズ(TBT)及びトリフェニルスズ(TPT))によって,ごく低濃度で特異的に誘導される腹足類のインポセックスのわが国における経年変化と現状の概略を種々の野外調査結果などに基づいて記述した.1990~1991年の汚染レベルに比べると近年の海水中の有機スズ濃度は低減したと見られるものの,イボニシの体内有機スズ濃度の低減率は海水中のそれよりも緩やかであり,またその低減率が海域により異なっていた.また環境中の有機スズ濃度の相対的な減少が観察されるものの,イボニシのインポセックス発症閾値をなお上回る水準であるため,インポセックス症状については全国的に見ても,また定点(神奈川県・油壺)観察による経年変化として見ても,十分な改善が認められなかった.この背景には,国際的には大型船舶を中心になお有機スズ含有塗料の使用が継続していることとともに,底泥からの再溶出の可能性及びイボニシの有機スズに対する感受性の高さなどが関連していると推察された.
2 0 0 0 IR 流れ藻葉上動物群集の形成パターン(シンポジウム:海洋生物の漂流-沿岸からの輸送と生態-)
- 著者
- 青木 優和 田中 克彦 熊谷 直喜 伊藤 敦 サバン ベギネール 小松 輝久
- 出版者
- 日本海洋学会沿岸海洋研究部会
- 雑誌
- 沿岸海洋研究 (ISSN:13422758)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.2, pp.137-140, 2009
東シナ海から黒潮流域圏を漂流する流れ藻の葉上動物について2002年から2007年の春期に白鳳丸および淡青丸での航海調査を行った.沖合域で採集された流れ藻では,採集場所に拘らず葉上動物群集の組成が類似する傾向があり,群集多様度はガラモ場葉上動物相と比して一般的に低く,沖合のものほど低い傾向が認められた.優占動物上位は主に等脚類と端脚類で,最も卓越し海域と流れ藻の種類によらず出現した種がナガレモヘラムシだが,海域によってその個体群組成は異なった.端脚類のうちヨコエビ類で優占したのは基質藻体を食するヒゲナガヨコエビ科およびモクズヨコエビ科の1-2種だった.ワレカラ類でも沖合では特定の1-2種が優占し,とくに東シナ海で卓越したCaprella andreaeでは,その個体群組成から過大な魚類捕食圧が示唆された.流れ藻葉上動物群集の組成や個体群構造の特徴は,流れ藻の漂流期間や周辺環境を知るための手がかりとなる可能性がある.
- 著者
- 大島 慶一郎 小野 純 清水 大輔
- 出版者
- 日本海洋学会
- 雑誌
- 沿岸海洋研究 (ISSN:13422758)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.2, pp.115-124, 2008-02-29
オホーツク海の陸棚上の流速場をよく再現している3次元海洋循環モデルを用いて,粒子追跡実験を行った.モデルは日々の風応力と月平均の海面熱フラックスで駆動されている.アムール川からの汚染物質等の漂流・拡散を想定して,アムール河口に起源を持つ海水の0m層と15m層における粒子追跡実験を行った.15m層では,粒子を投下する月・年に拘らず,10月一気に東樺太海流が強まるのに伴って粒子はサハリン東海岸沖を南下し始め,12〜1月に北海道沖に到達する.表層0mでは,海流だけでなく風によるドリフトの効果が加わり,粒子の挙動は年によって異なる.沖向きの風が強い年ほど,粒子は東樺太海流の主流からはずれてしまい,北海道沖までは到達しない傾向が強くなる.2006年2〜3月に知床に漂着した油まみれの海鳥の死骸の起源を探るため,後方粒子追跡実験を行った.その結果,海鳥は北方から,おそらくはサハリン東岸のどこかから東樺太海流に乗って知床に漂着したであろうことが示唆された.
1 0 0 0 OA 放射性物質と海洋生態系
- 著者
- 石丸 隆 伊藤 友加里 神田 穣太
- 出版者
- 日本海洋学会 沿岸海洋研究会
- 雑誌
- 沿岸海洋研究 (ISSN:13422758)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.143-149, 2017 (Released:2020-02-12)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1
2011年3月11日の福島第一原発事故により大量の放射性物質が海洋生態系に拡散した.我々は同年7月以降,ほぼ半年ごとに練習船による調査を行ってきた.プランクトンネット試料のCs-137濃度は時間とともには低下せず,大きく変動した.原因は,オートラジオグラフィーにより確認された高セシウム線量粒子の混在であると考えられる.ベントスでは,事故当初は原発近傍とその南側で高い濃度のCs-137が観察された.その後原発近傍では低下したが,原発南側の岸よりで下げ止まっている.2014年12月から1年半の間,原発近傍の水深約25m の定点で,大量ろ過器により採集した懸濁粒子のCs-137濃度は約2,000Bq/kg-dry で変化したが有意な低下の傾向はなく,またCs-137濃度全体に対する高線量粒 子の寄与は大きかった.陸域からの高線量粒子の供給が続いていると考えられるが,高線量粒子は不溶性であることから魚類に移行することはない.
1 0 0 0 OA 生物の 分野 か ら見 た瀬戸 内海 の 海洋環境
- 著者
- 村上 彰男
- 出版者
- 日本海洋学会 沿岸海洋研究会
- 雑誌
- 沿岸海洋研究 (ISSN:13422758)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.2, pp.31-36, 1972 (Released:2020-02-12)
1 0 0 0 OA 伊 勢 湾 ・ 三 河 湾 の 地 形 ・ 地 質
- 著者
- 桑原 徹
- 出版者
- 日本海洋学会 沿岸海洋研究会
- 雑誌
- 沿岸海洋研究 (ISSN:13422758)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.69-77, 1977 (Released:2020-02-12)
1 0 0 0 OA 底 泥 に 残 さ れ た 鉛 汚染 の 歴 史
- 著者
- 平尾 良光
- 出版者
- 日本海洋学会 沿岸海洋研究会
- 雑誌
- 沿岸海洋研究 (ISSN:13422758)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.2, pp.136-145, 1988 (Released:2020-02-12)
1 0 0 0 OA 富山湾におけるブリ,スルメイカ,ホタルイカの 漁況と日本海の海洋環境との関係
- 著者
- 小塚 晃 北川 慎介 南條 暢聡 辻本 良
- 出版者
- 日本海洋学会 沿岸海洋研究会
- 雑誌
- 沿岸海洋研究 (ISSN:13422758)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.1, pp.81-86, 2020 (Released:2020-09-12)
- 参考文献数
- 20
富山湾では400年以上も前から定置漁業が盛んであり,暖水性の回遊魚を中心に漁獲してきた.主要漁獲物であるブリ, スルメイカおよびホタルイカについて,漁獲変動と海洋環境との関係を調べた.ブリでは,日本周辺海域の海水温の上昇 に伴い分布域がオホーツク海まで拡大し,2000年代後半以降に北海道の漁獲量が急増した.また,南下期である冬季の富 山湾への来遊状況は,12月に山形県沖が暖かく能登半島北西沖が冷たい水塊配置のときに好漁となる傾向が認められた. 富山県沿岸で1月~3月に漁獲されるスルメイカは,日本海北部海域の1月期における水温が低い年に南下経路が沿岸よ りとなり,漁獲量が多くなる傾向があった.日本海北部海域の水温上昇は,冬季の富山湾へのスルメイカの来遊量を減少 させる要因となると考えられる.ホタルイカでは,2008年まで,日本海における主産卵場である山陰沖の5月の水温が高 いと,翌年の富山湾漁獲量が多くなる傾向が認められた.しかし,2009年以降,山陰沖水温環境指標と富山湾漁獲量との 間の関係性が悪くなり,その要因の解明が必要となっている.これらの種は,東シナ海や日本海を産卵場とし,日本海を 広く回遊する.対馬暖流の勢力は,加入量や仔稚魚の分散にも関与し,富山湾への来遊は,日本海の水温や水塊配置に大 きく依存している.地球温暖化やレジームシフトによる海洋環境の変化により,日本海や東シナ海において産卵場や回遊 状況が変化し,長期的に富山湾の漁況が変化していくことが懸念される.
1 0 0 0 OA 瀬戸内海における栄養塩濃度等の水質変化とその要因
- 著者
- 阿保 勝之 秋山 諭 原田 和弘 中地 良樹 林 浩志 村田 憲一 和西 昭仁 石川 陽子 益井 敏光 西川 智 山田 京平 野田 誠 徳光 俊二
- 出版者
- 日本海洋学会 沿岸海洋研究会
- 雑誌
- 沿岸海洋研究 (ISSN:13422758)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.2, pp.101-111, 2018 (Released:2020-02-12)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 4
1972~2013年の約40年間にわたる浅海定線調査データをもとに,瀬戸内海における栄養塩濃度などの水質や海洋環境の長期変化傾向を明らかにした.水温は温暖化の影響で上昇しており,特に秋季の上昇率が高かった.透明度は,大阪湾を除く瀬戸内海では1990年代以降,大阪湾では2000年以降に上昇した.瀬戸内海の栄養塩濃度は減少傾向であった.DIN濃度は,大阪湾を除く瀬戸内海では1970年代に急激に低下した後,2000年代以降に再び低下が見られた.大阪湾では,1970年代の低下は見られなかったが,1990年以降に大幅な低下が見られた.DIP 濃度は,1970年代に高かったが1980年頃に低下し,大阪湾を除く瀬戸内海ではその後は横ばい,大阪湾の表層ではその後も低下を続けた.栄養塩濃度の低下については,陸域負荷削減が大きく影響しているが,底泥や外海からの供給量低下や近年の全天日射量の増加も栄養塩濃度の低下に影響を及ぼしていると考えられた.
1 0 0 0 OA 高解像度センサ(SAR)
- 著者
- 磯口 治
- 出版者
- 日本海洋学会 沿岸海洋研究会
- 雑誌
- 沿岸海洋研究 (ISSN:13422758)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.1, pp.11-16, 2016 (Released:2020-02-12)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1
合成開口レーダ(SAR)は高解像度で海面粗度を画像化するセンサであり,沿岸域の海上風,波浪,潮目等を高解像度 で検出可能である.本報告ではそれらのパラメータの検出メカニズムおよび,沿岸域への応用事例について紹介する.
1 0 0 0 OA 大阪湾のエスチュアリー循環流と貧酸素水塊
- 著者
- 中嶋 昌紀 藤原 建紀
- 出版者
- 日本海洋学会 沿岸海洋研究会
- 雑誌
- 沿岸海洋研究 (ISSN:13422758)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.2, pp.157-163, 2007 (Released:2020-02-12)
- 被引用文献数
- 5
1 0 0 0 OA 海岸工学の諸問題
- 著者
- 本間 仁
- 出版者
- 日本海洋学会 沿岸海洋研究会
- 雑誌
- 沿岸海洋研究 (ISSN:13422758)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.12-13, 1962 (Released:2020-02-12)
1 0 0 0 OA 噴火湾沿岸域の 水温変動
- 著者
- 佐藤 千鶴 磯田 豊 清水 学
- 出版者
- 日本海洋学会 沿岸海洋研究会
- 雑誌
- 沿岸海洋研究 (ISSN:13422758)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.1, pp.73-83, 2004 (Released:2020-02-12)