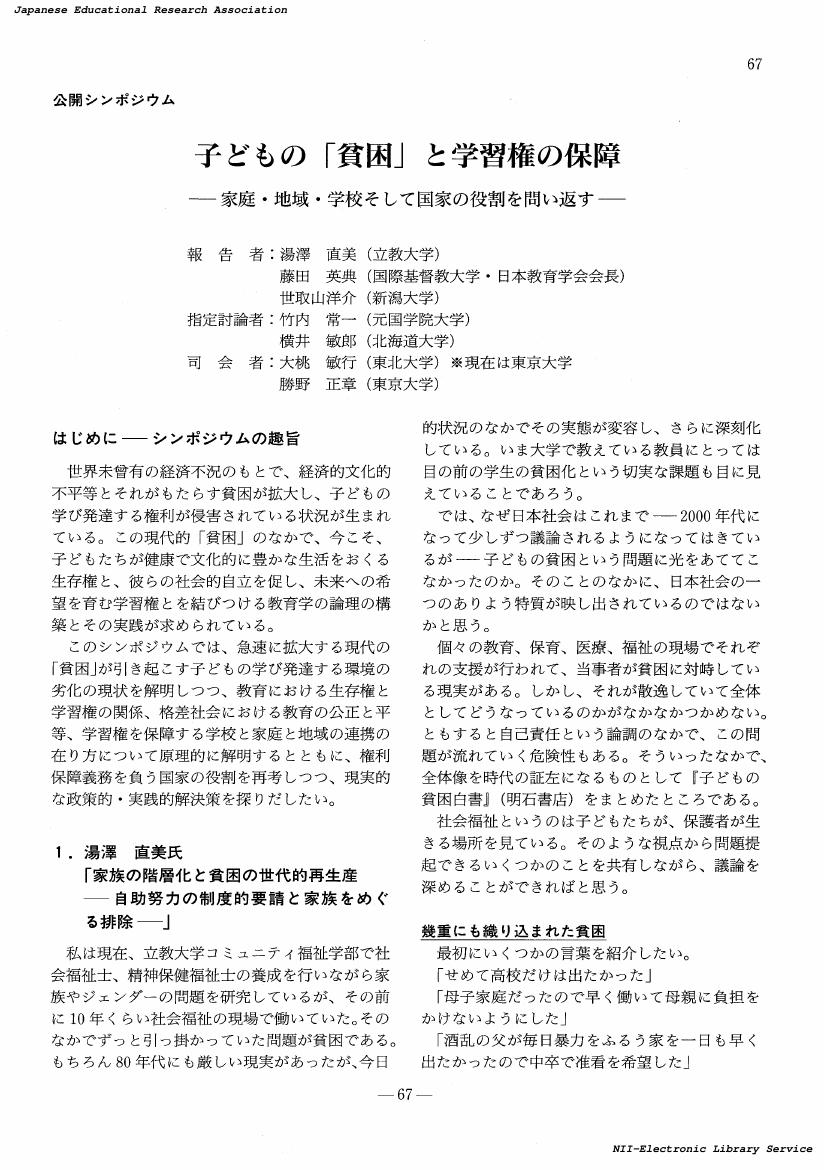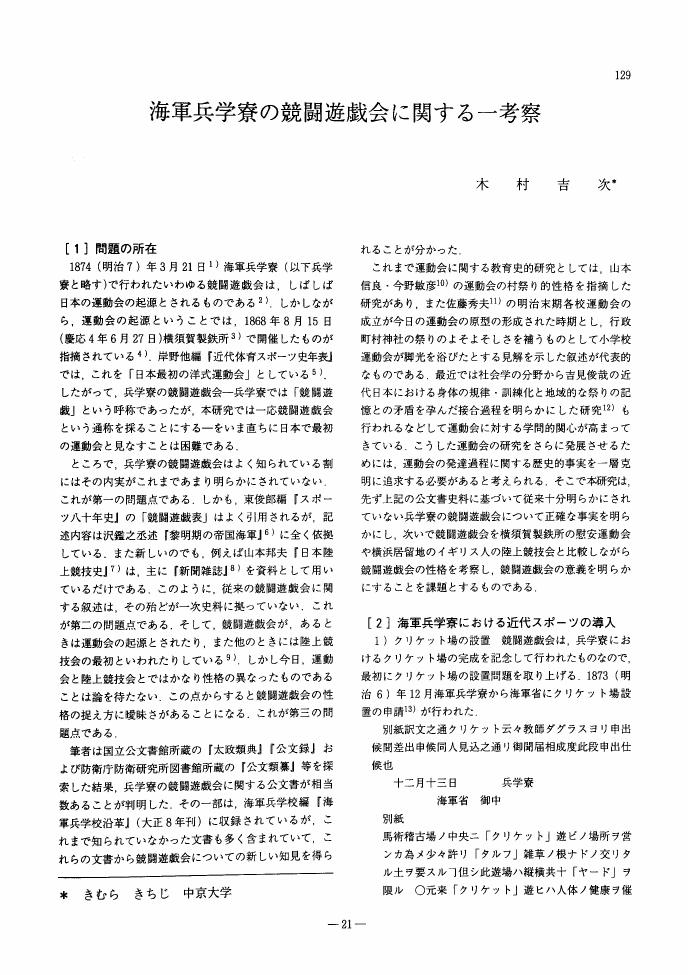2 0 0 0 OA パネルデータを用いた学力格差の変化についての研究
- 著者
- 中西 啓喜
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.4, pp.583-593, 2015 (Released:2016-05-18)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 1
本稿の目的は、算数・数学の学力パネルデータの分析から、義務教育段階を通じた学力の社会階層間格差の変化についての実態を示すことである。分析より得られた知見は、①学力格差の変化は流動的ではなく、初期に獲得した学力はほとんど変化しないということ、②こうした学力格差は、両親が大卒の児童生徒の方が両親非大卒の児童生徒よりも高い学力水準を維持しやすいこと、③学力に対する個人の努力(学習時間)の独立したポジティブな効果は確認できたが、親学歴による学力格差は維持されること、の3点である。
2 0 0 0 OA Charles W. EliotとAbraham Flexnerのカレッジ・大学論 : 「何のための質保証か」を考えるために(【テーマB-4】高等教育改革と質保証,テーマ型研究発表【B】,発表要旨)
- 著者
- 原 圭寛
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 日本教育学会大會研究発表要項 (ISSN:2433071X)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, pp.370-371, 2012-08-22 (Released:2018-04-20)
2 0 0 0 OA 日米におけるアクティブ・ラーニング論の成立と展開
- 著者
- 西岡 加名恵
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.3, pp.311-319, 2017 (Released:2018-04-27)
- 参考文献数
- 65
2 0 0 0 OA 教育の公共性と国家関与をめぐる争点と課題
- 著者
- 高橋 哲
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.2, pp.245-256, 2005-06-30 (Released:2007-12-27)
2 0 0 0 OA 西ドイツ教育政策の基本的性格
- 著者
- 森 隆夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.3, pp.161-172, 1962-09-30 (Released:2009-01-13)
- 参考文献数
- 66
- 著者
- 湯澤 直美 藤田 英典 世取山 洋介 竹内 常一 横井 敏郎 勝野 正章
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.1, pp.67-77, 2010-03-31 (Released:2017-11-28)
2 0 0 0 OA 海軍兵学寮の競闘遊戯会に関する一考察
- 著者
- 木村 吉次
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.2, pp.129-138, 1996-06-30 (Released:2009-01-13)
- 参考文献数
- 54
2 0 0 0 OA 木村 祐子 著『発達障害支援の社会学 医療化と実践家の解釈』
- 著者
- 越野 和之
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.2, pp.220-222, 2016 (Released:2016-08-06)
2 0 0 0 性教育(7) : 性交の指導,教育と宗教との関連
- 著者
- 高橋 誠
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 日本教育学会大會研究発表要項
- 巻号頁・発行日
- vol.44, 1985
- 著者
- 大森 愛
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 日本教育学会大會研究発表要項 (ISSN:2433071X)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, pp.124-125, 2010-08-13 (Released:2018-04-20)
- 著者
- 須永 哲思
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.3, pp.415-426, 2015
 本稿では、郷土教育全国協議会・桑原正雄と歴史教育者協議会・高橋磌一の間で1950年代後半に行われた論争について、1950年代前半の小学校社会科教科書の共同執筆に具体化されていた提携関係が対立的な論争へと進展していく過程・要因を、チンドン屋をめぐる教材に着目しながら検討した。そして、桑原が主張した「郷土教育」とは、親の社会生活の個別具体性・多様性を重視する側面と、それを資本の働きという生活に内在する構造連関として系統化する側面を、同時に両立しようとする試みであったことを明らかにした。
- 著者
- 大桃 敏行 吉良 直 黒田 友紀 高橋 哲 長嶺 宏作 鈴木 大裕
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 日本教育学会大會研究発表要項
- 巻号頁・発行日
- vol.74, pp.114-115, 2015
2 0 0 0 教育原理では何が教えられてきたのか
- 著者
- 知念 渉
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 日本教育学会大會研究発表要項
- 巻号頁・発行日
- vol.76, pp.240-241, 2017
- 著者
- 井上 義巳
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 日本教育学会大會研究発表要項
- 巻号頁・発行日
- vol.23, 1964
- 著者
- 茂木 輝順
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 日本教育学会大會研究発表要項
- 巻号頁・発行日
- vol.66, pp.170-171, 2007
- 著者
- 野口 武悟 前田 稔
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 日本教育学会大會研究発表要項 (ISSN:2433071X)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, pp.330-331, 2011-08-22 (Released:2018-04-20)
2 0 0 0 OA PISAリテラシーを飼いならす—グローバルな機能的リテラシーとナショナルな教育内容—
- 著者
- 松下 佳代
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.2, pp.150-163, 2014 (Released:2015-06-18)
- 参考文献数
- 51
- 被引用文献数
- 4
本稿の目的は、OECD-PISAのリテラシー概念がどのような性格をもち、参加国の教育政策にどのような影響を与えているのかを検討することを通じて、PISAリテラシーを「飼いならす」(Hacking, 1990)こと、すなわち、その影響をコントロール可能なものにすることにある。本稿ではまず、PISAが、マグネット経済や機械との競争というロジックに支えられながら、教育指標としての規範性を強め、国家間の比較と政策借用を通じて教育改革を促す道具になっていることを明らかにした。さらに、1950年代以降のリテラシーの概念史の中に位置づけることによって、PISAリテラシーが〈内容的知識やポリティクスの視点を捨象し、グローバルに共通すると仮想された機能的リテラシー〉という性格をもつことを浮きぼりにした。ナショナルなレベルでの教育内容の編成にあたっては、捨象されたこれらの部分を取り戻し、能力と知識の関係を再構成する必要がある。
- 著者
- 神林 寿幸
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.1, pp.25-35, 2015 (Released:2016-05-19)
- 参考文献数
- 22
近年、教員の多忙化が政策課題とされており、教育学研究でも事務処理などの周辺的職務に伴う教員の多忙化が複数指摘されてきた。しかしこれらの指摘は十分な実証に基づくものではなかった。そこで本稿では現存する1950~60年代と2000年代後半の教員の労働時間調査について、一般線形モデルを用いた比較を行った。その結果、1950~60年代に比べて、2000年代後半以降の教員は、事務処理等の周辺的職務に長い時間を費やしているとは必ずしもいえず、他方で教育活動(特に課外活動)に費やす時間が長いことが明らかとなった。
2 0 0 0 OA 生涯学習と学校教育に関する考察学習権の視点から
- 著者
- 朝倉 征夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.3, pp.204-213, 1991-09-30 (Released:2009-01-13)
- 参考文献数
- 42
2 0 0 0 OA 不就学障害児の死亡例の実態調査研究
- 著者
- 藤本 文朗
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.1, pp.73-81, 1974-03-30 (Released:2009-01-13)
- 参考文献数
- 15