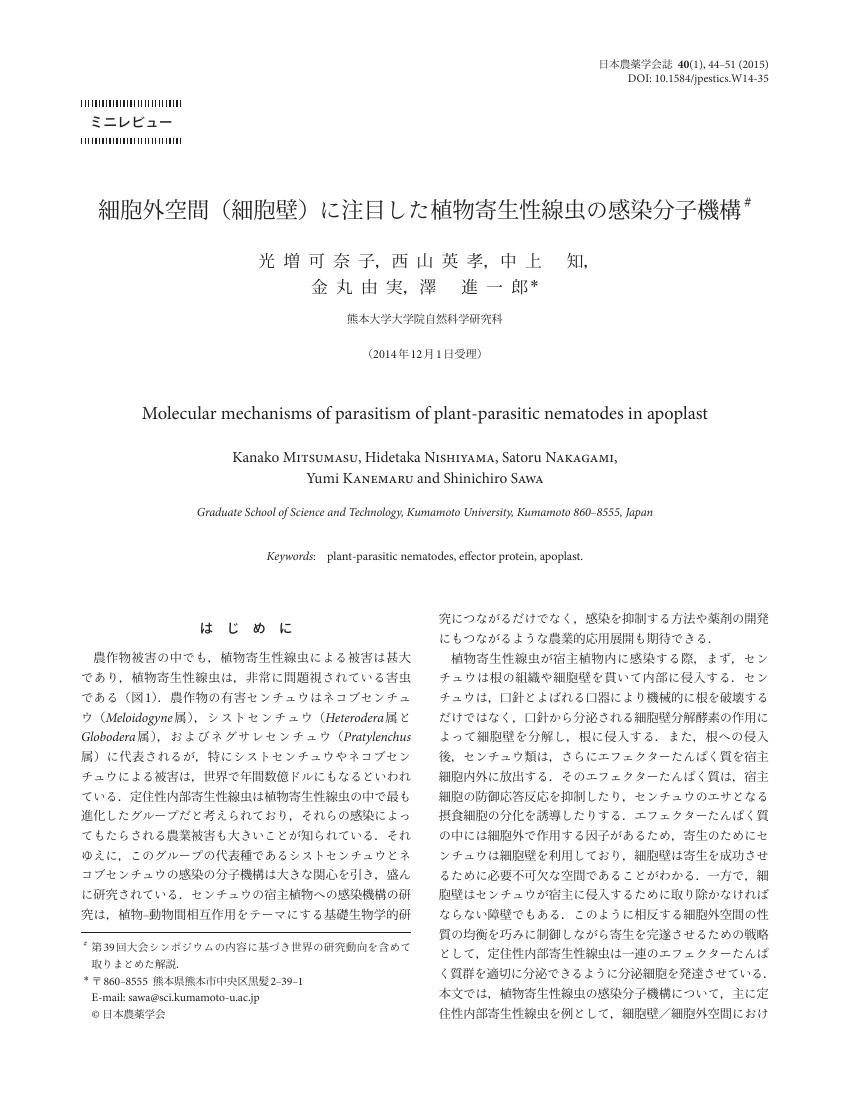1 0 0 0 OA 酒石酸モランテルの毒性試験の概要
- 著者
- ファイザー製薬株式会社農産事業部農産開発部
- 出版者
- 日本農薬学会
- 雑誌
- 日本農薬学会誌 (ISSN:03851559)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.4, pp.S323-S325, 1992-11-20
酒石酸モランテルの安全性評価のため各種毒性試験を行なった.その結果, 本剤の急性毒性は比較的弱く, 普通物に該当する.眼に対する刺激性はわずかに認められたが, 薬剤の希釈により刺激性は軽減した.また, 皮膚に対する刺激性はなかったが, 皮膚感作性は陽性であり, 皮膚にアレルギー反応を生じる可能性があると判断された.一方, 6か月毒性試験では高用量群(27, 500ppm)において, 死亡例の発生, 体重の減少, 摂餌量の減少, 剖検時の全身性の消耗, 諸器官の萎縮性変化などがみられたが, 本剤投与による特異的な変化は認められなかった.変異原性は陰性であった.また, 催奇形性に関しても問題はなかった.酒石酸モランテル液剤であるグリンガードは昭和57年11月に登録を取得した.また, 8%液剤であるグリンガード・エイトは昭和61年7月に登録を取得し, マツノザイセンチュウの侵入・増殖を阻止して松枯れを防止する樹幹注入剤として使用されている.酒石酸モランテルは, 定められた使用基準を遵守すれば, 安全性が確保されるものであり, 松枯れを防止する有用な農薬として上市以来好評を得ている.
1 0 0 0 除草剤ピラフルフェンエチルの開発
- 著者
- 三浦 友三 馬渕 勉 東村 稔 天沼 利宏
- 出版者
- 日本農薬学会
- 雑誌
- Journal of Pesticide Science (ISSN:1348589X)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.2, pp.235-240, 2003
ピラフルフェンエチル(pyraflufen-ethyl)は日本農薬(株)によって創製され、実用化されたプロトポルフィリノーゲン酸化酵素(Protox)阻害型除草剤である。本化合物はコムギに対して高い安全性を示すと共に広範囲の広葉雑草に対して10g a.i./ha前後の低薬量で極めて高い除草活性を示す。特にコムギ栽培における難防除雑草の一つであるヤエムグラ(Galium aparine)に卓効を示す。ピラフルフェンエチルは日本ではムギ用除草剤として、エコパートフロアブルの商品名で1999年に農薬登録の許可を得て販売を開始した。また同時に果樹園の下草防除や非農耕地の非選択性除草剤として、グリホサートトリメシウム塩との混合剤であるサンダーボルトの販売も開始した。さらに、2001年バレイショ枯凋剤として、デシカン乳剤の販売を開始した。これらは海外においても14か国で登録・上市され、数か国で開発途上にある。本稿では、ピラフルフェンエチルの創出の経緯、工業的製造法、構造活性相関、除草活性、作用機構、各種毒性試験結果について概要を述べる。
1 0 0 0 OA ストリゴラクトンの構造多様性と植物界における分布
1 0 0 0 マダラサソリ毒液に含まれる殺虫性ペプチドの単離・同定
- 著者
- 大木 愛子 大氣 新平 小泉 和也 佐藤 幸治 河野 均 BOGER Peter 若林 攻
- 出版者
- 日本農薬学会
- 雑誌
- 日本農薬学会誌 (ISSN:03851559)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.4, pp.309-313, 1997-11-20
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 3
Peroxidizing除草剤の植物毒性活性に対する2-substituted 4, 6-bis(ethylamino)-1, 3, 5-triazine系化合物の効果を単細胞緑藻Scenedesmus acutusを用いて検討した.Oxyfluorfenまたはchlorophthalimに起因する植物毒性活性の緩和, いわゆる"diuron効果"が2-substituted 4, 6-bis(ethylamino)-1, 3, 5-triazineの共存下で認められた.すなわち, 細胞中でのクロロフィル減少, エタン発生およびprotoporphyrin-IX (Proto-IX)の蓄積が緩和された.また, peroxidationの緩和の度合は1, 3, 5-triazine系化合物の光合成電子伝達系(PET)阻害活性に比例した.
1 0 0 0 水稲用殺菌剤メトミノストロビンの開発
- 著者
- Fonagy Adrien 松本 正吾 内海 恭一 折笠 千登世 満井 喬
- 出版者
- 日本農薬学会
- 雑誌
- 日本農薬学会誌 (ISSN:03851559)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.47-54, 1992-02-20
- 被引用文献数
- 5
カイコおよびハスモンヨトウを用い, 合成したカイコのPBANのフェロモン腺に対する作用を, in vivoおよびin vitroで検討した.合成PBANを断頭したカイコ雌成虫に注射すると濃度依存的にボンビコールの生産が促され, また, その生産量は注射後90∿120分で最大となった.一方, 合成PBANを含むGrace培地でカイコおよびハスモンヨトウのフェロモン腺を培養したところ, 両種とも濃度依存的にフェロモンの生産が促され, その生産量は培養開始後90∿120分で最大となった.さらに, 両種におけるフェロモン生産はカルシウムイオノフォアを含むGrace培地でフェロモン腺を培養しても引き起こされることから, カイコおよびハスモンヨトウにおいて, PBANの標的器官がフェロモン腺であること, また, その作用の発現にはカルシウムイオンが介在していることが示唆された.
1 0 0 0 中国冷凍野菜の取り組み経緯について(読物企画)
- 著者
- 伊東 敏行
- 出版者
- 日本農薬学会
- 雑誌
- Journal of pesticide science (ISSN:1348589X)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.1, pp.66-72, 2010
- 被引用文献数
- 1
日本冷凍食品協会によれば、2008年の冷凍食品生産額は国内生産量約6600億円、海外輸入を合わせると約9000億円を超える規模となっている。2008年における日本の冷凍食品消費量は約250万トンであり、そして国民一人当たりの消費量は現在約19.4kgである。これが、現在の日本における冷凍食品の実態である。この中で、味の素冷凍食品株式会社(以下、当社)は、主な業務としてギョーザやシュウマイなどを代表とする冷凍食品の製造・販売を行っており、年間約1100億円の販売規模に達している。その生産拠点は国内9工場、海外8工場の合計17工場になる。一方、現在日本における食料自給率はカロリーベースで40%であり、そのため海外からの食料輸入に依存せざるを得ない状況にあることは周知のとおりである。冷凍食品においても図1のとおり、その輸入量(冷凍野菜輸入量+調理冷凍食品輸入量)は、約100万トンであり、われわれ冷凍食品を製造するメーカーにとっても国産のみならず海外に原料を求めまた製品生産を検討し、それに依存していかなければならない現状にある。その輸入食材は、検疫を通過後国内に流通するが、検疫では食品のリスクを想定し、残留農薬等色々な検査が行われているが、さらに国内のお客様から安心・安全の信頼を得るためには輸入食材の残留農薬に対する各企業の対応は避けて通れない状況にある。ここでは、当社における取り組みを中心に、中国冷凍野菜の製造行程における残留農薬に対する対応状況について紹介する。
1 0 0 0 OA 除草剤キザロホップエチルの作用機構
- 著者
- 中平 国光
- 出版者
- 日本農薬学会
- 雑誌
- Journal of Pesticide Science (ISSN:1348589X)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.3, pp.357-366, 1998-08-20 (Released:2010-08-05)
- 参考文献数
- 36
- 被引用文献数
- 3 3
- 著者
- 汲田 泉
- 出版者
- 日本農薬学会
- 雑誌
- 日本農薬学会誌 (ISSN:03851559)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.4, pp.404-408, 2002
- 参考文献数
- 1
ステロールの生合成経路の阻害剤としては、これまでさまざまなタイプのものが知られている。P-450阻害によるメチル化を阻害するアゾール系化合物は、合成的自由度が大きく非常に多数の化合物が農業用、医薬用として実用化されており、殺菌剤・抗真菌剤の中で重要な位置をしめている。二重結合の異性化・還元化反応の阻害剤としてはモルフォリン系殺菌剤が知られており、うどんこ病剤として広く使用されている。スクワレンエポキシダーゼ阻害剤としては医療用抗真菌剤として、アリルアミン系・チオカルバミン酸系の二つのタイプが実用化されている。In vitro系において割合広い抗菌スペクトラムを有しており、新しい農業用殺菌剤の可能性もあると思われる。スクワレンエポキシドサイクラーゼ阻害剤としてはまだ実用化されたものはないが、長鎖アルキルイミダゾールが阻害剤として知られており、今後の新しいターゲットの一つと考えられる。農薬の探索研究はこれまで、総合的な評価ができるいわゆる"ぶっかけ試験"を中心としてきた。しかし、農薬の領域においても作用機作の研究などが大きく進み、生理生化学的手法をとりいれた生合理的アプローチの基盤が整ってきた。ターゲットとして、生化学的評価のしやすいステロールの生合成系を選定し、その阻害活性を有する殺菌剤の探索を行った。方法としては、単に抗菌力の強弱ではなく活性の質的な面に注目し、菌の形態観察(膜の異常は菌糸の形態異常を引き起こすと思われる)やステロールの分析を行いながら化合物を選抜して行くことにした。それにより、今までの方法では見過ごされるようなリード骨格を新たな視点で取り上げ発展させ、より合理的な新規殺菌剤の探索研究を目指した。
1 0 0 0 OA 細胞外空間(細胞壁)に注目した植物寄生性線虫の感染分子機構
- 著者
- デスマーチェリーア J. M. ゴールドリング M. ホーガン R.
- 出版者
- 日本農薬学会
- 雑誌
- 日本農薬学会誌 (ISSN:03851559)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.4, pp.539-545, 1980
- 被引用文献数
- 2
もみ, 玄米, 白米, 大麦中の貯穀害虫防除剤の6カ月貯蔵後の残留量を調査した.残留量の実測値は, 温度, 平衝相対湿度, 減少速度定数を用いたモデルによる推定値に近似していた.もみに施用された防除剤は精米工程により, もみがらとぬかに分布した.米の炊飯による残留量の減少は防除剤の種類により異なり, ジクロルボス, メタクリホス, カルバリルではとくに大きかった.すペての防除剤は大麦をマルトとする工程で減少し, メタクリホスの減少が顕著であった.
1 0 0 0 メタノール-リン酸抽出による黒ボク土におけるクロルピリホスの測定
- 著者
- ラハマン G. K. M. M. 本山 直樹
- 出版者
- 日本農薬学会
- 雑誌
- 日本農薬学会誌 (ISSN:03851559)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.4, pp.387-391, 2000
- 参考文献数
- 21
有機リン殺虫剤クロルピリホスの畑土条件下での残留性を千葉と松戸の黒ボク土を用いて土壌の滅菌処理, 温度(15, 25, 35℃)や水分(20, 30, 40%)を変えて室内実験により研究した.土壌からメタノールで抽出後, 85%リン酸処理によって残留するクロルピリホスを遊離させ, 再びメタノールで抽出した.遊離したクロルピリホスは千葉土壌で最大18%, 松戸土壌で10%検出されたが, 長期間土壌中に残留した.土壌中の半減期は千葉土壌で28日, 松戸土壌で14日であり, 温度の上昇に伴って分解は速くなった.メタノールで抽出されない残留体は千葉>松戸であり, 有機炭素含量と正の相関を示し, 土壌有機物への吸着が示唆された.両土壌とも滅菌処理によって分解速度は遅くなったが, 遊離するクロルピリホスは酸処理によってあまり差がなかった.
1 0 0 0 OA 昆虫RDL GABA受容体の構造と薬剤感受性に関する研究
- 著者
- 中尾 俊史
- 出版者
- 日本農薬学会
- 雑誌
- 日本農薬学会誌 (ISSN:21870365)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.2, pp.163-170, 2015-08-20 (Released:2016-03-10)
- 参考文献数
- 26
- 著者
- 原田 和生 黒野 友理香 長澤 沙弥 小田 知佳 那須 雄大 若林 孝俊 杉本 幸裕 松浦 秀幸 村中 聡 平田 收正 岡澤 敦司
- 出版者
- 日本農薬学会
- 雑誌
- Journal of Pesticide Science (ISSN:1348589X)
- 巻号頁・発行日
- pp.D17-036, (Released:2017-10-26)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 5
根寄生植物は重要農作物に寄生し収量を低下させるため,世界の食糧生産に深刻な被害を及ぼしている.近年,我々は放線菌Streptomyces ficellusの生産するノジリマイシン(NJ)が根寄生植物種子の発芽を阻害することを見出した.本研究ではS. ficellusのNJ生産性向上を目指した培地改良,および未精製培養物の根寄生植物防除剤としての適用可能性について検討した.従来のNJ生産培地に使用されていたPharmamedia™を他の汎用的な培地成分に置換したところ,マリンブロスによりNJ生産量が向上した.4日間培養を行ったところ,培地中のNJ含量は710 mg/Lに達し,従来の17倍まで向上した.得られた培養液を各寄生植物種子に処理したところ,NJ 標準溶液と同等の発芽阻害活性を示した.本研究で示した当該培養法は根寄生植物防除剤生産開発につながると期待される.
1 0 0 0 OA トリフルラリンの毒性試験の概要
- 著者
- 塩野義製薬株式会社植物薬品開発部 武田薬品工業株式会社アグロ事業部農薬研究所
- 出版者
- 日本農薬学会
- 雑誌
- Journal of Pesticide Science (ISSN:1348589X)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.3, pp.557-561, 1991-08-20 (Released:2010-08-05)
トリフルラリンの安全性評価のための各種毒性試験を実施した.本剤の急性毒性は弱く普通物に該当する. しかし乳剤, 粒剤ともウサギにおいて眼刺激性が認められ, 乳剤では皮膚刺激性も認められた. また乳剤ではモルモットにおける皮膚感作性が陽性であった. 一方, 原体のサルにおける経皮吸収率は約0.1%ときわめて低く, ウサギにおける亜急性経皮毒性試験でも全身性の毒性症状は認められなかった.慢性毒性/発がん性試験では, 中間・高用量群のラットおよびマウスに体重増加の抑制, 肝臓重量の増加, および進行性糸球体腎症 (炎), 腎結石等の腎毒性が認められた. イヌでは高用量群に肝臓重量の増加が認められたのみであった. 発がん性はマウスでは認められず, ラットでは中間・高用量群で膀胱腫瘍, 全用量群で腎臓腫瘍の発生率が上昇したが, 腫瘍の総発生率にはトリフルラリン投与による影響は認められなかった.ラットにおける2世代繁殖試験では繁殖に及ぼす影響は認められず, 催奇形性試験では, ラットでは1000mg/kg/日以下, ウサギでは225mg/kg/日以下の用量で催奇形性は認められなかった. 各種変異原性試験の結果はすべて陰性であった.薬理試験ではトリフルラリンに特異的な作用というよりもむしろ急性中毒症状と考えられる異常歩行, 振戦等の中枢神経系に対する影響が認められたが, トリフルラリンのおもな薬理作用は利尿作用および肝機能抑制作用であった. 本剤の解毒薬としてはグルタチオン, グルクロン酸アミドおよび硫酸アトロピンが有効であった.トリフルラリンは昭和41年, 乳剤の大豆, ラッカセイ, カンショ, ナタネ, 小麦, ニンジン, キャベツ, 大根, トマトで日本において初めて登録され, 昭和44年には2.5%粒剤のラッカセイ, 3.0%粒剤の水稲に登録された. その後他作物への適用拡大を順次実施し, 畑作物, 野菜を始め, 花き花木, 工芸作物, 果樹, 公園・庭園等幅広い分野に登録された.トリフルラリンの登録保留基準値は, 米, 麦・雑穀, 果実, 野菜, イモ類, 豆類, 茶のいずれも0.01ppm (ただしニンジンは0.2ppm) と設定されている.トリフルラリンは定められた使用基準を遵守すれば安全性の高い農薬であり, 有用な農業資材の一つとして上市以来好評を得ている.
- 著者
- 陳 き 太田 広人 佐々木 健介 尾添 富美代 尾添 嘉久
- 出版者
- 日本農薬学会
- 雑誌
- Journal of pesticide science (ISSN:1348589X)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.4, pp.473-480, 2011-11
(R)‐オクトパミン(OA)との相互作用に関わるカイコ由来β‐アドレナリン様オクトパミンレセプターのアミノ酸残基を同定するために,オルトステリック部位と予測される部位に1アミノ酸置換をもつ7変異体を作製してHGK-293細胞に発現させ,(R)‐OAとの反応により細胞内cAMPレベルを上昇させる活性を測定した。その結果,S206A変異体は活性を保持していたが,その他の変異体(D115A,S202A,Y300F,Y300N,Y300L,Y300A)は活性を示さなかった。この結果とホモロジーモデリング/ドッキングシュミレーションの結果から,Ser202とTyr300は(R)‐OAのフェノール性ヒドロキシル基と相互作用し,Asp115はβ‐ヒドロキシル基及び側鎖アミノ基と相互作用することが推察された。
- 著者
- 井藤 和人 生嶋 隆博 巣山 弘介
- 出版者
- 日本農薬学会
- 雑誌
- 日本農薬学会誌 (ISSN:1348589X)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.1, pp.51-54, 2003
- 被引用文献数
- 1
除草剤ザークD51(ダイムロン・ベンスルフロンメチル、ZD)および殺菌剤フジワンモンカット(イソプロチオラン・フルトラニル、MC)粉剤が水田土壌における微生物群集構造に及ぼす影響についてバイオログGNプレートを用いた室内実験により評価した。ZDは常用量の50倍の濃度においてもバイオログプレートの発色にかかわる微生物群集構造を変化させることはなかった。一方、MCは常用量では微生物群集構造に影響を及ぼさなかったが、50倍量では少なくとも4週間にわたりバイオログパターンを明確に変化させた。この時点においてバイオログプレートで測定した炭素源利用活性には影響が認められなかった。MCが微生物群集構造に及ぼす影響の大きさを評価するため、水田土壌の微生物群集構造に大きく影響を及ぼすことがこれまでに明らかにされている土壌の湛水による影響とMC(常用量の10倍の濃度)による影響の大きさとを比較した。MCを添加してから1週間後では土壌の湛水による影響の方が大きかったが、4週間後にはMCによる影響の方が大きかった。このように、農薬の影響による土壌微生物群集構造の変化の大きさと自然環境条件下における土壌微生物群集構造の変化の大きさを比較することにより、農薬が土壌微生物群集構造に及ぼす影響の大きさを評価することができると考えられた。
- 著者
- 辻 孝三 堀出 文男 美濃部 正夫 佐々木 正夫 白神 昇 広明 修
- 出版者
- 日本農薬学会
- 雑誌
- 日本農薬学会誌 (ISSN:03851559)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.3, pp.371-384, 1980-08-20
- 被引用文献数
- 1
スミチオンを空気中でDTA測定を行なうと(I)(150∿190℃), (II)(210∿235℃), (III)(270∿285℃)の3本の発熱ピークが観測される.一方窒素中では(II), (III)に相当する2本の発熱ピークが観測されるのみである.これらのピークは次のように同定された.ピーク(I) : 二酸化イオウガス発生を伴うスミオキソンの生成, ピーク(II) : S-メチルスミチオンからのジメチルサルファイドの発生とポリメタホスフェートの生成, ピーク(III) : フェノール環の炭化とジメチルサルファイド, ジメチルジサルファイドおよびエタンガスの発生.また, 193℃までスミチオンを加熱するとS-メチルスミチオンが生成するが, これに対応したDTAピークは観測されなかった.スミチオンと酸素の反応は拡散律速であり試料表面での反応が主である.スミオキソンの生成熱は170∿180 kcal/molである.