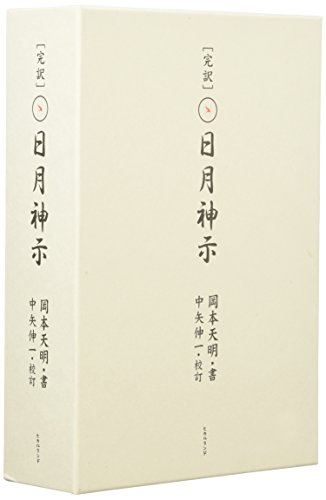1 0 0 0 OA 皿ばねの変形挙動に及ぼす端部摩擦の影響
- 著者
- 尾崎 伸吾 津田 兼 田島 典拓 冨永 潤
- 出版者
- 公益社団法人 自動車技術会
- 雑誌
- 自動車技術会論文集 (ISSN:02878321)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.6, pp.1205-1210, 2010 (Released:2011-02-10)
- 参考文献数
- 8
皿ばねの荷重-たわみ関係は上下端の摩擦境界の影響によりヒステリシスを呈するが,既存の設計式ではこれを適切に評価できない.本研究では,有限要素解析に基づく系統的な検討を実施し,皿ばねの変形挙動に及ぼす摩擦境界の影響について検討した.また,ヒステリシスを考慮した荷重-たわみ関係の評価法を提案した.
1 0 0 0 三菱重工技報 = Mitsubishi Juko giho
- 出版者
- 三菱重工業
- 巻号頁・発行日
- 1964
1 0 0 0 三菱重工技報 = Mitsubishi Juko giho
- 出版者
- 三菱重工業
- 巻号頁・発行日
- vol.4(6), no.22, 1967-11
1 0 0 0 三菱重工技報 = Mitsubishi Juko giho
- 出版者
- 三菱重工業
- 巻号頁・発行日
- vol.3(5), no.14, 1966-09
1 0 0 0 OA 日本語―ベトナム語の双方向に見られる明示化ストラテジー
- 著者
- グエン ヴァン・ティ・ミン
- 出版者
- 日本通訳翻訳学会
- 雑誌
- 通訳翻訳研究 (ISSN:18837522)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.15-35, 2014 (Released:2021-11-29)
- 参考文献数
- 21
Information explicitation is a popular methodology in interpretation. Studies on this process tend to focus on common language pairs, often including English, but there has never been a research conducted on minority languages such as Thai, Vietnamese, Indonesian, etc. During this study, we collected data about the interpretation from Japanese to Vietnamese and vice versa, identif ied, categorized and evaluated the effectiveness of the information explicitation strategies used in the interpretation process of Japanese - Vietnamese language pair.
1 0 0 0 防衛庁技術研究本部二十五年史
- 著者
- 防衛庁技術研究本部創立25周年記念行事企画委員会 編
- 出版者
- 防衛庁技術研究本部創立25周年記念行事企画委員会
- 巻号頁・発行日
- 1978
1 0 0 0 OA 聴覚刺激による情動変化が瞳孔径に与える影響と視覚障害者への応用
- 著者
- 中島 浩二
- 出版者
- 一般社団法人 産業応用工学会
- 雑誌
- 産業応用工学会論文誌 (ISSN:2189373X)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.2, pp.39-43, 2014 (Released:2016-09-01)
- 参考文献数
- 8
We conducted an experiment to infer emotional changes induced by auditory stimulation using the pupil diameter and investigated whether the experiment could be applicable to the visually impaired people as well. The difference caused by the kind of the auditory stimulations observed in the pupil diameter of the sighted people group was also observed in the visually impaired people group in the same manner. A possibility was suggested that a pupil diameter could become an index of emotional changes in the visually impaired people as well.
1 0 0 0 OA 異言語間における言説分析―『源氏物語』 ロシア語訳の事例から アンダソヴァマラル
- 出版者
- 物語研究会
- 雑誌
- 物語研究 (ISSN:13481622)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.158-174, 2018 (Released:2021-07-01)
1 0 0 0 OA スポーツの世界の物語性 : 「からだ」から表現へ
- 著者
- 矢野 徳郎
- 巻号頁・発行日
- 2022-04-01
132p
1 0 0 0 OA 海外紀行文の総合的研究―視覚的想像力の諸相をめぐって
近代以降、日本人の海外渡航に伴う紀行文、旅行記、旅行日記などは膨大な量に及ぶ。本研究ではその堆積を基礎に、日本人が残した海外体験の実相を追及するとともに、そこには異文化への興味を媒介とする自己の相対化が断行されていたことが了解される。それはまた歴史的な事象によって変転する自身の運命との対峙ともなっている。移民や戦争によって戦地に連れ去られる兵士など、日本人が経験した多様な海外体験は膨大な記録となって積み重ねられているが、その殆どが忘れられている現状を鑑み、それらの資料の発掘と、別の視点からの照射は、あらたな文化研究を拓いていくものと考えている。
1 0 0 0 アメリカ映画 = Cine-America
- 出版者
- アメリカ映画研究所
- 巻号頁・発行日
- no.1, 1946-11
1 0 0 0 OA 松山平野における弥生社会の展開(論考編2 各地の弥生集落)
- 著者
- 柴田 昌児
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.149, pp.197-231, 2009-03-31
西部瀬戸内の松山平野で展開した弥生社会の復元に向けて,本稿では弥生集落の動態を検討したうえでその様相と特質を抽出する。そして密集型大規模拠点集落である文京遺跡や首長居館を擁する樽味四反地遺跡を中心とした久米遺跡群の形成過程を検討することで,松山平野における弥生社会の集団関係,そして古墳時代社会に移ろう首長層の動態について検討する。まず人間が社会生活を営む空間そのものを表している概念として「集落」をとらえたうえで,その一部である弥生時代遺跡を抽出した。そして河川・扇状地などの地形的完結性のなかで遺跡が分布する一定の範囲を「遺跡群」と呼称する。松山平野では8個の遺跡群を設定することができる。弥生集落は,まず前期前葉に海岸部に出現し,前期末から中期前葉にかけて遺跡数が増加,一部に環壕を伴う集落が現れる。そして中期後葉になると全ての遺跡群で集落の展開が認められ,道後城北遺跡群では文京遺跡が出現する。機能分節した居住空間構成を実現した文京遺跡は,出自の異なる集団が共存することで成立した密集型大規模拠点集落である。そして集落内に居住した首長層は,北部九州を主とした西方社会との交渉を実現させ,威信財や生産財を獲得し,集落内部で金属器やガラス製品生産などを行い,そして平形銅剣を中心とした共同体祭祀を共有することで東方の瀬戸内社会との交流・交渉を実現させたと考えられる。後期に入ると文京遺跡は突如,解体し,集団は再編成され,後期後半には独立した首長居館を擁する久米遺跡群が新たに階層分化を遂げた突出した地域共同体として台頭する。こうした解体・再編成された後期弥生社会の弥生集落は,久米遺跡群に代表されるいくつかの地域共同体である「紐帯領域」を生成し,松山平野における特定首長を頂点とした地域社会の基盤を形づくり,古墳時代前半期の首長墓形成に関わる地域集団の単位を形成したのである。
1 0 0 0 OA X 社会政策の危機と国民生活 : 一九七〇年代以降の日本の社会保障の展開
- 著者
- 横山 和彦
- 出版者
- 社会政策学会
- 雑誌
- 社会政策叢書 (ISSN:24331392)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.225-247, 1986-10-18 (Released:2018-04-01)
1 0 0 0 OA ホームレスの就労自立支援に向けた発達障害傾向の1次スクリーニングテスト
- 著者
- 藤本 学
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第79回大会 (ISSN:24337609)
- 巻号頁・発行日
- pp.1EV-150, 2015-09-22 (Released:2020-03-27)
1 0 0 0 OA シリコン接合素子を用いた原子力電池
- 著者
- 鈴木 一道 田淵 秀穂 石松 健二
- 出版者
- 公益社団法人 日本アイソトープ協会
- 雑誌
- RADIOISOTOPES (ISSN:00338303)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.5, pp.282-287, 1974-05-15 (Released:2010-09-07)
- 参考文献数
- 4
シリコンp-n接合素子および147Pm線源 (有効放射能0.1~0.2Ci) をそれぞれ5枚交互に重ねあわせて原子力電池を構成した。最大出力1.2μW, エネノレギー変換効率0.3%を得た。単色電子ビームを使用した実験から, 素子の最大出力は入力の1.2~1.3乗で増加することがわかった。147Pm線源に対して最大出力を与えるシリコンp-n接合素子の接合部深さは2~4μであった。さらに, 147Pmを線源にした場合, 素子の放射線損傷による最大出力の低下は5%/6, 200時間であった。