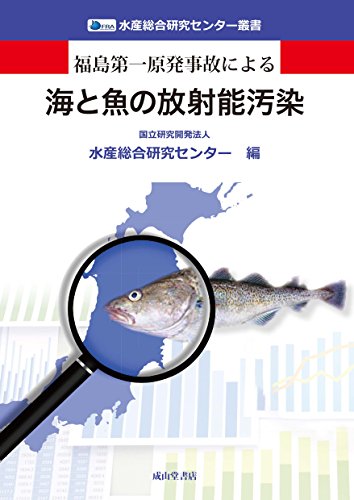1 0 0 0 OA 高分子物質の熱分解生成物とその有害性
- 著者
- 長谷川 貴陽史
- 出版者
- 公益社団法人 都市住宅学会
- 雑誌
- 都市住宅学 (ISSN:13418157)
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, no.53, pp.29-33, 2006-04-25 (Released:2012-08-01)
- 参考文献数
- 17
「住所がなければ、子どもを学校にやれない。証明書がなければ結婚できないし、社会保障給付を請求できない。読み書きのできない人は、公式に排除されていようがいまいが、実質的には政治に関与できないようになっている。ある機能領域から排除されているがゆえに、他の機能領域へも包摂されえなくなっているのである。」(ニクラス・ルーマン)
1 0 0 0 OA レセプトデータを用いた妊娠中における糖尿病の罹患と治療薬の処方状況の調査
- 著者
- 岡田 裕子 赤岩 奈々香 前田 恵里
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床薬理学会
- 雑誌
- 日本臨床薬理学会学術総会抄録集 第42回日本臨床薬理学会学術総会 (ISSN:24365580)
- 巻号頁・発行日
- pp.1-P-B-1, 2021 (Released:2021-12-17)
【目的】 メトホルミンは、海外では妊娠糖尿病に使用可能であり、使用により母体の体重増加や妊娠高血圧症候群、児の新生児低血糖のリスクが低下したことが報告されている。一方、日本では妊婦又は妊娠している可能性のある女性に禁忌であり、現状では大規模データを使用した処方状況の調査は実施されていない。そこで本研究では、レセプトデータを用いて、妊娠中の糖尿病の合併と、メトホルミンを含む糖尿病治療薬の処方状況について調査した。【方法】 株式会社JMDCの保有する妊婦レセプトデータ(2005年1月-2017年6月診療分)107,629名分より、妊娠前に糖尿病(ICD-10コード:E10-E14)、及び妊娠糖尿病(ICD-10コード:O24)と診断を受けていた妊婦及び、妊娠中(出産日から280日遡る)に糖尿病と診断を受けた妊婦を特定し、各病態における診断状況と処方薬について調査した。処方データより糖尿病治療薬(ATCコード:A10)を妊娠中に使用していた妊婦から、処方人数、処方割合について調査した。本研究は高崎健康福祉大学倫理審査委員会の承認を受けて行った。【結果・考察】 妊娠前に糖尿病の診断を受けていた妊婦は 1,502人(1.4%)、妊娠中に糖尿病と診断を受けた妊婦は4,763人(4.4%)であった。妊娠前に診断を受けた群、妊娠中に診断を受けた群の両方で、1型糖尿病より2型糖尿病が多かった。全病態において、インスリン単独治療が最も多く、第一選択薬である傾向が確認できた。次に処方が多いのは、メトホルミンであり、糖尿病治療薬を処方されていない妊婦も多数確認できた。我が国における妊娠糖尿病の罹患率は7-9%であり、本研究のレセプト調査における妊娠糖尿病罹患率と比較すると、大きく差はなく、本データが概ね日本全体を反映していると考えられた。インスリン以外の治療薬が処方されていた妊婦も確認できたが、初期には妊娠に気付かず服用していた妊婦も含まれていた可能性が示唆された。また、メトホルミンに関しては、妊娠0-31日以内に治療を中止している妊婦もおり、多嚢胞性卵巣症候群による排卵障害の治療に処方され、妊娠が判明し処方中止した例も含まれているのではないかと考えられた。【結論】インスリン単独治療が最も多く、メトホルミン使用例も確認できた。今回、メトホルミン服用妊婦数が少なかったことから、メトホルミン服用妊婦数の多い母集団を使用し、安全性について検討することが今後の課題であると考えられる。
1 0 0 0 OA チューリングテストによるAIと人の特徴分析の予備的研究
- 著者
- 赤堀 侃司
- 出版者
- AI時代の教育学会
- 雑誌
- AI時代の教育論文誌 (ISSN:24364509)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.1-6, 2019 (Released:2021-09-10)
- 参考文献数
- 10
人工知能(以下,AIと略す)と人の特性についてチューリングテストを用いて抽出した結果を基に, 学習に適用することを目的として本研究を実施した。チューリングテストを用いて,問いかけに対してAIが答える回答と特定の人が答える回答を,60名の実験協力者に提示し,どちらの回答がAIかを判定してもらいその正答率を求めた。同時にAIの回答内容を吟味して,もし人間だと仮定したらどの年齢レベルかを推定してもらった。その結果,AIだと正答した率は17問全体の平均値が0.81と高い値であった。また人間だと仮定した時の推定年齢は,平均的にはおよそ中学生レベルと推定された。ただし,この結果は提示した問いの内容に強く依存することがわかった。さらに年齢推定において,その理由を自由記述で書いてもらい分析した結果,AIと人間の顕著な特徴が見出せた。この結果を元に, AI時代を生きる子どもたちの学習についての示唆を得た。
- 著者
- 森岡 千廣 北野 朋子 蔵本 成美 伊藤 萌夏
- 出版者
- 日本語教育方法研究会
- 雑誌
- 日本語教育方法研究会誌 (ISSN:18813968)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.2, pp.22-23, 2022 (Released:2022-06-13)
- 参考文献数
- 2
The authors have conducted an activity aimed at creating a video for exchange students in a Japanese language school describing “life as exchange students in Japan.” The purpose of the video is to help with enhancing these exchange students’ language skills and intercultural awareness. The video also aims to encourage Japanese people with whom the video is shared to be interested in foreigners living in Japan. The creators were interviewed twice – once after editing the video, and again after receiving feedback from Japanese people who watched it. The results were that they felt a sense of achievement, especially regarding collaboration with classmates. They were also proud to see that Japanese viewers and exchange students had deepened their willingness to communicate with each other.
1 0 0 0 OA IV 普及・展示事業
- 出版者
- 東洋文庫
- 雑誌
- 東洋文庫年報 = Toyo Bunko nenpō (ISSN:1344476X)
- 巻号頁・発行日
- vol.2020, pp.142-146, 2022-03-16
- 著者
- 石丸 晶子
- 出版者
- 至文堂
- 雑誌
- 国文学解釈と鑑賞 (ISSN:03869911)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.6, pp.p62-66, 1989-06
1 0 0 0 OA 疑「偽古文尚書」考 (中)
- 著者
- 野村 茂夫
- 出版者
- 愛知教育大学
- 雑誌
- 愛知教育大学研究報告. 人文科学 (ISSN:03887375)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.164-153, 1988-02-25
1 0 0 0 福島第一原発事故による海と魚の放射能汚染
- 著者
- 水産総合研究センター編
- 出版者
- 成山堂書店
- 巻号頁・発行日
- 2016
1 0 0 0 OA 広告史的『戦後雑誌広告論』の試み
- 著者
- 島守 光雄
- 出版者
- 日本出版学会
- 雑誌
- 出版研究 (ISSN:03853659)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.80-114, 1977-12-25 (Released:2020-03-31)
- 参考文献数
- 19
1 0 0 0 OA 『北斎漫画』の研究 -その成立と諸問題
- 著者
- 永田 生慈
- 出版者
- 国際浮世絵学会
- 雑誌
- 浮世絵芸術 (ISSN:00415979)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, pp.3-32, 1976 (Released:2020-10-16)
- 著者
- Yuki NAGAMATSU Hiroshi NAGAMATSU Hiroshi IKEDA Hiroshi SHIMIZU
- 出版者
- The Japanese Society for Dental Materials and Devices
- 雑誌
- Dental Materials Journal (ISSN:02874547)
- 巻号頁・発行日
- pp.2020-454, (Released:2021-06-30)
- 参考文献数
- 47
- 被引用文献数
- 4
Electrolyzed waters, containing mainly hypochlorous acid, are used in dental practice because of their high microbicidal effect. For wider use, three neutral electrolyzed water-based gels, namely, HOCl-containing aqueous gels were prepared with a thickening/gelling agent in this study. We evaluated their microbicidal effects against four strains and storage stabilities indicated by available chlorine concentration. Immediately after preparation, all gels (70 ppm) could completely remove microbes by a 3-min treatment. The gel prepared with xanthan gum remarkably reduced its available chlorine concentration even under shaded and refrigerated storage conditions, failing to maintain its microbicidal effect following 1-day storage, whereas other gels, prepared with carboxyvinyl polymer or agar, maintained effective concentration (>20 ppm), with high microbicidal effects following 9-day and 21-day storage, respectively. Neutral electrolyzed water-based gels might be useful to remove oral microbes. Based on our results, agar is the most suitable thickening/gelling agent from the viewpoint of storage stability.
1 0 0 0 OA (書評)福井重雅著「漢代官史登用制度の研究」
- 著者
- 若江 賢三
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.1990, no.40, pp.320-326, 1991-03-30 (Released:2009-11-16)
- 著者
- Mustafa Boğan Mustafa Sabak Mehmet Murat Oktay Hasan Gümüşboğa Tutku Tek Tufan Alatlı
- 出版者
- THE JAPANESE ASSOCIATION OF RURAL MEDICINE
- 雑誌
- Journal of Rural Medicine (ISSN:1880487X)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.3, pp.98-103, 2020 (Released:2020-07-17)
- 参考文献数
- 17
Objective: This study is unique as it examines biological materials brought to the emergency department. The purpose of this study was to investigate the reasons behind the presence of nonhuman biological material in the emergency department.Methods: The materials brought were photographed and a pre-prepared survey form was filled in following examination.Results: A total of 46 biological materials were brought to the emergency department within a 12-month period. Ticks were the most frequently brought material, and the most common reason for bringing them was to get the creature removed from the body. Situations in which the physician did not have knowledge about the material were more frequent among those that were neutral about being satisfied with the attitude of the physician towards the material brought, and satisfaction was higher in cases when the physician was knowledgeable, although this was not statistically significant.Conclusion: Physicians should not condemn biological materials brought into the department after exposure. If possible, they should try to gain more knowledge about them. If the material is not to be stored, once it is made sure that it is not dangerous, it should be disposed of in a medical waste bin. Physicians should be knowledgeable toward the frequency and the types of such agents in their region.
1 0 0 0 OA 援助論における義務の問題-消極的義務と積極的義務のはざま
- 著者
- 馬渕 浩二 Koji Mabuchi
- 雑誌
- 中央学院大学人間・自然論叢 = The Bulletin of Chuo-Gakuin University ―Man & Nature― (ISSN:13409506)
- 巻号頁・発行日
- no.39, pp.176-146, 2015-01-01
南方熊楠が『ネイチャー』誌に投稿したものの掲載されなかった英文論文の分析を通して、自然科学と人文科学の分離過程の時期と、どのジャンルが自然科学に残された/排除されたかを明らかにする。現在の科学というものは、どの雑誌に掲載されるかで、その論文(および著者)が所属するジャンル・分野が決定されている。『ネイチャー』は世界最高峰の科学誌であり、そこに掲載されない分野・ジャンルは、「それは自然科学ではない」と宣言されているに等しい。このような自然科学の側からの動きが、なぜ起こったのかを明らかにすることが、本研究の目的である。
1 0 0 0 OA 微振動を抑制する免震装置の開発
- 著者
- 谷地畝 和夫 稲井 慎介 山本 健史 得能 将紀 小林 正人
- 出版者
- 一般社団法人 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会技術報告集 (ISSN:13419463)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.65, pp.136-141, 2021-02-20 (Released:2021-02-20)
- 参考文献数
- 10
The seismic isolation structure has a habitability problem that it tends to be vibrated when it is always used. Therefore, we have newly developed a seismic isolation device that controls vibration in the infinitesimal range. The seismic isolation device is an elastic slide bearing and an oil damper integrated, and the performance of the damper in the infinitesimal vibration range was confirmed by vibration tests. We confirmed the effect of adopting it in a building by analysis. We also conducted dynamic tests to verify the performance of the seismic isolation device and put it into practical use.
1 0 0 0 OA コミュニケーションとしての査読
- 著者
- 尾見 康博
- 出版者
- 一般社団法人 日本発達心理学会
- 雑誌
- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.1, pp.62-65, 2001-04-20 (Released:2017-07-20)