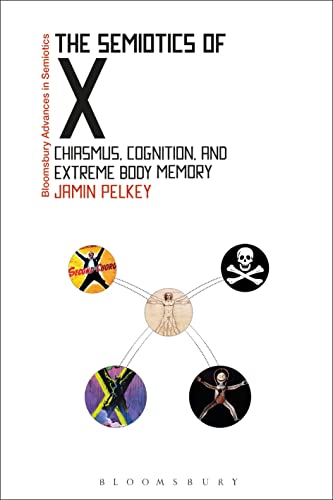1 0 0 0 OA 小学校の廊下の多様化と融合:建築空間のプランニングに関する考察
- 著者
- 鈴木 賢一
- 雑誌
- 芸術工学への誘い = Bulletin Graduate School of Design & Architecture Nagoya City University (ISSN:21850429)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.145-165, 1997-02-28
1 0 0 0 OA 温度依存性を考慮した車両運動解析用タイヤモデルの開発
- 著者
- 水野 雅彦 酒井 英樹 大山 鋼造 磯村 吉高
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会論文集 C編 (ISSN:03875024)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.711, pp.3208-3215, 2005-11-25 (Released:2011-03-04)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 2
The results of vehicle performance tests often vary depending on differences in the road surface temperature. It is believed that these changes can partially be attributed to the effect of tire surface temperature. The aim of this study is to develop a tire force model considering the dependence of tire surface temperature. The newly developed tire model is composed of two functions, the thermodynamic function that allows us to consider changes in the tire surface temperature and the force function that allows for the effects of tire surface temperature. The parameters of this model are identified using the measured data obtained with an indoor test facility. To prove the validity of the developed model, the surface temperature and the tire force values are predicted using this model. The simulation results agreed rather well with the experimental results.
1 0 0 0 OA スポーツ障害・外傷に対する鍼通電療法 - 周波数の違いによる臨床の実際 -
- 著者
- 宮本 俊和
- 出版者
- 一般社団法人 日本東洋医学系物理療法学会
- 雑誌
- 日本東洋医学系物理療法学会誌 (ISSN:21875316)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.2, pp.9-16, 2016 (Released:2020-05-20)
- 参考文献数
- 32
低周波鍼通電療法は、スポーツ分野で広く応用されている。鍼治療は、スポーツ動作の繰り返しによって生じる慢性のスポーツ障害の治療、スポーツ外傷・障害の予防、コンディションの維持など薬物療法より適応範囲が広い。 低周波鍼通電療法は、1970年代に鍼麻酔法として中国で紹介され、それ以降、諸外国で鍼鎮痛のメカニズムが研究されるようになった。また、骨格筋に対する研究では、一過性の筋疲労による筋力や筋持久力の低下を早期に回復することが報告されている。動物実験では、①筋損傷の修復を早める、②筋萎縮の進行を抑制する、③浮腫を抑制する効果があるなど、組織学的にも検証されつつある。スポーツ外傷・障害に対しては、大学スポーツ選手の外傷・障害の効果、腰痛に対する効果、肉離れに対する効果などが報告されている。このように低周波鍼通電はスポーツ分野で広く用いられている。 私たちは、スポーツ外傷・障害の低周波鍼通電療法を行なう際に、周波数を以下の3つに分類して治療を行っている。 (1) 1〜3 Hzは、筋肉が単収縮する周波数で筋の緊張緩和や神経痛などに用いる。また、疼痛閾値の上昇、免疫機能を高めるためには、合谷穴—孔最穴、足三里穴—三陰交穴など手指や足趾が収縮するような刺激をする。電流量は筋肉が収縮する程度の強さとする。通電時間は、通常15分程度とするが、鍼麻酔などによる全身の痛覚閾値の上昇を期待する場合は30分行う。 (2) 30〜60 Hzは、筋肉が強縮する周波数で筋疲労の軽減や腱炎などに用いる。アキレス腱炎や筋腱移行部に起こった肉離れなどで用いる。間欠的な刺激をする場合が多い。電流量は刺激した筋肉または腱が強縮する強さとする。持続的刺激以外に間欠的な通電刺激を行うことが多い。通電時間は15分程度とする。 (3) 100〜120 Hzは、筋収縮は起こらないが通電局所に刺激を感じる周波数である。関節部の痛みなどの局所鎮痛や腫脹の軽減などに用いる。電流量は、刺鍼部に刺激を感じる程度とする。持続的刺激以外に間欠的な通電刺激を行うことが多い。通電時間は15分程度とする。 本稿では、スポーツ外傷・障害の治療法を紹介するとともに、運動後の免疫力低下に及ぼす効果について紹介する。
I discuss the propagation of very low frequency infrasound that come from volcanic eruptions from near surface to the ionosphere based on the observations of GNSS-TEC, broadband seismometers and barometers. Infrasound or some other atmospheric wave under ~10 mHz can reach to the ionosphere and shake the ionized atmosphere. For example, a great earthquake induces not only ground motions or tsunamis but also atmospheric perturbations and some of them propagate upward to the ionosphere. Such waves are interpreted as the acoustic modal wave, the tsunamigenic gravity wave or the atmospheric wave coupled to the seismic Rayleigh wave. Ionospheric perturbations by volcanic eruptions are also sometimes reported. In my master thesis written in 2015, I discussed the ionospheric disturbances made by the 2014 Kelud volcano eruption. It induced acoustic trap mode by continuous eruption. In the thesis, I would introduce the investigation about the propagation of the atmospheric disturbance by the 2015 Kuchinoerabujima eruption. I analyzed 1 Hz sampled GNSS-TEC time series, broadband seismograms and barograms installed around the volcano. The features of the ionospheric disturbances observed in the two case are totally different. I can confirm again with more assurance that the difference comes from the sequence of the volcanic eruptions.
1 0 0 0 OA 臨床研究のエビデンスを薬局現場へ:COMPASS, COMPASS-BP研究の結果から
- 著者
- 岡田 浩
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)
- 巻号頁・発行日
- vol.142, no.3, pp.211-214, 2022-03-01 (Released:2022-03-01)
- 参考文献数
- 8
Evidence-based medicine (EBM) has led to the development of evidence-based guidelines. The quality of guidelines has been improved by measuring their quality with The Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation II (AGREE II) and Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation (GRADE). However, evidenced by guidelines not implemented in clinical practice or society, the evidence-practice gap has become apparent. The dissemination and implementation research, which studies methods to solve this problem, has attracted the attention of both clinicians and clinical researchers in recent years. In hypertension and diabetes, it is possible to prevent complications by maintaining good blood pressure and blood glucose levels. However, it is difficult for patients to maintain good laboratory values over the long term, and there has been no solution to this problem. Recently, it has been reported that pharmacists in the U.S. and Canada can improve patient outcomes over the long term by using pharmacies to treat these diseases. This review describes the results of the COMPASS study (diabetes) and the COMPASS-BP study (hypertension), which are the first cluster randomized controlled trials conducted in pharmacies in Japan. In addition, it discusses the possibility of implementation in pharmacies in Japan.
1 0 0 0 OA 転機におけるキャリア支援のオートエスノグラフィー
1 0 0 0 Voice of voices
- 出版者
- 朝日放送
- 巻号頁・発行日
- no.16, 1959-10
1 0 0 0 奈良県立奈良図書館月報
- 出版者
- 奈良県立奈良図書館
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.11, 1930-11
- 著者
- Jamin Pelkey
- 出版者
- Bloomsbury Academic
- 巻号頁・発行日
- 2017
1 0 0 0 OA CDDP誘発消化器症状に対するMetoclopramide大量投与法の検討
- 著者
- 山田 弘之 久保 将彦 村井 須美子 坂倉 康夫
- 出版者
- 耳鼻咽喉科臨床学会
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科臨床 (ISSN:00326313)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.7, pp.1163-1168, 1987-07-01 (Released:2011-11-04)
- 参考文献数
- 12
Large doses of metoclopramide as an antiemetics were administered to 9 patients recieving cisplatin (CDDP) (50mg/m2) for head and neck cancers. Metoclopramide, 2mg/kg was administered four times intravenously on the first day of CDDP therapy and once a day on days 2-7. Neither emesis nor nausea occurred in 8 of the 9 patients (89%). Side effbcts were minimal: mild sleepiness(66.7%)and diarrhea(22.2%). It is concluded that the antiemetic effect of intravenous metoclopramide in large amounts can prevent cisplatin-induced emesis.
1 0 0 0 OA ストレスタンパク質とミクログリアによるアミロイドβ貪食機能
- 著者
- 北村 佳久 高田 和幸 谷口 隆之
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.124, no.6, pp.407-413, 2004 (Released:2004-11-26)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 1 1
小胞体はタンパク質の品質管理を行う細胞内小器官であり,その機能不全によって折り畳み構造の異常なタンパク質が増加・蓄積する.異常タンパク質の蓄積が基盤となり発症する疾患はコンフォメーション病と呼ばれ,アルツハイマー病(AD)などの神経変性疾患がその疾患の一つとして考えられている.AD脳では,細胞外におけるアミロイドβタンパク質(Aβ)の蓄積により形成される老人斑や,神経細胞内で異常リン酸化タウタンパク質の蓄積により形成される神経原線維変化が観察されるが,現在では,脳内Aβの蓄積がAD発症メカニズムの上流に位置すると考えられている.細胞外でのAβ蓄積に対するストレス応答反応として,ミクログリアが老人斑に集積するが,その役割は不明である.近年,我々は,ラット培養ミクログリアがAβ1-42(Aβ42)を貪食し分解すること,その貪食には低分子量Gタンパク質のRac1やその下流で働くWiskott-Aldrich syndrome protein family verprolin-homologous protein(WAVE)により制御されるアクチン線維の再構築が関与することを明らかにした.さらに,ミクログリアによるAβ42貪食は,ストレスタンパク質であるHeat shock proteins(Hsp)により増強され,反対に,核内タンパク質として知られるHigh mobility group box protein-1(HMGB1)により阻害されることがわかった.このような,ミクログリアによるAβ42貪食メカニズムの解明や調節に関する研究を基盤として,新規AD治療法の開発が期待される.
1 0 0 0 能力差に応じた各科の指導 : 移行措置をふまえた指導の革新
1 0 0 0 OA ワカサギ人工受精卵の孵化ならびに孵化仔魚の生残に対する飼育水の塩分濃度の影響
- 著者
- 岩井 寿夫 長間 弘宣
- 出版者
- Japanese Society for Aquaculture Science
- 雑誌
- 水産増殖 (ISSN:03714217)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.2, pp.95-102, 1986-09-30 (Released:2010-03-09)
- 参考文献数
- 14