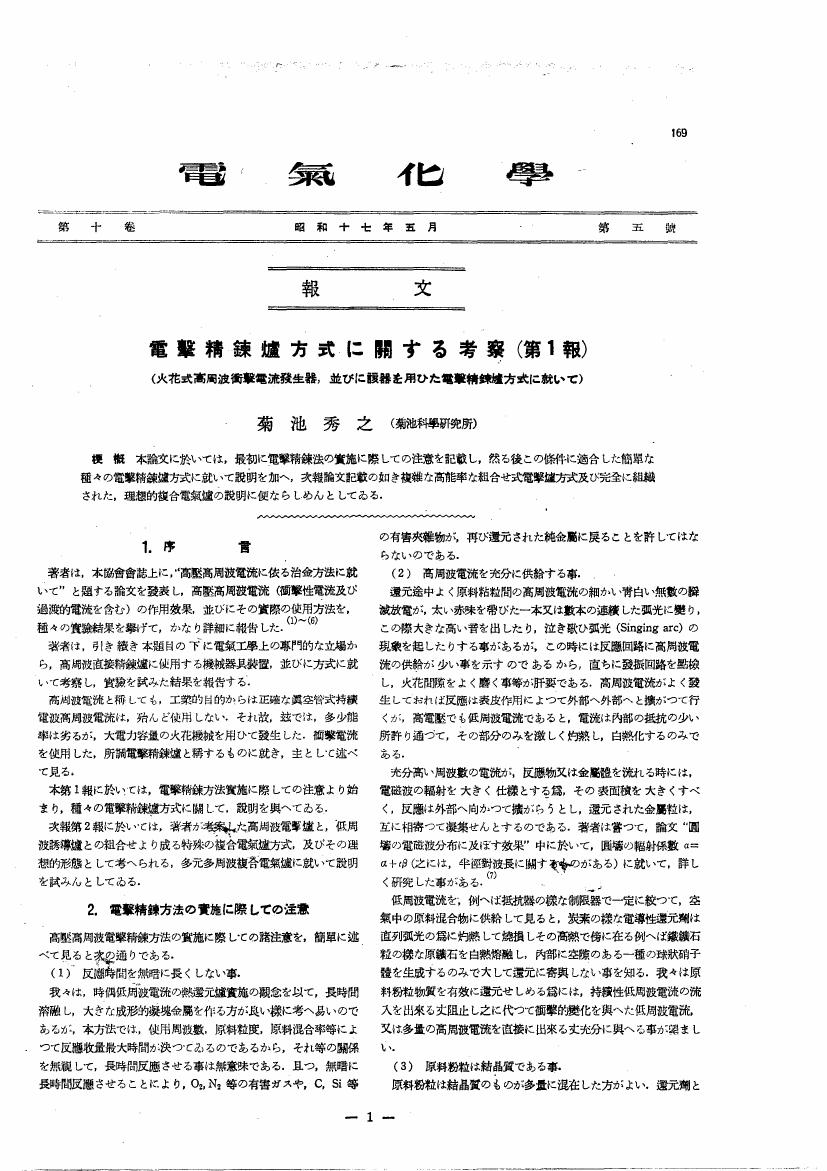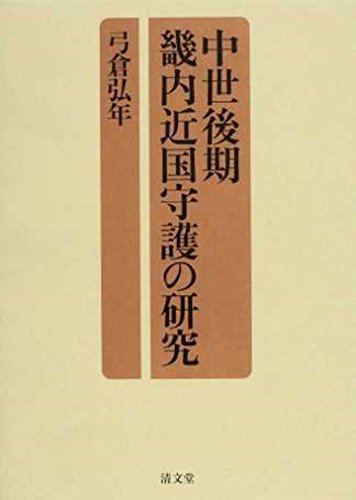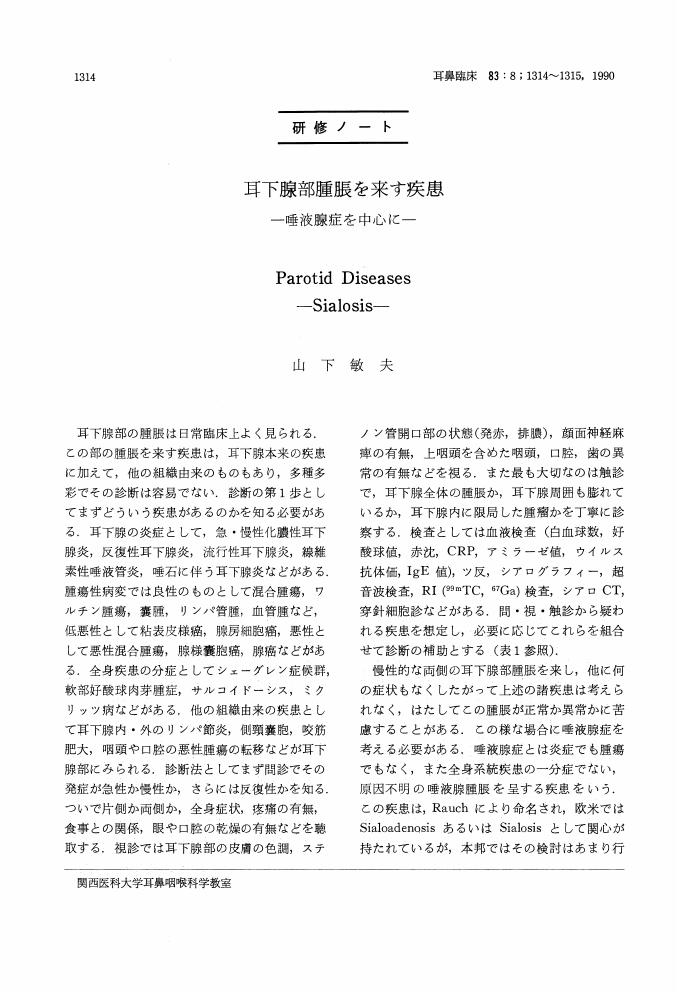1 0 0 0 コラム:ヘルスサイエンス情報専門員:認定制度活用の一例
- 著者
- 牛澤 典子
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.6, pp.220-223, 2022-06-01 (Released:2022-06-01)
- 著者
- 砂生 絵里奈
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.6, pp.215-219, 2022-06-01 (Released:2022-06-01)
- 著者
- 井上 透
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.6, pp.210-214, 2022-06-01 (Released:2022-06-01)
デジタルアーカイブは,文化・科学・教育・産業資源をデジタル化により保存・継承・公開することで,情報への継続したアクセスを担保し,意思決定やイノベーション,リスクコントロールを支援することで人々の生活を豊かにする営為・システムである。デジタルアーカイブを開発,運営する人材,デジタル・アーキビストへのニーズは増加している。2006年に始められた日本デジタル・アーキビスト資格認定機構による人材育成制度は①対象・文化の理解,②情報のデジタル記録と利用,そのための③法と倫理から構成されており,図書館司書,博物館学芸員,自治体職員,教育関係者,企業関係者等約6,700名へ資格を与えている。
- 著者
- 北川 正路
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.6, pp.204-209, 2022-06-01 (Released:2022-06-01)
特定非営利活動法人日本医学図書館協会は,2004年1月に,認定資格「ヘルスサイエンス情報専門員」の申請募集を開始した。本認定資格は,「基礎」,「中級」,「上級」の3種類から構成され,3種類とも,業績と専門職活動によるポイントを自己申告することにより審査・認定がなされる。現在の認定資格の申請,審査・認定の方法は,2014年に本協会にて承認された「専門職能力開発プログラム」に基づいて定められており,認定資格事業が,教育・研究関連の事業と連携して,専門職能力の向上における自己研鑽,自己啓発を支援することを想定している。更に,認定資格の認定は,ヘルスサイエンス情報専門職の専門性が内外に認識されるきっかけとなっている。
- 著者
- 大谷 康晴
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.6, pp.198-203, 2022-06-01 (Released:2022-06-01)
日本図書館協会認定司書は2010年に開始して制度として定着している。しかし,その発足には多くの時間を要している。その原因は「専門性評価」そのものにもあるため簡単な問題ではない。それでも,インフォプロには「専門性評価」は必要と考える。たとえば司書の場合,外部から見てその知識・技能を測ることが難しく社会的評価が低い状態に陥っている。これは経済学でいうレモン市場の状況に近い。この状況を改善するため認定司書のような「専門性評価」は必要であり,インフォプロにおいても同様であると考える。
1 0 0 0 特集:「インフォプロの認定制度」の編集にあたって
- 著者
- 青野 正太
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.6, pp.191, 2022-06-01 (Released:2022-06-01)
今月号は,「インフォプロの認定制度」と題してお届けします。昨今,図書館においては職員の非正規率の増加が指摘され,日本図書館協会図書館政策企画委員会専門職制度検討チームから「専門職制度検討チーム報告~非正規雇用職員が職員数の多くを占める時代における職員制度のあり方について~」(2019年3月)という報告が出されました1)。さらに,日本私立大学連盟が提言した「ポストコロナ時代の大学のあり方~デジタルを活用した新しい学びの実現~」(2021年8月)においては,“基準で想定されている専門的職員(第38条3)である司書は図書館機能の多様化に伴って,図書館職員に求められる能力も多様化したため,形骸化している”と指摘されています2)3)。このように,図書館司書をはじめとするインフォプロの働く環境は厳しい状況にあります。そうした中で,認定制度はスキルや経験を証明することにつながるとともに,キャリア形成を支援する手段となることが期待されます。そこで本特集では,インフォプロの認定制度について経緯を含めて解説し,その意義や今後果たしうる役割を明らかにしたいと考えています。まず,総論として,相模女子大学学芸学部の宮原志津子様には,専門職の質保証として機能している海外の図書館情報学専門職資格の事例を取り上げ,日本の司書資格における課題を示していただきました。次に各論として,3種類の認定制度について,制度運営に携わっている方に,制度づくりの背景から今後の課題に至るまで解説していただきました。青山学院大学コミュニティ人間科学部の大谷康晴様には,日本図書館協会が2010年に創設した認定司書制度についてご解説いただいた上で,専門性評価の必要性と制度化における課題についても触れていただきました。東京慈恵医科大学学術情報センターの北川正路様には,日本医学図書館協会が2004年に創設したヘルスサイエンス情報専門員制度についてご解説いただきました。岐阜女子大学文化創造学部の井上透様には,2006年に始められた日本デジタル・アーキビスト資格認定機構によるデジタル・アーキビスト認定を中心とする人材育成制度についてご解説いただきました。最後に,認定制度の活用事例として,認定司書,ヘルスサイエンス情報専門員として活躍されているインフォプロの方に取組内容をお寄せいただきました。日本図書館協会認定司書第1060号である砂生絵里奈様には,ご自身の認定司書としての活動についてご解説いただきました。ヘルスサイエンス情報専門員(上級)である牛澤典子様には,ご自身のヘルスサイエンス情報専門員としての活動についてご解説いただきました。読者の皆様におかれましては,本特集記事を通して認定制度の現状を理解していただくとともに,制度の活用についても知っていただき,インフォプロのキャリア形成について考えるきっかけとなれば幸甚です。なお,情報科学技術協会で実施している検索技術者検定もインフォプロの能力を認定する制度といえるものですが,別稿で扱う予定のため,今回は取り上げていません。(会誌編集担当委員:青野正太(主査),安達修介,長谷川智,長谷川幸代)1) 専門職制度検討チーム報告:非正規雇用職員が職員数の多くを占める時代における職員制度のあり方について.日本図書館協会図書館政策企画委員会専門職制度検討チーム.2019,34p.http://www.jla.or.jp/Portals/0/data/iinkai/seisakukikaku/senmonshokuseido.pdf, (参照2022-04-26)2) ポストコロナ時代の大学のあり方:デジタルを活用した新しい学びの実現.日本私立大学連盟.2021,23p.https://www.shidairen.or.jp/files/user/20200803postcorona.pdf, (参照2022-04-26)3) なお,日本私立大学連盟は2021年10月21日に“ポストコロナ時代に向け,図書館という場の機能は高度化・多様化する極めて重要な存在”であり,“その機能と合わせ司書の役割は,専門職員として更に大きな意味を持つものであるにも関わらず,現行の大学設置基準の条文では不十分であり,改めてその役割を再定義する必要がある”旨を説明するページを公開しています。“提言「ポストコロナ時代の大学のあり方」における図書館等の記述について”日本私立大学連盟.https://www.shidairen.or.jp/topics_details/id=3412, (参照2022-04-26)
- 著者
- 羽吹 幸 長田 優子 磯村 一弘 Miyuki HABUKI Yuko NAGATA Kazuhiro ISOMURA
- 雑誌
- 国際交流基金日本語教育紀要 = The Japan Foundation Japanese-Language Education Bulletin (ISSN:13495658)
- 巻号頁・発行日
- no.9, pp.59-72, 2013-03-01
映像教材「エリンが挑戦!にほんごできます。」は、「日本語学習」と「文化理解」を目標とした映像素材を提供することを意図して制作された教材で、テレビ版、DVD教材、WEB版とメディアを変えて展開してきた。本稿では2010年から公開しているWEB版のアクセスログと2回のユーザー評価の結果を元に、WEB版「エリン」が世界の日本語学習者からどのように受け入れられたかを考察する。アクセスログによる利用状況では、継続的にページビュー数を増やし、かつ明確な目的を持ったユーザーに利用されている様子が伺える。2回のアンケート調査では非常に高い肯定的評価が得られた。特に、独学に適したコンテンツやインタラクティブな学習方法が評価されており、サイトの制作意図が効果的に活かされていることがわかった。今後は多言語化や画面仕様の改修によりサイトのユーザビリティを高め、さらに多くのユーザー獲得を目指していきたい。
1 0 0 0 OA 永久歯の虫歯発生率と砂糖摂取量に関する疫学的調査
- 著者
- 奥野 和子
- 出版者
- The Japanese Society of Nutrition and Dietetics
- 雑誌
- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.1, pp.19-24, 1976-01-25 (Released:2010-10-29)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 3
A clear relationship between gross sugar consumption and the number of dental caries cases has been found out by many workers. However, this kind of information does not help the activities of dentists or nutritionists toward the prevention of dental caries. A practical strategy to this requires detail information on the amount of sugar consumption due to the specific food eaten by a given group.In this paper, Decayed, Missing, Filled Teeth (DMF) and sugar consumption are related through food and dental surveys of 1058 boys and 1597 girls belonging to different age groups in junior and senior high schools.Findings obtained are as follows:(1) The girls' mean DMF increases sharply and consistently with age. The mean DMF of boys does not increase so sharply as girls but comes to flat at an age of the first year of the senior high school.(2) In the same age group, the sugar intake of girls from soft drinks and sweets is much higher than that of the boys. This may be one of the main reasons why the mean DMF of girls is larger than that of boys. Therefore, dentists or nutritionists should take more efforts to improve food practice of girls.
1 0 0 0 OA 実現されつつある「ユニヴァーシティ広場」としての駒場IIキャンパス
- 著者
- 原 広司
- 出版者
- 東京大学生産技術研究所
- 雑誌
- 生産研究 (ISSN:0037105X)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.3, pp.202-205, 2009 (Released:2009-07-06)
- 参考文献数
- 1
1 0 0 0 OA 電撃精錬炉方式に関する考察(第1報)
- 著者
- 菊池 秀之
- 出版者
- 公益社団法人 電気化学会
- 雑誌
- 電氣化學 (ISSN:03669440)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.5, pp.169-172, 1942-05-05 (Released:2019-11-21)
1 0 0 0 OA 100歳以上の超高齢者における大腿骨近位部骨折手術症例の術後調査
- 著者
- 千々岩 芳朗 金澤 和貴 戸倉 晋 泉 秀樹
- 出版者
- 西日本整形・災害外科学会
- 雑誌
- 整形外科と災害外科 (ISSN:00371033)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.1, pp.89-90, 2022-03-25 (Released:2022-05-06)
- 参考文献数
- 9
100歳以上の大腿骨近位部骨折9症例9股の術後生命予後と歩行能力の変化について検討した.術後30日以内死亡率は22.2%で,平均余命は1.77年であった.術後歩行再獲得率は43%であり,術前より約1.3段階の歩行能力の低下を認めた.100歳以上の超高齢者であっても生命予後及び術後歩行再獲得率が有意に低下するわけではなく,充分な術前評価と周術期管理を行った上で積極的に手術療法を行うべきであると考えられる.
1 0 0 0 中世後期畿内近国守護の研究
- 著者
- Nurdan Paker Derya Bugdayci Goksen Goksenoglu Demet Tekdöş Demircioğlu Nur Kesiktas Nurhan Ince
- 出版者
- The Society of Physical Therapy Science
- 雑誌
- Journal of Physical Therapy Science (ISSN:09155287)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.12, pp.3675-3679, 2015 (Released:2015-12-28)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 36 55
[Purpose] The aim of this study was to investigate the relationship between gait speed and various factors in ambulatory patients with idiopathic Parkinson’s disease. [Subjects] Fifty ambulatory patients with idiopathic Parkinson’s disease who were admitted to an outpatient clinic were included in this cross-sectional study. [Methods] The Hoehn and Yahr Scale was used for measurement of the disease severity. Gait speed was measured by the 10-Meter Walk Test. Mobility status was assessed by Timed Up and Go Test. The Hospital Anxiety and Depression Scale was used for evaluation of emotional state. Cognitive status was examined with the Mini-Mental State Examination. The Downton Index was used for fall risk assessment. Balance was evaluated with the Berg Balance Scale. Comorbidity was measured with the Cumulative Illness Rating Scale. The 36-Item Short Form Health Survey was completed for measurement of quality of life. [Results] The mean age was 66.7 (47–83) years. Twenty-eight (56%) patients were men. Gait speed was correlated positively with height, male gender, Mini-Mental Examination score, Berg Balance Scale score and physical summary scores of the 36-Item Short Form Health Survey. On the other hand, there was a negative correlation between gait speed and age, disease severity, TUG time, Downton Index, fear of falling, previous falls and the anxiety and depression scores of the Hospital Anxiety and Depression Scale. There was no correlation between gait speed and comorbidity. [Conclusion] The factors related with the slower gait speed are, elder age, clinically advanced disease, poor mobility, fear of falling, falling history, higher falling risk, and mood disorder.
1 0 0 0 OA 九州北部及び隣接地に於ける社寺所蔵棟札の内容 : 記号と呪符
- 著者
- 佐藤 正彦
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.484, pp.213-219, 1996-06-30 (Released:2017-02-02)
- 被引用文献数
- 1 1
Since a fire is the most dreaded disaster for a wooden building, signs and symbols of fire prevention are commonly used on "munafuda" (dedication board). These sings are, for instance "[figure]" symbolizing water, or ones which stand for the sun, the moon and stars. Especially, stars of 28 hotels are popular, such as "△" representing the star of the triangular seat, that is, the north heaven. The Chinese character 'seal' is used as a magical sign of 'cutting of a seal' and also of 'enclosing something inside' ; sometimes the mere symbol "[figure]" is applied in the same occasions."[figure]" occasionally symbolizes four kings. The sign "[figure]", meaning 'nine characters are cut' in Yin and Yang theory, is used. Again, in Buddhist temples, munafuda registers "卍" symbols.
1 0 0 0 OA 純粋手続き的正義と分配パタン指定の隘路 ―理論と制度的指針の検討
- 著者
- 大庭 大
- 出版者
- 日本政治学会
- 雑誌
- 年報政治学 (ISSN:05494192)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.2, pp.2_312-2_335, 2019 (Released:2020-12-21)
- 参考文献数
- 35
本稿は、純粋手続き的正義の理論に焦点を当て、その理論的意義を明らかにするとともに、制度的考察までを射程に含む分配的正義の有力なアプローチとしてこれを提示することを目指す。純粋手続き的正義のアプローチがロールズ理論の体系において一貫性をもつことの論証を通じて、その理論的擁護可能性を示したのち、純粋手続き的正義のアプローチが制度・政策のパタン指定性について独自の視点を提供し、制度的構想を導く指針ともなりうることを示す。より細かくは、まず1 ~ 2節で、純粋手続き的正義について、ロールズの議論を分析・整理することでその特徴の精確な見取り図を提示する。純粋手続き的正義の異なる類型をみたのち、原理適用段階における正義の指令を統べるアプローチとして、準純粋手続き的正義の社会過程説を特定する。そのうえで3節では、パタン指定という論点を中心にロールズ的な純粋手続き的正義の分配制度上の含意を論じる。4節では純粋手続き的正義の非ロールズ的構想について検討する。
1 0 0 0 OA 耳下腺部腫脹を来す疾患 ―唾液腺症を中心に―
- 著者
- 山下 敏夫
- 出版者
- 耳鼻咽喉科臨床学会
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科臨床 (ISSN:00326313)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.8, pp.1314-1315, 1990-08-01 (Released:2011-11-04)
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 工業的立場から見たC4の化学
- 著者
- 桜木 健民
- 出版者
- The Society of Synthetic Organic Chemistry, Japan
- 雑誌
- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.3, pp.256-261, 1967-03-01 (Released:2011-03-01)
- 参考文献数
- 13