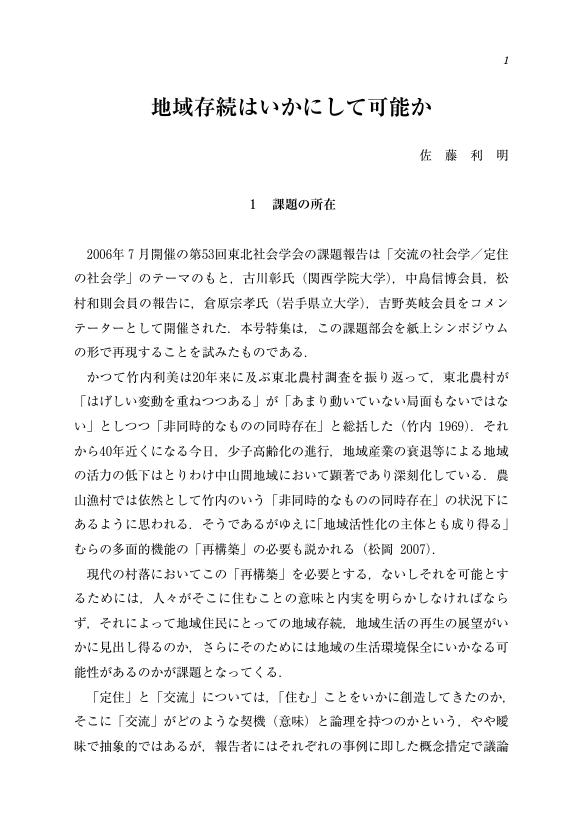1 0 0 0 OA 「ドクトリン」としての「ガヴァナンス」
- 著者
- 牧原 出
- 出版者
- 東北社会学会
- 雑誌
- 社会学年報 (ISSN:02873133)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.47-48, 2008-07-17 (Released:2013-12-27)
- 参考文献数
- 3
1 0 0 0 OA グローバル・ガヴァナンスとヨーロッパ・ガヴァナンス ―政治学から―
- 著者
- 坪郷 實
- 出版者
- 東北社会学会
- 雑誌
- 社会学年報 (ISSN:02873133)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.5-16, 2008-07-17 (Released:2013-12-27)
- 参考文献数
- 23
本稿では,参加ガヴァナンスの視点から,「国民国家を超えるガヴァナンス」について議論をした.参加ガヴァナンスは,「多様な主体による問題解決のための機会を創出する」ものであり,「参加と討議による合意形成」を重視する新たな民主主義の展開である.グローバル・ガヴァナンスは,国際レジームをはじめとする政府間による政策調整システムと,ガヴァナンスの法化と社会化を基礎とする国家横断的な制度やネットワークによる政策調整システムからなる複合的政策調整システムであり,非階層的政策調整を基本とする.他方,「ヨーロッパ・ガヴァナンス」は,超国家機関による階層的政策調整システムと政府間・国家横断的ネットワークによる非階層的政策調整システムの組み合わせによる重層的ガヴァナンスである.EUにおける政策調整は,ヨーロッパ域外を含む国際組織における調整とリンクしており,「拡大された重層的システム」である.さらに,ベァツェルが述べているように,EUに「独特な」超国家機関による「階層的制御の影」が,ヨーロッパ・ガヴァナンスの特徴でもある.重層的ガヴァナンスにおいては,とりわけ民主主義の正統性問題がある.この問題は,「ガヴァナンスがよい政治結果を導いたか」,「政策づくりのプロセスへの多様なアクターの参加拡大」ともかかわるが,実践的には困難が伴う課題である.さらに,重層的ガヴァナンスにおいては,多様なアクター間のコミュニケーションと相互学習プロセスが重視されている.ヨーロッパ・ガヴァナンスは,グローバル・ガヴァナンスの一構成要素であり,その形成プロセスの可能性を示唆するものである.
- 著者
- 山口 健一
- 出版者
- 東北社会学会
- 雑誌
- 社会学年報 (ISSN:02873133)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.149-169, 2007-07-20 (Released:2013-10-23)
- 参考文献数
- 11
本稿はA.ストラウスの相互行為論における,パーソナルな行為者が有するアイデンティティの変容と持続性について検討する. 諸状況においてパーソナルな行為者が意図的であれ非意図的であれ集団の成員として行為する(名づける)とき,その行為者はその行為が示す集合的アイデンティティを有する.パーソナルな行為者は状況的にも時間的にも複数の集合的アイデンティティを有し,それらは時間の経過とともに変容する.またパーソナルな行為者の経歴は,同一化・脱同一化していく地位移行であり,常に新たな集合的アイデンティティを獲得するプロセスである.これがパーソナルな行為者が有する集合的アイデンティティの変容である. パーソナルな行為者による再帰的行為としてのパーソナルなアイデンティティは,過去から未来にわたる経歴における複数の集合的アイデンティティを秩序化したものである.これは再帰的行為の時点においてその行為者が属す集団の用語法によって行われる.しかし再帰的行為の都度パーソナルなアイデンティティの正当性が問われるため,パーソナルなアイデンティティを持続させる営みは継続していく.これがパーソナルな行為者が有するパーソナルなアイデンティティの持続性である.
1 0 0 0 OA 現代日本社会における格差意識
- 著者
- 林 雄亮
- 出版者
- 東北社会学会
- 雑誌
- 社会学年報 (ISSN:02873133)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.189-209, 2007-07-20 (Released:2013-10-23)
- 参考文献数
- 24
本稿の目的は,人々の格差に対する意識の実態を調査分析によって明らかにすることである.用いるデータセットは「2006年格差と不平等に関する仙台市民意識調査」である. 本調査研究で扱った社会格差は,大学進学機会,就職機会,職業上の成功機会,所得,資産,医療サービス受給機会,年金の格差である.これらの格差に対する意識は格差認知(どのくらいの格差があると認知されているか)と格差許容度(認知された格差が許容できるかどうか)に区別される.それぞれの分布は格差の種類によって異なり,全体的には機会の格差は小さく,結果の格差は大きく認知され,福祉の格差についての許容度が低く,所得や資産の格差についての許容度が高いことがわかる.そしてこれらの格差意識は,因子分析の結果,従来の伝統的な階層意識とは別の次元に存在している.さらに,格差意識と社会的属性との関連では,比較的低地位者の格差認知が高く,格差許容度が低い.しかしながら,多変量解析の結果,社会的属性の影響は決して強くはない.
1 0 0 0 OA 有害事象における不信増幅のプロセス ―医療訴訟の事例分析から―
1 0 0 0 OA 『社会分業論』再考 ―ナショナリズム論の視角から―
- 著者
- 安達 智史
- 出版者
- 東北社会学会
- 雑誌
- 社会学年報 (ISSN:02873133)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.105-125, 2007-07-20 (Released:2013-10-23)
- 参考文献数
- 11
本稿は,デュルケムの『社会分業論』をナショナリズム論の視角から検討することにより,ネイションという観念を近代社会における連帯の条件として提示することを目的とする.『社会分業論』は,「人格崇拝」および「中間集団論」を論じた著作として,今日なお高く評価されている.人格崇拝の規範は,組織的社会において復元的法律に宿り,社会の機能連関つまり分業を担保する.だが,人格崇拝はいかにして可能なのだろうか.法律は制裁的機能を弱められているのだから,人格に向けられた集合意識は沸騰しない.崇拝には,具体的な表象が必要とされる.本稿では,その表象として,「ネイション」という観念に注目する.そして,集合表象としてのネイションと中間集団による集合意識との結びつきが,深い多様性をもった諸個人の連帯を可能にさせる「道徳的個人主義」を形成することを明らかにする.
1 0 0 0 OA 介護職の業務確立に関する一考察 ―介護老人福祉施設における職種間連携を通して―
- 著者
- 京須 希実子
- 出版者
- 東北社会学会
- 雑誌
- 社会学年報 (ISSN:02873133)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.233-253, 2007-07-20 (Released:2013-10-23)
- 参考文献数
- 9
本論文は,介護老人福祉施設で働く介護職が他専門職,特に密接な関係にある看護師・社会福祉士・栄養士との連携・協働を通して自らの業務内容を確立していく過程を追うことで,介護職の業務確立に関する1つの知見を提示することを目的とする.X県内の介護老人福祉施設A園・B園において参与観察及びインタビューを行い,そこで収集したデータをもとに分析を行った. その結果,介護老人福祉施設における介護職は,入居者の身体介助を軸に業務を行っていた.彼らは,身辺介助業務を専ら任されるようになったことで,常に入居者の傍にいることができ,その結果,どの職種よりも多くの入居者に関する情報を把握することができる状態に置かれていた.そして,彼らは,それぞれの知識に基づいてケアを行う他職種の支援を受けつつ,その情報をもとに,入居者を生活者と捉えるという独自の視点から,業務を行っていた.こうした介護職の独自性は,他職種にも認められつつあり,そこから介護職の専門性が確立される可能性も示唆される. しかし,こうした介護職の業務の在り方は,介護老人福祉施設の職員構成に支えられてはじめて成り立つものであって,職員構成の変化により,入居者の多様な情報を把握できる立場に介護職以外の職種がおかれたとき,連携・協働の在り方の変化及び介護職の業務内容の変化が生じる可能性も考えられる.
1 0 0 0 OA 地域リーダーのありかたと共有される価値をめぐって
- 著者
- 吉野 英岐
- 出版者
- 東北社会学会
- 雑誌
- 社会学年報 (ISSN:02873133)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.99-104, 2007-07-20 (Released:2013-10-23)
1 0 0 0 OA <交流と定住>に触発される「学」と「実践」
- 著者
- 倉原 宗孝
- 出版者
- 東北社会学会
- 雑誌
- 社会学年報 (ISSN:02873133)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.91-98, 2007-07-20 (Released:2013-10-23)
- 参考文献数
- 4
1 0 0 0 OA 「芝生」によるスキー民宿再生の試み ―岩手県八幡平市細野地区の事例―
- 著者
- 中島 信博
- 出版者
- 東北社会学会
- 雑誌
- 社会学年報 (ISSN:02873133)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.31-59, 2007-07-20 (Released:2013-10-23)
- 参考文献数
- 12
本稿は岩手県の山村で農家により自律的に取り組まれたあらたな事業を検討することで,そこでの論理を析出しようとする.具体的には大型のスキー場開発に付随して展開してきた民宿の村が,入り込み客の減少という危機に対応するなかでサッカー場経営に乗り出し,これによって「芝生」の価値を発見すると同時に,有志による組合を結成することで経営を安定化することに取り組んだ事例である.そこでは山村ゆえの目まぐるしい生業変遷の歴史の中で培われてきた経営の体験が活かされており,特に市場感覚にすぐれた対応を分析できる.また,有志が共同で新規の事業に取り組む段階と,ある程度軌道に乗ってからのより広範な家々が共同で運営していく方式も観察できた.初期の段階では既存の資源を最大限に有効利用することで投資を抑え,リスクを最小にする工夫が多様に凝らされていた.また運営にあたっては伝統的なレトリックで共同性を確保し,これによって対外的な競争力も維持している戦略も読み取れた.
1 0 0 0 OA 地域存続はいかにして可能か
- 著者
- 佐藤 利明
- 出版者
- 東北社会学会
- 雑誌
- 社会学年報 (ISSN:02873133)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.1-6, 2007-07-20 (Released:2013-10-23)
- 参考文献数
- 4
1 0 0 0 OA 定住者の知と交流の論理 ―愛知県矢作川の事例から―
- 著者
- 古川 彰
- 出版者
- 東北社会学会
- 雑誌
- 社会学年報 (ISSN:02873133)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.7-29, 2007-07-20 (Released:2013-09-20)
- 参考文献数
- 14
本稿の目的は主に愛知県矢作川流域の所有,管理,利用にかかわる関係主体(アクター)の歴史過程の検討を通して,定住者(コミュニティ)の知と交流の論理について議論することである.とくに本稿では,河川環境保全主体としては注目されてこなかった内水面漁協,河川につよい権利を持つ農業水利団体,河川管理者としての行政,そして環境保全などにつよい関心をもって1980年代から登場する市民グループとの関わりの変化に焦点をあてて記述,分析をおこなった. その結果,1990年代以降の河川の環境化によって,諸アクターの活動は流域社会へと開かれ(流域社会化),それぞれのコミュニティに固定化されてきた範域的な関係主体(アクター)が,多様なアクターと関係を取り結ぶことで,アクター間の垣根を低くしてゆるやかに結ばれる関係的なアクターへと変化し,あらたな開かれたコミュニティを形成しつつあるプロセスを明らかにした.
1 0 0 0 OA 看護師の過労と長時間勤務 サービス残業はなぜなされるのか―
- 著者
- 佐藤 典子
- 出版者
- 日仏社会学会
- 雑誌
- 日仏社会学会年報 (ISSN:13437313)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, pp.1-16, 2019-11-30 (Released:2021-08-25)
2008 年、若手看護師が過労死認定される事件が相次ぎ、同年の日本看護協会の調査では、23 人に1人、約2 万人の看護師が過労死危険レベル(残業時間が月60 時間となった判例から)で働いている(特に経験の浅い20 代の看護師)ことがわかった。勤務時間インターバルは、ホワイトカラー全体では、11 時間未満が10.4%、教員が26.3%だが、日本看護協会によれば、2 交代制、3 交代制勤務の看護師は、3交代制ではインターバルが実質4 時間、2 交代制の場合、80%以上の看護師が15 時間以上、 17 時間の長時間夜勤を行っているなど、シフトが厳守されないことによる長時間労働を行っていることが示された。 そこで、看護師の過労(死)は、なぜ、生まれるのか。長時間労働は、いかにしてなされるのか。また、サービス残業の問題などを看護師の働き方を時間から考えることで新たな視点を示したい。というのは、看護職の時間外労働による過労が常態化し、それに見合った手当がなされていないこと、それ以外にも、看護職本来の業務以外に行うことが自明視されていることが看護職にとっての大きな負担となっているからである。それでは、なぜこのようなことが起きているのかということについて、いくつかの視点から考察したい。
- 著者
- 千葉 太郎 加藤 明子 浜渡 千春
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.5, pp.408-415, 2011-05-01 (Released:2017-08-01)
- 参考文献数
- 14
近年は医療に関する種々の問題が表面化しており,これらの問題は過重労働を介して医療従事者の健康を損ねることにつながっていると思われる.そこで,問題点と過重労働との関連や医療従事者の健康を守るための対策について,特に勤務医を対象として考察した.わが国はOECD諸国の中で人口あたりの医師数は少なく,また病院数は減少傾向にある.厚生労働省によると,勤務医の1週間の総労働時間は63.3時間ときわめて長い.さらには医療関係訴訟も増加している.これらの状況から,勤務医は劣悪な労働状況の中で過重労働を強いられているといえる.日本医師会の調査では,勤務医には睡眠状況の悪い者が多く,また自分の体調不良を他の医師に相談する者は少なく,悲しみを自覚する医師,死や自殺について考える医師も少なからずみられるという.さらに医師の自殺は2005年に年間90件あり,自殺率は一般の日本人と比べて1.3倍と高い.このような労働状況とその帰結としての心身の不健康は,医療費抑制政策,新医師臨床研修制度,さらに医師-患者間の関係性の希薄化などと関連すると考えられる.勤務医の健康を守るために最も重要なのは,「人的資源」としての医療従事者の健康を守ることによって国民の健康と命を守るという立場から,国が対策に取り組むことである.
1 0 0 0 OA [細川忠興同夫人等書状]
- 巻号頁・発行日
- vol.第4軸 細川忠興夫人消息 二,
1 0 0 0 OA 発熱と易疲労感に対して半夏瀉心湯が有効であった一例
- 著者
- 沢井 かおり 渡辺 賢治
- 出版者
- 一般社団法人 日本東洋医学会
- 雑誌
- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.4, pp.311-315, 2015 (Released:2016-02-09)
- 参考文献数
- 11
発熱と易疲労感は感染症や悪性腫瘍,膠原病で生じるが,原因不明のことも多い。今回発熱と易疲労感が長期間続く女性に対し,消化器症状に注目して半夏瀉心湯を用いたところ,著明に改善した症例を経験したので報告する。 症例は47歳女性で,3年前月経不順や不正出血とともに発熱と易疲労感が出現した。夕方から38°C弱の発熱があり,朝から倦怠感が強く就業不能のこともあった。血液検査で肝機能,腎機能,炎症反応などに異常はなく,腹部CT 検査は子宮筋腫を認めるのみであった。漢方医学的診断はやや虚証,寒熱錯雑証,気滞・瘀血で,軟便・下痢傾向という消化器症状と心下痞鞕に注目して半夏瀉心湯を投与したところ,1ヵ月で発熱は37°C前後に低下し,身体が楽になって就業不能の日が減った。5ヵ月後には体温が36°C台となり,易疲労感は消失した。半夏瀉心湯は,消化器症状があり心下痞鞕を呈する症例の様々な症状に有効である可能性が示唆された。
- 著者
- Masayuki Takeda Yusuke Shibata Tetsuya Matsumoto Takuya Kida Ayumi Shinohara Shuichi Fukamachi Takeshi Shinohara Setsuo Arikawa
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.3, pp.370-384, 2001-03-15
This paper describes our recent studies onstring pattern matching in compressed textsmainly from practical viewpoints.The aim is to speed up the string pattern matching task in comparison with an ordinary search over the original texts.We have successfully developed (1) an AC type algorithmfor searching in Huffman encoded files and (2) a KMP typealgorithm and (3) a BM type algorithm for searchingin files compressed by the so-called byte pair encoding (BPE).Each of the algorithms reduces the search timeat nearly the same rate as the compression ratio.Surprisingly the BM type algorithm runs over BPE compressed filesabout $1.2$--$3.0$ times faster thanthe exact match routines of the software package {?tt agrep} which is known as the fastest pattern matching tool.
- 出版者
- 地域医療振興協会地域医療研究所
- 巻号頁・発行日
- vol.12(5), no.139, 1998-05
1 0 0 0 OA 芍薬甘草湯の併用が症状の改善に有効であった破傷風の1例
- 著者
- 中永 士師明
- 出版者
- 一般社団法人 日本東洋医学会
- 雑誌
- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.4, pp.471-476, 2009 (Released:2010-01-13)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 4 5
芍薬甘草湯は筋弛緩目的に使用される漢方薬である。今回,破傷風の全身痙攣の緩和目的に芍薬甘草湯を併用した1例を経験した。患者は32歳の男性で,飼い犬に咬まれた咬傷から破傷風を発症した。全身痙攣に対してプロポフォールを投与し,芍薬甘草湯も併用したところ,プロポフォールを漸減することができた。持続勃起症,腹痛,振戦,不眠などが一過性にみられたが,芍薬甘草湯の服用を継続することで消失した。患者は後遺症なく第14病日に退院した。これまでに破傷風に芍薬甘草湯を使用した報告はないが,筋痙攣の制御や自律神経系過緊張の緩和を目標に使用できると思われた。
1 0 0 0 OA 長縄宣博著『イスラームのロシア:帝国・宗教・公共圏 1905-1917』
- 著者
- 渡邊 日日
- 出版者
- 日本ロシア文学会
- 雑誌
- ロシア語ロシア文学研究 (ISSN:03873277)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, pp.176-199, 2018-10-15 (Released:2019-05-22)