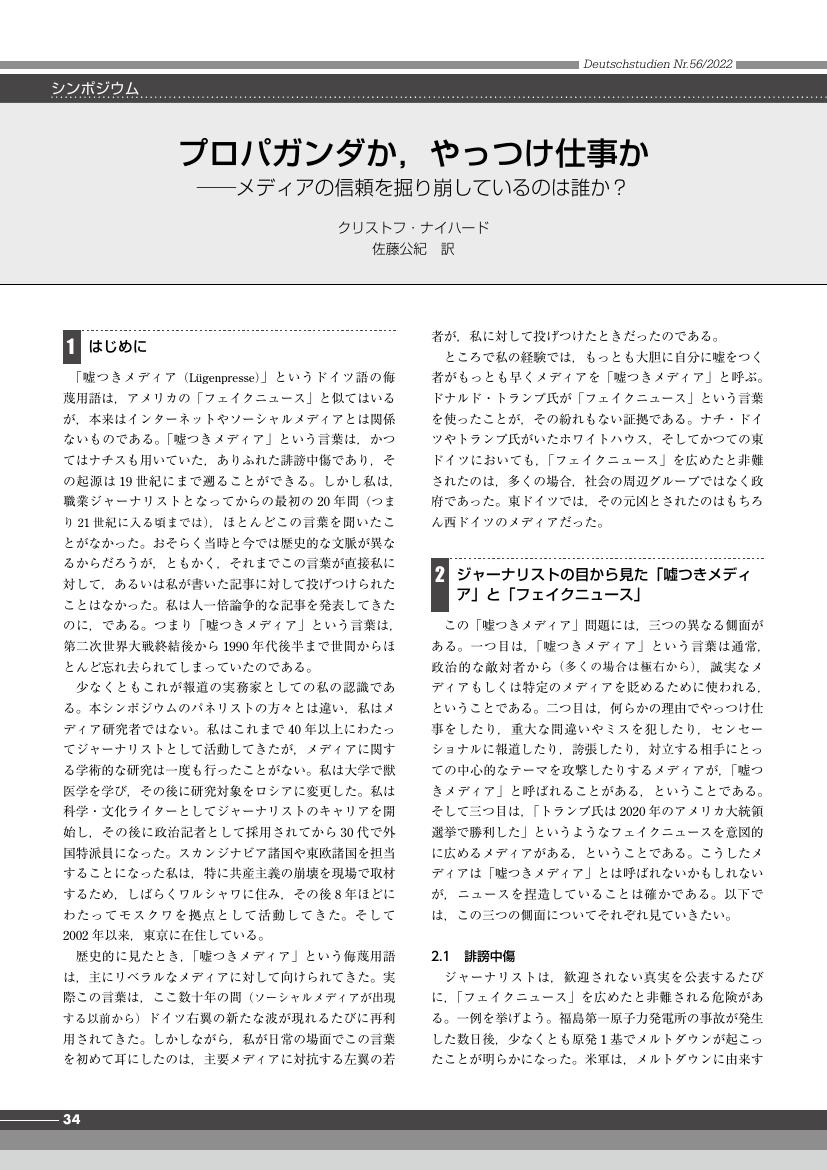1 0 0 0 OA 1950年代の在日朝鮮人美術家の活動 「在日朝鮮美術会」を中心に
- 著者
- 白 凛
- 出版者
- カルチュラル・スタディーズ学会
- 雑誌
- 年報カルチュラル・スタディーズ (ISSN:21879222)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.137, 2017 (Released:2019-10-09)
- 参考文献数
- 6
本稿は50 年代の在日朝鮮人美術家の活動の背景に焦点をあて、彼らの美術作品やグルー プがいかなるものであったかを明らかにするものである。特に在日朝鮮人美術家が組織し た初めての本格的なグループである「在日朝鮮美術会」に着目した。冒頭では、これにつ いてこれまで直接的に論じたものがなく本稿で初めて扱うことになるため二つの留意点を 述べたうえで本稿の目的を述べた。第一章では調査状況について述べた。第一節では美術 作品の調査について美術館や博物館、個人蔵のものも含めこれらの管理状況に触れた。第 二節ではこれまでに発掘した一次史料、第三節では聞き取り調査について、それぞれ本稿 で扱う史料を中心に簡潔に述べた。中心となる第二章では1950 年代の彼らの活動について いくつかの事例を挙げて論じた。第一節では美術家たちが個別の経験を積んでいた1940 年 代終盤から1953 年までの活動を整理した。第二節では在日朝鮮美術会の結成を後押しした 金昌徳を中心とした美術家たちの活動について述べた。第三節では彼らの表現方法につい て白玲の制作を中心に論じ、続く第四節では彼らのテーマ制作について一次史料をもとに 分析した。50 年代の彼らの作品は、いかに描くべきか、何を描くべきかについての模索の 末に生まれたことを明らかにした。第三章では、彼らの作品の発表の場と反響について述 べた。第一節では「日本アンデパンダン展」、第二節では「日朝友好展」、第三節では「連立展」 を取り上げた。最終章では、本稿でとりあげた在日朝鮮人美術家が、植民地や戦争に人生 を翻弄されたという共通の境遇と、解放民族として堂々と生き表現したいという共通の希 求を持っており、朝鮮人美術家としていかに生き表現するかについての答えを共に模索す る美術家が必要であった点を明らかにし、ここに集団の必然性があると結論付けた。最後 に今後の課題を提示した。
1 0 0 0 OA トランプランドにおける文化政治 政権発足から最初の100日間
- 著者
- コンドリー イアン 栗栖 由喜
- 出版者
- カルチュラル・スタディーズ学会
- 雑誌
- 年報カルチュラル・スタディーズ (ISSN:21879222)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.25, 2017 (Released:2019-10-09)
- 参考文献数
- 4
1 0 0 0 OA 特集のねらい
- 著者
- 有元 健
- 出版者
- カルチュラル・スタディーズ学会
- 雑誌
- 年報カルチュラル・スタディーズ (ISSN:21879222)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.3, 2017 (Released:2019-10-09)
- 著者
- 時津 啓
- 出版者
- カルチュラル・スタディーズ学会
- 雑誌
- 年報カルチュラル・スタディーズ (ISSN:21879222)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.79, 2017 (Released:2019-10-09)
- 参考文献数
- 27
本稿は、メディアと生徒の関係に注目し、バッキンガムが抑圧/自律の二元論をいかに構成し、それが学校教育論としていかに応用されていったのかを検討した。さらに、バッキンガムの展開から二元論が有する両義性を明示し、その学校教育論としての可能性を考察した。バッキンガムは、マスメディアのイデオロギー性(メディアの特性論)をめぐってマスターマンと論争を行い、メディアの特性と子どもへの影響を結びつける。そしてメディアと生徒の関係を抑圧/自律の二元論で捉える。その後この二元論は、授業実践における教師の役割と結びつけられ、マスターマンを批判するために利用された。さらには、メディア批判の教育論/メディア制作の教育論、読むこと/書くこと、受動的知識/能動的知識などの教育方法論へも応用され、新たな二元論を生み出すことになった。デューイやイリイチとも連続性を有するこの二元論を、本稿は、同時代の社会状況、とりわけメディア教育のカリキュラム化(制度化)と照らし合わせた。 バッキンガムとマスターマンの理論展開に注目すると、両者はメディア教育のカリキュラム化(制度化)内部でメディアと生徒の関係を捉えるようになる。具体的には、抑圧/自律の両義性を強調するようになる。本稿は、この展開からマスターマン(「解放の教育学」)とバッキンガム(「参加の教育学」)の学校教育論としての妥当性を検討し、次のことを明示した。マスターマンの試みは抑圧関係を前提とする「解放の教育学」のため、抑圧/自律の両義性と矛盾する。それに対してバッキンガムの試みは、生徒が授業参加を通して身体レベル、物質レベルにおいて漸進的にメディアとの関係を構築していく可能性がある。本稿は、制度と「知」の関係を模索するメディア教育学者バッキンガムの理論展開から、「解放の教育学」から「参加の教育学」への転換の必要性を明らかにした。
1 0 0 0 OA ウガリト語動詞用法の一問題 三人称男性複数未完了形をめぐって
- 著者
- 小野寺 幸也
- 出版者
- 一般社団法人 日本オリエント学会
- 雑誌
- オリエント (ISSN:00305219)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.2, pp.17-39,199, 1976 (Released:2010-03-12)
It was as early as 1938 when A. Goetze pointed out the existence of tagtulu (na) verbal form in Ugaritic third masculine plural imperfect conjugation. But virtually all the scholars have done away with this phenomenon as “peculiarity” (e. g. C. H. Gordon), and have not dared to go any further.If we read, however, the text of the Keret Epic carefully, it becomes clear that yagtulu (na) form, which has been universally regarded as the usual verbal form in 3m. pl. impf., does not occur at all. All the thirteen cases in 3m. pl. take the form of tagtulu (na). This finding by the present writer prompted him to investigate all the other Ugaritic material from this viewpoint. The result has been rather drastic. The y-preformative form in 3m. pl. does not appear in the Aqhat Epic either. All the eight examples are in the tagtulu (na) form. Only in the Baal and Anath Cycle and in other minor texts shows up the y-form a few times.In order to explain this interesting phenomenon, one would have to take into consideration the fact that in Amarna Canaanite t-form is employed more frequently than y-preformative conjugation in 3m. pl., a fact first detected by Wm. Moran in 1951. At the same time, one should also pay attention to the situation of Classical Hebrew, where some examples of t-form appear, although to far smaller extent than in Ugaritic and Amarna Canaanite.Based on the results derived from the considerations summarized above, the writer would like to propose some hypotheses as to the possibility of using tagtulu (na) form in 3m. pl. (1) as a chronological criterion to date groups of Ugaritic literature, and (2) as a clue to tighten the link which connects Canaanite dialects or as a clue to subdivide the Northwest Semitic languages in general.
- 著者
- 山口 晃
- 出版者
- 公益社団法人 日本放射線技術学会
- 雑誌
- 日本放射線技術学会雑誌 (ISSN:03694305)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.1, pp.32-37, 2002 (Released:2017-06-30)
1 0 0 0 OA 依存性の発達的研究: III 大学・高校生との比較における中学生女子の依存性
- 著者
- 高橋 恵子
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.2, pp.65-75, 1970-06-30 (Released:2013-02-19)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 2
本研究は, すでに報告した大学・高校生の結果と比較しつつ中学生の依存性の様相をとらえ, 青年期における依存性の発達的変容を考える資料を得ようとするものであった。その結果, 明らかにされたのは次の点であった。1) 依存構造対象間の機能分化の程度は, 一般的にいえば中学生では, 高校・大学生に比べ明確ではなかった。その証拠としては, まず第1に対象間の機能分化がすすみ, よく構造化された, 単一の焦点を持つF型は中学生では25%でしかなく, 高校・大学生に比べて少ない。そして, 第2に, F型と判定される場合にも他の型における同じ対象よりはという相対的な意味では, 焦点となっている対象が中核的とはいえるが, 大学生の同じ型にくらべれば, 機能分化が明確でないと思われる型がみられた。たとえば, 愛情の対象型では, 得点からいえば焦点と判定される愛情の対象であるが, たしかに, 他の型における愛情の対象とは明らかに機能が異なり, 中核的であるとはいえ親友もまた重視されていて, 〈愛情の対象-親友〉型という2F型的な特徴をもっていたのである。また, 親友型でも, 親友よりも母親の方がより中核的と思われるところがあった, という具合である。また, 依存構造の発達の指標のひとつとして, 依存の対象の数の増加・範囲の拡大ということが考えられたのであるが (高橋, 尊1968a), 中学生では, 高校一大学生に比べ, 愛情の対象, 敬する人などに対しての無答が多いことが注目された。つまり, F型でも, そして同じ焦点のF型でも, また型としてのよい構造的特性をそなえていても, 中学生ではそこに含まれる要素がまだ少なく, 発達につれて変化する可能性があるといえるのである。2) 依存要求の強度依存要求の強度は予想どおり, 中学生が高校・大学生に比べて高いということはなかった。母親型が上位・下位群に同程度出現するのに対し, 愛情の対象は上位群でのみ出現しやすいということからすれば, 依存要求の強度は, 幼少時に獲得されたものが一定不変であるとか, 成長につれて減少していくとか考えるのは妥当ではなく, むしろ, ある対象, たとえば愛情の対象に出会ったということにより, 逆にそれ以前より依存要求が強くなるということすらあると考えられよう。3) 中学生女子における依存性依存構造の内容についてみれば, 中学生における依存の対象には次のような特徴がみられた。(1) 単一の焦点となる対象としては, 中学生では, 母親が特に多く, 次が愛情の対象, ついで親友が多く, 父親, きょうだいは焦点になりにくい。 (母親は女子においては一貫して重要な依存行動のむけられる対象であるが, 中学生ではまたいちだんとそうである。(3) 逆に, 父親は女子においては一貫して依存行動をひきおこしにくい対象であるが, 中学生では大学生や高校生, とくに後者に比べれば, かなり重要な対象に近いといえる。しかし, この傾向も, 1年生で顕著なだけで学年の上昇につれて父一娘間には心理的な距離がでてくるし, また, 母親とともになら対象になりうるという高校生でみられた特徴がやはりすでに現われている。父親はなぜ単一では依存の対象になりにくいのであろうか。ひとつには, 父親が「たよりにしている」とか, 様式 (4) とかの道具的あるいは間接的ニュアンスの強い依存行動の向けられる対象になることを考えると, 父親は情緒的な依存行動の対象にはもともとなりにくいのかもしれない。父一娘関係は依存行動というものではなく, 別の角度からとらえることがふさわしいものとも考えられる。が, また一方では, 母親とともにしか対象になりにくいということが, 母一娘関係の中に, 母・父の夫婦関係が微妙に影響していることを示唆していると思われる。(4) MFないし準MF型でも, 母親は対象のうちのひとりになることがもっとも多く, また, 2F, 準2F型では<母親-父親>という組合わせが, また, 3F, 準3F 型では<母親-父親-X>というものが多くなっており, 中学生では依存行動の対象としては, なによりも母親が, そして母親に伴なわれるという条件つきで父親が, 重要だといえる。(5) 親友は, 高校生にくらべ全般的には中学生ではあまり重要な対象ではない。焦点となった親友の場合でも, 必ずしも中核的とはいえないものもあった。(6}愛情の対象は, 中学1年生からすでにわずかながら出現している。が, 全般的には, 現実にもいないし, いると仮定もできないというものが多い。そして, 愛情の対象が焦点になった型においても, 愛情の対象は, 次に重要な親友とともに中核になっているという未熟さをもっていた。
- 著者
- 宇都宮 浄人
- 出版者
- 日本ドイツ学会
- 雑誌
- ドイツ研究 (ISSN:13441035)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, pp.67-70, 2022-03-30 (Released:2022-05-09)
- 参考文献数
- 1
1 0 0 0 ルール地方の水管理組合─その事業内容と共同管理構造
- 著者
- 大重 光太郎
- 出版者
- 日本ドイツ学会
- 雑誌
- ドイツ研究 (ISSN:13441035)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, pp.71-74, 2022-03-30 (Released:2022-05-09)
- 著者
- 辻 朋季
- 出版者
- 日本ドイツ学会
- 雑誌
- ドイツ研究 (ISSN:13441035)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, pp.51-60, 2022-03-30 (Released:2022-05-09)
- 参考文献数
- 67
- 著者
- 小野 一
- 出版者
- 日本ドイツ学会
- 雑誌
- ドイツ研究 (ISSN:13441035)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, pp.75-77, 2022-03-30 (Released:2022-05-09)
- 参考文献数
- 1
- 著者
- 高田 博行
- 出版者
- 日本ドイツ学会
- 雑誌
- ドイツ研究 (ISSN:13441035)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, pp.12-25, 2022-03-30 (Released:2022-05-09)
- 参考文献数
- 96
1 0 0 0 ドイツのメディアと日本のメディア─社会との関係性から見る相違
- 著者
- 林 香里
- 出版者
- 日本ドイツ学会
- 雑誌
- ドイツ研究 (ISSN:13441035)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, pp.5-11, 2022-03-30 (Released:2022-05-09)
- 参考文献数
- 20
- 著者
- 穂鷹 知美
- 出版者
- 日本ドイツ学会
- 雑誌
- ドイツ研究 (ISSN:13441035)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, pp.26-33, 2022-03-30 (Released:2022-05-09)
- 参考文献数
- 33
- 著者
- ナイハード クリストフ(翻訳:佐藤 公紀)
- 出版者
- 日本ドイツ学会
- 雑誌
- ドイツ研究 (ISSN:13441035)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, pp.34-38, 2022-03-30 (Released:2022-05-09)
- 参考文献数
- 8
- 著者
- 西山 暁義
- 出版者
- 日本ドイツ学会
- 雑誌
- ドイツ研究 (ISSN:13441035)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, pp.3-4, 2022-03-30 (Released:2022-05-09)
- 参考文献数
- 5
- 著者
- Takaaki Abe
- 出版者
- The Japanese Society for Mathematical Economics
- 雑誌
- 数理経済学会誌 (ISSN:24363162)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.38-66, 2022 (Released:2022-03-31)
- 参考文献数
- 12
Hart and Kurz (1983) introduced four stability concepts, called α-, β-, γ-, and δ-stability. In contrast to the intensive studies on their conceptual aspects, these notions have rarely been adopted to analyze stable coalition structures in an application because the definitions consist of multiple intermediate steps. The purpose of this paper is to solve these practical difficulties. We provide an explicit form for each of the four stability concepts and reformulate each concept without using any intermediate steps. Moreover, we offer some sufficient conditions that guarantee the existence of stable coalition structures and the inclusion relation among the four stability notions. In addition, we propose a new approach to characterize the notions of stability. An application of our results to Cournot oligopoly is also provided.