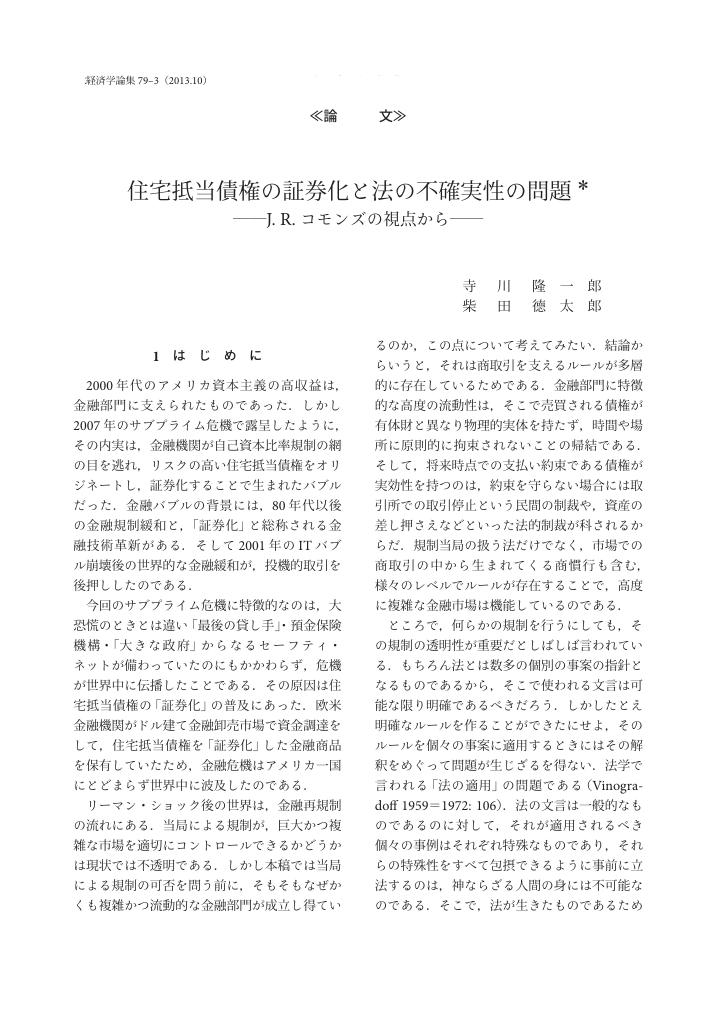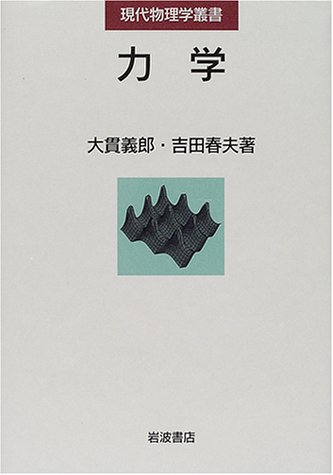- 著者
- 馬場 哲
- 出版者
- 東京大学大学院経済学研究科
- 雑誌
- 経済学論集 (ISSN:00229768)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.2, pp.2-26, 2013-07-01 (Released:2022-03-25)
- 参考文献数
- 15
1 0 0 0 OA 質的な特性に根ざした会計基準の開発 ――IASBによる概念フレームワークの討議資料――
- 著者
- 米山 正樹
- 出版者
- 東京大学大学院経済学研究科
- 雑誌
- 経済学論集 (ISSN:00229768)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.2, pp.27-94, 2013-07-01 (Released:2022-03-25)
- 参考文献数
- 11
- 著者
- Yoshiro MIWA
- 出版者
- Graduate School of Economics, The University of Tokyo
- 雑誌
- 経済学論集 (ISSN:00229768)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.3, pp.33-77, 2013-10-01 (Released:2022-03-25)
- 参考文献数
- 31
For more than half a century, inventory investment has attracted wide attention as a major cause of shortterm macroeconomic fluctuations, and the mechanisms involved have been the focus of many major studies. Yet microeconomists and business people familiar with corporate behavior have frequently expressed misgivings about the enterprise.Using Japanese quarterly GDP inventory investment statistics both by commodity and by category, 1994~2010, I investigate the nature of quarterly inventory statistics and the inventory investment behavior, and draw two conclusions. First, statisticians estimate the quarterly statistics under severe time constraints, and their resulting figures incorporate seasonal variations which dominate the quarterly fluctuations. This fluctuation mostly disappears in annual data. Secondly, when I examine the inventory variation after the Lehman Shock in the autumn of 2008, I find neither a notable increase in inventory stock nor a long-run stock adjustment process. Given the size of this unforeseen exogenous shock, most observers expected a large inventory stock accumulation to follow. That the accumulation did not follow suggests that the focus on inventory variation may be misplaced.For inventory investment data estimation, Japan is an ideal OECD country, with generous statistics availability. The conclusions of this research, drawn from the quarterly GDP inventory statistics, will stimulate the interest both in the study of inventory data in other countries focusing on its estimation process and source statistics, and in the great variety of inventory investment. At the same time, the conclusions pose a grave implication not only for re-evaluation of the literature in inventory investment variations but also for other research topics in macroeconomics like monetary transmission mechanisms including “financial accelerator” theory.
- 著者
- 鶴田 満彦
- 出版者
- 東京大学大学院経済学研究科
- 雑誌
- 経済学論集 (ISSN:00229768)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.3, pp.78-81, 2013-10-01 (Released:2022-03-25)
1 0 0 0 OA 住宅抵当債権の証券化と法の不確実性の問題 ――J. R. コモンズの視点から――
- 著者
- 寺川 隆一郎 柴田 德太郎
- 出版者
- 東京大学大学院経済学研究科
- 雑誌
- 経済学論集 (ISSN:00229768)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.3, pp.2-32, 2013-10-01 (Released:2022-03-25)
- 参考文献数
- 40
1 0 0 0 OA SDRによる国際通貨の価値尺度が国際統一通貨の役割を果す
- 著者
- 神田 善弘 カンダ ヨシヒロ Yoshihiro Kanda
- 雑誌
- 修道商学
- 巻号頁・発行日
- vol.55-2, pp.297-343, 2015-02-28
- 著者
- 奥村 久士
- 出版者
- 分子シミュレーション学会
- 雑誌
- アンサンブル (ISSN:18846750)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.44, pp.29-33, 2008 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 5
1 0 0 0 OA パネルデータを用いた非分離的モデルの識別に関するサーベイ
- 著者
- 石原 卓弥
- 出版者
- 東京大学経済学研究会
- 雑誌
- 東京大学 経済学研究 (ISSN:2433989X)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, pp.1-5, 2019 (Released:2019-07-15)
本研究ノートは,非分離的モデルのパネルデータを用いた識別に関する最近の研究成果のサー ベイ論文である.非分離的モデルは個人の異質性を考慮したモデルであり,近年,その重要性が 広く認識されるようになっている.非分離的パネルデータモデルの識別に関する多くの研究で は,“stayers”と呼ばれるサンプルが識別の鍵となっている.そこで本研究ノートでは,第2 節で “stayers”と呼ばれるサンプルを用いた2 つの論文を紹介する.しかし,これらの識別方法ではDID (difference-in-difference)モデルをカバーすることができない.そこで,第3 節で“stayers”を 用いない非分離的モデルの識別方法を紹介する.
- 著者
- 小島 一浩
- 出版者
- 東京大学経済学研究会
- 雑誌
- 東京大学 経済学研究 (ISSN:2433989X)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, pp.1-2, 2019 (Released:2019-12-21)
1 0 0 0 OA 【修士論文要旨紹介】技術革新と社会保険制度下での医療支出
- 著者
- 賈 美虹
- 出版者
- 東京大学経済学研究会
- 雑誌
- 東京大学 経済学研究 (ISSN:2433989X)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, pp.45, 2018 (Released:2019-01-25)
1 0 0 0 OA 【修士論文要旨紹介】所得分配ショックと流動性の罠と総需要
- 著者
- 徐 路
- 出版者
- 東京大学経済学研究会
- 雑誌
- 東京大学 経済学研究 (ISSN:2433989X)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, pp.44, 2018 (Released:2019-01-25)
- 著者
- 曾 涛
- 出版者
- 東京大学経済学研究会
- 雑誌
- 東京大学 経済学研究 (ISSN:2433989X)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, pp.43, 2018 (Released:2019-01-25)
1 0 0 0 OA 資本主義的生産における労働の熟練
- 著者
- 塩見 由梨
- 出版者
- 東京大学経済学研究会
- 雑誌
- 東京大学 経済学研究 (ISSN:2433989X)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, pp.33-42, 2018 (Released:2019-01-25)
本稿は,マルクス経済学における熟練労働論の再構築を試みるものである.『資本論』以来,マルクス経済学の労働像は「単純な不熟練労働者」と想定され,熟練概念は積極的にとり上げられてこなかった.しかし,近年は労働の生産性の差に注目が向けられるようになり,熟練概念の再構築は急務となってきている.そこで第I章では,これまで熟練労働と対置して用いられてきた複雑労働,不熟練労働,平均労働の観念と熟練労働との関係を検討し,熟練労働として扱うべき問題を整理した. 第II章では,同じ作業をしても成果に差が生ずる原因として,労働過程における熟練の作用点を確定した.労働者は労働過程で定型化されていない制御の契機を担うため,同じ技術的条件にあってもその制御方法により異なる成果をひき出す.ただし制御の不定形性は,優れた熟練が存在する余地とともに,劣った成果しか生まない不熟練の余地もつくりだす.ここに資本の行動として,優れた成果をひき出すため熟練労働を取りこもうとする側面と,劣った成果を回避するため労働過程での熟練度の余地を解体しようとする側面の二つの方向が見出されることになる.
1 0 0 0 OA 消費者の異質性を考慮した推薦商品カテゴリーの検討
- 著者
- 三富 悠紀
- 出版者
- 東京大学経済学研究会
- 雑誌
- 東京大学 経済学研究 (ISSN:2433989X)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, pp.1-13, 2018 (Released:2019-01-25)
マーケティングにおいて,消費者に対して「いつ」,「どんな商品」をプロモーションするかというのは,重要な問題である.本研究では,スーパーマーケットにおける各消費者の「揚物惣菜」「ヨーグルト」「牛乳」「菓子パン」「鶏卵」の5つの商品カテゴリーの購買間隔がワイブル分布に従うモデルの構築を試みた.分析モデルから得られた形状パラメータと尺度パラメータから,5つの商品カテゴリーについて,消費者ごとの購買傾向を明らかにした.分析結果に基づき,消費者ごとのプロモ―ションを行う商品カテゴリーについて改善の可能性を提示した.
1 0 0 0 OA 華族名鑑 : 新調更正
1 0 0 0 OA 「変位電流は磁場を創らない」を考察するモデルについて(変位電流とは何か)
- 著者
- 斎藤 吉彦
- 出版者
- 日本物理教育学会
- 雑誌
- 物理教育 (ISSN:03856992)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.3, pp.209-212, 2012-09-03 (Released:2017-02-10)
- 参考文献数
- 5
本誌の企画「変位電流とは何か」で,3編の論文が「変位電流は磁場を創らない」の議論を与えている。これらは,時間変化をする球対称電場の存在の正否が要となっている。本稿は,この電場がマクスウェル方程式と矛盾することを根拠に,設定されたモデルを否定する。さらに,モデルが仮定する荷電粒子の運動が非物理的であることを具体的に示す。本編の議論は電磁場の相対論的理解が背景にあり,教育者にとって電磁気学の相対論的理解の必要性を主張する。
1 0 0 0 OA 禪學札記
- 著者
- 衣川 賢次
- 雑誌
- 花園大学文学部研究紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.48, pp.87-142, 2016-03
- 著者
- 野本 潤矢 石橋 裕 小林 法一 小林 隆司
- 出版者
- 一般社団法人 日本作業療法士協会
- 雑誌
- 作業療法 (ISSN:02894920)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.6, pp.706-713, 2019-12-15 (Released:2019-12-15)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1
訪問型サービスC(以下,訪問C)は,介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防・生活支援サービス事業の1つであり,ADL/IADL課題の改善を主目標に,3ヵ月程度の短期間で支援を終結させる点が特徴である.要支援2認定のA氏は,作業工程の多さや洗濯かごの運搬距離の長さから,洗濯物を干す動作に努力の増大と効率性の低下を認めた.A氏が少ない疲労で効率よく干すことを目的に,洗濯物干しハンガーの位置変更など,作業遂行に焦点を当てて環境設定や動作方法を中心に助言した.その結果,3回の助言でA氏の作業遂行能力や健康関連QOLが向上した.作業療法士が訪問Cを担うことにより,短期間でADL/IADLの改善につなげることができると示唆された.
1 0 0 0 力学
- 著者
- 大貫義郎 吉田春夫著
- 出版者
- 岩波書店
- 巻号頁・発行日
- 2001
1 0 0 0 OA 自由落下三体問題における衝突軌道、振動運動とカオス
- 著者
- 谷川 清隆 Kiyotaka TANIKAWA
- 出版者
- 総合研究大学院大学
- 雑誌
- 非線形現象の数理
- 巻号頁・発行日
- pp.59-67, 1997-03
谷川清隆[国立天文台]