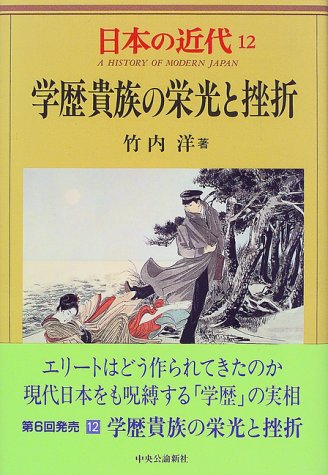1 0 0 0 OA I.DKDの疾患概念と腎臓専門医への紹介基準
- 著者
- 岡田 浩一
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.108, no.5, pp.901-906, 2019-05-10 (Released:2020-05-10)
- 参考文献数
- 10
近年,顕性アルブミン尿を伴わずに糸球体濾過量(glomerular filtration rate:GFR)が低下する非典型的な糖尿病関連腎症が増加しており,古典的な糖尿病性腎症を含む包括的な病名として,糖尿病性腎臓病(diabetic kidney disease:DKD)が用いられるようになった.DKDの早期診断のためには,尿アルブミンとeGFR(estimated GFR)の測定が必要であり,適切な管理には,紹介基準に沿ったタイムリーな病診連携の開始が重要となる.
1 0 0 0 支那疆域沿革圖 : 附略説
1 0 0 0 實測東京全圖
- 著者
- 吉田晋 赤松範靜製圖 河田羆校正
- 出版者
- 地理局地誌課
- 巻号頁・発行日
- 1878
1 0 0 0 大日本國全圖
- 著者
- 地理局地誌課 [編]
- 出版者
- 地理局地誌課
- 巻号頁・発行日
- 1883
1 0 0 0 實測東京全圖
- 著者
- 吉田晋 赤松範靜製圖 河田羆校正
- 出版者
- 地理局地誌課
- 巻号頁・発行日
- 1879
1 0 0 0 中心市街地活性化におけるまちづくり会社の役割と課題
- 著者
- 甲斐田 晴子
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.2, pp.141-150, 2016
1 0 0 0 IR 職場でのセクハラの判断基準及び使用者責任について : 中・日・米の裁判例と比較して
- 著者
- 馮 雪
- 出版者
- 北海道大学大学院法学研究科
- 雑誌
- 北大法政ジャーナル
- 巻号頁・発行日
- no.28, pp.117-153, 2021-12-06
1 0 0 0 2S3-2 携帯ライフログデータを活用した心理拘束時間解析の試み
- 著者
- 榎原 毅 松河 剛司 山田 泰行
- 出版者
- 一般社団法人 日本人間工学会
- 雑誌
- 人間工学 (ISSN:05494974)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, pp.S88-S89, 2015
1 0 0 0 OA JSICK: 日本語構成的推論・類似度データセットの構築
- 著者
- 谷中 瞳 峯島 宏次
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第35回 (2021)
- 巻号頁・発行日
- pp.4J3GS6f02, 2021 (Released:2021-06-14)
単語と文の構造に基づいて新しい文を構成的に理解し,文間の意味的関係を認識することは,より人間らしい自然言語理解をコンピュータによって実現するための基本的な課題の一つである.本研究では,英語の構成的推論・類似度データセットSICKを人手で日本語に翻訳することで日本語の含意関係認識・文間類似度データセットJSICKを構築し,JSICKを学習した汎用言語モデルBERTが否定表現や量化表現といった多様な意味現象を構成的に捉えられているかについて,意味現象のタイプごとに評価を行う.さらに,語順を変えても意味内容が変わらないという日本語独自の性質を考慮して,モデルが意味現象を構成的に捉えているかについて分析を行う.実験の結果,現行の汎用言語モデルは数量表現や語順の入れ替えの扱いにおいて,改善の余地があることが示唆された.
1 0 0 0 学歴貴族の栄光と挫折
1 0 0 0 OA 英語学はどのように英語教育に寄与できるのか 教育現場からの示唆
- 著者
- 中川 右也
- 出版者
- 関西英語教育学会
- 雑誌
- KELESジャーナル (ISSN:24238732)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.41-60, 2019 (Released:2020-04-26)
1 0 0 0 OA ダウン症と耳鼻咽喉科疾患
- 著者
- 飯野 ゆき子
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)
- 巻号頁・発行日
- vol.123, no.1, pp.81-83, 2020-01-20 (Released:2020-02-05)
- 参考文献数
- 12
測器近傍の障害物の有無が気温に与える影響を定量的に評価するため,放射による観測誤差が最大で0.04℃の高精度な測器による気温観測を行い,空間広さ(「周囲の障害物と測器との距離」と「障害物の高さ」との比)に注目して解析した.観測は,首都大学東京南大沢キャンパスの陸上競技場の芝地上6地点において,2014年8月22日~9月17日に行い,その内1地点では不織布の囲いを設置して,空間広さが小さい状態を人工的に作り出した.その結果,日中は,空間広さが小さくて天気がよいほど気温が高くなり,いわゆる日だまり効果(測器近傍の障害物による風速の減少に伴う地上気温の上昇)の影響が示唆された.一方,夜間は,空間広さが小さい地点ほど気温が低くなった.これは,囲いによる風速減少により上空大気との熱交換が抑制されるとともに,囲いの中に冷気がたまりやすくなることで放射冷却の効果が強められたことが原因と考えられる.また,日中と比べて夜間には地点間の気温差は小さくなったが,これは日中と夜間の正味放射量および風速の違いを反映したものと考えられる.
1 0 0 0 OA 露領沿海地方及接壤地方圖
- 著者
- 南満洲鐵道株式會社社長室調査課 編纂
- 出版者
- 南満洲鐵道
- 巻号頁・発行日
- 1923
- 著者
- 吉田 正義 出島 富士夫
- 出版者
- 日本応用動物昆虫学会
- 雑誌
- 日本応用動物昆虫学会誌 (ISSN:00214914)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.4, pp.244-250, 1958
1) 圃場におけるハリガネムシの分布の実態を知らんがため,春(大麦畑)秋(白菜畑)の2期ハリガネムシが耕土上層に棲息する時期をねらって,作物を中心とした区劃および植物の根株を単位にハリガネムシを採集して,2年目以降の幼虫に対する個体群の分布様式について調査した。<br>2) 秋期および春期における区劃ならびに根株単位の分布様式はいずれもPólya Eggenberger分布に適合した。根株単位の頻度分布は区劃単位のそれに比してχ<sup>2</sup>検定は高い信頼度で適合した。<br>3) 白菜の根部以外の区劃内に棲息するハリガネムシの数は,根部の土壌に棲息するそれに比較してきわめて少ないので,密度を推定するには1区劃全部の土壌を調査する方法より植物の根部の土壤のみを対象とするほうが得策かも知れない。<br>4) ハリガネムシの分布が栽培植物に対して高い集中性を示したが,その理由としてa)成虫の産卵は栽培植物の周辺の土壤にばらばらに行われることb)摂食期の幼虫は栽培植物に好んで潜入する性質をもつことc)非摂食期においても栽培植物の真下に当る耕土の下部に潜入していることが考えられる。<br>5) 集中性をはばむ事柄として,マルクビクシコメツキの幼虫のように経過の長い昆虫では,栽培植物に集中したものを耕転により分散させることが考えられるが,春期の甘藷の畝立作業や秋期の麦作は2年目以降のハリガネムシが耕土の下層に潜入した後に当るため大きな影響は考えられない。<br>6) 大麦畑における頻度分布もおおむね白菜畑におけると同様な傾向を示した。<br>7) 調査圃場はいずれも西側が高く東側に低いゆるやかな傾斜地であったが,分布は何れも低い場所に多く認められた。これは成虫が風の当らない日だまりの低地に集中産卵を行うことによるものであろう。<br>8) 棲息密度の増加と集中性について,<i>S<sup>2</sup>/x</i>により比較すれば,各区とも1より大きく,密度が高くなるにつれて高い集中性がみられ,各区ともPólya Eggenberger分布に当てはまった。<br>9) 白菜の被害程度の異なる株を任意に選び根部に棲息するハリガネムシの数を調査した。採集虫数は枯死葉と健全葉の混合株区に最も多く,次は枯死株区,健全株区,欠株区の順であった。<br>10) アリの巣やモグラの孔のある場所ではハリガネムシは比較的少なく採集された。また圃場はコガネムシ類の多数棲息する場所であるが,ハリガネムシの密度の多い場所では,コガネムシの幼虫はほとんど採集できず圃場の周辺にのみ少しずつしか採集されなかった。<br>11) 圃場に栽培されている植物が少ない場合はハリガネムシもコガネムシの幼虫も根部に集中するが,ハリガネムシは肉食性でもあるのでコガネムシの体内に潜入して同虫を倒すためであろう。<br>12) このことはハリガネムシを採集する時,しばしば1頭のコガネムシの幼虫に10数頭のハリガネムシが集中して潜入しているのを観察したり,同じ容器でヒメコガネの幼虫とハリガネムシを混合して飼育する時,コガネムシ幼虫の体内に多数のハリガネムシが潜入することなどにより容易に推察される。