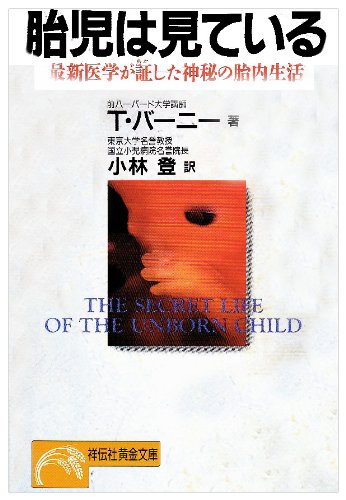1 0 0 0 コロナ禍の大学の状況およびフラッシュメモリ研究開発の思い出
- 著者
- 渡辺 重佳
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会誌 (ISSN:13405551)
- 巻号頁・発行日
- vol.141, no.5, pp.261, 2021-05-01 (Released:2021-05-01)
2005年に(株)東芝を退職し,以来15年間,湘南工科大学の教員を務めています。この原稿の執筆中の2021年1月には学長に就任して2年近くになります。大学在籍中に後述する3次元型メモリや論理LSIに関する10件以上の論文を電気学会の論文誌に掲載させていただき誠に
1 0 0 0 OA 漢語の連濁と意味用法の史的変遷に関する研究
1 0 0 0 OA 明治期における政治・宗教・教育
1 0 0 0 OA なぜ被災者が津波常習地へと帰るのか――気仙沼市唐桑町の海難史のなかの津波――
- 著者
- 植田 今日子
- 出版者
- 環境社会学会
- 雑誌
- 環境社会学研究 (ISSN:24340618)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.60-81, 2012-11-20 (Released:2018-11-20)
- 被引用文献数
- 2
本稿の目的は,2011年3月11日の津波で甚大な被害をうけた三陸地方沿岸の集落の人びとが,なぜ海がすぐそばに迫る災禍のあった地へふたたび帰ろうとするのかを明らかにすることである。事例としてたどるのは,津波常習地である三陸地方,宮城県気仙沼市唐桑町に位置する被災集落である。この集落では52世帯中44世帯の家屋が津波で流失したが,津波被災からわずか1ヵ月あまりで防災集団移転のための組織をつくり,2011(平成23)年度末には県内でももっとも早く集団移転の予算をとりつけるにいたった。舞根の人びとが集団移転をするうえで条件としたのは,移転先が家屋流失を免れた8世帯の人びとの待つ舞根の土地であること,そして海が見える場所であることであった。本稿は津波被災直後から一貫して海岸へ帰ろうとする一集落の海との関わりから,彼らが災禍をもたらした海に近づこうとする合理性を明らかにするものである。海で食べてきた一集落の人びとの実践から明らかになったのは,慣れ親しんだ多様な性格をもつ海は,どうすればそれぞれの場所で食わせてくれるのかをよく知り,長い海難史のなかで培われた“死と向き合う技法”と“海で食っていく技法”の双方が効力を発揮する海であった。すなわち,舞根の人びとにとって被災後なお海のもとへ帰ろうとすることが“合理的”であるのは,海がもたらしてきた大小の災禍を受容することなしに,海がもたらしてくれる豊穣にあずかることはできないという態度に裏打ちされている。
1 0 0 0 胎児は見ている : 最新医学が証した神秘の胎内生活
1 0 0 0 OA iPhone を用いた顔面神経麻痺評価アプリの開発
- 著者
- 長谷部 孝毅 堀 龍介 児嶋 剛 岡上 雄介 藤村 真太郎 鹿子島 大貴 田口 敦士 庄司 和彦
- 出版者
- 公益財団法人 天理よろづ相談所 医学研究所
- 雑誌
- 天理医学紀要 (ISSN:13441817)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.50-51, 2020-12-25 (Released:2020-07-17)
【目的】顔面神経麻痺疾患において,予後予測,治療効果判定のために正確な評価が必要である.誘発筋電図(electroneurography; ENoG)などの電気生理学的評価方法の他に,柳原法などに代表される顔面各部位の動きを評価し,その合計で麻痺程度を評価する主観的評価方法が簡便であり広く使われている.しかしながら,顔面表情の動きを見た目で評価する方法は複数あるものの,いずれにも共通する欠点として,あくまで主観的評価のため検者間で差異が生じる可能性がある他,各部位は3 段階評価のため,わずかな改善などを点数では評価しきれないという点が挙げられる.それらを解決する方法として,画像解析による評価方法はいくつか報告されているが,解析の手間や装置の問題などから広くは使われていない.一方で,近年米Apple 社の販売するスマートフォン(iPhone X 以降) は,その認証方式として顔認証を用いており,顔面運動を正確に捉えることが可能である.そこで我々は,顔面神経麻痺に対する客観的かつ簡便な評価方法を確立することを試みた. 【方法】iPhone XS を用いて検証した.各顔面の部位の動きを係数化し最大値を取得し,左右の比較を行うことで顔面神経麻痺を評価するアプリを作成した.それを用いて外来受診した顔面神経麻痺患者の評価を行い,主観的評価法との比較,及びENoG,積分筋電図との比較を行った. 【結果】アプリでの評価は既存の主観的評価方法と相関しており,特に頬,鼻翼,口角では強い相関が見られた.また,ENoG では相関関係が見られなかったものの,積分筋電図でも相関が見られた. 【結論】デバイスは一般に普及しているため,臨床応用に向けての素地は整っており,目的としていた客観的かつ簡便な評価アプリは開発出来た.顔面の動きの捉え方は,病態生理に基づきさらなる検証およびアップデートが必要ではあるが,非耳鼻科医,さらに言えば患者本人でも現状評価を行うことができるようになることが期待される.
1 0 0 0 OA インターネットによるカウンセリング,援助活動(14):自己受容の視点から
- 著者
- 林 潔
- 雑誌
- 白梅学園大学・短期大学情報教育研究 = Annual Report
- 巻号頁・発行日
- vol.23, pp.1-13, 2020-03-31
1 0 0 0 OA インターネットによるカウンセリング,援助活動(13):セルフコンパッションの視点から
- 著者
- 林 潔 ハヤシ キヨシ Kiyoshi HAYASHI
- 雑誌
- 白梅学園大学・短期大学情報教育研究
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.1-14, 2019-03-31
1 0 0 0 OA インターネットによるカウンセリング,援助活動(12): 問題解決と自己コントロール
- 著者
- 林 潔 ハヤシ キヨシ Kiyoshi HAYASHI
- 雑誌
- 白梅学園大学・短期大学情報教育研究
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.1-14, 2018-03-31
1 0 0 0 OA インターネットによるカウンセリング,援助活動(11) : 感情労働へのCBT的かかわり
- 著者
- 林 潔 ハヤシ キヨシ Kiyoshi Hayashi
- 雑誌
- 白梅学園大学・短期大学情報教育研究
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.1-12, 2017-03-31
1 0 0 0 OA インターネットによるカウンセリング,援助活動(10) : CBTの手続きを用いた援助活動
- 著者
- 林 潔 ハヤシ キヨシ Kiyoshi HAYASHI
- 雑誌
- 白梅学園大学・短期大学情報教育研究
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.9-17, 2016-03-31
- 著者
- 林 潔 ハヤシ キヨシ Kiyoshi Hayashi
- 雑誌
- 白梅学園大学・短期大学情報教育研究
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.22-31, 2010-03-31
- 著者
- なかの まき
- 出版者
- 「社会言語学」刊行会
- 雑誌
- 社会言語学 (ISSN:13464078)
- 巻号頁・発行日
- no.13, pp.17-41, 2013
1 0 0 0 ブルシット・ジョブ現象について (特集 コンプライアンス社会)
- 著者
- グレーバー デヴィッド 芳賀 達彦 酒井 隆史
- 出版者
- 青土社
- 雑誌
- 現代思想
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.13, pp.45-52, 2019-10
1 0 0 0 OA インターネットによるカウンセリング,援助活動(8) : 中国の活動を中心に
- 著者
- 林 潔 ハヤシ キヨシ
- 雑誌
- 白梅学園大学・短期大学情報教育研究
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.9-16, 2009-03-31
- 著者
- 牧田 泰一 藤原 匡晃
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.11, pp.798-808, 2018
<p>福井県は,誰もが自由に使えるオープンデータの活用推進を県内全域で行っている。県内全市町の内容・様式を統一したデータを都道府県として初めて公開し,機械判別に適した様式でデータを公開することで,二次利用を推進している。そして,データを公開するだけでなく,アプリコンテストや普及活動等を行っており,オープンデータを活用したアプリケーション開発数は全国トップクラスである。また,福井県鯖江市は日本で初めてオープンデータに取り組んだ先進自治体であり,オープンデータによる行政の透明化,市民参加,そして官民の連携を進めている。こうした福井県の取り組みと,鯖江市の注目すべき先進事例を紹介する。</p>
1 0 0 0 OA インターネットによるカウンセリング,援助活動(7) : 高齢者と家族援助の可能性
- 著者
- 林 潔 ハヤシ キヨシ Kiyoshi Hayashi
- 雑誌
- 白梅学園大学・短期大学情報教育研究
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.15-20, 2008
- 著者
- 林 潔 ハヤシ キヨシ Kiyoshi Hayashi
- 雑誌
- 白梅学園大学・短期大学情報教育研究
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.9-18, 2007-03-31
1 0 0 0 OA インターネットによるカウンセリング,援助活動について(5)
- 著者
- 林 潔 ハヤシ キヨシ Kiyoshi Hayashi
- 雑誌
- 白梅学園大学・短期大学情報教育研究
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.11-20, 2006-03-31