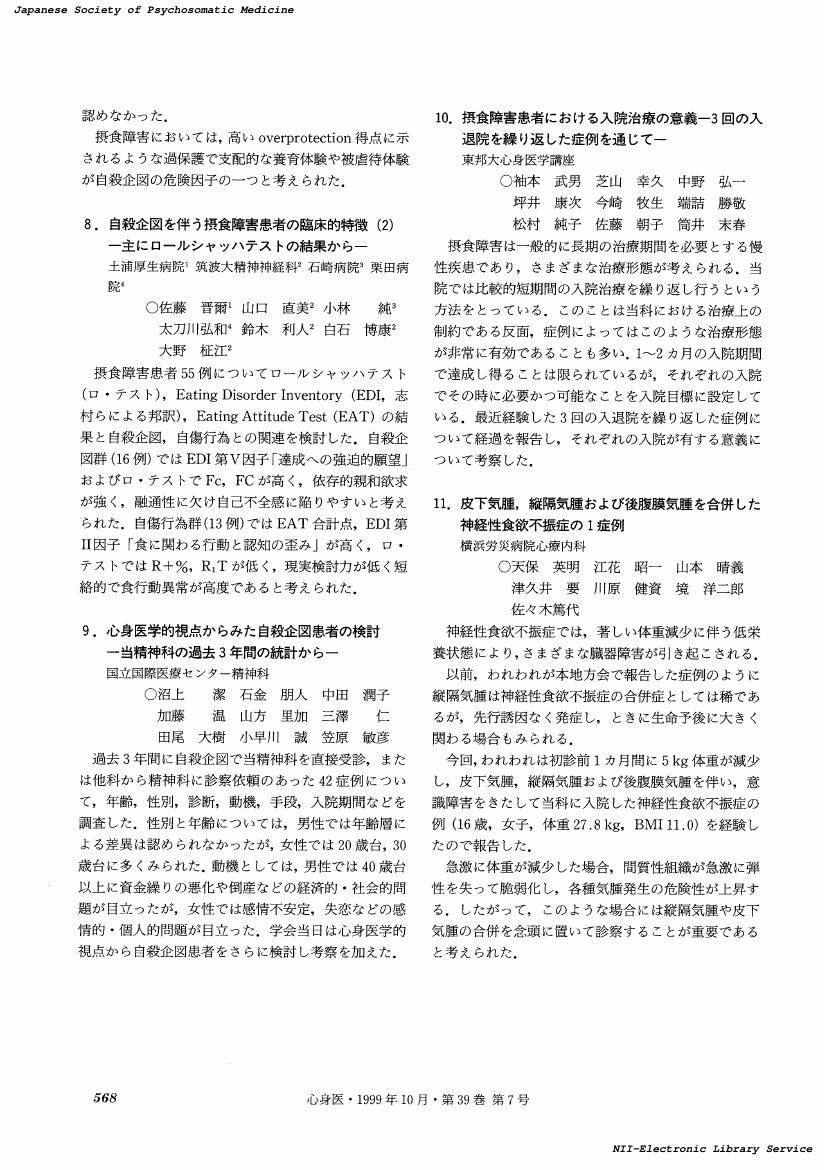1 0 0 0 OA ナナホシテントウとナミテントウの野外における産卵開始時期と産卵場所の差異
- 著者
- 高橋 敬一
- 出版者
- 日本応用動物昆虫学会
- 雑誌
- 日本応用動物昆虫学会誌 (ISSN:00214914)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.3, pp.253-254, 1987-08-25 (Released:2009-02-12)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 13 15
1 0 0 0 OA 遊びと思弁哲学―ホワイトヘッドの方法論と宇宙論―
- 著者
- 村田 康常
- 出版者
- 日本ホワイトヘッド・プロセス学会
- 雑誌
- プロセス思想 (ISSN:21853207)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.108-127, 2019 (Released:2020-12-28)
This essay’s argument centers on two points. The first concerns the suitability of the term “play” to succinctly describe our actual world, which A. N. Whitehead called the world where conflict takes place between “the spirit of change,” which creatively advances toward novelty, and “the spirit of conservation” (Whitehead, 1967/1925, p. 201) —a world where the becoming and perishing of actual entities take place. The second point is that Whitehead’s method of speculative philosophy that includes an exhaustive discussion about this world of play is itself adequately described by the term “play.” Whitehead called the method of his philosophical exploration “speculative philosophy,” describing it as an attempt beginning with “immediate experience” to construct an “adequate and coherent logical system of general ideas” via “imaginative generalization” (Whitehead, 1978/1929, pp. 3-7). What becomes crucial in this search for generality is a “leap of imagination” that entails a departure from the restrictions and particularities of our immediate experience. Whitehead’s comparison of this leap of imagination—a methodology of speculative philosophy—to the flight of an airplane (Whitehead, 1978/1929, p. 5) is well known. We will use another of his metaphorical expressions, “play of free imagination” (ibid.), to refer to this free flight of imagination in this essay. Whitehead suggests that the element of play, as an unrestricted flight of imagination, plays a crucial role in speculative philosophy, as much as does rigorous logic. As such, the concept of play has double meanings in Whitehead’s speculative philosophy, namely because the world that speculative philosophy explores can be understood as a world of play, and the method of speculative philosophy’s exploration involves a play of imagination. This essay will attempt to construct a dialogue between Whitehead’s philosophy of the organism and the philosophies of play, particularly those by F. von Schiller, F. Nietzsche, J. Huizinga, R. Caillois, W. Benjamin, and E. Fink, in order to thoroughly discuss the double meanings of play within speculative philosophy.
1 0 0 0 ペインクリニックにおけるクリティカルパスの導入
- 著者
- 北浦 道夫 西本 雅彦 佐牟田 健 戸田 成志
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本医療マネジメント学会
- 雑誌
- 医療マネジメント学会雑誌 (ISSN:13456903)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.3, pp.440-444, 2003
当院のペインクリニックでは主に痛みを持っ患者を対象に神経ブロックが行われているが、その合併症は多岐にわたっている。そのため、ペインクリニックにクリティカルパスを導入し、患者および医療従事者の理解度の向上、合併症の早期発見、インフォームドコンセントの充実、業務の効率化、チーム医療の充実、コスト管理などに効果を上げているので紹介する。<BR>当科でクリティカルパスを導入しているのは神経ブロックでは腹腔神経叢ブロック、胸・腰部交感神経節ブロック、神経根ブロック、三叉神経節ブロックなどであり、疾患では顔面神経麻痺に導入している。クリティカルパスは1種類のブロックにっき、患者用パス、医療従事者用パス、患者説明パスの3種類となっている。<BR>また、ペインクリニックにおいても採算を度外視して行われる時代ではもはや無い。現在導入されつつあるDiagnosis Procedure Combination (DPC) に対応できるように我々は各種ブロックに対し、コスト計算を行っている。<BR>現在電子カルテの導入に向け、クリティカルパスとオーダリングシステムをリンクさせることにより、よりいっそう効率的な医療を提供できるように努力中である。クリティカルパスの作成は医師だけで行うのは困難であり、看護師、放射線技師などの医療従事者は当然としてコスト管理については医療事務の協力も得ており、よりよいクリティカルパスを導入できるように推進中である。
1 0 0 0 OA 歌舞伎取り締まりと役者の身分
- 著者
- 山下 興作
- 出版者
- 高知大学
- 雑誌
- 高知大学学術研究報告 人文科学編 (ISSN:03890457)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, pp.157-166, 1996-12-25
1 0 0 0 OA マイクロ波による脳組織内加温法
- 著者
- 佐藤 透 西本 詮
- 出版者
- Japanese Society for Thermal Medicine
- 雑誌
- 日本ハイパーサーミア学会誌 (ISSN:09112529)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.4, pp.351-370, 1990-12-01 (Released:2009-09-29)
- 参考文献数
- 53
Interstitial microwave brain hyperthermia was reviewed with several comments on the implantable microwave antenna and treatment planning. Results of the phase-I clinical trials were briefly summarized. Further Studies would be necessory to develop the system for controlling the individual antenna power independently by the each thermometry information, to accumulate the basic data for planning and simulation of the treatment, and to make the clinical protocol for combination therapy of hyperthermia and radiation and/or chemotherapy.
- 著者
- 田中 津久志 矢崎 亮 大嶋 孝志
- 出版者
- 公益社団法人 有機合成化学協会
- 雑誌
- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.5, pp.417-426, 2021-05-01 (Released:2021-05-11)
- 参考文献数
- 72
Enolization of carboxylic acid derivatives is the central science of fundamental carbonyl chemistry. The catalytic methods to activate carboxylic acid remained unexplored due to the intrinsic low acidity of α-protons, although enormous examples of catalytic activation (enolization) method for aldehydes, ketones, and ester derivatives have been reported. The innate Brønsted acidic carboxylic acid functionality also disrupts the deprotonation of α-protons. Therefore, more than two equivalents of a strong base such as lithium diisopropylamide are required for efficient enolization, which makes chemoselective enolization of carboxylic acid over more acidic carbonyls a formidable task. Furthermore, recent enolization methods were only applied to redox-neutral coupling using 2e- electrophiles and catalytic α-functionalization of carboxylic acids through a 1e- radical process, which could complement the chemoselectivity, and functional group tolerance restricted in the classical 2e- ion reaction, has never been achieved. Herein, we developed chemoselective catalytic activation of carboxylic acid equivalent, acylpyra-zole, and carboxylic acid for a 1e- radical process without external addition of stoichiometric amounts of Brønsted base. The present chemoselective catalysis could be applied to late-stage α-amination and oxidation, allowing for concise access to highly versatile unnatural α-amino acid and hydroxy acid derivatives. Moreover, chemoselective α-functionalization of less reactive carboxylic acids was achieved over innately more reactive carbonyl functionalities.
1 0 0 0 OA SHK片手入力方式のポケッタブルコンピュータへの適用
- 著者
- 杉本 正勝
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告モバイルコンピューティングとユビキタス通信(MBL)
- 巻号頁・発行日
- vol.1998, no.53(1998-MBL-005), pp.72-76, 1998-05-28
モーバイルコンピューティングの将来ビジョンの一つである「財布サイズコンピュータ」をめざして、高速テキスト入力可能なポケッタブル・デバイスを試作した。テキスト入力にパソコン上で実績のあるSHK片手操作キー方式(Single Hand Keys)を採用した。英語・日本語に対応している。試作したシステム概要、機能・使い方、入力速度、今後の課題等を述べる。
- 著者
- 色川 大輔
- 出版者
- 國學院大學国語研究会
- 雑誌
- 国語研究 (ISSN:04506677)
- 巻号頁・発行日
- no.84, pp.18-31, 2021-02
1 0 0 0 脳波・視線同時計測による文読解時の周辺視野の役割の解明
1 0 0 0 OA アントシアニンおよびその代謝物の血液脳関門透過性の検討
目的:アントシアニン(AC)を経口摂取することで様々な機能性が報告されており、その中にアルツハイマー型認知症予防効果がある。しかし、ACは摂取後、体内で各種フェノール酸へと代謝されることが知られており、この効果に寄与する活性成分が特定されていない。そこで本研究では、ACおよびAC由来の代謝物とされ、尿中で検出される各種フェノール酸に関して、血液脳関門(BBB)の透過性を比較することで、AC投与時の有効成分の探索を行った。方法:雄性Wistar RatにカシスAC抽出物あるいはイチゴAC濃縮粉末をそれぞれ経口投与し、投与前、投与後0~4h, 4~8h, 8~24hに尿を回収し、尿中のACおよび代謝物をLC-MSMSで定量した。また、投与後2, 18hにおける脳中のACおよび代謝物もLC-MSMSで分析した。続いて、Wistar Rat由来のBBBキットを用いてACおよび代謝物のBBB透過性を検討した。結果および考察:カシスAC抽出物およびイチゴAC濃縮粉末を投与したラットの尿からは、ACおよび代謝物として3,4-Dihydroxybenzoic acid (PCA), Caffeic acid, Vanillic acid, Gallic acid, Ferulic acid, Syringic acid, 4-Hydroxybenzoic acid(4-HBA), 3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid(HPPA), 2,4,6-Trihydroxybenzaldehyde(PGAldehyde), 2,4,6-Trihydroxybenzoic acid(PGAcid), Hippuric acidが検出された。これらの化合物は投与前の尿中にはほとんど含まれていなかった。そのうちカシスAC抽出物投与のラット脳組織中には、Gallic acidおよびHippuric acidが、イチゴAC濃縮粉末投与のラット脳組織中にはAC、4-HBA, PCA, Hippuric acid, そしてHPPAが存在することが分かった。これらの化合物を中心にBBB透過性を検討したところ、ACと比較してHPPAなどの一部のフェノール酸におけるBBB透過性が高いことが分かった。このことから、ACが体内で変換されて様々なフェノール酸となり、効果を発揮する可能性が示唆された。
1 0 0 0 「抄物コーパス」の構築とコーパスを応用した日本語史研究
1 0 0 0 ポイントプログラムのビジネスモデルとグローバル展開活用
- 著者
- 安岡 寛道
- 出版者
- 一般社団法人 経営情報学会
- 雑誌
- 経営情報学会 全国研究発表大会要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2009, pp.58, 2009
企業が発行するポイントやマイレージのプログラムのビジネスモデルを分析・整理し、それらをグローバルに展開・活用する方法を提案する。まず、ポイント・マイレージの発行額は、2007年度に国内で6800億円を超え、顧客囲い込みや顧客情報の収集を目的として、航空会社や家電量販店のような民間企業だけでなく、公共サービス、行政機関、さらには教育機関にまで導入され始めている。これらに関連するビジネスは、顧客囲い込みによる本業の活性化のみならず、ポイント自体を販売したり、システム利用料を徴収するなど、いくつかのビジネスモデルに整理される。また、地域経済の活性化、カーボンオフセット(CO2排出量削減)などにまで実施・検討範囲が広がっており、これらを活用して、グローバルに展開する方法を提示する。
- 著者
- Wei Peng Yan-Yan Ma Kun Zhang Ai-Yu Zhou Yu Zhang Huaqian Wang Zhiyun Du Deng-Gao Zhao
- 出版者
- The Pharmaceutical Society of Japan
- 雑誌
- Chemical and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:00092363)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.6, pp.609-615, 2016-06-01 (Released:2016-06-01)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 9 14
Long-term use of nonsteroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs) may cause serious side effects such as gastric mucosal damage. Resveratrol, a naturally dietary polyphenol, exhibited anti-inflammatory activity and a protective effect against gastric mucosa damage induced by NSAIDs. In this regard, we synthesized a series of resveratrol-based NSAIDs derivatives and evaluated their anti-inflammatory activity against nitric oxide (NO) overproduction in lipopolysaccharide (LPS)-stimulated RAW264.7 macrophages. We identified mono-substituted resveratrol–ibuprofen combination 21 as the most potent anti-inflammatory agent, which is more active than a physical mixture of ibuprofen and resveratrol, individual ibuprofen, or individual resveratrol. In addition, compound 21 exerted potent inhibitory effects on the LPS-induced expression of tumor necrosis factor-α (TNF-α) and interleukin-1β (IL-1β). Furthermore, compound 21 significantly increased the survival rate in an LPS-induced acute inflammatory model and produced markedly less gastric damage than ibuprofen. It was found that compound 21 may be a potent anti-inflammatory agent for the treatment of inflammation-related diseases.
- 著者
- 鹿江 宏明 鈴木 盛久
- 出版者
- 比治山大学・比治山大学短期大学部
- 雑誌
- 比治山大学・比治山大学短期大学部教職課程研究 Review of the research on teachers training (ISSN:21891745)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.173-180, 2015-03
- 著者
- 隆島 史夫 日比谷 京 ファンバン ガン 会田 勝美
- 出版者
- 日本水産學會
- 雑誌
- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.1, pp.43-49, 1972
- 被引用文献数
- 35
In order to clarify the endocrine control over the egg yolk formation, the effects of estrogenic substance (diethylstilbestrol), androgenic substance (methyltestosterone), thyroid hormone (powdered mammalian thyroid gland), and adrenocorticotropin on plasma lipid and lipoprotein in rainbow trout were examined. Levels of total lipid and lipoprotein in plasma were raised by estrogen treatment. The liver of estrogen-treated fish was hypertrophic, and contained more lipid, protein and nucleic acids. It is concluded that the lipoporotein is synthesized in liver and released into the blood under the influence of ovarian steroid hormone. On the contrary, the levels of lipid and lipoprotein were reduced by thyroid powder administration. From these results it is suspected that an endocrine correlation mechanism affects the metabolism of lipoproteins that are deposited in the oocytes.