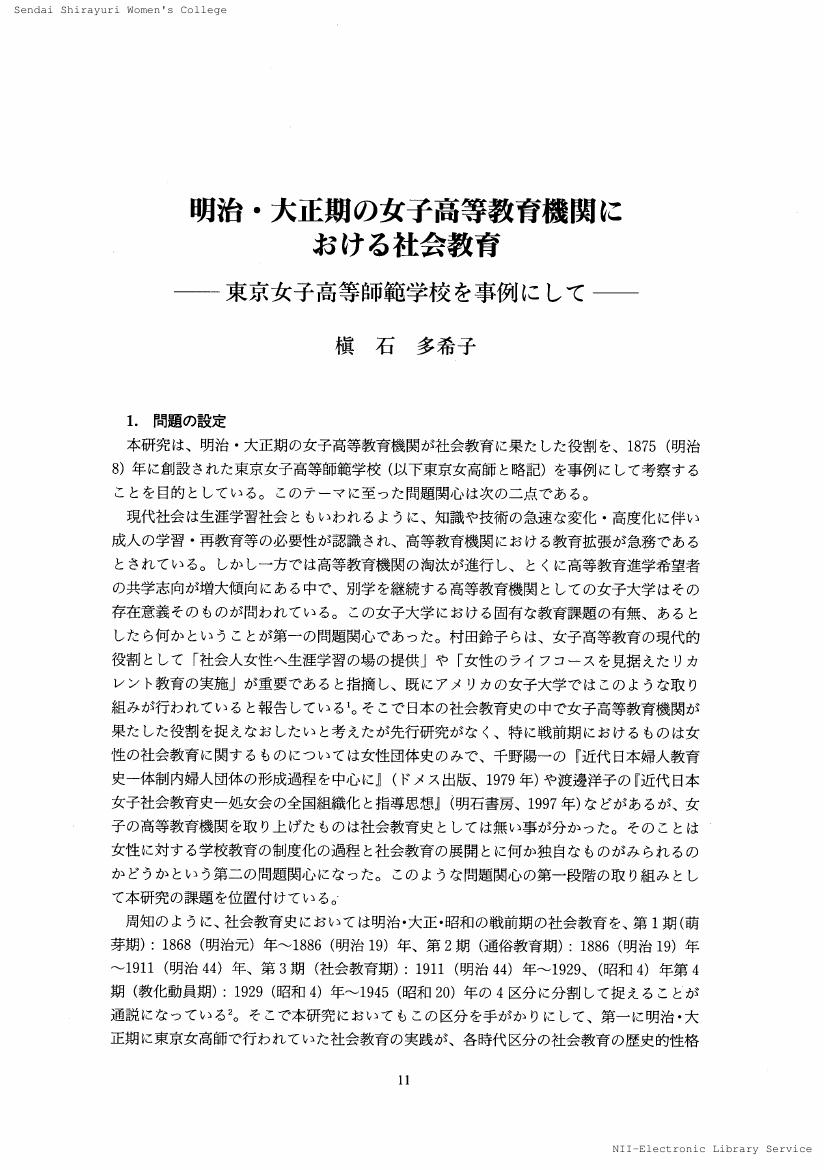- 著者
- 槙石 多希子
- 出版者
- 学校法人白百合学園 仙台白百合女子大学
- 雑誌
- 仙台白百合女子大学紀要 (ISSN:13427350)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.11-23, 2001 (Released:2018-07-20)
- 著者
- 興膳 宏
- 出版者
- 日仏東洋学会
- 雑誌
- 通信 : Circulaire de la Societe franco-japonaise des etudes orientales (ISSN:09156119)
- 巻号頁・発行日
- no.43, pp.21-27, 2020-03
1 0 0 0 IR アメリカ合衆国の入国拒否制度の研究
- 著者
- 萩野 芳夫
- 出版者
- 南山大学法学会
- 雑誌
- 南山法学 = Nanzan Law Review (ISSN:03871592)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.1-32, 1977-12-20
1 0 0 0 OA 十二指腸潰瘍穿孔に似た外傷性直腸穿孔:伏せられた受傷機転
- 著者
- 水村 直人 奥村 哲 豊田 翔 小川 雅生 川崎 誠康
- 出版者
- 日本腹部救急医学会
- 雑誌
- 日本腹部救急医学会雑誌 (ISSN:13402242)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.4, pp.783-785, 2018-05-31 (Released:2019-12-07)
- 参考文献数
- 10
経肛門異物では患者から正確な情報が得られない場合がある。十二指腸潰瘍の既往がある50歳代の男性が,食後からの心窩部痛で救急搬送された。CT検査では十二指腸周囲に遊離ガスと大量腹水を認めた。十二指腸潰瘍穿孔と初期診断したが,直腸診での鮮血,高い腹水CT値より外傷性下部消化管穿孔の可能性を考えた。最終的にプライバシーに配慮した問診を行い,肛門から同性パートナーの前腕を挿入したことが判明した。開腹所見では,直腸Rsが穿孔,S状結腸に漿膜筋層断裂を認め,ハルトマン手術を施行した。本症例は十二指腸潰瘍穿孔に極めて類似していたが,伏せられた受傷機転が穿孔部位の術前診断に重要であった。
1 0 0 0 秘曲尽くし事件の起きた時期--長明大原在住期の可能性
- 著者
- 今村 みゑ子
- 出版者
- 説話文学会
- 雑誌
- 説話文学研究 (ISSN:02886707)
- 巻号頁・発行日
- no.25, pp.p24-35, 1990-06
- 著者
- Keijiro Saku Bo Zhang Keita Noda The PATROL Trial Investigators
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.6, pp.1493-1505, 2011 (Released:2011-05-25)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 140 94
Background: Atorvastatin, rosuvastatin and pitavastatin are available for intensive, aggressive low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C)-lowering therapy in clinical practice. The objective of the Randomized Head-to-Head Comparison of Pitavastatin, Atorvastatin, and Rosuvastatin for Safety and Efficacy (Quantity and Quality of LDL) (PATROL) Trial was to compare the safety and efficacy of atorvastatin, rosuvastatin and pitavastatin head to head in patients with hypercholesterolemia. This is the first prospective randomized multi-center trial to compare these strong statins (UMIN Registration No: 000000586). Methods and Results: Patients with risk factors for coronary artery disease and elevated LDL-C levels were randomized to receive atorvastatin (10mg/day), rosuvastatin (2.5mg/day), or pitavastatin (2mg/day) for 16 weeks. Safety was assessed in terms of adverse event rates, including abnormal clinical laboratory variables related to liver and kidney function and skeletal muscle. Efficacy was assessed by the changes in the levels and patterns of lipoproteins. Three hundred and two patients (from 51 centers) were enrolled, and these 3 strong statins equally reduced LDL-C and LDL particles, as well as fast-migrating LDL (modified LDL) by 40-45%. Newly developed pitavastatin was non-inferior to the other 2 statins in lowering LDL-C. There were no differences in the rate of adverse drug reactions among the 3 groups, but HbA1c was increased while uric acid was decreased in the atorvastatin and rosuvastatin groups. Conclusions: The safety and efficacy of these 3 strong statins are equal. It is suggested that the use of these 3 statins be completely dependent on physician discretion based on patient background. (Circ J 2011; 75: 1493-1505)
1 0 0 0 なにわ町人学者
- 著者
- 毎日新聞社社会部 編
- 出版者
- 所書店
- 巻号頁・発行日
- 1967
1 0 0 0 俳味
- 著者
- 大日本徘諧講習會 [編]
- 出版者
- 文成社 (発売)
- 巻号頁・発行日
- 1910
1 0 0 0 OA 18世紀における清朝のモンゴルに対する法支配
- 著者
- 中生 勝美
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 民族學研究 (ISSN:00215023)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.1, pp.47-65, 1997
民族研究所は, 戦時中の短い期間に存続した。そこの研究員は, 戦後に活躍する民族学者が数多く在籍していた。しかし, 「戦争協力をした研究所」との批判があり, その実態は明らかにされていない。民族研究所は, 終戦とともに廃庁となったため, 残された資料は完全でない。そこで, 公文書と関係者の聞き取りから, 民族研究所の設立経緯と活動内容を調べ, ウィーンに留学していた岡正雄の民族研究所設立の構想, その人脈に加え, 日本の民族学者を組織していた古野清人の協力で, 民族研究所が設立された経緯を明らかにできた。民族研究所の設立目的は, 日本軍の占領地を現地調査することにより, 現地の異民族工作のための基礎資料を集めることであった。しかし実際には, 直接的な民族政策への参与はなく, 現地調査や文献研究により, 学術的に水準の高い研究が生まれた。特に, 岡正雄がウィーン学派への疑問から, イギリス的社会人類学へ問題関心を転換しており, フィールドワークによる異文化研究を, 民族研究所で実現したいと考えていた。戦後の日本民族学会をリードするメンバーは, 戦後になってヨーロッパやアメリカの人類学を受容したのではなく, 戦時中に設立された民族研究所の時代には, すでに海外の研究動向に目を配りつつ, 占領地や植民地のフィールドワークにより, 戦後に連続する研究を始めている。その一方で, 国策機関としての民族研究所が運営されたため, 研究所の蔵書の一部が, 占領地の略奪図書を中心に集められていたことなども明らかになった。中国には「飲水想源」(水を飲むとき, 源を想う)という諺がある。日本民族学のルーツを直視して, 負の遺産も含めた歴史を記憶する作業は, 民族学の現在を考える上で意義があるのではないだろうか。
- 著者
- 山本 浩貴
- 出版者
- 国立美術館東京国立近代美術館
- 雑誌
- 現代の眼 = Newsletter of the National Museum of Modern Art, Tokyo : 東京国立近代美術館ニュース
- 巻号頁・発行日
- no.630, pp.4-5, 2019-01
1 0 0 0 OA 地方小都市再生の前提条件 滋賀県長浜市第三セクター「黒壁」の登場と地域社会の変容
- 著者
- 矢部 拓也
- 出版者
- 日本都市社会学会
- 雑誌
- 日本都市社会学会年報 (ISSN:13414585)
- 巻号頁・発行日
- vol.2000, no.18, pp.51-66, 2000-07-08 (Released:2011-02-07)
- 参考文献数
- 33
1 0 0 0 テトリス®の技能向上を目指したHOLD使用傾向の基礎的分析
- 著者
- 梶並 知記 松村 瞬 辻 裕之
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.11, pp.1747-1755, 2017-11-15
本稿では,テトリス®のプレイにおける,HOLD機能の使用傾向について4つの観点から分析した結果を報告する.テトリス®は,盤面に上方から落下してくる4つの正方形を組み合わせたテトリミノと呼ばれる7種類のブロックを用いてプレイするパズルゲームである.プレイヤは,落下中のテトリミノに回転操作を加えて横1ライン隙間なく埋め,そのラインを消す.テトリス®には,落下中のテトリミノを,後で使うために一時的に保持するHOLD機能を備えている.従来,テトリス®を対象にした研究には,AIを用いた自動プレイに関するものや,テトリス®が人間に与える影響に関するものがある.それらの従来研究に対し,本研究は,人間であるプレイヤのテトリス®のプレイ技能向上を長期目標とした研究の1ステップである.本稿では,テトリス®のプレイヤをプレイ技能に応じて熟練者と非熟練者の2つに分類し,プレイヤのプレイ技能に応じてHOLD機能の使用傾向について分析する.Tetris Online Polandから操作ログファイルを収集し,(1) HOLD機能を使用する頻度,(2) HOLDするテトリミノの種類,(3) HOLDするテトリミノの順序,(4) HOLDミスの頻度が,プレイ技能に応じて異なることを示す.
- 著者
- 小林 浩子
- 出版者
- 羽陽学園短期大学
- 雑誌
- 羽陽学園短期大学紀要 = Bulletin of Uyo Gakuen College (ISSN:02873656)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.1, pp.31-37, 2007-02-01
本稿では、トリイ・ヘイデンのノンフィクション小説『シーラという子』の続編ともいえる作品『タイガーと呼ばれた子』を取り上げ、被虐待児に対するより良い教育方法を模索する。この作品では、小学校の特殊学級担任時代に教師として教育にかかわった、問題児であり被虐待児シーラと数年後に再会したトリイが、自らの「癒しの教育」がシーラに与えた影響の大きさと、それがトリイのクラスを卒業した後のシーラ自身に必ずしも良い影響を及ぼしてはいなかったことを、そしてさらなるトラウマを与えていたことを、ティーンエイジャーとなったシーラから指摘され、衝撃を受ける。しかしながらトリイは、そのショックを受け止め、シーラとさらに関わりを持ち続けることで、二人が抱えるトラウマを再認識し、そのトラウマを乗り越える新たな「癒しの教育」を見つけ出す。その過程を、トラウマからの「リハビリテーション」と「ハビリテーション」の違いという視点から考察する。
1 0 0 0 OA 日本国憲法の制定経緯等に関する参考人の発言の要点
- 著者
- 衆議院憲法調査会事務局
- 出版者
- 衆議院
- 巻号頁・発行日
- 2000-05
- 著者
- 衆議院憲法調査会事務局
- 出版者
- 衆議院
- 巻号頁・発行日
- 2002-02
1 0 0 0 OA 憲法訴訟に関連する用語等の解説
- 著者
- 衆議院憲法調査会事務局
- 出版者
- 衆議院
- 巻号頁・発行日
- 2000-05