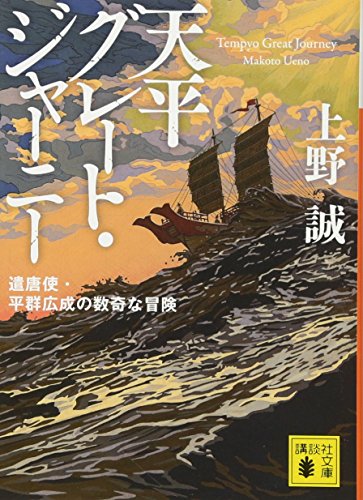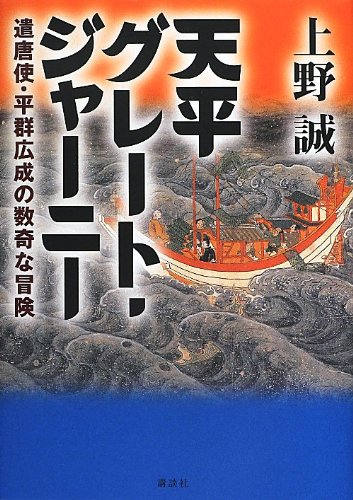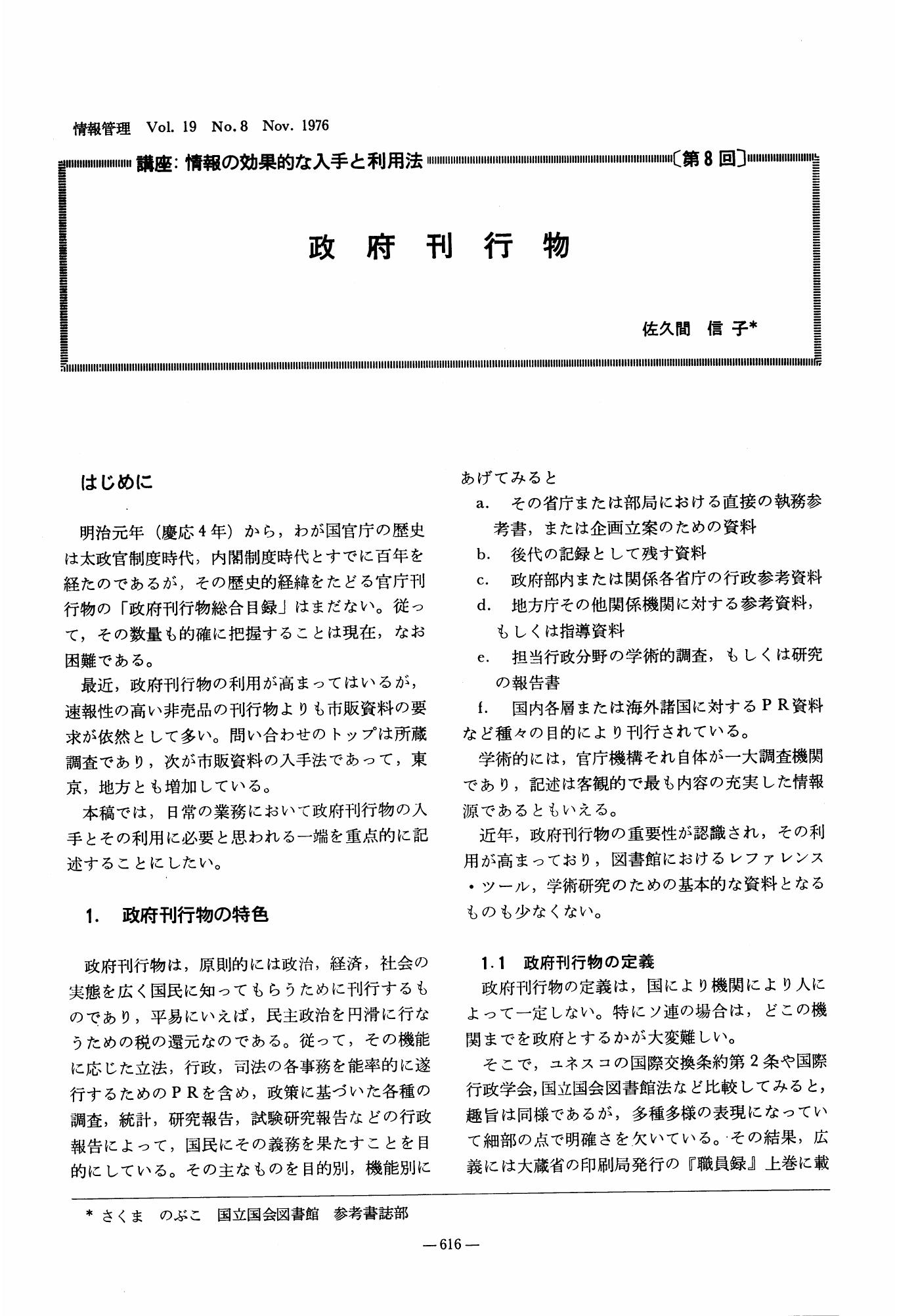1 0 0 0 OA 憤怒・和解・自由 : 許鞍華の映画について (上)
- 著者
- 川田 耕 Koh Kawata 京都学園大学経済学部
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.2, pp.47-60, 2008-02-01
現代の香港においてもっとも優れた映画監督、許鞍華(1947年~)の作品を通時的に分析することによって、そこに世界と自己をめぐる独創的な認識が展開されていることを明らかにする。許鞍華は、78年のテレビ・ドラマ『来客』から82年の『投奔怒海』にいたる「ベトナム三部曲」において、返還後の香港の運命を寓話的に警告するなどといった社会的な批判をすることにとどまらず、我々の生きる世界が根源的に理不尽で過酷なものであるという迫害的な世界観を激しい憤怒をもって提示した。けれども、次第に自分の人生への回顧と自省の傾向を強めていき、母親との和解を主題とした90年の『客途秋恨』以降は、具体的な人間関係を主題とするより安定したものに変化するとともに、男たちの身勝手な姿を辛辣に、しかし悲哀をもって描くようになる(『女人、四十』『半生縁』など)。こうした転換をへて、許鞍華は、かねて散発的に取り上げてきた「望まれない妊娠」というモチーフを中心的なテーマにすえてそれに内省的に取り組むにいたる。それが許鞍華の映画作家としての頂点をなす『千言寓語』(99年)と『男人四十』(2001年)であり、そこで彼女は、理不尽にもみえる世界と社会のなかでの、愛情と生殖と欲望をめぐる、生きることのダイナミズムを表現する。さらに『姨媽的後現代生活』(06年)では、自分の人生への失望とともに、後の世代への希望を表明する。
1 0 0 0 天平グレート・ジャーニー : 遣唐使・平群広成の数奇な冒険
1 0 0 0 天平グレート・ジャーニー : 遣唐使・平群広成の数奇な冒険
- 著者
- 渡辺信一
- 出版者
- 野村総合研究所
- 雑誌
- NRIパブリックマネジメントレビュー
- 巻号頁・発行日
- vol.2014年(6月), no.131, 2014-06
1 0 0 0 OA II. BWR形原子力発電所の設計と構成
- 著者
- 世古 隆哉
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電氣學會雜誌 (ISSN:00202878)
- 巻号頁・発行日
- vol.106, no.11, pp.1057-1058, 1986-11-20 (Released:2008-04-17)
1 0 0 0 2A1-H4 福島視察と科学史を活用した「ポスト3.11の放射線教育」(ポスト3.11の科学教育を科学論の視点より考える,課題研究,学びの原点への回帰-学習の質を高める科学教育研究-)
- 著者
- 河野 俊哉
- 出版者
- 一般社団法人 日本科学教育学会
- 雑誌
- 日本科学教育学会年会論文集 (ISSN:21863628)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.42-43, 2013
2010年度の発表「科学リテラシーの観点から「科学教育と科学史」を再考する」においては,『21世紀科学』をはじめとする近年の英米の代表的な教科書を検討し,従来型の「体系重視」から,「文脈・脈絡(コンテクスト)重視」への移行を指摘した.また、それ自体は英米の事例をもとに書かれていたため,日本独自の教科書やカリキュラム開発の必要性を主張した.その後東日本大震災を経験した日本は,本当の意味での科学への「信頼の危機」を経験し,現在では,とりわけ放射線教育において新たなる教材の試みが求められている.本発表では,福島視察と科学史の知見を活用した新たなる放射線教育の事例を提示するが,そのことにより科学史,STS,そして科学コミュニケーションを包含する「科学論」の知見が重要な役回りを果たすことを中等教育と高等教育,それぞれの事例を通して明らかにする.
1 0 0 0 OA リコイルカーブを用いたNd-Fe-B 系HDDR 磁粉の磁化過程解析
- 著者
- 槙 智仁 広沢 哲
- 出版者
- 公益社団法人 日本磁気学会
- 雑誌
- 日本応用磁気学会誌 (ISSN:02850192)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.3, pp.189-192, 2007 (Released:2007-05-31)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1 1
The magnetization mechanism of an Nd-Fe-B HDDR magnet was studied by measuring its recoil curves. When compared with those of isotropic Nd-Fe-B sintered, HDDR, and melt-spun magnets, the behavior of the recoil curves of the HDDR magnet was similar to that of the recoil curves of the melt-spun magnet. This means that the isotropic HDDR magnet behaved like single-domain particles. In addition, calculated isotropic recoil curve that assumes only rotation of the magnetization of single-domain particles showed the same tendency as the recoil curves of the HDDR magnet. This result indicates that the recoil curves of an isotropic HDDR magnet were dominated by rotation of the magnetization, and were not significantly influenced by domain wall movement. Moreover, the recoil curve of an anisotropic HDDR magnet behaved similarly to calculated anisotropic recoil curve based on the rotation of the magnetization of single-domain particles with an orientation distribution. This means that the recoil curves of an anisotropic HDDR magnet were also dominated by rotation of the magnetization. These results suggest that the HDDR magnet behaved like single-domain particles in its recoil curves, which were dominated by rotation of the magnetization and were not significantly influenced by domain wall movement.
1 0 0 0 OA 2016スコットランドリンクワーカープログラム視察研修報告書
- 著者
- 八巻 貴穂 小田 史郎
- 出版者
- 北翔大学
- 雑誌
- 北翔大学生涯スポーツ学部研究紀要 = Bulletin of Hokusho University School of Lifelong Sport (ISSN:18849563)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.201-206, 2017
1 0 0 0 OA 異世界へつながる境目 : 「雪おんな」と「夢十夜」における「水」のイメージについて
- 著者
- 秦 裕緯
- 出版者
- 熊本大学
- 雑誌
- 熊本大学社会文化研究 (ISSN:1348530X)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.207-218, 2018-03-25
There are a lot of similarities between Patrick Lafcadio Hearn and Natsume Soseki. These two authors are known for both their similar work and experiences. The focus of this study is the images of water in Hearn's retold ghost story Yuki-Onna and Yume-Juya (which is also called Ten Nights Dreams), a series of short pieces by Soseki. The image of water appears frequently and plays an important part in both the two works. However, the expressions of water are different in both stories. There are two similar spaces consisted of the image of water existing in these two stories, which also acts as the connection and boundary to another world. Water plays opposite roles in marriage and mother-child relationship in Yuki-Onna and simultaneously, is an important metaphor between life and death in Yume-jiya. This study compares the similarities and differences by analyzing the two images of water in these two works and tries to clarify how and why they are shaped in these ways.
1 0 0 0 OA 情報の効果的な入手と利用法〔第8回〕 政府刊行物
- 著者
- 佐久間 信子
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.8, pp.616-624, 1976-11-01 (Released:2016-03-16)
- 参考文献数
- 2
- 著者
- 百留 恵美子
- 出版者
- 日本認知言語学会
- 雑誌
- 日本認知言語学会論文集 Papers from the National Conference of the Japanese Cognitive Linguistics Association
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.642-647, 2013
- 著者
- 宮本 司
- 出版者
- 中国社会文化学会
- 雑誌
- 中国 : 社会と文化 (ISSN:09129308)
- 巻号頁・発行日
- no.35, pp.132-153, 2020-07
1 0 0 0 OA 日本憲政発達史・条約改正史論
1 0 0 0 図書館学遺産セレクション
- 出版者
- 金沢文圃閣