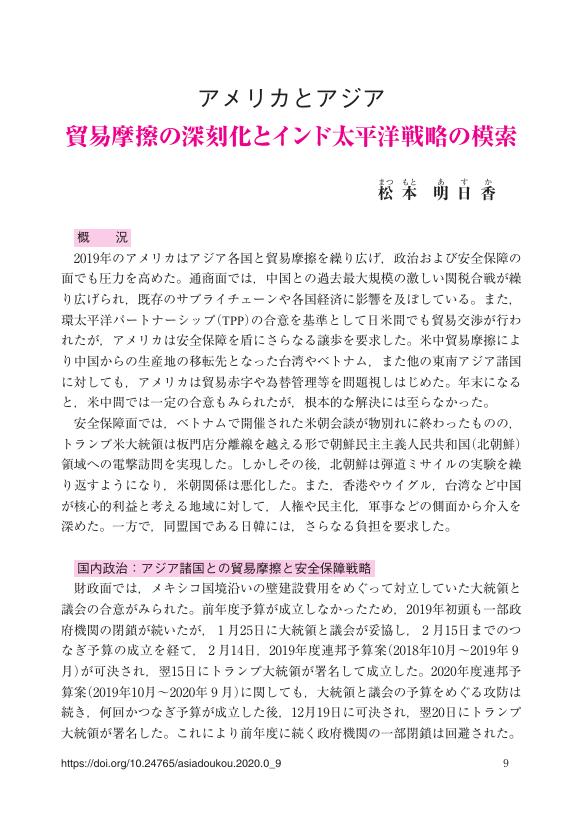- 著者
- KUROSAWA H
- 雑誌
- Hear and Vessel
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.48-50, 1985
- 被引用文献数
- 1 2
1 0 0 0 OA 生体システム論
- 著者
- 井上 昌次郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本生体医工学会
- 雑誌
- 医用電子と生体工学 (ISSN:00213292)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.2, pp.45-51, 1974-04-30 (Released:2011-03-09)
- 参考文献数
- 11
An attempt to know the principle of control in the living systems by investigators in broad fields of nonbiological disciplines may give rise to the following expectation. The present-day technological civilization has urged every unit component and every unit process of our society to organize into certain purpose-pursuing systems, which have never existed before. Such huge artificial systems have brought about a tremendous development on one hand, but an unexpected transitional chaos on the other, which covers a world-wide range of disturbances to the harmony in our biosphere. Meanwhile, a biological organism exists as a totality, exhibiting a beautiful harmony not only with other external components but also with its own internal components. Consequently, the control principle governing the biological systems may give some valuable suggestions for the construction and well maintenance of artificial systems, through reorganizing our view of value. On the basis of such presupposition, discussions extend to how we can categorize living organisms into systems from phylogenetical, ontogenetical, distributional, morphological, biochemical, physiological, behavioral standpoints and so forth, referring to the integrative role played by the neuroendocrine control system. Then some characteristics of biological systems such as the a posteriori nature which is related to adaptability, individuality and feedback mechanism, the reproductivity and reutility associated with chain-relations and cyclicity, the variety and individual differences, and the incompleteness and nonlinearity related to dynamic stability, are described in comparison with artificial systems. The methodology applied to the analysis and synthesis of biological performances are also briefly reviewed. Finally, the difference between the status of our-recognition and the initial expectation is clarified together with some optimistic encouragement based on an analogy with evolutional history of the living organisms.
1 0 0 0 OA 近江日野商人の独自性と売薬行商の展開
- 著者
- 幸田 浩文
- 出版者
- 東洋大学経営力創成研究センター
- 雑誌
- 経営力創成研究 = Journal of Creative Management (ISSN:18800521)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.5-20, 2018-03
近江商人は、江戸時代に現在の滋賀県・琵琶湖周辺の近江地方から発祥した高島・八幡・日野・湖東商人の総称である。近江商人は、地元の裕福な商人と豊富な労働力を結びつけ、本家を地元に置き、行商先に店舗を設けることで、独自の流通網を構築した。とくに日野商人は他の近江商人のように大都市ではなく、北関東と東北の小都市ならびにその周辺地域で行商し、その土地に次々と店舗を開き、その出店を通じて商品を委託販売した。1701 年に近江・日野町の正野玄三により合薬が創製され、その薬効が好評を博するにつれ、次第に古くから日野行商の主力商品であった日野椀に取って代わり、新たに日野売薬が従来の販売網を通じて委託販売されるようになった。それを支援したのが1680 年に設立された商人の仲間組織である「大当番仲間」であった。この組織の活動はその後明治時代初期までおよそ200 年余り続けられ、日野売薬の発展に大いに貢献した。
1 0 0 0 OA 竹内仁遺稿
- 著者
- 竹内仁遺稿刊行会 編
- 出版者
- 竹内仁遺稿刊行会[ほか]
- 巻号頁・発行日
- 1928
1 0 0 0 OA 一般公衆浴場(銭湯)における温浴、温冷交代浴の心身への影響の検討
- 著者
- 早坂 信哉 三橋 浩之 亀田 佐知子 早坂 健杜 石田 心
- 出版者
- 一般財団法人 日本健康開発財団
- 雑誌
- 日本健康開発雑誌 (ISSN:2432602X)
- 巻号頁・発行日
- pp.202142G07, (Released:2021-02-09)
- 参考文献数
- 13
背景・目的 一般公衆浴場である銭湯を定期的に利用する者は幸福度が高いなどの心身への関連をこれまで筆者らは横断研究で報告してきた。銭湯は浴槽が複数あり温水単体による通常入浴の他、冷水浴を用いた温冷交代浴をしやすい環境にあるが、銭湯におけるこれらの入浴の効果を測定した研究は少ない。本研究では銭湯における通常入浴及び温冷交代浴の心身への影響を介入研究によって明らかにすることを目的とした。方法 同一被験者内前後比較試験として、成人男女10名を対象に、銭湯で通常入浴 (40℃10分全身浴)、温冷交代浴(40℃3分全身浴→25℃1分四肢末端シャワー浴(2度繰り返し)→40℃4分全身浴で終了)をそれぞれ単回行い、入浴前後で16項目の心身の主観的評価項目、体温、唾液コルチゾール、オキシトシンを測定した。結果 前後比較では、心身の主観的評価項目では通常入浴は幸福感など11項目、温冷交代浴では13項目が入浴後に好評価となった。通常入浴では唾液コルチゾールが入浴後に有意に低下し(p=0.005)、前後の変化量は群間比較で温冷交代浴と比べて通常入浴が大きかった(p=0.049)。考察 通常入浴、温冷交代浴とも心身への主観的評価は入浴後に好評価となりいずれの入浴法でも心身へ良い影響を与えることが推測された。温冷交代浴の優位性が報告されることがあるが、本研究では通常入浴でも好影響が確認できた。
1 0 0 0 OA 表情豊かな顔ロボットの開発と受付システムの実現
- 著者
- 小林 宏
- 出版者
- The Robotics Society of Japan
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.6, pp.708-711, 2006-09-15 (Released:2010-08-25)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 6 2
1 0 0 0 OA 禅宗文化圏における摩利支天像の受容と展開 - 信濃小笠原氏ゆかりの開善寺の事例から -
- 著者
- 織田 顕行
- 出版者
- 飯田市美術博物館
- 雑誌
- 飯田市美術博物館 研究紀要 (ISSN:13412086)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.45-60, 2017 (Released:2017-09-29)
1 0 0 0 OA がんゲノム医療における薬剤師の役割
- 著者
- 寺田 智祐
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)
- 巻号頁・発行日
- vol.140, no.5, pp.663-666, 2020-05-01 (Released:2020-05-01)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 1
The development of cancer genomic medicine has been embraced as an important new policy issue in “The 3rd Basic Plan to Promote Cancer Control Programs” formulated by the Japanese government. Cancer-associated gene panel testing has been recognized by the public health insurance system since July 2019, and is a critical component of the clinical implementation of genomic science. Because of this dynamic change in cancer medicine, pharmacists are now expected to acquire knowledge about genomic science, and to apply it to individualized and appropriate pharmacotherapies. This review outlines the roles of pharmacists in cancer genomic medicine.
1 0 0 0 OA 沖縄諸島における農耕の起源――沖縄本島を中心に
- 著者
- 高宮 広土
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 日本文化の深層と沖縄 = The Deep Roots of Japanese Culture and Okinawa
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.117-132, 1996-12-27
1 0 0 0 童話コンクール受賞作品集
- 出版者
- 阪急電鉄
1 0 0 0 意匠法の目的と部分意匠論 : 文化的所産の財産法的保護
- 著者
- 辻中 豊 李 政煕 廉 載鎬 TSUJINAKA Yutaka LEE Chung-Hee YEOM Jaeho
- 出版者
- 木鐸社
- 雑誌
- レヴァイアサン (ISSN:13438166)
- 巻号頁・発行日
- no.23, pp.18-49, 1998-10
無作為抽出法による日韓国体調査と日米韓の事業所統計等の詳細な比較分析によって、一九八七年以後の韓国の政治体制と市民社会の位相を浮き彫りにする。九〇年代の市民団体の爆発的増加、団体多元性の進展は、いかなる変容を韓国社会にもたらしたのか。
1 0 0 0 OA 仮面が隠すもの、暴くもの--ルイザ・メイ・オルコットのセンセーション・ノベル
- 著者
- 羽澄 直子
- 出版者
- 名古屋女子大学
- 雑誌
- 名古屋女子大学紀要 人文・社会編 = Journal of Nagoya Women's University,humanities・social science (ISSN:09152261)
- 巻号頁・発行日
- no.49, pp.245-253, 2003-03
1 0 0 0 OA アメリカとアジア 貿易摩擦の深刻化とインド太平洋戦略の模索
- 著者
- 松本 明日香(まつもと あすか)
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- アジア動向年報 (ISSN:09151109)
- 巻号頁・発行日
- vol.2020, pp.9-22, 2020 (Released:2020-12-17)
1 0 0 0 OA 2019年のASEAN インド太平洋構想の発表
- 著者
- 鈴木 早苗(すずき さなえ)
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- アジア動向年報 (ISSN:09151109)
- 巻号頁・発行日
- vol.2020, pp.179-192, 2020 (Released:2020-12-17)
- 著者
- 竹沢 尚一郎
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.4, pp.1025-1026, 2011
- 著者
- 永山 くに子 我部山 キヨ子
- 出版者
- 京都大学医学部保健学科
- 雑誌
- 健康科学 (ISSN:18802826)
- 巻号頁・発行日
- no.3, pp.49-53, 2006
- 著者
- 後藤 大介 赤崎 将 北川 敏一
- 出版者
- 基礎有機化学会(基礎有機化学連合討論会)
- 雑誌
- 基礎有機化学討論会要旨集(基礎有機化学連合討論会予稿集)
- 巻号頁・発行日
- vol.2008, pp.147, 2008
1,2-ジクロロエタン中、AlCl<SUB>3</SUB>とC<SUB>60</SUB>の反応により、クロロエチル付加体(CH<SUB>3</SUB>CHCl-C<SUB>60</SUB>-Cl)が得られた。この付加体をフラレノール(CH<SUB>3</SUB>CHCl-C<SUB>60</SUB>-OH)に変換した後、強酸で処理することにより、新規フラーレンカチオン (CH<SUB>3</SUB>CHCl-C<SUB>60</SUB><SUP>+</SUP>)を発生させNMR観測することに成功した。これらのカチオンの構造と安定性を、これまでに報告した他のアルキルC<SUB>60</SUB>カチオンと比較して報告する。