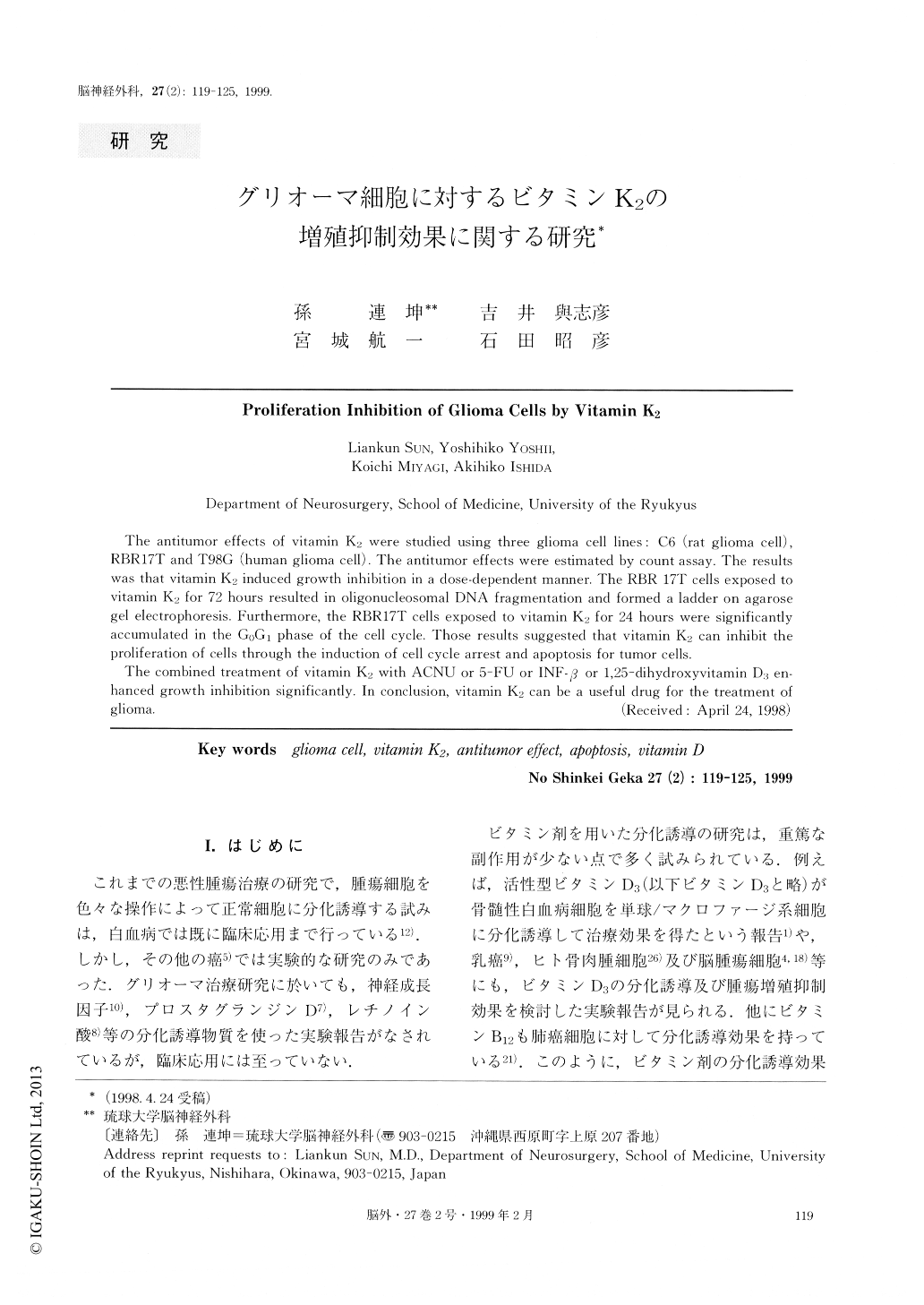1 0 0 0 OA 最近のゲームプログラミング研究の動向 (<小特集>「ゲームプログラミング」)
- 著者
- 松原 仁
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能 (ISSN:21882266)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.6, pp.835-845, 1995-11-01 (Released:2020-09-29)
1 0 0 0 世界お伽噺 : 合本
1 0 0 0 グリオーマ細胞に対するビタミンK2の増殖抑制効果に関する研究
I.はじめに これまでの悪性腫瘍治療の研究で,腫瘍細胞を色々な操作によって正常細胞に分化誘導する試みは,白血病では既に臨床応用まで行っている12).しかし,その他の癌5)では実験的な研究のみであった.グリオーマ治療研究に於いても,神経成長因子10),プロスタグランジンD7),レチノイン酸8)等の分化誘導物質を使った実験報告がなされているが,臨床応用には至っていない. ビタミン剤を用いた分化誘導の研究は,重篤な副作用が少ない点で多く試みられている.例えば,活性型ビタミンD3(以下ビタミンD3と略)が骨髄性白血病細胞を単球/マクロファージ系細胞に分化誘導して治療効果を得たという報告1)や,乳癌9),ヒト骨肉腫細胞26)及び脳腫瘍細胞4,18)等にも,ビタミンD3の分化誘導及び腫瘍増殖抑制効果を検討した実験報告が見られる.他にビタミンB12も肺癌細胞に対して分化誘導効果を持っている21).このように,ビタミン剤の分化誘導効果や腫瘍増殖抑制効果は今後,種々のビタミン剤で検討されていくものと思われる.
1 0 0 0 OA 深層学習による医療文書からの病名と医療行為の抽出
- 著者
- 堂坂 浩二 石井 雅樹 伊東 嗣功
- 出版者
- 秋田県立大学(地域連携・研究推進センター)
- 雑誌
- 秋田県立大学ウェブジャーナルB(研究成果部門) = Akita prefectural University Web Journal B(Results of research)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.209-215, 2019-09-30
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.1151, pp.70-72, 2002-07-22
オリンパス光学工業のデジタルカメラが売れている。3月21日に発売された「CAMEDIA(キャメディア)C-2 Zoom」。カメラ量販店のヨドバシカメラでは、発売3カ月以上を経ても売れ筋商品の3位に食い込んでいる。 販売好調の理由は価格にある。200万画素で光学式3倍ズームレンズを搭載。この性能で2万9800円という店頭価格は、ライバル他社の製品を1万円は下回る。
1 0 0 0 OA トルコの教育改革--欧州水準を目指した量的拡大と世俗主義維持の機能
- 著者
- 丸山 英樹
- 出版者
- 国立教育政策研究所
- 雑誌
- 国立教育政策研究所紀要 (ISSN:13468618)
- 巻号頁・発行日
- vol.135, pp.137-151, 2006-03
1 0 0 0 OA 土壌微生物による炭酸カルシウム析出に及ぼす温度の影響
- 著者
- 川﨑 了 小潟 暁 広吉 直樹 恒川 昌美 金子 勝比古 寺島 麗
- 出版者
- 一般社団法人 日本応用地質学会
- 雑誌
- 応用地質 (ISSN:02867737)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.1, pp.10-18, 2010 (Released:2013-03-31)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 14 15
筆者らは, 土や岩の代表的なセメント物質である炭酸カルシウムまたはシリカを主成分とし, 微生物の代謝活動により土や岩の間隙や岩の割れ目を自然に閉塞させる新たな概念に基づくグラウト, すなわち, バイオグラウトを開発するための基礎的な研究を実施中である. 本論文では, 炭酸カルシウムを用いたバイオグラウト, すなわち, 炭酸カルシウム法に関して検討を実施した結果について報告する. 具体的には, 日本各地より採取した自然の土壌中に生息する微生物を用いて試験管による炭酸カルシウムの析出試験を行い, 試験時における温度の違いが炭酸カルシウム析出に与える影響について調査した. その結果, 温度5~35℃の低~中温域において, 土壌微生物により炭酸カルシウムが試験管内に析出することが示唆された. 一方, 試験に用いた土壌微生物の菌数測定および遺伝子解析を実施し, 試験前後の土壌中に含まれる微生物相の変化に関して, 生菌数, 最も出現頻度の高い菌の菌数およびその帰属分類群を用いることにより比較を行った. その結果, それらは主にPenicillium属およびAspergillus属の菌類であり, 有機栄養源を活発に代謝することにより菌数が増加したものと推定された.
- 著者
- Takumi KOMIYA Akihiro MORI Naohito NISHII Hitomi ODA Eri ONOZAWA Seri SEKI Toshinori SAKO
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- pp.2-0345, (Released:2021-03-05)
A 5-year-old castrated male domestic shorthair cat was diagnosed with diabetic ketoacidosis and severe insulin resistance. Although the conventional treatment for diabetic ketoacidosis was provided, the cat required frequent hospitalization because of severe dehydration and repeated diabetic ketoacidosis. We detected anti-insulin antibodies for human in this cat. Serum insulin-binding IgG levels were markedly elevated compared with those in healthy cats and other diabetic cats. We initiated prednisolone to suppress the effects of anti-insulin antibodies. After initiation of prednisolone, the cat was gradually recovered with increasing activity and appetite. Furthermore, satisfactory glycemic control was achieved with combined subcutaneous injection of insulin detemir and insulin degludec.
1 0 0 0 調製時における塩および油添加タイミングの違いによる塩味の感じ方
<p>【目的】減塩につながる調味方法としては,食品内部に塩味を拡散させず,食べる直前に食品表面に塩味をつける方法がある。これまでに,うま味や酸味を添加することで塩味強度が強まるという報告はあるが,油を添加した場合の塩味の感じ方についての報告は見当たらない。そこで,油添加に着目し,調製時における塩および油添加タイミングの違いによる塩味の感じ方について検討した。</p><p>【方法】塩および油添加タイミングを変えた飯表面に塩味をつけた試料(塩味表面試料)と,塩水で炊飯した試料(塩味均一試料)の塩むすびモデル系試料を調製した。塩添加量は米重量の1.15 w/w%(飯の0.5w/w%),油添加量は米重量の2.0 w/w%とした。試料の形状測定(マイクロスコープVHX-6000),物性測定(レオナーRE2-33005C)を行った。また,官能評価により,同一塩分濃度下における塩味の感じ方について,呈味強度(塩味,甘味,うま味)および味の好ましさを5段階評点法により評価した。</p><p>【結果および考察】1. 形状測定:米飯対角幅,周囲長,面積において,塩味表面試料は,塩味均一試料よりも高値を示した。2. 物性測定:硬さにおいて,塩味表面試料は,塩味均一試料よりも有意に低値を示した。3. 官能評価:塩味表面試料は,塩味均一試料に比べ塩味強度は有意に高かった。また,炊飯前油添加試料は,炊飯後油添加試料よりも塩味強度は有意に高かった。炊飯前に油を添加し炊飯後に飯表面に塩味を付与すると,塩味の感じ方は強くなることが示唆された。官能評価の塩味強度と物性測定の凝集性および付着性で負の相関が認められた。結果,米飯の凝集性,付着性が小さいほど,塩味強度は高くなることが示唆された。</p>
1 0 0 0 戦間期におけるパテ・シネマ社の小型映画産業とその興亡
- 著者
- 福島 可奈子
- 出版者
- 日本映画学会
- 雑誌
- 映画研究 (ISSN:18815324)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.28-49, 2019
第一次から第二次世界大戦までの戦間期にフランスで発売された、パテ・シネマ社製小型映画の産業技術的特徴とその経営戦略について論じる。パテ・シネマ社は、第一次世界大戦直前まで生フィルム製造販売事業で世界的覇者だったが、大戦後の大不況によってアメリカのコダック社に覇権を奪われた。その結果在庫フィルムを無駄なく再利用することで新規開拓を目指し、パテ・ベビー(9ミリ半映画)やパテ・ルーラル(17ミリ半映画)といった独自の小型映画を生み出す。だが日本の先行研究では、パテ・ベビーを中心に日本国内での小型映画文化研究が主流で、フランスでの小型映画の開発事情を含めた産業技術面から十分に議論されてきたとは言い難 い。ゆえに本稿では、二つの大戦に翻弄された二人の経営者(シャルル・パテとベルナール・ナタン)の経営手腕から、パテ・シネマ社が小型映画発売に至る経営的かつ産業技術的必然性を具体的に明らかにした。それによってパテ・ベビーを含む小型映画事業そのものが、第一次世界大戦後の大不況と軍事技術の転用なしには誕生し得なかったことを指摘した。
1 0 0 0 OA 桐生高等工業学校二十五年史
- 著者
- 桐生高等工業学校 編
- 出版者
- 桐生高等工業学校
- 巻号頁・発行日
- 1942
1 0 0 0 OA 思想形成期の田中耕太郎
- 著者
- 半澤 孝麿
- 出版者
- JAPANESE POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION
- 雑誌
- 年報政治学 (ISSN:05494192)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.208-240, 1976-03-30 (Released:2009-12-21)
1 0 0 0 IR 大学における幾何学初年度教育の現状と課題
- 著者
- 小林 雅子
- 出版者
- 佛教大学教育学部学会
- 雑誌
- 佛教大学教育学部学会紀要 = Bulletin of the Faculty of Education of Bukkyo University (ISSN:13474782)
- 巻号頁・発行日
- no.17, pp.39-49, 2018
学生が大学で幾何学を学ぶにあたり,高校までのような,ユークリッド空間内の図形の問題を解くのではなく,ユークリッド空間の部分集合としての図形のとらえ方などを習得するため,集合の記号や不等号の表す領域等,それまで図形と関連しては意識していなかった対象物を再確認することになる。その際,大学の数学テキストでは往々にして当然のように用いられている数学記号や図形の表現方法が学生には定着しておらず,幾何の問題そのもの以前に表現方法の理解不足から問題解決に至らないことがしばしばある。 そこで本稿では幾何学初年度講義において学生に調査を行い,図形表現方法の定着がどの程度であるか考察する。大学幾何学教育図形表現ユークリッド幾何
- 著者
- 平山 明仁 安東 潤
- 出版者
- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会
- 雑誌
- 日本船舶海洋工学会講演会論文集 1 (ISSN:24241628)
- 巻号頁・発行日
- pp.313-316, 2005 (Released:2017-12-28)
1 0 0 0 大阪府立図書館紀要
- 著者
- 大阪府立中之島図書館, 大阪府立中央図書館 編
- 出版者
- 大阪府立中之島図書館
- 巻号頁・発行日
- no.34, 1998-04