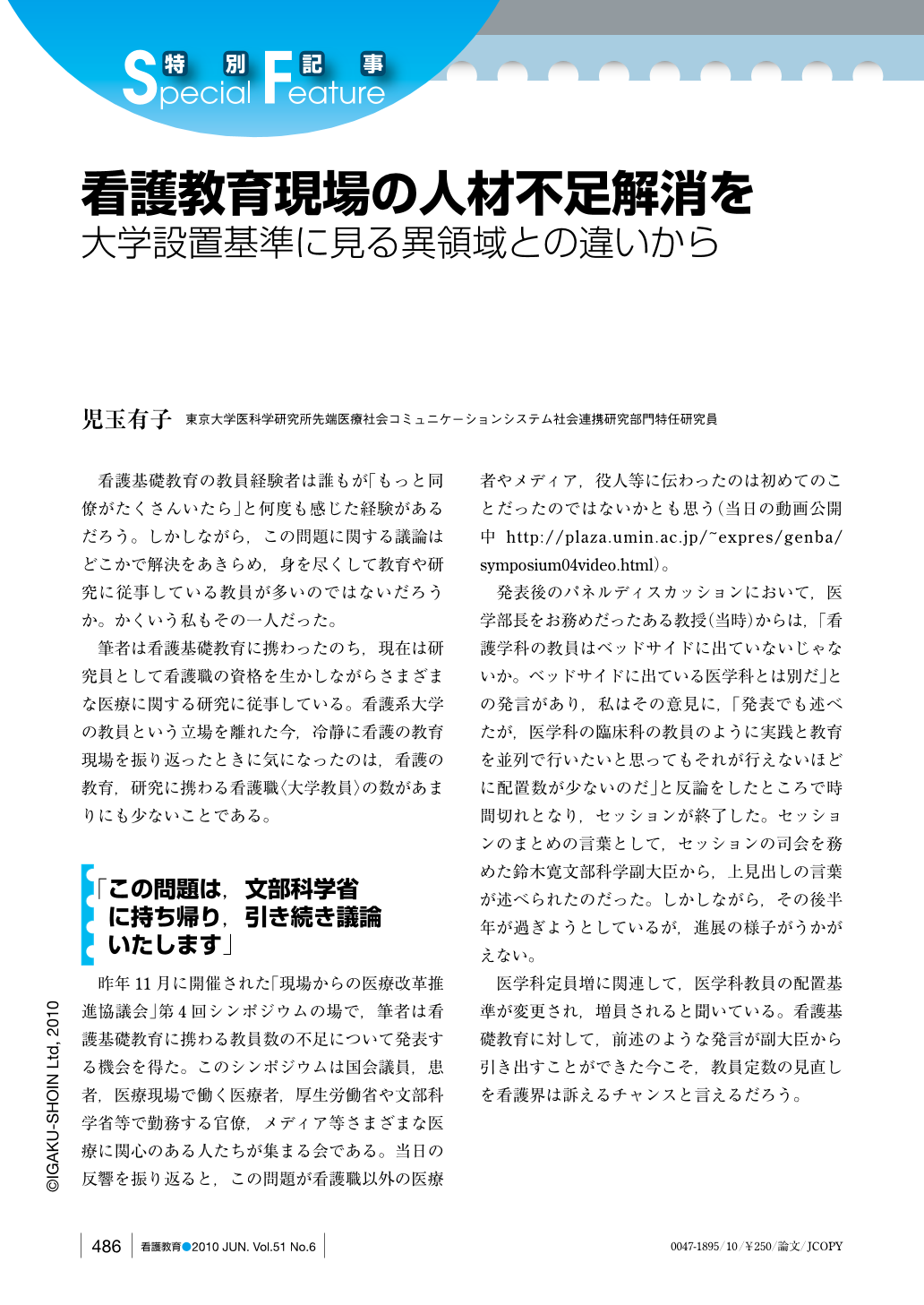- 著者
- 西田 和正 河合 恒 解良 武士 中田 晴美 佐藤 和之 大渕 修一
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.8, pp.518-527, 2020-08-15 (Released:2020-09-01)
- 参考文献数
- 28
目的 我々は,フレイル高齢者では,地域における役割がないことが,社会からの離脱を早め,二次的に心身機能維持の意欲が低下していると考え,地域保健モデルであるコミュニティアズパートナー(Community As Partner:CAP)に基づく介入によって地域における役割期待の認知を促す,住民主体フレイル予防活動支援プログラムを開発した。本報告では,このプログラムを自治体の介護予防事業等で実施できるよう,プログラムの実践例の紹介と,その評価を通して,実施可能性と実施上の留意点を検討した。方法 プログラムは週1回90分の教室で,「学習期」,「課題抽出期」,「体験・実践期」の3期全10回4か月間で構成した。教室は,ワークブックを用いたフレイル予防や地域資源に関する学習と,CAPに基づく地域診断やグループワークを専門職が支援する内容とした。このプログラムの実践を,地域高齢者を対象としたコホート研究のフィールドにおいて行った。基本チェックリストでプレフレイル・フレイルに該当する160人に対して案内を郵送し参加者を募集し,プログラムによる介入と,介入前後にフレイルや地域資源に対する理解度や,フレイル予防行動変容ステージについてのアンケートを行った。本報告では,参加率やフレイルの内訳,脱落率,介入前後のアンケートをもとにプログラムの実施可能性と実施上の留意点を検討した。結果 参加者は42人で(参加率26.3%),プレフレイル25人,フレイル17人であった。脱落者は10人であった(脱落率23.8%)。介入前後でフレイルの理解は5項目中4項目,地域資源の理解は,11項目中6項目で統計的に有意な向上を認めた(P<0.05)。フレイル予防行動変容ステージは,維持・向上したものが26人(81.2%)だった。結論 住民によるグループワークを専門職が支援するプログラムであっても,専門職が直接介入する従来型プログラムと同程度の約3割の参加率があった。一方,脱落率はやや高く,事前説明会で参加者に教室の特徴を理解させることや,教室中はグループワークに参加しやすくするための専門職の支援が重要であると考えられた。また,アンケート結果から,プログラムによってフレイルや地域資源への理解度が向上し,フレイル予防行動の獲得も示唆された。
1 0 0 0 OA Pilsicainide Intoxication with Neuropsychiatric Symptoms Treated with Continuous Hemodiafiltration
- 著者
- Marina Asano Takuto Hayakawa Yuki Kato Kyogo Kawada Shuji Goto Joel Branch Hideaki Shimizu
- 出版者
- The Japanese Society of Internal Medicine
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.17, pp.2191-2195, 2020-09-01 (Released:2020-09-01)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 3
A 72-year-old lady with atrial fibrillation and chronic renal failure was hospitalized due to bradycardic shock with electrocardiographic QRS prolongation. She had experienced limb shaking two days before hospitalization, and additionally developed hallucinations one day before admission. Pilsicainide intoxication was diagnosed from a review of her medications and electrocardiographic findings. Consequently, continuous hemodiafiltration was performed resulting in a resolution of the hallucinations and the QRS prolongation. This is a rare case of psychiatric symptoms caused by pilsicainide intoxication. It is important to know the mode of excretion of a drug and to adjust its dose, so that such drug-related incidents can be avoided.
1 0 0 0 IR ボアソナードと三兄弟
- 著者
- 村上 一博
- 出版者
- 明治大学史資料センター
- 雑誌
- 大学史紀要 (ISSN:13498231)
- 巻号頁・発行日
- no.25, pp.76-93, 2019-03-30
1 0 0 0 OA 当院における脊椎圧迫骨折患者の離床と歩行獲得経過について
- 著者
- 岩佐 志歩 館 博明 庄野 泰弘
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.40 Suppl. No.2 (第48回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.48101241, 2013 (Released:2013-06-20)
【はじめに、目的】 脊椎圧迫骨折における保存療法は、画像所見で骨折の程度を把握し急性期の安静臥床後、患者の状態に応じてコルセットを装着しリハビリテーション(以下、リハビリ)が開始される。当院においても、患者の状態に応じて離床しリハビリによってADLの拡大に取り組んでいる。しかし、離床から退院に至るまでの歩行獲得経過に不明な点も多い。今回、当院における脊椎圧迫骨折患者の離床と歩行獲得経過について検討を行った。【方法】 2009年1月から2012年3月までに入院加療した65歳以上の脊椎圧迫骨折患者45名(平均82.0±6.6歳)を対象とした。入院前は全例自宅で生活し、歩行は独歩もしくは伝い歩きであった。退院時の歩行レベルによって歩行自立群(自立群:27名)と歩行介助群(介助群:18名)に分類し、年齢、受傷椎体、受傷椎体数、圧潰率、コルセットの種類、離床までの期間、リハビリ開始までの期間、歩行開始までの期間、入院期間、リハビリ開始時の歩行能力、リハビリ開始2週目の歩行能力、退院時の歩行能力、退院時の転帰先につき電子カルテより後方視的に比較検討した。なお、歩行レベルは車椅子、歩行器歩行、杖歩行(介助)、杖歩行(自立)、独歩の5項目に分類した。また、統計処理にはunpaired t-testとカイ二乗検定を使用した。【倫理的配慮、説明と同意】 本研究はヘルシンキ宣言に基づき、個人が特定されないように個人情報の保護に配慮して検討を行った。【結果】 受傷椎体数(自立群:1.6±1.1椎体 vs 介助群:3.1±2.4椎体 p<0.01)、離床までの期間(自立群:1.7±2.3日 vs 介助群:3.9±4.8日 p<0.05)、歩行開始までの期間(自立群:5.9±4.7日 vs 介助群:11.2±6.2日 p<0.01)、入院期間(自立群:34.5±16.3日 vs 介助群:46.0±15.9日 p≦0.01)、に有意差があった。年齢、受傷椎体、圧潰率、コルセットの種類、リハビリ開始までの期間、リハビリ開始時の歩行能力に差はなかった。リハビリ開始2週目の歩行能力は、自立群では杖歩行(介助)が多かったのに対し、介助群では歩行器歩行が多かった(p<0.05)。退院時の歩行能力は、自立群では杖歩行(自立)以上であったのに対し、介助群では杖歩行(介助)が多かった(p<0.05)。転帰先は、自立群では全例自宅退院したのに対し、介助群では大部分が回復期リハビリテーション病棟(以下、回復期)への転院を要した(p<0.05)。【考察】 当院の傾向として、受傷椎体数が少なく早期離床が可能であった患者は、リハビリ開始前より病棟での歩行を開始していたためリハビリ開始と同時に積極的な歩行練習を行うことが可能であり、リハビリ開始2週目には杖歩行(介助)、退院時には杖歩行(自立)もしくは独歩で自宅退院した。また、入院期間も短かった。それに対し受傷椎体数が多く離床までに時間を要した患者は、リハビリ開始後から歩行練習を行い、リハビリ開始2週目には歩行器歩行、退院時には杖歩行(介助)と歩行獲得までに時間を要したため回復期へ転院となった。受傷椎体数、離床までの期間、リハビリ開始2週目の歩行能力は、退院時の歩行レベルや転帰先、入院期間の指標になると考えられる。今後は、離床や歩行獲得までの経過に疼痛や併存疾患などがどのような影響を及ぼしているのかを含めて検討を重ねていきたい。【理学療法学研究としての意義】 脊椎圧迫骨折の保存治療は、安静臥床後、リハビリテーションによってADLの拡大を目指すのが一般的であるが、離床から歩行獲得経過に不明な点が多かった。歩行獲得までの経過を明確にすることで、患者の歩行レベルや転帰先を早期に予測する判断材料となり得る。
1 0 0 0 OA 池田淑子編著『アメリカ人の見たゴジラ 日本人の見たゴジラ』大阪大学出版会、2019年3月
- 著者
- 志村 三代子
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.104, pp.286-290, 2020-07-25 (Released:2020-08-25)
1 0 0 0 OA 配電系統における電圧変動
- 著者
- 小澤 知広
- 出版者
- 一般社団法人 電気設備学会
- 雑誌
- 電気設備学会誌 (ISSN:09100350)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.10, pp.781-783, 2005-10-10 (Released:2015-06-26)
- 参考文献数
- 2
1 0 0 0 OA 菅原慶乃著『映画館のなかの近代 映画観客の上海史』晃洋書房、2019年7月
- 著者
- 劉 文兵
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.104, pp.268-270, 2020-07-25 (Released:2020-08-25)
1 0 0 0 OA 中村秀之著『暁のアーカイヴ——戦後日本映画の歴史的経験』東京大学出版会、2019年7月
- 著者
- 大澤 浄
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.104, pp.256-260, 2020-07-25 (Released:2020-08-25)
1 0 0 0 OA 1930年代の批評言説からみる小津映画の「日本的なもの」
- 著者
- 具 慧原
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.104, pp.31-50, 2020-07-25 (Released:2020-08-25)
- 参考文献数
- 56
小津の「日本的なもの」は、彼の戦後作品が1970年代にアメリカの論者たちによって伝統的なものと解釈されて以来、盛んに議論された。しかし従来の研究は主に表象の分析に偏っているため、小津を初めて「日本的」と評価した1930年代の議論の全貌は十分に検討されていない。従って本稿は言説史的方法論を取り入れ、小津安二郎の「日本的なもの」が1930年代の日本国内においてどのように論じられたかを批評言説に即して考察し、当時に言われた「日本的なもの」という概念の内実を明らかにすることを目指す。第一に、小津に対する「日本的」という評価の出現を確認する。その上で、こうした評価を起こした三つの要因として、『出来ごころ』に見られる変化や小津の小市民映画を重視する批評家の態度、そして「日本的なもの」を話題にする日本映画批評の全体的傾向を提示する。第二に、これらの要因を踏まえながら、今村太平、北川冬彦、沢村勉の論稿を彼らの批評的立場に即して検討する。これを通して小津の「日本的なもの」は「二次元性」「腹藝・靜」「文化的混淆」として捉えられ、さらにそれらは伝統的なものに限定されておらず、小津の同時代の監督が共有するものとしてみなされたことを示す。その結果、小津の生きていた時代の日本国内における「日本的なもの」の議論は、その始まりからアメリカの短絡的な議論とは全く違い、一層複雑な様相を帯びていることが明らかになる。
1 0 0 0 IR 豫楽院 近衞家熈公年譜稿(2)
- 著者
- 緑川 明憲
- 出版者
- 京都大学大学院文学研究科国語学国文学研究室
- 雑誌
- 京都大学國文學論叢 (ISSN:13451723)
- 巻号頁・発行日
- no.24, pp.87-121, 2010-09
看護基礎教育の教員経験者は誰もが「もっと同僚がたくさんいたら」と何度も感じた経験があるだろう。しかしながら,この問題に関する議論はどこかで解決をあきらめ,身を尽くして教育や研究に従事している教員が多いのではないだろうか。かくいう私もその一人だった。 筆者は看護基礎教育に携わったのち,現在は研究員として看護職の資格を生かしながらさまざまな医療に関する研究に従事している。看護系大学の教員という立場を離れた今,冷静に看護の教育現場を振り返ったときに気になったのは,看護の教育,研究に携わる看護職〈大学教員〉の数があまりにも少ないことである。
1 0 0 0 IR 戦国大名分国における領主層の編成原理をめぐって
- 著者
- 村井 良介
- 出版者
- 大阪市立大学日本史学会
- 雑誌
- 市大日本史 (ISSN:13484508)
- 巻号頁・発行日
- no.17, pp.14-39, 2014-05
1 0 0 0 OA 有機金属化学の基礎から最近の進歩まで 第1回 有機遷移金属化学の基礎-化学結合の考え方
- 著者
- 小宮 三四郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本ゴム協会
- 雑誌
- 日本ゴム協会誌 (ISSN:0029022X)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, no.7, pp.270-275, 2015 (Released:2015-09-10)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 1
Fundamental minimum basic ideas for understanding structure and chemical bond of organotransition metal compounds as well as mechanisms of transition metal promoted catalyses and organic chemical transformations including bonding concepts, orbital hybridization, electron-deficient bond, back-donation, 18-electron rule, coordinative unsaturation, crystal field theory, fluxionality, nomenclature are described.
1 0 0 0 OA 5.臨床上問題となる薬剤間相互作用とその留意点
1 0 0 0 総説 QT時間の調節
- 著者
- 井上 博
- 出版者
- Japan Heart Foundation
- 雑誌
- 心臓 (ISSN:05864488)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.3, pp.191-201, 1995
QT時間の延長は特発性QT延長症候群や抗不整脈薬によるtorsade de pointes発生との関係で重要視されている.III群薬を使用する機会が増加しつつある今日,QT時間調節の生理的,病理的要因について理解しておくことは大切である.QT時間は心拍数によって変動するが,心拍数を変化させる要因によっても修飾を受ける.このため日常使用されるBazettの式によるQTc時間は,実際の心拍数によるQT時間の変化と一致しないことがしばしば見られる.健常例では自律神経によって心拍数に応じた変化をするとともに,夜間に長いという日内変動を示す.糖尿病,心室頻拍,心筋症,特発性QT延長症候群や抗不整脈薬投与などでは,健常例とは異なったQT時間の変動が観察される.QT時間調節の異常の機序の解明により,このような病態での心室性不整脈の治療が進歩することが期待される.
1 0 0 0 樺太に於ける樺太鑛業株式會社經營の炭礦現況
- 著者
- 戸田 薫一
- 出版者
- 一般社団法人 資源・素材学会
- 雑誌
- 日本鑛業會誌 (ISSN:03694194)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.615, pp.462-475, 1936
This paper is a brief description of the present state of 3 collieries (Taihei, Taiei, and Siritori), which belong to Karafuto Mining Co., Ltd.
1 0 0 0 人工膵臓(第4報)
- 著者
- 池田 章一郎 田代 憲子 伊藤 要 小島 洋彦 伊藤 勝基 近藤 達平
- 出版者
- 一般社団法人 日本人工臓器学会
- 雑誌
- 人工臓器 (ISSN:03000818)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.7-10, 1978
Glucose sensor for implantable artificial pancreas has been developed in our laboratories. Glucose oxidase is immobilized on the surface of the Nylon membrane filter with glutaraldehyde. This type of sensor is much better than the sensor with GOD entarapping method, in the response range of the glucose concentration and in the length of the life.<br>The exact relationship between sensor current and blood sugar level is recognized in animal experiment.
1 0 0 0 ゲルタブレットタイプのハイブリッド型人工すい臓の試み
- 著者
- 岩田 博夫 雨宮 浩 阿久津 哲造
- 出版者
- 一般社団法人 日本人工臓器学会
- 雑誌
- 人工臓器 (ISSN:03000818)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.3, pp.1324-1327, 1989
直径約10mm、厚さ1-2mm程度のハイドロゲルにラ島を封入したゲルタブレットタイプのハイブリッド型人工膵臓を試作した。ゲルタブレット作製には光架橋性ポリビニルアルコール(PVA-SbQ)を用いた。PVA-SbQ水溶液とラ島の混合液に光照射することで、ラ島封入ゲルタブレットを作製した。ゲルタブレット内に封入されたラ島をin vitroで長期間培養したところ、ラ島は本来の球形の形態を保持し続け、さらに培養開始から20日すぎまではインスリン分泌量は急速に低下したが、その後はほぼ一定のインスリン分泌量を示した。さらにゲルタブレットタイプは、たとえゲルの一部が破損したとしても影響を受けるラ島は少なく、移植部位から比較的簡単に取り出せ、さらに厚さを薄くすることで、グルコース濃度変化に素早く応答してインスリンを分泌できる等々の利点があり、今後ハイブリッド型人工膵臓として有望なタイプであると考える。
1 0 0 0 人工膵臓
- 著者
- 吉見 靖男
- 出版者
- 一般社団法人 日本人工臓器学会
- 雑誌
- 人工臓器 (ISSN:03000818)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.3, pp.197-198, 2012-12-15
- 参考文献数
- 11