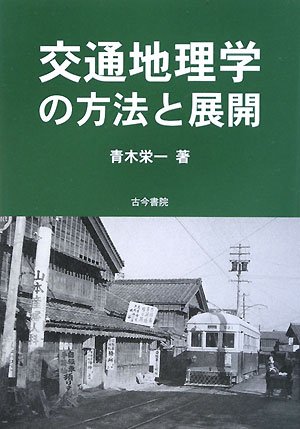5 0 0 0 OA モガニ属をめぐる分類学的・生態学的研究から見えてきた沿岸岩礁域生態系の多様性
- 著者
- 大土 直哉
- 出版者
- 日本甲殻類学会
- 雑誌
- CANCER (ISSN:09181989)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, pp.57-63, 2019-08-01 (Released:2019-09-03)
- 参考文献数
- 26
5 0 0 0 OA リハビリテーションにおける電気刺激療法の展望
- 著者
- 渡部 幸司 長岡 正範
- 出版者
- 順天堂医学会
- 雑誌
- 順天堂医学 (ISSN:00226769)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.1, pp.29-36, 2010-02-28 (Released:2014-11-21)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 2 2
リハビリテーションの分野で電気刺激療法は, 従来, 鎮痛や筋力強化などの目的で使用されているが, 有効性がほとんど証明されていない. 今回, 電気刺激療法の有効性が認められない理由, さらに新しく開発された方法を紹介し, 今後の展望について検討した. 電気刺激療法は, 対象や刺激条件がさまざまであるため, 目標別の刺激条件を概説した. 従来は, 神経・筋に対する治療法がほとんどであったが, 近年, それ以外にも糖輸送体タンパク質増加, 血管新生や血流増加なども報告されている. 神経・筋に対する治療法では, 電気刺激による筋収縮が生理的な筋収縮とは違うという問題点がある. それに対し, 新しい方法であるハイブリッド訓練法と随意運動介助型電気刺激装置は, 随意運動と同時に行うことで, 生理的な筋収縮も得る方法である. 今後, 電気刺激療法を他の運動療法と併用することなどで, さらに発展が期待できる.
5 0 0 0 OA アスベストとナノファイバ:共通点と相違点
- 著者
- 阿部 修治 長沢 順一
- 出版者
- 一般社団法人日本リスク学会
- 雑誌
- 日本リスク研究学会誌 (ISSN:09155465)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.4, pp.231-240, 2013 (Released:2014-05-30)
- 参考文献数
- 37
- 被引用文献数
- 1
An overview is presented on the comparison between asbestos and nanofiber from the viewpoint of risk perception. After reviewing various fundamental concepts related to fibers, it is pointed out that asbestos and nanofiber have significant differences in size and structure, although both fall into the category of respirable fiber. The results of hazard evaluation for asbestos and related fibers show significant variability among materials, thus making a simple extrapolation of previous knowledge to nanofiber impossible. Therefore, the risk analysis of various nanofibers, such as carbon nanotubes, needs to be carried out for individual classes with specific size, shape, and other structural characteristics. Towards this end, an increasing number of toxicological studies are indeed under way, especially for carbon nanotubes.
5 0 0 0 OA 2021年ノーベル化学賞受賞者ベンジャミン・リスト博士の姿に見る豊かな発見に出会うヒント
- 著者
- 北海道大学 CoSTEP 北海道大学 化学反応創成研究拠点 (WPI-ICReDD) 北海道大学 広報課 学術国際広報担当 梶井 宏樹 ステッカー コリン ピント ソハイル・キーガン 南波 直樹 リスト ベンジャミン 辻 信弥
- 出版者
- 北海道大学 高等教育推進機構 オープンエデュケーションセンター 科学技術コミュニケーション教育研究部門(CoSTEP)
- 巻号頁・発行日
- pp.1-2, 2022-03-28
5 0 0 0 OA 源氏雲浮世画合 蓬生 久松・山崎の久作
5 0 0 0 ブルデューにおける界概念:理論と調査の媒介として
- 著者
- 磯 直樹
- 出版者
- 社会学研究会
- 雑誌
- ソシオロジ (ISSN:05841380)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.1, pp.37-53,200, 2008
In this paper I will first introduce Bourdieu's idea of field, a network, or configuration, of objective relations between positions. Then I will show how it integrates theory and empirical research. In the history of Sociology, the relationship between theory and empirical research has been a grand theme, and Bourdieu was committed to integrating the two throughout his career. I will also examine the work of Blumer, an important predecessor to Bourdieu. While both his "sensitizing concept" and his "definitive concept" have limits, Bourdieu's "open concepts" which include habitus, capital and field have more possibilities and significances than Blumer's. The field is a social sphere which has a limit around itself and each has its own rules within. For Bourdieu, the field is considered together with habitus and capital, and also as a part of his theory of practice. The concept of field enables us to analyze social phenomena for which we have lacked a theoretical framework. We can also use the concept of field to relate and integrate differentempirical research. One example can be found in the study of social difference. Bourdieu's sociology makes sense in combination with the works of other sociologists because it owes so much to them. We should ask the question "Bourdieu and what else?" rather than think in terms of a dichotomy such as "Bourdieu or not." This will lead to a productive discussion.
5 0 0 0 OA 裁量労働制をめぐる課題
- 著者
- 中里孝
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 調査と情報 (ISSN:13492098)
- 巻号頁・発行日
- no.1189, 2022-03-31
5 0 0 0 OA 現代朝鮮語の「副動詞+主題助詞」 ―日本語のテハとの対照―
- 著者
- 黒島 規史
- 出版者
- 朝鮮語研究会
- 雑誌
- 朝鮮語研究 (ISSN:13472690)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.91-120, 2022-02-22 (Released:2022-03-31)
현대 한국어에서는 부동사 뒤에 주제(topic) 조사 ‘-는/은’이 결합할 수 있으며 그 통합형은 여러 의미를 나타낸다. 그 중에서도 시간 관계를 표현하는 부동사는 주제 조사와 결합함으로써 다의성을 띤다. 본 연구는 한국어의 ‘-고, -(아/어)서, -고서, -다가 + -는’과, 이 통합형들과 같은 구성을 가진 일본어의 -te=wa를 대상으로 ‘부동사 + 주제 조사’의 다의성을 의미지도(semantic map)를 이용해 밝히는 것을 목적으로 한다. 본 연구에서는 ‘부동사 + 주제 조사’가 나타내는 의미를 반복, 습관, 역접, 연속, 조건(불가피, 현상, 판단, 명령・경고)로 나눈 다음에 의미지도를 그림으로써 각 통합형의 의미 차이를 명확히 파악할 수 있게 되었다. 더 나아가 이 의미지도에 계기, 원인・이유를 더해 부동사가 나타내는 의미의 연속성을 제시하며 계기와 같은 시간적인 의미와 이유, 조건과 같은 논리적인 의미의 중간에 위치하는 의미로서 연속・발견의 중요성을 강조했다.
- 著者
- 石山 恒貴
- 出版者
- 法政大学イノベーション・マネジメント研究センター
- 雑誌
- イノベーション・マネジメント (ISSN:13492233)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.149-152, 2022-03-31 (Released:2022-03-31)
- 参考文献数
- 3
5 0 0 0 陰陽道祭祀の成立と展開
- 著者
- 岡田 荘司
- 出版者
- 学術雑誌目次速報データベース由来
- 雑誌
- 国学院大学日本文化研究所紀要 (ISSN:0073876X)
- 巻号頁・発行日
- no.54, pp.p87-127, 1984-09
5 0 0 0 交通地理学の方法と展開
5 0 0 0 OA ICUにおける看護師の終末期ケアへの認識に関連する要因
- 著者
- 長岡 佳世子 市村 久美子
- 出版者
- 日本緩和医療学会
- 雑誌
- Palliative Care Research (ISSN:18805302)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.4, pp.289-299, 2021 (Released:2021-10-26)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 2
【目的】ICU看護師の終末期ケアの認識と終末期ケアの認識の関連要因を明らかにすることである.【方法】救命救急センターのICU経験3年目以上の看護師650名に,基本属性,終末期ケアへの認識について無記名自記式質問紙を郵送した.終末期ケアへの認識の構成概念を従属変数としたロジスティック回帰分析を行った.【結果】有効回答277名を得た.終末期ケアへの認識は三つの構成概念が抽出された.終末期ケアへの認識との関連要因は,「家族ケアへの困難感」は「ICU経験10年以上」「PNS」,「終末期ケアへの否定感」は「30-39歳」「40歳以上」「終末期に関するマニュアル・ガイドライン」,「終末期ケアへの肯定感」は「終末期ケアへの関心」に有意な関連があった.【結論】終末期ケアへの認識を高めるためには,看護師個人の終末期ケアの経験,関心,終末期に関するマニュアルやガイドラインの活用といった要因に働きかける必要がある.
5 0 0 0 OA オンライン学習環境における大学生の学びと支援ニーズ 千葉大学の学生を対象とした事例調査
- 著者
- 谷 奈穂 伊勢 幸恵 佐々木 智穂 國本 千裕
- 出版者
- 国公私立大学図書館協力委員会
- 雑誌
- 大学図書館研究 (ISSN:03860507)
- 巻号頁・発行日
- vol.120, pp.2131, 2022-03-31 (Released:2022-03-18)
COVID-19の感染拡大にともなう入構制限により,大学での学びはオンラインが中心となり,学生の学習状況は変化した。本稿では,オンライン学習環境における適切な学習支援を探る目的で,学生の学習実態・直面する困難・支援ニーズについて,千葉大学の学生を対象とした日記法とインタビューによる質的調査を実施した。調査結果は,(1)メディア授業の特性,(2)学習時のコミュニケーション,(3)学習環境および学習リソースの3観点で分析し,今後必要な学習支援について考察した。そのうえで,千葉大学における学習支援の検証を実施し,今後の展望について述べた。
カドミウムによる環境汚染がもたらす健康被害、すなわち慢性カドミウム中毒は、その重篤例が、イタイイタイ病であり、非重篤例がカドミウム腎症(近位尿細管障害)という腎障害である。しかるに、環境省と環境省が組織化した医学研究班は、この腎障害を公害病とは認めていない。カドミウム中毒問題は水俣病問題と並ぶわが国を代表する公害問題であるが、両公害問題がたどった歴史的過程には、(1)複数の汚染地域のうち一部の地域しか公害病指定されず、しかも、(2)非重篤例など多くの被害者が被害者と認められてこなかった、という共通点を見て取ることができる。このカドミウム中毒問題において、われわれは、既に、富山県神通川流域、長崎県対馬、群馬県安中の事例と、それにかかわる全国的状況について、報告書としてまとめている。本報告書は、そこで得られた知見を踏まえ、兵庫県生野(市川流域)と石川県梯川流域の事例、そして、カドミウム腎症の公害病未指定問題の探求をとおして、上記の研究課題に迫ろうという意図のもとに執筆されている。第1章では、わが国のカドミウム問題の全体像を紹介し、生野、梯川の事例の位置づけを提示した。公害問題における被害・加害構造を解明しようとするとき、国や加害企業の対応とともに重要なのが、被害者に最も身近に接する地元行政の対策に関する考察である。それについて、第2章では、生野について、第3章では、梯川について考察した。その結果、(1)「被害者の発見」「補償の獲得」「健康管理」のあり方は、国の姿勢や判断等によって、全て規定されるわけではなく、各県レベルにおける、行政、地元大学研究者、住民運動の三者、特には県行政の対応の積極度によって、大きな違いが存在したこと、そして、(2)この違いは、各地の被害者が置かれた状況(派生的被害のレベル、健康管理の有無等)を大きく左右したこと、等を明らかにした。梯川の場合、さらに注目されるのは、世界をリードするほどの医学研究の成果である。この地での、腎障害に関する研究成果は、WHOのCriteriaにも、コーデックスの初期の米中カドミウム濃度基準0.2ppm以下という提案にも反映されている。つまり、世界の人々の健康管理に生かされているのである。しかし、わが国政府は、梯川をはじめ各地のカドミウム腎症の多発をカドミウムによるものと認めていない。世界で評価されているわが国の研究を、なぜわが国政府は評価しないのか。第4章では、この問いを、環境省とその医学研究班に対する社会学的検討を通して探求した。