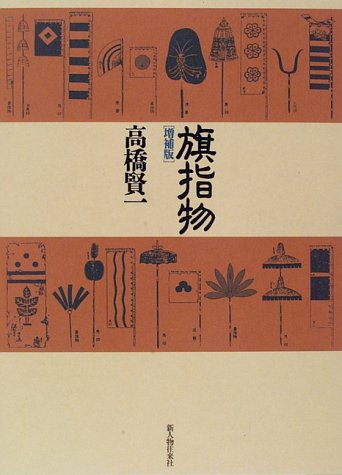- 著者
- 計良 由香
- 出版者
- 一般社団法人 日本特殊教育学会
- 雑誌
- 特殊教育学研究 (ISSN:03873374)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.1, pp.11-18, 2008
- 被引用文献数
- 3
本稿は、軽度発達障害児の通級による指導と特別支援教育推進の方向性について検討することを目的とした。従来から軽度発達障害児とかかわってきた言語難聴担当者を対象としたアンケート調査を実施し、新潟県と福島県の69名から回答を得た。担当者の約9割が指導対象ではない軽度発達障害児を指導し、そのうち約5割が指導上の課題として目標設定の難しさと通級による指導の評価の難しさを挙げた。また、回答者の4分の1が校内の特別支援教育コーディネーターを兼務していた。言語難聴担当者が軽度発達障害児の指導および校内の特別支援教育推進にあたることは必要であり、そのためには軽度発達障害児の支援に携わる関係者の連携促進と通級指導教室の増設が急務であることが示唆された。
1 0 0 0 OA ベンヤミンのギリシア悲劇論 : 「英雄」の「反抗」と「沈黙」
- 著者
- 小林 哲也
- 出版者
- 京都大学大学院人間・環境学研究科現代文明論講座文明構造論分野『文明構造論』刊行会
- 雑誌
- 文明構造論 : 京都大学大学院人間・環境学研究科現代文明論講座文明構造論分野論集 (ISSN:18804152)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.63-93, 2011-09-12
1 0 0 0 OA ソクラティク・ダイアローグ
- 著者
- 森 芳周
- 出版者
- 大阪大学大学院文学研究科臨床哲学研究室
- 雑誌
- 臨床哲学のメチエ
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.4-19, 2000
1 0 0 0 OA 「ともに考える」ための道具:"Socratic Dialogue"の経験から
- 著者
- 堀江 剛
- 出版者
- 大阪大学大学院文学研究科臨床哲学研究室
- 雑誌
- 臨床哲学のメチエ
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.14-18, 1999
1 0 0 0 OA 《資料》ダイアローグを営むためのいくつかの決めごと
- 出版者
- 大阪大学大学院文学研究科臨床哲学研究室
- 雑誌
- 臨床哲学のメチエ
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.54-55, 2000
1 0 0 0 IR 『万葉集』に於ける「変字法」の一考察 : 対句表現を中心として
- 著者
- 進藤 康子 Yasuko Shintou 九州情報大学経営情報学部非常勤
- 出版者
- 九州情報大学
- 雑誌
- 九州情報大学研究論集 (ISSN:13492780)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.134-126, 2013-03
万葉集の変(かえ)字法(じほう)から、対句を中心として、筆録者の言語意識に基づく、用字意識、表記意識を考察する。万葉集の表記法は、実に変化に富み、単に音声を形に写して表わすだけでなく、変字法による文字の可視的な領域での意味の拡充が、多種多様に意図されていることを論じ、万葉集のこの極めて特異な用字法の一端を明らかにした。
- 著者
- 菅原 布寿史
- 出版者
- 河原学園 人間環境大学
- 雑誌
- 人間と環境 (ISSN:21858365)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.117-142, 2011
徳川・五島本の構図は、絵具が剥落・変色した現状では形式的で静的なものと見られてきた。しかし、現在は最新の復元模本を参照することにより、当時の絵師がより優れた物語の視覚化を試行錯誤して生み出したダイナミックな構図を読み取ることができる。本稿では、徳川・五島本の内建造物が描かれた十八作品を分析。結果として、二分割した画面に主要なモチーフを配置することで物語内容を視覚的に表現した〈対置的スタティクス〉、様々な動勢が影響し合って動的な運動感で画面内を満たし、ドラマティックなインパクトが感性に訴えかける〈有機的ダイナミクス〉、そして両者の中間的な構図に分類した。そして、〈有機的ダイナミクス〉の構図である〈柏木グループ〉八作品の明度による視覚的刺激の強弱を基準にしたダイアグラムを作成し、ダイナミクスのメカニズムを分析する。
1 0 0 0 IR 銭稻孫訳『源氏物語』の特徴について(上)
- 著者
- 田中 幹子 鄭 寅瓏
- 出版者
- 札幌大学
- 雑誌
- 比較文化論叢 = Journal of comparative cultures : 札幌大学文化学部紀要 (ISSN:13466844)
- 巻号頁・発行日
- no.28, pp.110-80, 2013-03
1 0 0 0 IR 東日本巨大地震が留学生に与えた影響 : 地震1年後のインタビューを通して
- 著者
- 王 敏東 仙波 光明
- 出版者
- 徳島大学
- 雑誌
- 言語文化研究 (ISSN:13405632)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.163-184, 2012-12
This study interview overseas students from Taiwan on the impact induced by Japan earthquake occurred on March 11, 2011. The interviews on eight overseas students were conducted during February to May, 2012, with seven being interviewed once before and one student was for the first time being interviewed. Most overseas students loved Japan and disregarded the impact brought by the earthquake. These interviewees kept contact with Japan by continuous overseas study or by other routes. The communications with these students were not as fluently as last time, indicating the importance of Japan or overseas study in Japan declined.
1 0 0 0 IR 平安後期の「ことなしぶ」とその派生語の検討 : 付・異文「ことならふ」とその派生語
- 著者
- 堤 和博
- 出版者
- 徳島大学
- 雑誌
- 言語文化研究 (ISSN:13405632)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.1-32, 2012-12
1 0 0 0 IR 慶北方言の知覚方言学に関する研究
One of the principal concerns of traditional dialectology or dialect geography has been the discovery of isoglosses, the boundaries between two regions which differ with respect to some linguistic feature. J. K. Chambers & P. Trudgill had classified 7 items, that is lexical isogloss, pronunciation isogloss, phonetic isogloss, phonemic isogloss, morphological isogloss, syntactic isogloss and semantic isogloss(?)(1980:112-115), and had determined their function and their usefulness in dialectology. The categories described here are given in order of increasingly more abstract levels of linguistic structure, following current linguistic models.But I make new notion of 'Impressive isogloss'. It means that native speaker has the thought of his own dialect category. I integrated the native speakers' cognitions and made the dialect map of nonlinguistic feature. After analyzing the nonlinguistic map, I have confirmed that the 'Impressive isogloss' had relation to the grammatical difference (the ending of words) and the lexical divergence which differs in etymology by means of linguistic feature. Ultimately, this research will try to explain the Perceptual dialectology. The possibility of perceptual dialectology was confirmed in the present study.
- 著者
- 本多 幸子
- 出版者
- 同志社大学政策学会
- 雑誌
- 同志社政策科学研究 = Doshisha policy and managemant review (ISSN:18808336)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.2, pp.79-90, 2012-03
研究ノート(Note)学説史の中で公共空間といえば、やはりユルゲン・ハーバーマスの公共圏(Öffentlichkeit)を避けて通るわけにはいかない。本論は、ハーバーマスの出世作とも言える『公共性の構造転換』が、英訳ではpublic sphere となっていることに着目し、Öffentlichkeit 概念が包摂する空間性を問うことから出発し、ハーバーマス公共圏論の基本構図に迫った。本論は、まず、ハーバーマスのÖffentlichkeit 概念の特徴について再確認する作業を行い、次いで、古代ギリシアのポリス以降の市民的公共圏の4つの位相を、ハーバーマスのÖffentlichkeit 概念に即しつつ、検討する。
1 0 0 0 OA 現代ロシア語形容詞研究・序説 (I)
- 著者
- 臼山 利信
- 出版者
- 東京大学大学院人文社会系研究科スラヴ語スラヴ文学研究室
- 雑誌
- Slavistika : 東京大学大学院人文社会系研究科スラヴ語スラヴ文学研究室年報
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.39-60, 2004-02-20
1 0 0 0 校訂近世奇談全集
- 著者
- 田山花袋 柳田國男校訂
- 出版者
- 博文館
- 巻号頁・発行日
- 1903
1 0 0 0 來るべき戰爭に於ける潜水艦
- 著者
- K.M.
- 出版者
- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会
- 雑誌
- 造船協会雑纂
- 巻号頁・発行日
- vol.187, pp.663-665, 1937
1 0 0 0 255 ゴミムシ類の有機酸分泌に見られる一定性
- 著者
- 兼久 勝夫 山崎 良樹 河津 一儀
- 出版者
- 日本応用動物昆虫学会
- 雑誌
- 日本応用動物昆虫学会大会講演要旨
- 巻号頁・発行日
- no.23, 1979-10-10
1 0 0 0 出家佛教在家佛教と道元禪師の立場
- 著者
- 保坂 玉泉
- 出版者
- 駒澤大学
- 雑誌
- 駒澤大學研究紀要 (ISSN:0452361X)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.1-14, 1957-03