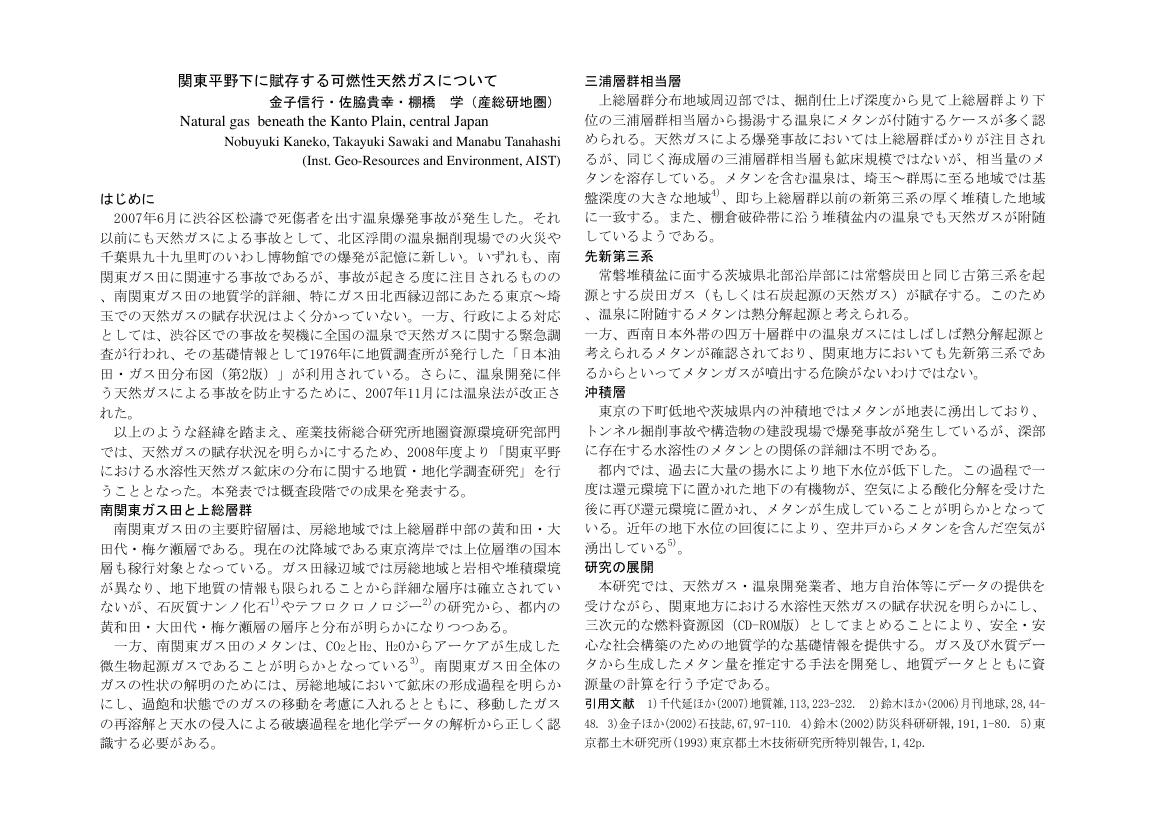3 0 0 0 OA 世界の神話と主な宗教に見られる土壌と大地
3 0 0 0 OA ユーザー・コミュニティ創発のシミュラークル
- 著者
- 片野 浩一
- 出版者
- 明星大学経営学部経営学科研究紀要編集委員会
- 雑誌
- 明星大学経営学研究紀要 = Meisei University, the bulletin of management science (ISSN:18808239)
- 巻号頁・発行日
- no.14, pp.79-90, 2019-03-15
3 0 0 0 OA 法幣制度と日支事変
- 出版者
- 大蔵省大臣官房財政経済調査課
- 巻号頁・発行日
- 1939
3 0 0 0 OA 神戸・異人館のペンキ色彩からみた町並みの変容
- 著者
- 森下 満 柳田 良造 野口 孝博
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.598, pp.109-115, 2005-12-30 (Released:2017-02-11)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 2 2
This study aims to clarify color transition of Kobe's townscape from the middle period of Meiji until now. Painted colors of western historic houses of Kobe have been investigated. On the other hand, a comparative analysis of Kobe and Hakodate's townscape have been conducted to the study. Obvious characteristics throughout the study are summarized as follows: 1) It has been known that Kobe's houses have been characterised by different colors, for example, external walls and windows are painted respectively by off-white, light beige (for walls) and, green and brown (for windows and posts). This study has obtained that different colors were used. Before the 1960s various and dark colors, especially dark green and gray, were popularly used. Since 1980, various influences of sightseeing and designated historic district, have affected changing the color of these houses to off-white color. 2) The changing of townscape color of both Kobe and Hakodate are different. Incase of Kobe, the townscape color did not chang for about sixty years and was stable for a long period, while Hakodate's case has shown different performance, hence their houses have been characterised by changeable color for a short period every twenty or thirty years.
3 0 0 0 OA 源平英雄競 根井大弥太行親
3 0 0 0 OA 関東平野下に賦存する可燃性天然ガスについて
- 著者
- 金子 信行 佐脇 貴幸 棚橋 学
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 日本地質学会学術大会講演要旨 第115年学術大会(2008秋田) (ISSN:13483935)
- 巻号頁・発行日
- pp.426, 2008 (Released:2009-02-20)
- 参考文献数
- 6
3 0 0 0 OA 明治天皇御製読本
- 出版者
- 京都府立桃山中学校金城会
- 巻号頁・発行日
- 1930
3 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1934年12月04日, 1934-12-04
- 著者
- 井上 芳保
- 出版者
- 日本社会臨床学会
- 雑誌
- 社会臨床雑誌 (ISSN:21850739)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.3, pp.16-18, 2020 (Released:2021-11-10)
3 0 0 0 OA 組織人としてのケースワーカー ― ストリートレベルの官僚制の再検討―
- 著者
- 関 智弘
- 出版者
- 日本行政学会
- 雑誌
- 年報行政研究 (ISSN:05481570)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, pp.81-98, 2014 (Released:2020-03-24)
- 被引用文献数
- 1
3 0 0 0 OA 法主体としての「ホームレス」?
- 著者
- 遠藤 比呂通
- 出版者
- The Japanese Association of Sociology of Law
- 雑誌
- 法社会学 (ISSN:04376161)
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, no.64, pp.140-152,279, 2006-03-30 (Released:2012-06-20)
- 参考文献数
- 33
It is 10 years since I first visited Kamagasaki, which is the biggest slum in Japan. "Are there any human rights exist in Japan?" "Kamayan", a Kamagasaki daily based worker, responded to my self-introduction that I had been teaching human rights law in Japan."Kamayan" was quite right in his allegation. Kamagasaki workers and homeless people were "displaced persons" in the sense used by Hanna Arendt in her influential book "The Origin of the Totalitarianism": their human rights were not violated, but they lost the right to have human rights itself.Since then, I have been street lawyer in Kamagasaki. Especially, I have been in charge of a forced eviction case against homeless people by Osaka City. We have been alleging in this case "a right to adequate housing" stipulated in the Social and Economic Covenant of Human Rights, because only these kinds of rights would confer "Kamayan" security of legal tenure beyond the scheme of Nation State, which was thought by Arendt as a hazard to human rights.From my experience as a street lawyer, the right to adequate housing should be properly defined only when homeless people themselves join the negotiation process. The Committee of the Covenant has been using 'genuine consultation' to describe this process. "Kamayan" should be treated as a legal agency in the field of law.
3 0 0 0 2つの人肉食(カニバリズム)殺人裁判-上-
- 著者
- 中村 治朗
- 出版者
- 判例時報社
- 雑誌
- 判例時報 (ISSN:04385888)
- 巻号頁・発行日
- no.1210, pp.p3-15, 1986-12-11
3 0 0 0 OA 実行機能とマインドフルネス
3 0 0 0 OA 集合住宅における経年的住環境運営に関する研究
- 著者
- 大月敏雄 [著]
- 巻号頁・発行日
- 1997
3 0 0 0 OA RNA代謝異常を介した神経変性疾患の発症病態
- 著者
- 余越 萌 河原 行郎
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.1, pp.37-41, 2015 (Released:2018-08-26)
- 参考文献数
- 25
アルツハイマー病やパーキンソン病に代表される神経変性疾患は,いずれも病態機序が解明されておらず,根治療法も確立していない.今後,高齢化社会の到来に伴い,患者数が着実に増加することは確実であり,早急な治療法の確立が強く望まれている.一方,近年の次世代シーケンサーの実用化に伴い,比較的少数の家系サンプルでも,疾患の遺伝子座が同定できるようになった.この結果,神経変性疾患においても,新たな原因遺伝子変異の報告が相次いでいる.特に,筋萎縮性側索硬化症(amyotrophic lateral sclerosis:ALS)や前頭側頭葉変性症(frontotemporal lobar degeneration:FTLD)では,次々とRNA結合タンパク質遺伝子の変異が同定されるようになり,発症病態にRNA代謝異常が深く関与していることが明らかとなりつつある.ALSは,上位および下位の運動神経細胞が選択的に変性脱落し,全身の筋力が低下する神経難病である.主に中年期以降に発症し,9割以上が孤発性である特徴を持つ.一般的には,感覚系や認知機能は障害されないが,以前より一部に認知障害を呈するケースがあることが知られていた.一方FTLDは,アルツハイマー病,レビー小体型認知症に続いて,3番目に多い神経変性型認知症性疾患である.ALSとFTLDでは,障害される神経細胞が異なることからも別の疾患と考えられてきたが,遺伝子座が同定されるにつれて,その一部は同じ疾患スペクトラム上にあることが明らかとなった.すなわち,同じRNA結合タンパク質遺伝子変異でも,ALSから発症するケースとFTLDから発症するケースがあり,進行とともに互いの症状を合併する.これらの知見は,疾患の発症病態や変性する神経細胞の特異性を考える上で,大きなパラダイムシフトを起こした.さらに2011年になって,一部のALSおよびFTLDにC9orf72(Chromosome 9 open reading frame 72)遺伝子のイントロンにあるGGGGCCリピート配列の異常伸長がその原因として同定された.この発見は,RNA代謝の調節因子であるタンパク質の機能異常も,調節される側のRNAの異常でもALSやFTLDになることを示唆しており,RNA結合タンパク質とRNA間のバランスの破綻が発症の根底にあると考えられるようになった.これまでにも,リピート配列の異常伸長に起因する神経変性疾患は,ハンチントン病や一部の脊髄小脳変性症など数多く知られており,凝集タンパク質がもたらす細胞毒性が神経変性を誘導すると考えられてきた.しかし,ALSやFTLDにおける一連の発見は,神経変性疾患の発症病態におけるRNA代謝異常やRNA毒性の重要性を認識する契機となり,急速に研究が進展しつつある.本稿では,RNA代謝に焦点を当てながら,最新の神経変性疾患の発症病態に関する知見を概説したい.
3 0 0 0 OA 台湾原住民における首狩
- 著者
- 山田 仁史
- 出版者
- 一般社団法人 アジア民族文化学会
- 雑誌
- アジア民族文化研究 (ISSN:13480758)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.1-101, 2008-03-31 (Released:2020-03-19)
- 参考文献数
- 177
3 0 0 0 OA 熱傷瘢痕より発生した基底細胞癌の1例
- 著者
- 大守 誠 寺師 浩人 田原 真也 福本 礼
- 出版者
- 日本皮膚悪性腫瘍学会
- 雑誌
- Skin Cancer (ISSN:09153535)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.3, pp.298-301, 2007-03-15 (Released:2010-08-05)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 1 1
80歳, 女性。湯たんぽによる低温熱傷を左下腿に負った。保存的治療にて創治癒をみたものの約1年半後に同部が潰瘍化した。保存的治療に反応せず, 上皮化と潰瘍化を繰り返したために7ヵ月後に潰瘍切除, 植皮術を施行した。病理結果は基底細胞癌であり, 追加切除を行い, 再度植皮術を行って治癒した。術後2年の現在まで再発を認めない。熱傷瘢痕より発生する基底細胞癌で本症例のように比較的経過の短いものは稀であり, 文献的考察を加えて報告した。
3 0 0 0 OA 免疫組織化学の原理と基本
- 著者
- 小澤 一史
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.154, no.4, pp.156-164, 2019 (Released:2019-10-10)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 2 3
免疫組織化学とは,抗体抗原反応という生体に存在する多様で特異的な分子認識機構を応用し,細胞,組織,臓器,個体の中に存在する特定の物質を探索し,可視化して観察する研究技法で,多くの領域で汎用されている.光学顕微鏡,電子顕微鏡,蛍光顕微鏡,共焦点レーザ走査顕微鏡などの顕微鏡を用いて観察する形態学と,免疫沈降法,Western blotting法などを用いて細胞や組織内の物質の存在を検出する生化学が合体し,形,構造とその中に存在する物質の同時観察が出来る研究手法である.このステップを簡単にまとめると,「抗原」と特異的に結合する「抗体」を反応させ,その抗原抗体反応した部位を「可視化」して顕微鏡で観察することが免疫組織化学の基本的なステップである.このステップにおいて,重要なポイントがいくつかあるが,その1番目は「よい一次抗体」を用いて明瞭で容易に,また再現性高く探索対象とする物質(抗原)を検出することである.2番目として,組織や細胞内の物質(抗原)の不動化,すなわち固定の必要性である.固定作業は一方で抗原の分子構造変化をもたらし,結果として抗原抗体反応を抑制することがある.従って固定と免疫染色性という相反性の問題を超える必要がある.3つめは「可視化」である.単に見えるだけではなく,特異的で明確に判断できるように見えなくてはいけない.これらのポイントを意識しながら正しい免疫組織化学反応を判別できるようにし,誤った検出結果,検出判断をしないことが大変に大切なことである.そのためのコントロール実験は常に意識すべき重要なポイントになる.