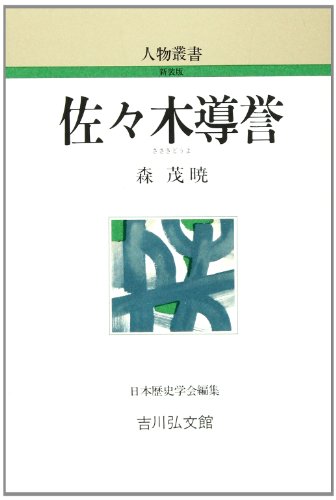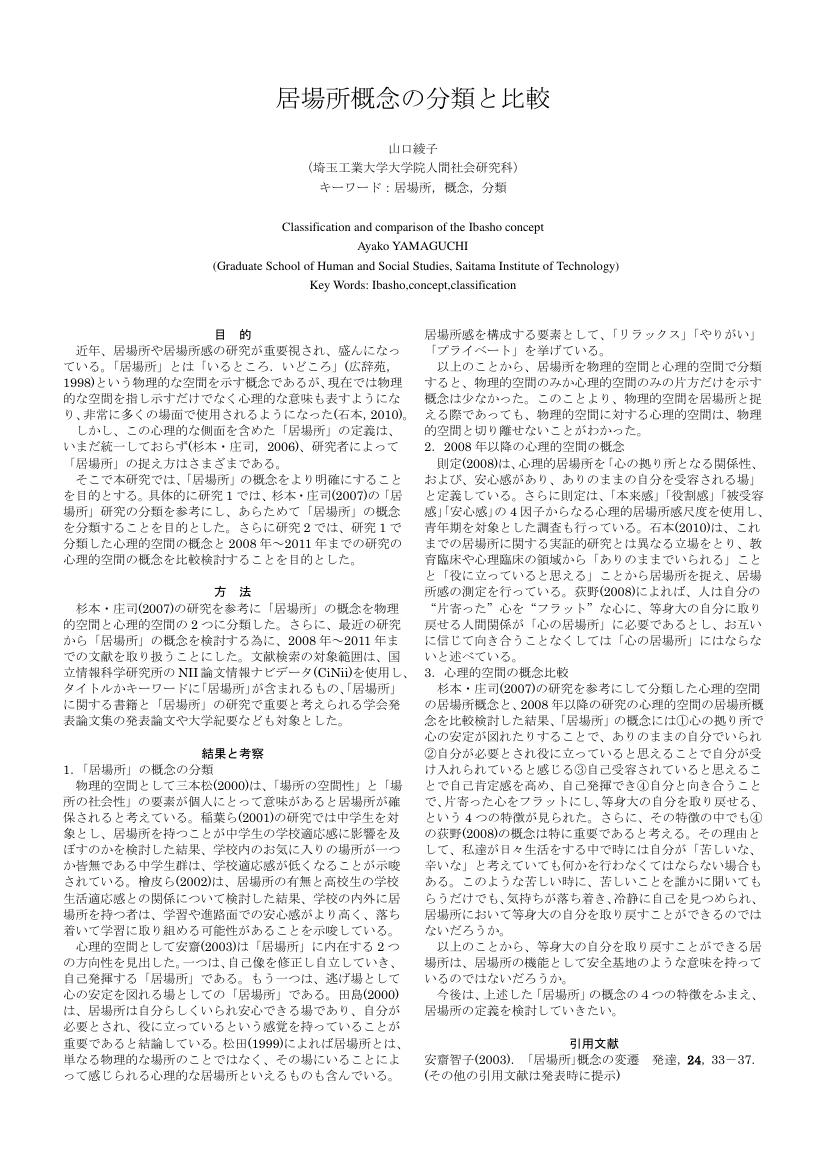2 0 0 0 IR ダンスの身体表現における感情認知とインタラクションに関する研究
- 著者
- 澤村 直輝 中野 航一郎 内田 祐司 高力 俊策
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床救急医学会
- 雑誌
- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.3, pp.615-619, 2022-06-30 (Released:2022-06-30)
- 参考文献数
- 10
市販薬であるトラベルミン®(ジフェンヒドラミンサリチル酸塩とジプロフィリンの合剤)による急性中毒は近年国内でも症例報告が散見される。うつ病の既往がある34歳男性が痙攣と意識障害で発見され,隣にトラベルミン® 120錠分の空箱(ジフェンヒドラミン換算3,100mg)を認め救急搬送された。来院時はGCS 3点(E1V1M1),瞳孔散大,眼球クローヌス,口腔内乾燥,心電図で右脚ブロック波形と頻脈を認めた。トライエージDOA®でフェンシクリジンが陽性であった。人工呼吸器管理,活性炭投与,炭酸水素ナトリウム投与,20%脂肪乳剤の投与を行い,血液透析を施行した。数時間後には心電図は正常化し第2 病日には意識レベルも改善した。横紋筋融解を合併したが軽快し,第9病日に独歩で精神科へ転院となった。トラベルミン®中毒の報告はまだ多くないが入手は簡単で,インターネットの自殺サイトで取り上げられることもあるため今後も増加が予想される。救急医療に携わる者にとって多彩な臨床所見や治療法の知識を深めることが重要である。
2 0 0 0 OA 希少糖D-プシコースのクッキー様焼菓子への利用について
- 著者
- 小川 眞紀子 山本 いず美 北畠 直文 早川 茂
- 出版者
- 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 平成27年度大会(一社)日本調理科学会
- 巻号頁・発行日
- pp.144, 2015 (Released:2015-08-24)
【目的】希少糖D-プシコース(以下Psi)は、エネルギー値がほぼゼロのノンカロリー単糖で、保水性が高く、メイラード反応が進みやすいことから、食品素材として特にベーカリー食品への利用が期待されている。本研究では、ハードタイプのクッキーであるショートブレッド(以下SB)とソフトタイプのクッキーであるソフトクッキー(以下SC)にPsiが適しているか否かを、ショ糖とPsiとの配合割合を換え、物性測定と官能評価により検討することを目的とした。【方法】ショ糖のみをコントロール(C)とし、ショ糖に置き換えてPsiを10%(P10)、20%(P20)、30%(P30)に配合した4種類のSB及びSCを作製し、物性測定と官能評価を行った。物性測定は、高さ測定および破断強度を測定した。官能評価は、軟らかさ、しっとり感など10の評価項目についてSD法で官能評価を行った。【結果】SB、SCともに焼き色は、C、P10、P20、P30の順に濃くなった。高さは、SBはC、P10、P20、P30の順に、SCではC、P10、P30、P20、の順に高くなった。破断強度測定から、SBはPsiの割合が多いほど破断変形は有意に高くなり、破断応力は有意に低く、破断歪率は有意に高くなった。SBは、Psiの割合が多いほど脆くて軟らかい特徴がSCよりも顕著であった。官能評価の結果から、テクスチャーはC、P10、P20、P30の順に軟らかいと感じた人が多かった。総合評価では、いずれもCよりもP10とP20で高い評価となった。今回の結果から、ショ糖の1~2割程度をPsiに置き換えることで、物性的にも嗜好的にも好ましいクッキー様焼菓子を作ることが可能であることが示唆された。
2 0 0 0 OA チヤプリンをめぐりて
- 著者
- 東京名映画観賞会 著
- 出版者
- 時事新報社
- 巻号頁・発行日
- 1932
- 著者
- 井本 佐保里 松本 海空
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.87, no.799, pp.1623-1633, 2022-09-01 (Released:2022-09-01)
- 参考文献数
- 14
This paper is to find the autonomous processes of resettlements after Kumamoto Earthquake 2016. Research was conducted in #1 Neighborhood-Association in Akitsu-school-district in Higashi-ward, Kumamoto City. There was no public reconstruction project and no collective resettlement policy in the area. Each victim was utilizing the resources of their own, relatives’, community’s and public. No victims went outside of Higashi-ward until they resettle in the original site. There were cases of dwelling in the original houses, dwelling in the apartments which they, their relatives’ or neighbors own in the area, and setting unit-house in his site.
2 0 0 0 OA 戦後昭和における冒険旅行を考える―遠心性の誘惑にとらわれた若者たち―
- 著者
- 長野 太郎 Taro NAGANO
- 雑誌
- 清泉女子大学人文科学研究所紀要 = BULLETIN OF SEISEN UNIVERSITY RESEARCH INSTITUTE FOR CULTURAL SCIENCE (ISSN:09109234)
- 巻号頁・発行日
- no.39, pp.112-91, 2018-03-31
本稿は、占領終了から昭和末年までの戦後昭和期(1952―1989)に、日本語で公刊された旅行記、旅を主題とするエッセイ、評論などを対象として、冒険旅行をめぐる言説の傾向を検討する。右肩あがりで経済成長をとげる一方、冷戦構造による世界の明確な分断が続いていたこの時期、海外旅行は今ほど身近なものではなく、海外に旅することそのものが冒険的なこころみであった。この時期の冒険旅行をめぐる言説は、さまざまな断層のなかに散在している。まずは、戦前からの国家主義を内包した探検のエートスが、京大野外研究派を通じて探検部に引き継がれ、1960年代中頃までつづいた。そこでは学術的新発見や、未踏地制覇のような記録が重視された。1964年に海外旅行が自由化されると、一部のエリート学生以外も探検的領域に足を踏み入れることが可能となり、前者の探検とはことなるスポーツ的行為、または冒険旅行が試みられるようになった。やがて、1960年代末の学園闘争をへて、探検のエートスは決定的に存立基盤を崩される。いよいよ多くの若者が海外に出かけ、長期の私的冒険旅行、いわゆる放浪の旅をおこなうと同時に、探検部もスポーツ的冒険路線に方向転換を余儀なくされた。戦後昭和において、海外旅行の大衆化、個人化が進行していくなかで、冒険旅行をめぐる言説は、私的物語となるか、スペクタクル化する方向をたどるかのいずれかであった。
2 0 0 0 OA 最近の偏向教育の問題状況
- 著者
- 永田 照夫
- 出版者
- The Japanese Association of Sociology of Law
- 雑誌
- 法社会学 (ISSN:04376161)
- 巻号頁・発行日
- vol.1972, no.24, pp.84-107,241, 1972-03-30 (Released:2009-04-03)
- 参考文献数
- 16
This is a study from the standpoint of sociology of law, of controversial points in about twenty among the many issues of partial or deflected education pointed out in elementary and secondary teaching and guidance everywhere in the past ten years. Some twenty cases picked up here are those of which the author has had opportunities to read the reco ds and materials at first hand.The standard of the existing laws most directly leading to the issues of partial or politically colored education in the strictest sense is the regulation of Article 8, Item 2 of the Fundamental Law of Education that states:“The schools prescribed by law shall refrain from political education or other political activities for or against any specific political party.”When parents and local influential people point out as partial or politically colored education, however, they often argue over trifles or dealings of political problems in controversy in present-day Japan. Therefore, the standards and definition of partial education are vague and unclear. Moreover, in those cases, they often try to solve the problems politically and administratively by direct suit to the local Boards of Education or local legislatures, rather than by educative method of discussions in the school.Responses of Boards of Education to these cases vary, but in general, they are compromising and at times they make use of these tendencies of parents and the influentials.When the cases lead to legal punishment, they are dealt with variously as violation of Article 32 of the Local Public Service Law (the duty to obey laws and superior officers' orders) or of the Personnel Authority Regulations (on political actions) or of the Courses of Study or as deviation from textbooks or as not using textbooks, rather than as violation of Article 8, Item 2 of the Fundamental Law of Education.Most of these cases have been given great publicity by mass communication and have come to present educational, legal and social problems peculiar to present-day Japan.These cases are, for the part of elementary and secondary school teachers, clear examples which show that freedom of education, and freedom of teaching in particular, are not guaranteed. This raises an important problem for teachers on the guarantee of professional freedom, but this is only one of the many difficult and complicated problems concerning partial or deflected education yet to be solved between parents and teachers, and between local communities and schools and teachers and teachers' unions.
2 0 0 0 文学史研究
- 著者
- 大阪市立大学国語国文学研究室文学史研究会 編
- 出版者
- 大阪市立大学国語国文学研究室文学史研究会
- 巻号頁・発行日
- no.35, 1994-12
2 0 0 0 OA シングルケース実験デザインのデータ解析
- 著者
- 古川 洋和
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.2, pp.182-188, 2020 (Released:2021-05-09)
2 0 0 0 OA 感性を考慮した自然言語文からの風景画像生成システム
- 著者
- 菅生 健介 萩原 将文
- 出版者
- Japan Society of Kansei Engineering
- 雑誌
- 日本感性工学会論文誌 (ISSN:18845258)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.2, pp.371-379, 2014 (Released:2014-04-30)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 2 1
This paper proposes a kansei-aware landscape picture creating system from natural language sentence. The proposed system creates a landscape picture by focusing on nouns. In the system, several concepts such as “sea” and “sky” and their many graphical parts are stored. Semantic estimation among input words plays an important role in the creating of a meaningful image representation of the input sentence. We use Google N-gram to cope with this issue, a lexical resource. As a result, restrictions on the input sentences can be greatly weakened and relevant constituents can be selected. In addition, the proposed system can express sense of season by selecting appropriate graphic parts with suitable color to the input sentence. Furthermore, the relation between colors and adjectives is also considered in the proposed system to reflect kansei aspects of the input sentence. Evaluation experiments have been carried out to show the effectiveness of the proposed system.
2 0 0 0 OA 大島郡郷土調査
- 著者
- 山口県大島郡小学校教育会 編
- 出版者
- 山口県大島郡小学校教員会
- 巻号頁・発行日
- 1935
2 0 0 0 OA 稲荷大神霊験記
- 著者
- 柄沢照覚, 平原貞治 著
- 出版者
- 神誠館
- 巻号頁・発行日
- 1915
2 0 0 0 OA 居場所概念の分類と比較
- 著者
- 山口 綾子
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第76回大会 (ISSN:24337609)
- 巻号頁・発行日
- pp.2EVB16, 2012-09-11 (Released:2020-12-29)