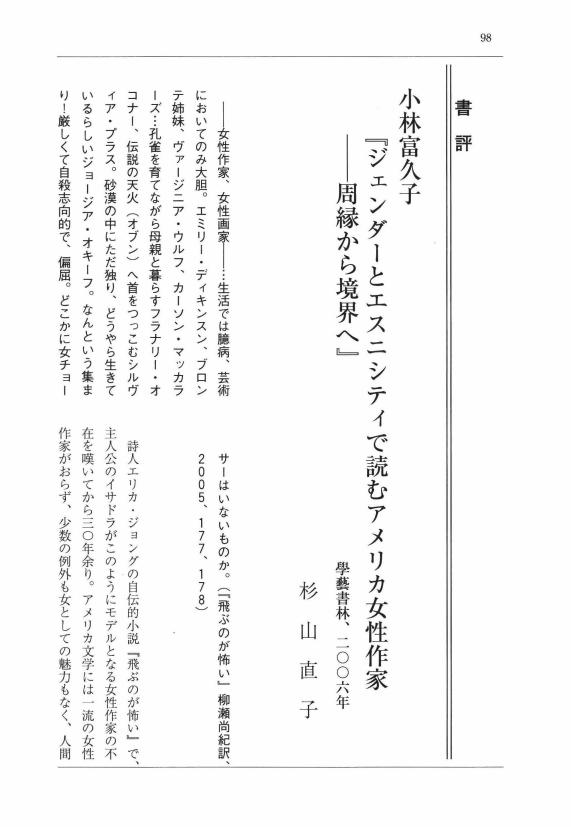2 0 0 0 OA 水道水中のトリハロメタンの煮沸除去に関する研究
- 著者
- 鵜崎 実 古庄 志真子 嶋津 暉之
- 出版者
- 美作女子大学〔ほか〕
- 雑誌
- 美作女子大学紀要 = Bulletin of Mimasaka Women′s College (ISSN:03897796)
- 巻号頁・発行日
- no.31, pp.65-71, 1998
2 0 0 0 OA 在日米軍の夜間離着陸訓練(NLP)と基地移設問題 : 米軍再編の隠れた課題
- 著者
- 鈴木滋
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- レファレンス (ISSN:1349208X)
- 巻号頁・発行日
- no.721, 2011-02
- 著者
- 山本健太郎
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- レファレンス (ISSN:1349208X)
- 巻号頁・発行日
- no.702, 2009-07
2 0 0 0 OA 最近10年間における労働法の規制緩和
- 著者
- 柳沢房子
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- レファレンス (ISSN:1349208X)
- 巻号頁・発行日
- no.687, 2008-04
2 0 0 0 OA ベルギーの政党政治と合意形成
- 著者
- 渡辺樹
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- レファレンス (ISSN:1349208X)
- 巻号頁・発行日
- no.686, 2008-03
2 0 0 0 OA 第2章 地中ケーブル
- 著者
- 古澤 久具
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電氣學會雜誌 (ISSN:00202878)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, no.5, pp.428-431, 1981-05-20 (Released:2008-04-17)
- 参考文献数
- 8
- 著者
- 佐治 晴夫 Haruo SAJI
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.109-128,
This paper describes one of the answers for the elementary question : "Why does the universe exist?" through the view point of 'the anthropic cosmological principle'. Also was shown that the size of human body was entirely determined by the size of the earth, that is, its radius and mass, respectively. This fact means that the possibility of human-beings' existence cannot be separated from a certain fine-tuning of physical constants. And the reason why the universe is so is because human-beings exist at present, that is, the existence of human-beings make possible to exist the universe at present that we can observe now. Finally, the author proposes the inter-disciplinary new field of science : "Mathematical Science of Art", as one of the Liberal Arts subjects.
- 著者
- 山田 泰彦
- 出版者
- 素粒子論グループ 素粒子論研究 編集部
- 雑誌
- 素粒子論研究 (ISSN:03711838)
- 巻号頁・発行日
- vol.92, no.3, pp.C180, 1995-12-20 (Released:2017-10-02)
2 0 0 0 OA 読者の熱中に伴う仮想の変化:仮想の特徴づけとして
- 著者
- 布山 美慕 日髙 昇平
- 出版者
- 日本認知科学会
- 雑誌
- 認知科学 (ISSN:13417924)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.2, pp.188-199, 2018-06-01 (Released:2018-12-01)
- 参考文献数
- 36
- 被引用文献数
- 4
We can imagine anything — not just an object at our hand, but also something we have never seen in our life, such as a dragon, number, heaven, and so on. In this article, we discuss a potential methodology to characterize such imagination as a conscious process, which we cannot sufficiently associate to the corresponding external stimuli. As one of such conscious processes, here we take reading of text, in which the reader construct a rich imaginary world along the storyline from looking at a quite limited visual stimulus, namely just a series of letters on a text. In particular, in the state of absorption, the reader often feels oneself into the imaginary world as a character. By reviewing past research on the absorption in reading, we propose a hypothesis, in which both conscious process itself and something in the conscious experience are objects, that is defined by the consistency between its intention and extension (inductive and deductive way of definition). In this hypothesis, difference between absorption and non-absorption is considered analogously as difference in the point of view of an object in consciousness. On the basis of the prediction of this hypothesis, we discuss empirical tests on our hypothesis.
- 著者
- 大平 和希子
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- アフリカレポート (ISSN:09115552)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, pp.1-13, 2020-02-17 (Released:2020-02-17)
- 参考文献数
- 22
ウガンダでは1995年憲法を皮切りに、慣習地の登記促進を通して、慣習地で暮らす人々の権利安定化を図ってきた。しかし、慣習地の登記が一向に進まない状況を受け、2013年に発表された国家土地政策は、慣習地の登記を担うはずの地方自治体の能力不足を指摘した上で、伝統的権威の慣習地ガバナンスへの関与を示唆した。これを踏まえて、本稿の目的は、伝統的権威が、慣習的権利の安定化を図る上で、地方自治体に代わる、あるいは、地方自治体と協働する一主体となりうるかという問いに答えることである。ウガンダ西部ブニョロ地域を事例に、地域住民と伝統的権威の関係性、地方自治体と伝統的権威の関係性の2点に着目し考察する。
- 著者
- 杉山 直子
- 出版者
- 日本女性学会
- 雑誌
- 女性学 (ISSN:1343697X)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.98-102, 2007-04-09 (Released:2021-12-09)
2 0 0 0 CGDLを用いたトリックテイキングゲーム自動生成手法の提案
- 著者
- 牧野 貴斗 濱川 礼
- 雑誌
- 研究報告ゲーム情報学(GI) (ISSN:21888736)
- 巻号頁・発行日
- vol.2021-GI-46, no.7, pp.1-6, 2021-06-12
本研究では CGDL (A Card Game Description Language) を用いてトリックテイキングゲームのルールを記述し深層生成を行いトリックテイキングゲームを自動生成する手法を提案する.トリックテイキングゲームとは,ナポレオンやコントラクトブリッジに代表される全員でカードを決められた枚数出し.出したカードの大小などで勝敗を決めるトリックを複数回繰り返すゲームのことである.人の顔を見ながらできるカードゲームは,コミュニケーション能力を養い,ゲームに勝つために考える過程で思考力を養うことができる知育能力があると考えられている.ただ同一のゲームを繰り返しているとセオリーが確立し思考機会の減少,遊び慣れからゲームに飽きてしまい,カードゲームの持つ知育能力が損なわれてしまう.そこで,常に新しいゲームを提供することができればこの問題を解決できると考え,カードゲームの自動生成を行った.ゲームの自動生成分野では遺伝的アルゴリズムを用いてチェッカーや Go などのバランスの取れたボードゲームを設計する試みなどがあるがこれらの研究では限られたバリエーションでしかルールを表現できていない.そこで本研究では CGDL を用いてトリックテイキングゲームのルールを記述することで様々な形式に対応させ,これを深層学習で学習させることで,ルールをより多彩に表現することを試み,生成したゲームの評価を行った.
2 0 0 0 OA 界面とソフトカプセル
- 著者
- 早川 栄治
- 出版者
- 日本膜学会
- 雑誌
- 膜 (ISSN:03851036)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.4, pp.177-182, 2011 (Released:2011-12-13)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1 1
Softgel capsules consist of a gelatin based shell or vegetable origin materials such as starch and carrageenan. They can be filled with liquids or pastes. Dynamic nature of the soft capsules affected by atmospheric condition or filled liquid is considered in view of the surface interaction.
- 著者
- 小倉 慶郎
- 出版者
- 大阪府立大学総合教育研究機構
- 雑誌
- 言語と文化 (ISSN:13478966)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.51-70, 2008-03-31
This paper aims to present the law of translation that governs the manner in which literal/free translation takes place. Since ancient times, the issue of whether translation should be source- or target-oriented has been furiously debated. Although one camp has always been lambasting the other for its strategy, the reasons for a translator's use of both methods were never clear. First, we examine the examples of translation in different genres and attempt to discover the rules that made the translator adopt one particular strategy. Next, we propose the law of translation with regard to "foreignizing/domesticating" strategies, which has thus far never been identified. Finally, we seek to check the validity of this law, citing a short history of translation in varied cultures.
2 0 0 0 OA 人工知能を用いた「あいみょん」分析
- 著者
- 植田 康孝 榎本 優奈
- 雑誌
- 江戸川大学紀要 = Bulletin of Edogawa University
- 巻号頁・発行日
- vol.30, 2020-03-15
近年,ストリーミングの台頭で音楽の聴き方が大きく変わりつつある。スマートフォンが変えた様々な生活スタイルの中でも,音楽は劇的に変化した消費行動の一つである。利用者の嗜好に合わせて人工知能が推薦曲を自動的に生成し,日々変化させる。ストリーミングを利用することにより,音楽消費が好みのアーティストや楽曲,アルバムを指定して聴くスタイルから,プレイリスト中心のスタイルへと大きく変化した。ストリーミングを使ってヒットするためには,プレイリストの活用が重要になる。そして,プレイリストに採用されるためには,繰り返し聴けるBGM にもなる楽曲となることを必要とする。色々なプレイリストに入る楽曲の方が再生回数を伸ばすには,メタルのような激しいサウンドの楽曲よりも,歌詞をじっくりと聴ける楽曲の方が適する。ストリーミングランキングにおいては,売り上げや動員よりも再生回数が指標となり,繰り返して何度も聴きたくなるシンプルな「楽曲の良さ」がヒットに直結する。レコード会社,アーティスト,芸能事務所,マスメディアの力が弱まり,歌詞や楽曲が重要となっている。この点がCD シングルランキングとの大きな違いである。 「あいみょん」も「トップ50」や「ネクストブレイク」など,各社の公式プレイリストに入ったことがストリーミングにおける人気に繋がった。「あいみょん」が人気となった最大の理由として,歌詞の良さが挙げられる。歌詞に彼女が得た人気の原因があり,ストリーミングという何度でも繰り返し聴きたくなる楽曲に有利なメディアと相乗効果を生んだことが,デビュー以降の急激な人気上昇を生み出した。本研究は,「あいみょん」の歌詞に着目,テキストマイニングにより歌詞を数量化したデータに考察を加えた。「あいみょん」の歌詞を分析すると,アーティストらしさが意識された語として「君」「僕」「あなた」「2 人」がすべての楽曲において多用されていることが分かった。
- 著者
- 小池 淳一
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:00215023)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.1, pp.119-123, 2002
2 0 0 0 OA 内視鏡下上咽頭擦過療法における経鼻綿棒法と経口咽頭捲綿子法,それぞれの特性
- 著者
- 田中 亜矢樹
- 出版者
- 日本口腔・咽頭科学会
- 雑誌
- 口腔・咽頭科 (ISSN:09175105)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1, pp.5-16, 2020 (Released:2021-03-31)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 1
慢性上咽頭炎の治療における上咽頭擦過療法には経鼻綿棒法と経口咽頭捲綿子法があり,各々盲目的に行う方法と内視鏡下に行う方法がある.それぞれに長所と短所があり,その特性を理解し症例に応じて使い分けることが臨床効果を向上させる上で重要である.経鼻法に用いる綿棒には直綿棒と弯曲綿棒があり局面によって使い分ける.経口法に用いる咽頭捲綿子にも擦過する上咽頭各部位に応じた使用法がある.経鼻綿棒と経口咽頭捲綿子のそれぞれの特性に基づいた基本的使用法について概説する.