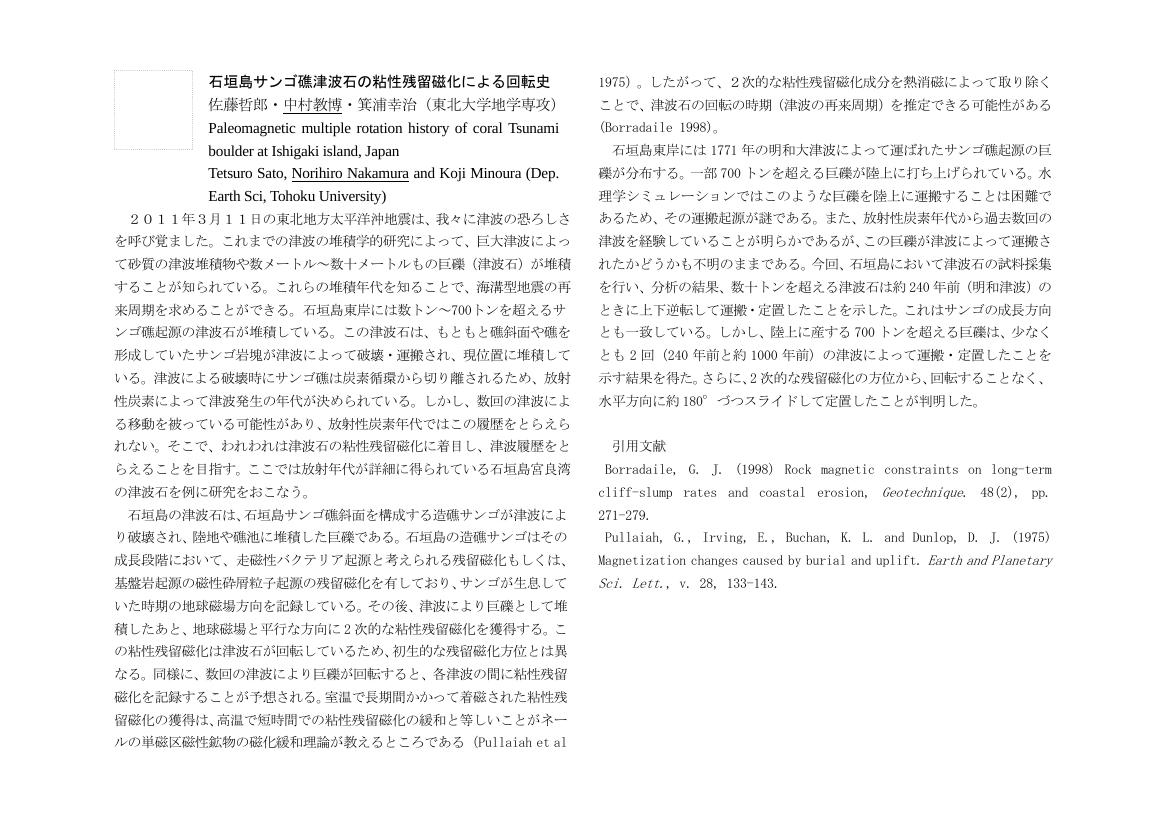2 0 0 0 OA 深層地下水変動から宮城県沖地震を予知する基礎研究
- 著者
- 岡田 真介 坂下 晋 今泉 俊文 岡田 篤正 中村 教博 福地 龍郎 松多 信尚 楮原 京子 戸田 茂 山口 覚 松原 由和 山本 正人 外處 仁 今井 幹浩 城森 明
- 出版者
- 社団法人 物理探査学会
- 雑誌
- 物理探査 (ISSN:09127984)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, pp.103-125, 2018 (Released:2018-12-28)
- 参考文献数
- 43
- 被引用文献数
- 2
活断層の評価を行うにあたっては,断層の地下形状も重要な情報の1つである。地下数十m以深の情報は,主に物理探査の結果から得ることができる。これまでには,物理探査は横ずれ活断層にはそれほど多く適用されてこなかったが,本研究では各種の物理探査を行い,横ずれ活断層に対する物理探査の適用性について検討した。対象地域は,近畿地方北西部の花崗岩地域に分布する郷村断層帯および山田断層帯として,4つの測線において,多項目の物理探査(反射法地震探査・屈折法地震探査・CSAMT探査・重力探査)を実施した。その結果,反射法地震探査は,地表下200〜300 m程度までの地下構造を,反射面群の不連続としてよく捉えていた。しかし,活断層の変位のセンスと一致しない構造も見られ,他の物理探査の結果と比較する必要があることがわかった。屈折法地震探査は,原理的に断層の角度を限定することは難しいが,横ずれ活断層の運動による破砕の影響と考えられる低速度領域をよく捉えることができた。CSAMT探査では,深部まで連続する低比抵抗帯が認められ,地下の活断層の位置および角度をよく捉えていたが,活断層以外に起因する比抵抗構造変化も捉えていることから,他の探査との併用によって,その要因を分離することが必要である。重力探査は,反射法地震探査と同様に上下変位量の小さい横ずれ活断層に対しては適さないと考えられてきたが,測定の精度と測定点密度を高くすることにより活断層に伴う重力変化を捉えることができた。
1 0 0 0 OA オンライン授業の現状と学生の評価 -基礎ゼミ受講者へのアンケート結果を中心に-
- 著者
- 松河 秀哉 山内 保典 佐藤 智子 中川 学 縣 拓充 中村 教博 串本 剛 杉本 和弘 渡邉 文枝
- 出版者
- 東北大学高度教養教育・学生支援機構
- 雑誌
- 東北大学高度教養教育・学生支援機構紀要 = BULLETIN OF THE INSTITUTE FOR EXCELLENCE IN HIGHER EDUCATION TOHOKU UNIVERSITY (ISSN:21895945)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.3-21, 2021-03
1 0 0 0 浮遊している過冷却珪酸塩メルトからのコンドリュール組織形成
太陽系形成初期過程におけるコンドリュール形成を模擬した珪酸塩メルト浮遊実験を行い,その結晶成長組織形成過程をフェーズ・フィールド・モデルによる計算機シミュレーションにより実験を行った.その結果は以下のとおりである.1.地上実験では容易に結晶化する珪酸塩メルトが,宇宙空間のような無容器浮遊実験では結晶化せずにガラス化してしまうことが初めてわかった.すなわち惑星間物質が結晶化するには星間ダストなどの微粒子と衝突することが必須であることが示唆される.この結果は,太陽系形成初期には非常に濃いダスト数密度が与えられていたことを示す.2.コンドリュールは従来言われていた平衡凝固ではなく500-1000Kという超高過冷却メルト(ハイパークールドメルト)からの結晶化であることが初めて示された.ハイパークールドメルトからは低過冷却結晶組織が安定に形成されることが熱力学的計算から予測されており,本研究は実験による証拠を提示したことにもなる.3.浮遊メルト結晶化実験,ならびに計算機シミュレーションの結果から,バードオリビンコンドリュールに固有の特徴的なリム構造は,従来言われているような徐冷過程(100K/hr)では形成されず,急冷過程(100K/s)によってのみ形成されることがわかった.4.コンドリュール再現実験結果から,直径1ミリのコンドリュールの結晶化が完了するまでの時間は,原始太陽系の冷却速度には無関係に約10秒程度であることが推定できた.この推定結果は従来説である数時間オーダーと比べて極めて短時間であり,コンドリュールは短時間イベントによる産物であることが予想される.この結果はコンドリュールに激しい蒸発の後が見られず揮発性成分が残されていることと調和的である.
1 0 0 0 OA 石垣島サンゴ礁津波石の粘性残留磁化による回転史
- 著者
- 佐藤 哲郎 中村 教博 箕浦 幸治
- 出版者
- The Geological Society of Japan
- 雑誌
- 日本地質学会学術大会講演要旨 (ISSN:13483935)
- 巻号頁・発行日
- pp.308, 2012 (Released:2013-03-26)
1 0 0 0 OA 野島地震断層の性状
- 著者
- 皆川 潤 大槻 憲四郎 青野 正夫 大友 淳一 中村 教博
- 出版者
- 一般社団法人日本応用地質学会
- 雑誌
- 応用地質 (ISSN:02867737)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.2, pp.154-166, 1995-06-10
- 被引用文献数
- 5 2
兵庫県南部地震(M7.2)<1)>は、1995年1月17日午前5時46分に、淡路島北方の明石海峡の地下深部14.3km付近を震源<1)>として発生し、淡路島北部から対岸の神戸市〜西宮市にかけて大きな被害を与えた。その被害域は直線的に延びた帯状の範囲に集中し、直下型の活断層の影響を強く受け、淡路島北部では地震断層が出現した。この地震断層は、活断層とされている野島断層(水野他<2)>、活断層研究会<3)>)にほぼ一致して出現したもので、生々しい断層の実体像を我々の眼前に現してくれた(この地震断層を以後野島地震断層と呼ぶことにする)。地震断層を含む活断層は第四紀に入ってからの新しい断層運動によって生じ、その地質的な現象が地形に反映されることが多いことから、調査に当っては地質的・地形的な両面から断層を調べていくことが必要である。今回現れた地震断層は、地質・地形の両面で現れた断層であり、この断層から"自然の厳しさ"とともに活断層の実体像の多くを学びとる必要がある。ここでは、地震発生後に実施した地震断層の性状と被害に関する現地調査結果を報告する。今後の活断層調査の一助となれば幸いである。