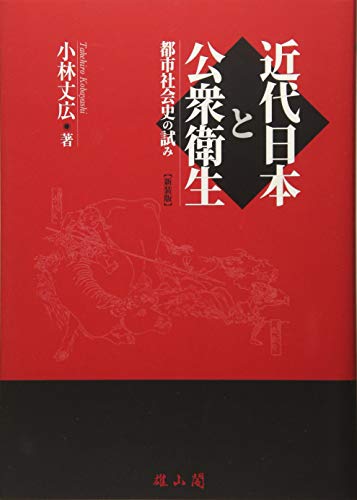5 0 0 0 IR 明治維新期の「市長」 (鎌田道隆先生・佐々木克先生退職記念号)
- 著者
- 小林 丈広
- 出版者
- 奈良大学史学会
- 雑誌
- 奈良史学 (ISSN:02894874)
- 巻号頁・発行日
- no.29, pp.55-94, 2011
3 0 0 0 OA 歴史における周縁と共生-疫病・触穢思想・女人結界・除災儀礼-
- 著者
- 鈴木 則子 脇田 晴子 平 雅行 梅澤 ふみ子 久保田 優 武藤 武藤 三枝 暁子 成田 龍一 武田 佐知子 小林 丈広 白杉 悦雄 谷口 美樹 福田 眞人 脇田 修 濱千代 早由美 長 志珠絵 尾鍋 智子 菅谷 文則 山崎 明子 加藤 美恵子 栗山 茂久
- 出版者
- 奈良女子大学
- 雑誌
- 基盤研究(A)
- 巻号頁・発行日
- 2008
本研究は、日本の歴史のなかで女性の周縁化(地位の劣化)が進行していく過程を、女性の身体に対する認識の歴史的変化に着目しつつ、医学・衛生・宗教・地域・出産/月経という主として五つの側面から検討を加えた。伝統的医学と近代医学それぞれの女性身体観、近代衛生政策における女性役割の位置づけ、仏教と神道の女性認識の変遷、血穢などに対する地域社会の対応の形成等について明らかにしえた。
3 0 0 0 近代日本と公衆衛生 : 都市社会史の試み
- 著者
- 小林 丈広
- 出版者
- 地方史研究協議会
- 雑誌
- 地方史研究 (ISSN:05777542)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.4, pp.48-53, 2021-08
1 0 0 0 障害の歴史性に関する学際統合研究 ー比較史的な日本観察ー
- 著者
- 高野 信治 山本 聡美 東 昇 中村 治 平田 勝政 鈴木 則子 山田 嚴子 細井 浩志 有坂 道子 福田 安典 大島 明秀 小林 丈広 丸本 由美子 藤本 誠 瀧澤 利行 小山 聡子 山下 麻衣 吉田 洋一
- 出版者
- 九州大学
- 雑誌
- 基盤研究(A)
- 巻号頁・発行日
- 2019-04-01
近年、欧米では前近代をも射程に身心機能の損傷と社会文化的に構築されたものという二つの局面を複合させて障害を捉え、人種、性(身体上)、民族の差異よりも、障害の有無が人間の区別・差別には重要とされる。日本では、かかる視角の研究はなく、障害は近代の画期性が重視される。しかし福祉問題の将来が懸念されるなか、比較史的観点も踏まえた障害の人類史的発想に立つ総合的理解は喫緊の課題だ。以上の問題意識より、疾病や傷害などから障害という、人を根源的に二分(正常・健常と異常・障害)する特異な見方が生じる経緯について、日本をめぐり、前近代から近代へと通時的に、また多様な観点から総合的に解析する。
1 0 0 0 OA 近代古都研究-歴史と都市をめぐる学際的研究
- 著者
- 高木 博志 伊従 勉 岩城 卓二 藤原 学 中嶋 節子 谷川 穣 小林 丈広 黒岩 康博 高久 嶺之介 原田 敬一 丸山 宏 田中 智子
- 出版者
- 京都大学
- 雑誌
- 基盤研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2008
日本における近代「古都」を、歴史学・建築史・造園史などから学際的に研究した。奈良・京都・首里といった古都と、岡山・名古屋・大阪・仙台・江田島・呉・熊本など旧城下町や軍都とを研究対象とした。研究会の他に、各地でフィールドワークも実施しつつ、「歴史」や「伝統」と政治的社会的現実との、近代におけるズレや関係性を考察した。また学都や軍都などの都市類型も論じた。個別業績以外に、論文集『近代歴史都市論』を発刊予定である。
1 0 0 0 IR 近代京都の町式目をめぐって--天神山町の場合
- 著者
- 小林 丈広
- 出版者
- 同志社大学人文科学研究所
- 雑誌
- 社会科学 (ISSN:04196759)
- 巻号頁・発行日
- no.79, pp.1-15, 2007
論説近代の地域住民組織のあり方を考えるために、祇園祭に山鉾を出す天神山町に残る町式目を検討した。前半では、その前提として、町共有文書のあり方やその調査の歩みについて概観した。町共有文書の調査や保存は、町運営や町づくりなどと同様に公共的性格を持つが、その実態は一部の人にしか知られていない。そこで、その紹介も兼ねて、調査の経過も記述した。後半では、天神山町に残るいくつかの町式目の変遷をたどった。とくに、一九〇二年の「借家人町則」に着目し、それが隣接する山伏山町の「借宅者町則」をモデルにしたものであることを明らかにした。近代京都の町運営の転換点については、これまで公同組合の設置を重視する見方が根強くあったが、少なくとも山鉾町では、山鉾の維持問題がその契機となった。町組織のような地域住民組織の歴史的研究はまだ始まったばかりであり、こうした具体例を通じて、個別事例を積み重ねていくことが重要であろう。