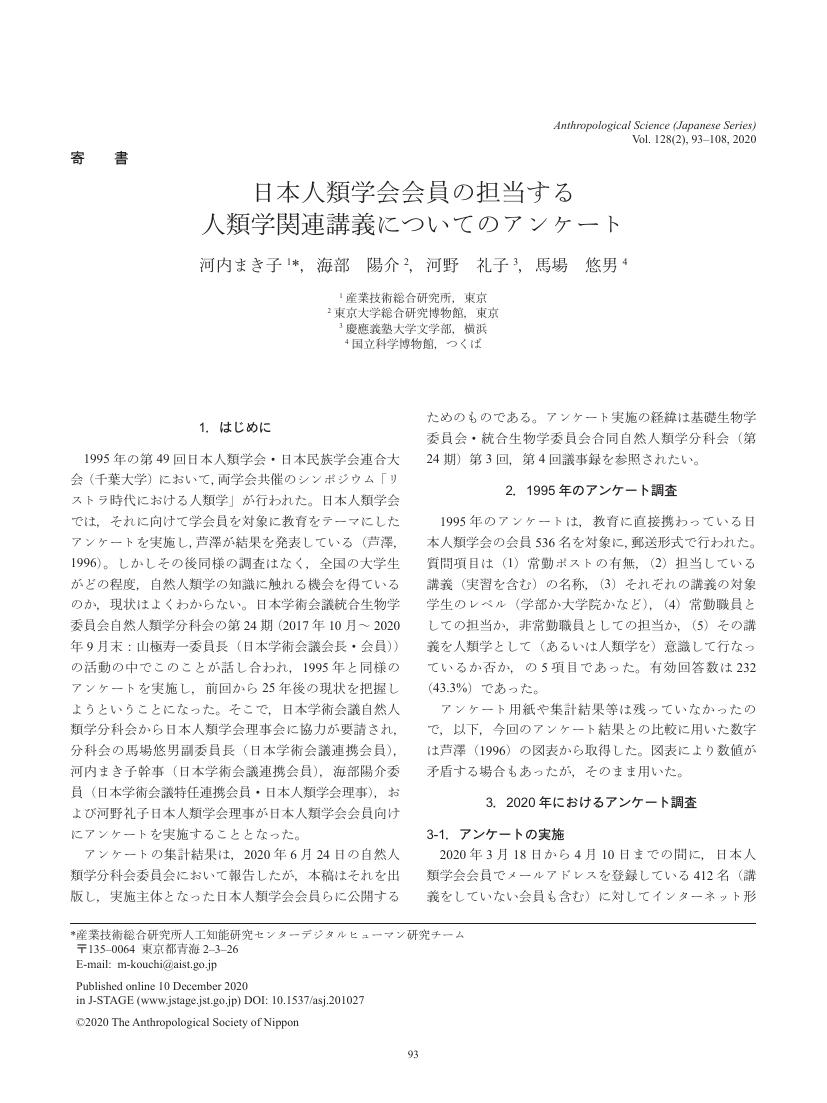30 0 0 0 エジプト、ルクソール西岸の新王国時代岩窟墓の形成と発展に関する調査研究
エジプト、ルクソール西岸アル=コーカ地区で、平成29年12月~平成30年1月に、さらに平成30年3月の2回にわたり調査を実施することができたことで、前年度同様、研究を進展することができた。当該地区には、第18王朝アメンヘテプ3世治世末期の高官ウセルハトの墓(TT47)の大規模な前庭部を中心として、数多くの岩窟墓が存在している。しかしながら厚い堆積砂礫に覆われていたため、未発見の岩窟墓が存在していることが想定された。これまでの調査によって、ウセルハト墓の前庭部の南側からKHT01とKHT02(コンスウエムヘブ墓)が、そして前庭部北東部からKHT03(コンスウ墓)の3基の岩窟墓を新たに発見することができ、従来の当該地区における岩窟墓の立地に関して新知見を売ることができた。平成29年度の調査によって、さらにKHT02(コンスウエムヘブ墓)前庭部の南側とTT47(ウセルハト墓)の前室南側上部の2か所において、新たな岩窟墓の存在を確信する箇所を確認することができた。これら2か所には、周辺の岩窟墓の状況から、いずれも第18王朝トトメス4世時代に属する岩窟墓の存在が予想される。そのため今後の調査により、この地区における岩窟墓の造営の変遷が一層明確になることが期待される。平成28年度に実施した大規模な堆積砂礫の除去作業によって出土した膨大な量の葬送用コーンの分析を通じて、当該地域における未発見の岩窟墓の複数の所有者の推定を可能とすることができた。これらの成果をまとめ発表することができた。平成29年度には、KHT02(コンスウエムヘブ墓)を中心として、岩盤工学の専門家と壁画の修復家の協力を受け、岩窟墓内部の壁面の保存修復作業を重点的に実施し、大きな成果をあげることができた。この結果、今後の岩盤脆弱で発掘作業が困難な部分の調査に対する目途を立てることを可能にした点でも意義は大きいと考えられる。
17 0 0 0 OA 縄文人に学ぶ ~顎の退縮による障害を防ぐには~
- 著者
- 馬場 悠男
- 出版者
- 日本健康医学会
- 雑誌
- 日本健康医学会雑誌 (ISSN:13430025)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.55-58, 2017-07-31 (Released:2017-11-30)
- 参考文献数
- 4
11 0 0 0 OA 更新世から縄文・弥生期にかけての日本人の変遷に関する総合的研究
- 著者
- 溝口 優司 中橋 孝博 安達 登 近藤 恵 米田 穣 松浦 秀治 馬場 悠男 篠田 謙一 諏訪 元 馬場 悠男 篠田 謙一 海部 陽介 河野 礼子 諏訪 元
- 出版者
- 独立行政法人国立科学博物館
- 雑誌
- 基盤研究(S)
- 巻号頁・発行日
- 2005
旧石器時代から縄文~弥生移行期まで、日本列島住民の身体的特徴がいかに変化したか、という問題を形態とDNAデータに基づいて再検討し、日本人形成過程の新シナリオを構築しようと試みた。結果、北海道縄文時代人の北東アジア由来の可能性や、縄文時代人の祖先探索には広くオーストラリアまでも調査すべきこと、また、港川人と縄文時代人の系譜的連続性見直しの必要性などが指摘された。シナリオ再構築への新たな1歩である。
6 0 0 0 OA 徳川将軍親族遺体のデジタル保存と考古学的・人類学的分析-大奥の実態に迫る-
上野寛永寺御裏方墓所から発掘された徳川将軍親族遺体のうち保存の良い15体の人骨について、修復・保存処理を施し、形態観察・写真撮影・CT撮影・計測を行って、デジタルデータとして記録保存した(馬場・坂上・河野)。さらに、遺骨の形態比較分析(馬場・坂上・茂原・中山)、ミトコンドリアDNAハプロタイプ分析(篠田)、安定同位体による食性分析および重金属分析(米田他)、寄生虫卵および花粉分析(松井・金原他)を行い、親族遺体の身体的特徴と特殊な生活形態を明らかにした。
4 0 0 0 OA 日本人の起源にかかわる南西陸橋と人の移動
- 著者
- 馬場 悠男
- 出版者
- Japan Association for Quaternary Research
- 雑誌
- 第四紀研究 (ISSN:04182642)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.3, pp.259-266, 1998-07-31 (Released:2009-08-21)
- 参考文献数
- 31
現代日本人の成立に関しては,明治時代から多くの研究者によって,北方および南方からやってきた複数の起源集団による混血の可能性が示唆され,今日でも広く認められている.すなわち,東アジア全体として,更新世末期(3~1万年前)には南方系と考えられる人々が分布していたが,最近(1万年~5,000年前)は北方系と考えられる人々が急速に拡大した,という理解の上に立って,縄文人は南方系の先住集団であり,弥生人は北方系の渡来集団であって,両者の混血によって現代日本人が成立した,と解釈するものである.このような解釈をまとめたのが埴原和朗の「二重構造モデル」である.その際の,南方および北方からの移動のルートとしては,南西陸橋あるいはその付近の海路が有力であるが,北方のルートの可能性も指摘されている.少なくとも,弥生人の渡来に関しては,九州北部を中心とする地域に集中したことはまちがいない.なお,尾本恵市は,遺伝学的データから,更新世後期にすでに南方系アジア人と北方系アジア人が分化していたと考えている.そうすると,縄文人も北方系の人々に起源を持つことになる.筆者は,化石人類の頭部形態から,縄文人の起源は更新世末期に北東アジア沿岸部に住んでいた人々であると考えている.
3 0 0 0 OA 人類の進化―最新研究から人間らしさの発達を探る―
- 著者
- 馬場 悠男
- 出版者
- 日本人類学会
- 雑誌
- Anthropological Science (Japanese Series) (ISSN:13443992)
- 巻号頁・発行日
- vol.122, no.1, pp.102-108, 2014 (Released:2014-06-24)
- 参考文献数
- 10
初等中等教育の限られた授業時間の中で,生徒たちに人類学および人類進化の本質を理解させ,現在と未来の私たちのあるべき姿を考えるヒントを与えられるような試案を提示した。具体的には,教えるべき理解の要点,教える際の注意点,簡易なストーリー説明,「人間らしさ」を示す最新の研究結果によるトピックを簡略に述べた。
2 0 0 0 OA 巨人関脇出羽ケ嶽骨格の形態学的研究
- 著者
- 鈴木 尚 馬場 悠男 神谷 敏郎
- 出版者
- The Anthropological Society of Nippon
- 雑誌
- 人類學雜誌 (ISSN:00035505)
- 巻号頁・発行日
- vol.94, no.4, pp.403-440, 1986 (Released:2008-02-26)
- 参考文献数
- 52
- 被引用文献数
- 1 1
脳下垂体の腫瘍にもとつく巨人症の形質を,力士•出羽ケ嶽の骨格について,人類学的に研究した。脳頭蓋の外形は巨大であるが,実は,骨の病的肥厚による矢状径と横径の著しい増大にもとつくもので,脳容積に異常はない。顔面は高径•幅径とも過成長をとげ,とくに前者が甚だしく,上顔より下顔部に進むほど加速される。さらに上•下顎骨の不平等な成長による咬合の左右差は,咀蠕筋の不相称を招き,結局,全頭蓋の左右不相称を生じた。四肢は身長に比しても長く,逆に体幹は太く短かったらしい。上肢骨は相対的にも極めて頑丈であるが,下肢骨はあまり頑丈ではない。上肢骨の大きさには特有の相補的な左右差あるいは不均衡が見られる。
2 0 0 0 日本人類学会会員の担当する人類学関連講義についてのアンケート
- 著者
- 河内 まき子 海部 陽介 河野 礼子 馬場 悠男
- 出版者
- 一般社団法人 日本人類学会
- 雑誌
- Anthropological Science (Japanese Series) (ISSN:13443992)
- 巻号頁・発行日
- vol.128, no.2, pp.93-108, 2020 (Released:2021-01-06)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 1 1
2 0 0 0 OA <国立科博専報>小塚原刑場跡出土人骨の形態学的特徴
- 著者
- 大谷 江里 馬場 悠男
- 出版者
- 国立科学博物館
- 雑誌
- 国立科学博物館専報 (ISSN:00824755)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.317-327, 2001
2 0 0 0 OA 動物の体型と歩行様式
- 著者
- 馬場 悠男
- 出版者
- バイオメカニズム学会
- 雑誌
- バイオメカニズム学会誌 (ISSN:02850885)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.3, pp.158-162, 1995-08-01 (Released:2016-10-31)
- 参考文献数
- 5
- 著者
- 香原 志勢 茂原 信生 西沢 寿晃 藤田 敬 大谷 江里 馬場 悠男
- 出版者
- The Anthropological Society of Nippon
- 雑誌
- Anthropological science. Japanese series : journal of the Anthropological Society of Nippon : 人類學雜誌 (ISSN:13443992)
- 巻号頁・発行日
- vol.119, no.2, pp.91-124, 2011-12-01
- 被引用文献数
- 4
長野県南佐久郡北相木村の縄文時代早期の地層(8300から8600 BP(未較正))から,12体の人骨(男性4体,女性4体の成人8体,および性別不明の幼児4体)が,1965年から1968年にかけての信州大学医学部解剖学教室を中心とする発掘で出土した。数少ない縄文時代早期人骨として貴重なもので,今回の研究は,これらの人骨の形態を報告し,従来明らかにされている縄文時代早期人骨の特徴を再検討するものである。顔高が低い,大腿骨の柱状性が著しい,歯の摩耗が顕著である,など一般的な縄文人の特徴を示すとともに,早前期人に一般的な「華奢」な特徴も示す。脳頭蓋は大きいが下顎骨は小さく,下顎体は早期人の中でもっとも薄い。下顎骨の筋突起は低いが前方に強く張り出している。上肢は華奢だが,下肢は縄文時代中後晩期人と同様に頑丈である。他の縄文時代早前期人と比較検討した結果,縄文時代早期人の特徴は,従来まとめられているものの若干の改定を含めて,次のように再確認された。1)顔面頭蓋が低い。2)下顎は小さいが,筋突起が前方に強く張り出す。3)下肢骨に比べて上肢骨が華奢である。4)下顎歯,特に前歯部には顕著な磨耗がある。<br>
2 0 0 0 OA 人間性教育の重要性について:成長パターンの人類進化的意義
- 著者
- 馬場 悠男
- 出版者
- 日本人類学会
- 雑誌
- Anthropological Science (Japanese Series) (ISSN:13443992)
- 巻号頁・発行日
- vol.116, no.2, pp.184-187, 2008 (Released:2008-12-27)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 1 1
小中高の生徒たちは,ヒトの成長期間が長いのは多くを学習するためであることを具体的に認識してはいない。個体成長曲線で知られるように,幼児期に急速な脳の成長があり,思春期以降に性的成熟がある。身体全体は,児童期に長い成長遅滞があり,その間に教育効果が上がるようになっている。教育の要素をこのような成長パターンに当てはめてみると,脳成長と身体成長とのズレは知育のため,身体成長と性的成熟のズレは徳育のためである。この二つのズレを実際の教育・学習によって適切に充填しないと,まともな自己実現は出来ない。このように手間はかかるが最終的に優れた適応力を発揮するライフヒストリーこそ人間性の中核であり,それが人類進化の過程でいかに獲得されたかを普及させるのは,人類学研究者の責務であろう。
2 0 0 0 江戸時代に制作された木骨に関する研究
江戸時代に医学教育研究のために10体余の木製人体骨格模型(木骨)が制作された。現存するのは星野木骨(身幹儀,1792年制作),各務木骨(1810年頃),奥田木骨2体(1820年頃),及び各務小木骨である。私たちは科研費により前4者と関連事項について調査研究した。真骨は全て刑死人のものであり,全ての木骨で舌骨が欠損している。星野木骨は医師,星野良悦が工人,原田孝次に制作させた等身大の成人男性骨格模型で,全ての模骨が揃っている。各骨は原則として別々に作られ,〓と〓孔で結合できる。骨は薄い茶色に,軟骨は白く塗られている。頭蓋冠は切っていないが,X線撮影及び内視鏡観察により,頭蓋内の構造も作られ,ほとんどが正確に頭蓋内外を連絡していた。各務木骨は医師,各務文献が田中某に作らせた等身大の成人男性骨格であるが,かなりの骨が欠損している。各骨は〓と〓孔で連結する。頭蓋は木片を繋ぎ合わせて作り,表面に和紙を張って薄茶色に彩色している。頭蓋冠は斜めに切られ,頭蓋内構造を観察できる。奥田木骨2体は同じ骨をモデルとし,奥田万里が細工師・池内某(またはその工房)に彫らせた等身大の成人女性骨格である。桧材を精巧に彫って形作り,一部の軟骨のみを白または褐色に彩色している。頭蓋は頭蓋冠を水平断し,内部構造が見える。奥田木骨は椅座位で展示できるように専用の台座や支柱があり,胸郭や骨盤は一体化し,組み立ての装具に工夫が見られる。各部の精粗については,それぞれの木骨で長短があるが,当時の日本にあった解剖学書の図に比べて極めて正確である。木骨は人骨を座右において観察できなかった江戸時代の医師が作らせた我国特有の医学資料で,正確・精巧に作られており,当時の医師の探究心,工人の観察眼の確かさ,技術の高さを伝える貴重な資料である。
1 0 0 0 OA 巨人関脇出羽ヶ嶽骨格の形態学的資料
- 著者
- 鈴木 尚 馬場 悠男 神谷 敏郎
- 出版者
- The Anthropological Society of Nippon
- 雑誌
- 人類學雜誌 (ISSN:00035505)
- 巻号頁・発行日
- vol.94, no.4, pp.441-468, 1986 (Released:2008-02-26)
- 参考文献数
- 2
元関脇出羽ヶ嶽の全身骨格に関する形態学的資料を報告する.計測はマルチンの教科書に準拠して行ない,結果を Table1~11にまとめた.写真はマイクロニッコール55mm で撮影し, Plate1~6にまとめた. X線写真は距離1.2mで撮影し,直焼像を Plate7~14にまとめた.X 線写真のスケールは骨自体の人きさではなく,フィルム面上の像の大きさを表わしている.骨格の形態学的記載および現代日本人との比較は,この資料報告に先行する本報告(巨人関脇出羽ヶ嶽骨格の形態学的研究,鈴木他1986)に載せた.
1 0 0 0 OA 幻の明石原人から実在の港川人まで
- 著者
- 馬場 悠男
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.2, pp.2_34-2_37, 2020-02-01 (Released:2020-06-26)
- 参考文献数
- 27
1 0 0 0 OA 栃原岩陰遺跡(長野県南佐久郡北相木村)出土の縄文時代早期人骨
- 著者
- 香原 志勢 茂原 信生 西沢 寿晃 藤田 敬 大谷 江里 馬場 悠男
- 出版者
- 日本人類学会
- 雑誌
- Anthropological Science (Japanese Series) (ISSN:13443992)
- 巻号頁・発行日
- pp.1111180003-1111180003, (Released:2011-11-22)
- 被引用文献数
- 3 4
長野県南佐久郡北相木村の縄文時代早期の地層(8300から8600 BP(未較正))から,12体の人骨(男性4体,女性4体の成人8体,および性別不明の幼児4体)が,1965年から1968年にかけての信州大学医学部解剖学教室を中心とする発掘で出土した。数少ない縄文時代早期人骨として貴重なもので,今回の研究は,これらの人骨の形態を報告し,従来明らかにされている縄文時代早期人骨の特徴を再検討するものである。顔高が低い,大腿骨の柱状性が著しい,歯の摩耗が顕著である,など一般的な縄文人の特徴を示すとともに,早前期人に一般的な「華奢」な特徴も示す。脳頭蓋は大きいが下顎骨は小さく,下顎体は早期人の中でもっとも薄い。下顎骨の筋突起は低いが前方に強く張り出している。上肢は華奢だが,下肢は縄文時代中後晩期人と同様に頑丈である。他の縄文時代早前期人と比較検討した結果,縄文時代早期人の特徴は,従来まとめられているものの若干の改定を含めて,次のように再確認された。1)顔面頭蓋が低い。2)下顎は小さいが,筋突起が前方に強く張り出す。3)下肢骨に比べて上肢骨が華奢である。4)下顎歯,特に前歯部には顕著な磨耗がある。
1 0 0 0 OA 栃原岩陰遺跡(長野県南佐久郡北相木村)出土の縄文時代早期人骨
- 著者
- 香原 志勢 茂原 信生 西沢 寿晃 藤田 敬 大谷 江里 馬場 悠男
- 出版者
- 日本人類学会
- 雑誌
- Anthropological Science (Japanese Series) (ISSN:13443992)
- 巻号頁・発行日
- vol.119, no.2, pp.91-124, 2011 (Released:2011-12-22)
- 参考文献数
- 75
- 被引用文献数
- 3 4
長野県南佐久郡北相木村の縄文時代早期の地層(8300から8600 BP(未較正))から,12体の人骨(男性4体,女性4体の成人8体,および性別不明の幼児4体)が,1965年から1968年にかけての信州大学医学部解剖学教室を中心とする発掘で出土した。数少ない縄文時代早期人骨として貴重なもので,今回の研究は,これらの人骨の形態を報告し,従来明らかにされている縄文時代早期人骨の特徴を再検討するものである。顔高が低い,大腿骨の柱状性が著しい,歯の摩耗が顕著である,など一般的な縄文人の特徴を示すとともに,早前期人に一般的な「華奢」な特徴も示す。脳頭蓋は大きいが下顎骨は小さく,下顎体は早期人の中でもっとも薄い。下顎骨の筋突起は低いが前方に強く張り出している。上肢は華奢だが,下肢は縄文時代中後晩期人と同様に頑丈である。他の縄文時代早前期人と比較検討した結果,縄文時代早期人の特徴は,従来まとめられているものの若干の改定を含めて,次のように再確認された。1)顔面頭蓋が低い。2)下顎は小さいが,筋突起が前方に強く張り出す。3)下肢骨に比べて上肢骨が華奢である。4)下顎歯,特に前歯部には顕著な磨耗がある。
1 0 0 0 OA 江戸時代の奥田木骨に見られる西洋医学振興と日本的職人芸
- 著者
- 馬場 悠男 鈴木 一義
- 出版者
- 国立科学博物館
- 雑誌
- Bulletin of the National Science Museum. Series D, Anthropology (ISSN:03853039)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, pp.1-9, 2005-12
In the late Edo era, a human skeleton intended for medical education was carved from cypress wood by a craftsman, Ikeuchi under the supervision of a medical doctor, Banri Okuda in Osaka City. The model for the carving was based on a criminal's skeleton. The skeleton was beautifully made to be articulated and assembled by various methods, which reveals excellent craftsmanship. By and large, the wooden skeleton shows morphological characteristics usually seen in early middle-aged females of the Edo era. The wooden skeleton might have been used for the promotion of European medicine, which was emergent in the Edo era Japan, rather than for practical medical education.