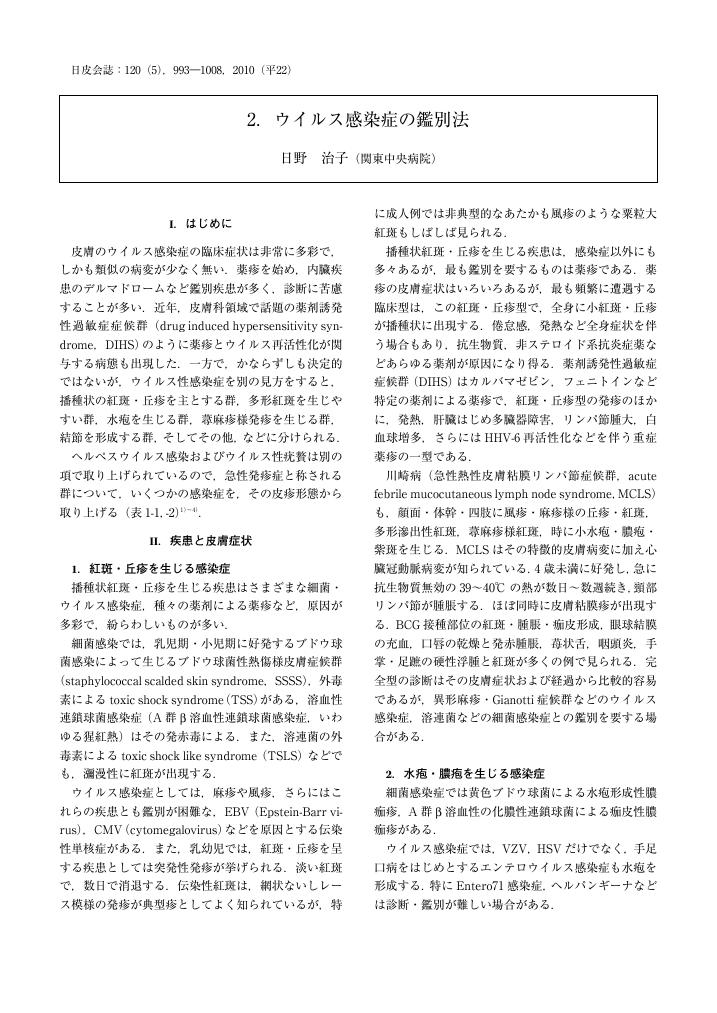- 著者
- 川村 由美 大塚 勤 山崎 雙次
- 出版者
- 公益社団法人 日本皮膚科学会
- 雑誌
- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)
- 巻号頁・発行日
- vol.115, no.9, pp.1321-1325, 2005-08-20 (Released:2014-12-10)
症例1 72歳,男性.1999年10月より肝細胞癌に対し計10回,経カテーテル的肝動脈化学塞栓術(以下TAI・TAE)施行.2000年7月,右背部に軽度の搔痒を伴う皮疹出現.周囲に毛細血管拡張を伴う黒褐色の色素沈着と一部脱色素斑が混在する硬化性局面を認めた.自覚症状,潰瘍等がみられないため外来でステロイド軟膏・ヘパリン類似物質軟膏外用にて経過観察中.症例2 56歳,男性.1994年7月,急性心筋梗塞に対して冠動脈造影(以下CAG)および経皮的冠動脈形成術(以下PTCA)施行.1995年8月より,右上背部に痂皮を伴う紅斑出現.2000年9月,一部潰瘍化し強い疼痛を伴ったため近医受診.抗生剤内服・外用にても軽快せず当科紹介.右上背部に径10×7.0 cm大,黒褐色の光沢を伴う硬化性局面あり,中央部に径5.0×4.5 cmの白色壊死を伴う潰瘍を認めた.治療は皮膚硬化部より1 cm離し,筋膜を含めて切除し分層植皮術施行.その後再発なし.2例とも組織所見にて真皮全層と一部皮下組織まで膠原線維の均質化と増生がみられ,付属器はほとんど認められない.いずれも臨床像はmorpheaと類似しており,慢性放射線皮膚炎との鑑別の必要性を考え報告する.
- 著者
- 古江 和久 古江 増隆
- 出版者
- 公益社団法人 日本皮膚科学会
- 雑誌
- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)
- 巻号頁・発行日
- vol.130, no.7, pp.1645-1652, 2020
<p>アトピー性皮膚炎では,Th2サイトカインの顕著な発現が認められる.加えてIL-17産生細胞の浸潤も報告されているが,その意義については未解明の部分が多い.本稿では,CCR6を発現するIL-17産生細胞の遊走因子であるCCL20産生に対する「搔破」の影響を<i>In vitro</i>表皮細胞搔破モデルを用いて検討した.表皮細胞シートを搔破するとCCL20産生放出が特異的に誘導されること,及びその産生量はIL-4,IL-13による影響を受けないことが明らかとなった.これらの結果から,IL-17産生細胞浸潤は「搔破」に伴う2次的な現象で,Th2サイトカインの影響下で起こっているわけではない可能性が示唆された.</p>
2 0 0 0 掌蹠角化症診療の手引き
- 著者
- 掌蹠角化症診療の手引き作成委員会 米田 耕造 久保 亮治 乃村 俊史 山本 明美 須賀 康 秋山 真志 金澤 伸雄 橋本 隆
- 出版者
- 公益社団法人 日本皮膚科学会
- 雑誌
- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)
- 巻号頁・発行日
- vol.130, no.9, pp.2017-2029, 2020
2 0 0 0 OA 乾癬における生物学的製剤の使用ガイダンス(2022年版)
2 0 0 0 OA 掌蹠膿疱症診療の手引き2022
- 著者
- 日本皮膚科学会掌蹠膿疱症診療の手引き策定委員会 照井 正 小林 里実 山本 俊幸 大久保 ゆかり 阿部 名美子 井汲 菜摘 石井 まどか 伊藤 明子 梅澤 慶紀 金蔵 拓郎 川上 洋 岸部 麻里 黒木 香奈 車谷 紋乃 河野 通良 清水 忠道 辻 成佳 十一 英子 中村 元樹 西田 絵美 葉山 惟大 平野 宏文 藤澤 大輔 藤城 幹山 藤田 英樹 松本 由香 森田 明理 村上 正基
- 出版者
- 公益社団法人 日本皮膚科学会
- 雑誌
- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)
- 巻号頁・発行日
- vol.132, no.9, pp.2055-2113, 2022-08-20 (Released:2022-08-23)
- 参考文献数
- 384
2 0 0 0 巻き爪と陥入爪の治療法
- 著者
- 原田 和俊 山口 美由紀 島田 眞路
- 出版者
- 公益社団法人 日本皮膚科学会
- 雑誌
- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)
- 巻号頁・発行日
- vol.123, no.11, pp.2069-2076, 2013-10-20 (Released:2014-10-30)
陥入爪とは爪甲が側爪郭を損傷し,炎症を引き起こした状態である.巻き爪とは遺伝的素因,生活環境などにより,爪甲が過度に彎曲した状態である.陥入爪の治療にはポリ塩化ビニル製チューブで陥入した爪甲を覆う方法や,アクリル樹脂を用いて側爪郭への陥入を除去する治療法などがある.疼痛を伴う巻き爪は,弾性ワイヤーなどを用いて過度の彎曲を矯正することが有効である.陥入爪と巻き爪の対応には,正確な診断を行い,各々の病態を理解し,正しい治療法を選択することが必要である.
2 0 0 0 円形脱毛症治療におけるエバスチンの有用性
- 著者
- 義澤 雄介 川名 誠司
- 出版者
- 公益社団法人 日本皮膚科学会
- 雑誌
- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)
- 巻号頁・発行日
- vol.115, no.10, pp.1473-1480, 2005-09-20 (Released:2014-12-10)
円形脱毛症の病変部には,リンパ球とともに肥満細胞の浸潤が認められ,円形脱毛症において肥満細胞が重要な病因的役割を果たしていることが推察されている.我々は,第2世代抗ヒスタミン薬であるエバスチンによる円形脱毛症治療を試み,その効果を検討した.円形脱毛症患者23例にエバスチン10 mgを1日1回投与し(エバスチン投与群),プラセーボ群として9例にディアゼパム2 mgを1日1回投与した(ディアゼパム投与群).それぞれ3カ月間投与し,脱毛病変の観察を行ったところ,エバスチン投与群では23例中14例(60.9%)に発毛を認め,ディアゼパム投与群では9例中1例(11.1%)のみに発毛を認め,その比率はエバスチン投与群で統計学的に有意に高かった(p=0.0179).また,ディアゼパム投与群で発毛を認めなかった8例に対し,ディアゼパム投与終了後からエバスチン10 mgを3カ月間投与したところ,6例に発毛が認められた.これらの結果は,円形脱毛症に対してエバスチンが有効であることを示唆した.エバスチン投与群において発毛を認めた14症例と認めなかった9症例に分けて検討すると,性別,罹病期間,重症度の構成に差はなかったが,平均年齢は発毛を認めた14症例で有意に高く(それぞれ45.3±16.9歳,25.3±9.3歳.p=0.0088),年齢が高いほどエバスチンの効果が高い可能性が考えられた.
- 著者
- 淺沼 由美子 北原 里恵 林田 優季 青山 裕美
- 出版者
- 公益社団法人 日本皮膚科学会
- 雑誌
- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)
- 巻号頁・発行日
- vol.129, no.10, pp.2165-2172, 2019-09-20 (Released:2019-09-20)
- 参考文献数
- 15
本邦では,医療費削減政策と,ヒトでの有効性評価が必須でないため,ジェネリック外用剤の市場占有率が増大している.我々はヘパリン類似物質含有保湿クリーム(水中油型)が基礎発汗を誘導し角層水分量を増加させることを見いだした.そこでヘパリン類似物質含有保湿クリーム後発品の保湿効果をimpression mold法で基礎発汗能を含めて先発品と比較した.後発品は角層水分量が増加せず,基礎発汗が同等に増加しなかった.保湿外用剤後発品の薬効評価は,角層水分量,基礎発汗誘導能などヒトでの複数の生物学的同等性試験で評価する必要があると考える.
2 0 0 0 外用コルチコステロイドの経皮吸収による全身的影響について
- 著者
- 山田 和宏
- 出版者
- 公益社団法人 日本皮膚科学会
- 雑誌
- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.11, pp.1079, 1972 (Released:2014-08-26)
著者は,4種の外用コルチコステロイド剤(0.25%17-α-desoxymethasone,0.2%~0.025% fluocinolone acetonide,0.12% betamethasone 17-valerate,0.02% flumethasone pivalate)を用いて,正常皮膚2例と病的皮膚(尋常性乾癬)10例における全身的影響の有無を下垂体副腎皮質機能と電解質(尿中または血中)の面より検索した.その結果(i)大量の外用コルチコステロイド剤を病的皮膚に,全身の単純塗布で用いた場合とODT療法で用いた場合の両方に,明らかな下垂体副腎皮質系の抑制(循環好酸球数並びに血中コルチコステロイド値の減少,尿中17-OHCS値の低下)がみられ,全身的影響が惹起されることを認めた.その抑制は,処置を中止すると,2~3日で元の値に復帰する事から,一時的である事も判明した.(ii)さらに正常皮膚における検索でも,大量のコルチコステロイド剤をODT療法で用いると,病的皮膚におけると同様に,下垂体副腎皮質系への抑制傾向がみられ,全身的影響出現の可能性を認めた.
2 0 0 0 ウイルス感染症の鑑別法
- 著者
- 日野 治子
- 出版者
- 公益社団法人 日本皮膚科学会
- 雑誌
- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)
- 巻号頁・発行日
- vol.120, no.5, pp.993-1008, 2010-04-20 (Released:2014-11-28)
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 2.物理性蕁麻疹―診断への道すじと難治例への対応―
- 著者
- 牧野 輝彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本皮膚科学会
- 雑誌
- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)
- 巻号頁・発行日
- vol.127, no.8, pp.1751-1755, 2017-07-20 (Released:2017-07-20)
- 参考文献数
- 24
物理性蕁麻疹は皮膚表面の機械的刺激,寒冷曝露,日光照射,温熱負荷,水との接触などにより生じる蕁麻疹の総称である.寒冷蕁麻疹は寒気や冷水にさらされた際に膨疹を生じる蕁麻疹であり,その診断には家族性か後天性か,全身性か局所性かなど系統だった鑑別を要する.また,日光蕁麻疹は太陽光線に曝露した皮膚に限局して膨疹が生じる比較的なまれな蕁麻疹であり,その作用波長は本邦では可視光線であることが多い.一般に日光曝露の回避と抗ヒスタミン薬内服による治療がおこなわれるが,しばしば治療抵抗例を経験する.このような症例に対して近年UVA急速減感作療法の有効性が報告されている.本稿では,寒冷蕁麻疹と日光蕁麻疹に焦点をあて,その診断のポイントや治療について解説する.
2 0 0 0 皮脂排出機能並びにそれの皮表に於ける性状に関する研究
- 著者
- 土屋 明
- 出版者
- 公益社団法人 日本皮膚科学会
- 雑誌
- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.4, pp.295, 1962 (Released:2014-08-29)
皮表脂質は脂腺排泄管から排出されたものと角質層から由来したものとで成立ち,皮表に一種の薄い脂質の膜を形成しているものであるが,この皮表脂膜は皮膚柔軟性の保持,体温放射,乾燥化,細菌侵襲等に対する防禦能としての機能を有し,皮膚生理に重要な役割を演じているものであり,古くからその性状機能等が諸家によつて研究され論じられてきている.近年この皮脂に対して発汗が重大な影響を与えるものとして注目される様になつた.即ち皮表脂膜は脂質と汗のemulsionによつて形成されており,前記の皮膚表面に於ける種々の機能はこのsurface filmがemulsionであるという性状に依つて明解に説明しうると主張されたり,又一方これに対し実験的にこのemulsion説を追求し少なからず疑義を表明している者もあり,未だに皮表脂質と汗の関係に就いては結論的なものが見出されず現状に至つている.私は単位時間内に新たに排出された皮脂をオスミウム酸濾紙により観察し,これによつて皮脂腺の排出程度を推量し,皮脂腺機能の諸問題のうち,その2,3について検討し,更に位相差顕微鏡を用いてsurface filmの性状を観察,検討を加え見るべき知見を得たので諸家の報告と比較検討しつつ独自の見解について報告する.
2 0 0 0 軟膏剤の伸展性・塗布量に及ぼす温度の影響
- 著者
- 大谷 道輝 鏡 真衣 野澤 茜 松元 美香 山村 喜一 江藤 隆史
- 出版者
- 公益社団法人 日本皮膚科学会
- 雑誌
- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)
- 巻号頁・発行日
- vol.122, no.3, pp.613-618, 2012-03-20 (Released:2014-11-13)
- 被引用文献数
- 1
皮膚外用剤は塗布量が効果に影響を与える.この皮膚外用剤の塗布量は基剤や剤形により影響される.温度も塗布量に影響するが,これに関する検討はほとんど報告されていない.そこで,皮膚外用剤の伸展性あるいは塗布量に与える温度の影響について1°Cと30°Cでスプレッドメーターと健常人を用いて調べた.1°Cから30°Cの上昇により油脂性基剤では伸展性は2倍,降伏値は大幅に減少した.油脂性基剤の塗布量は約2倍に増加した.W/O型乳剤性基剤も伸展性や塗布量が同様に増加した.これに対し,水溶性基剤およびO/W型乳剤性基剤では1°Cから30°Cの上昇により伸展性,降伏値はほとんど低下せず,塗布量も変化は認められなかった.これらのことから,患者の塗布量に関する説明では油脂性基剤およびW/O乳剤性基剤では温度による伸展および塗布量への影響を考慮する必要があることが示唆された.
- 著者
- 川島 眞
- 出版者
- 公益社団法人 日本皮膚科学会
- 雑誌
- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)
- 巻号頁・発行日
- vol.123, no.8, pp.1527-1536, 2013-07-20 (Released:2014-10-30)
近年,癌治療における分子標的薬の使用頻度の増加に伴い,その副作用としての皮膚障害への対応が課題となってきている.そこで,分子標的薬による癌治療に随伴する皮膚障害に対する皮膚科医の診療実態や意識についての現状を把握し,今後の課題について考察することを目的として,全国の皮膚科医を対象とした調査を行った.対象と方法:2011年12月~2012年1月に医療従事者向けポータルサイト「CareNet」会員である皮膚科医を対象とし,二度にわたるインターネット調査を行った.結果:分子標的薬に起因する皮膚障害の診療経験の確認を目的とした一次調査で,その診療経験は,勤務医で88.5%(154/174名),開業医で61.0%(61/100名)であった.より広く診療経験者を対象とし,改めて診療の実態や意識を確認することを目的とした二次調査において,診療頻度は開業医では年間5例以下が85%を占めたが,病院勤務医では年間10例前後が多かった.また,病院勤務医では患者の9割近くが他科からの紹介で受診していたが,開業医では自発的受診が7割近くを占めた.治療においては,ステロイド外用剤,テトラサイクリン系抗生物質内服,保湿外用剤を主に使用する医師が大半である一方,抗菌外用剤を主に使用する医師も一定数いることが明らかとなった.皮膚科医のほとんどが,癌診療科・施設との早期からの連携が必要であると認識し,分子標的薬による皮膚障害に対し,主体的に取り組むべきと考えていることが示された.考察:分子標的薬による皮膚障害に対し,多くの皮膚科医が既に取り組んでいる実態が明らかとなった.一方その診療において,癌薬物治療専門科・施設との連携は手探りともいえる.癌患者の治療を支援する観点から,分子標的薬による癌治療に随伴する皮膚障害の有効な治療方法の確立,また,それを実施するため,皮膚科医はその重要な役割を認識し,研鑽を重ねるとともに,癌薬物治療専門科・施設との密な連携に取り組む必要があると考えた.
2 0 0 0 OA 緊急提言
- 出版者
- 公益社団法人 日本皮膚科学会
- 雑誌
- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)
- 巻号頁・発行日
- vol.131, no.5, pp.1107, 2021-04-13 (Released:2021-05-15)
2 0 0 0 フシジン酸耐性黄色ブドウ球菌の急増
- 著者
- 神崎 寛子 秋山 尚範 金本 昭紀子 阿部 能子 山田 琢 荒田 次郎 梅村 茂夫 池田 政身
- 出版者
- 公益社団法人 日本皮膚科学会
- 雑誌
- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)
- 巻号頁・発行日
- vol.99, no.4, pp.507, 1989 (Released:2014-08-11)
我々は1987年1月より1988年10月の間に分離された204株の黄色ブドウ球菌のフシジン酸(FA)に対するMICを測定し,また高知医大で1987年9月から1988年9月に分離された123株の黄色ブ菌のFAに対するMICと比較した.1987年1月から1988年3月の分離菌では5/123(4.1%)に耐性菌(MIC≧12.5μg/ml)が認められたのみであったが,1988年4月より10月の分離菌では42/81(51.9%)の耐性菌が認められた.高度FA耐性株は全てメチシリン耐性菌であった.高知医大ではMIC1.56~3.13μg/mlの株が少数認められたのみであった.高知医大の結果で耐性株が認められていないことよりFA耐性菌の出現には現在のところ地域差があるものと思われた.FAは現在外用剤としてのみ使用されているが,耐性出現の早い薬剤として知られており,このような薬剤を外用剤として使用することは耐性菌を増加させる可能性を強く示唆した.
2 0 0 0 レチノイドの表皮ランゲルハンス細胞に及ぼす影響について
- 著者
- 小林 勝
- 出版者
- 公益社団法人 日本皮膚科学会
- 雑誌
- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)
- 巻号頁・発行日
- vol.93, no.7, pp.763, 1983 (Released:2014-08-20)
レチノイド(etretinate)を CH3/He マウスに連日経口投与し,表皮ラングルハンス細胞(L細胞),ことにその分布密度と形態に及ぼす影響について検討した.L 細胞の分布密度は投与量(4mg/kg および 16mg/kg)と部位(耳,足脈,尾)により若干の差はあるが,ほぼ同様の傾向を示して変動した.すなわち,投与開始直後にL細胞は一過性に増加するが,以後は減少傾向を示し,2週後には最低値となる.しかし,その後投与を続けることにより回復傾向がみられた.このL細胞の分布密度の変動は表皮の厚さがレチノイド投与により変動する経過ときわめてよく一致た.一方,レチノイド投与により胞体が縮少し,樹枝状突起が細長く伸びた L 細胞が多数観察された.足蹠皮膚の垂直切片における観察では,投与2週日以後,基底層から真皮上層にla抗原陽性の樹枝状細胞がみられ,L細胞かあたかも真皮へ脱落しかけているような所見が得られた. 以上の実験を通じて,L 細胞は表皮内において抗原提示細胞としての機能を果すべく,角化細胞と密接な関連を保ちながら,その分布密度を調節し,恒常性を保ちつつあることか考えられた.
2 0 0 0 COVID-19関連皮疹と診断した4例
- 著者
- 野﨑 尋意 小松 成綱 橋本 喜夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本皮膚科学会
- 雑誌
- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)
- 巻号頁・発行日
- vol.131, no.6, pp.1539-1544, 2021-05-20 (Released:2021-05-20)
- 参考文献数
- 10
2020年11月下旬,当院で患者計181人が感染する事態となるCOVID-19クラスターが発生した.うち,皮疹が出現したのは4人だった.全例が何らかの基礎疾患を有しており,中等症以上のCOVID-19肺炎を発症した.皮疹は肺炎に対するステロイド治療の終了や減量に伴って出現しやすい傾向があり,体幹部に多く,性状は一部網状を呈する,紅斑性皮疹あるいは蕁麻疹だった.COVID-19関連皮疹は患者の基礎疾患に起因する皮疹や薬疹などとの鑑別が重要だが,その鑑別は時に困難である.
2 0 0 0 3.ピレスロイド抵抗性アタマジラミ症
- 著者
- 山口 さやか 高橋 健造
- 出版者
- 公益社団法人 日本皮膚科学会
- 雑誌
- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)
- 巻号頁・発行日
- vol.127, no.10, pp.2305-2311, 2017-09-20 (Released:2017-09-22)
- 参考文献数
- 14
日本ではアタマジラミ症に対する治療薬として,ピレスロイド系薬剤のフェノトリン0.4%配合の市販薬のみが認可されている.欧米ではこのピレスロイド系薬剤の無効なアタマジラミが蔓延し,沖縄県でも蔓延していることがわかった.本稿では抵抗性の機序や海外のアタマジラミ治療薬,沖縄県内の取り組みや実際的な駆除法を解説する.ノーベル賞受賞者の大野智博士が開発したイベルメクチンは,抵抗性アタマジラミにも有効であるが,日本では保険適応がなく使用出来ない.
2 0 0 0 3.アタマジラミ症:世界の現状と日本の課題
- 著者
- 山口 さやか 高橋 健造
- 出版者
- 公益社団法人 日本皮膚科学会
- 雑誌
- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)
- 巻号頁・発行日
- vol.129, no.12, pp.2513-2517, 2019-11-20 (Released:2019-11-20)
- 参考文献数
- 12
アタマジラミは,市販されているピレスロイド製剤を用いて家庭内で駆虫してきたため,これまで皮膚科医が介入する機会はほとんどなかった.しかし近年,ピレスロイド製剤で駆虫できない難治性アタマジラミ症が世界中で広がり,日本でも遭遇する機会が増えている.アタマジラミの特徴,治療法,感染対策について解説するとともに,ピレスロイド抵抗性アタマジラミの耐性化機序や日本の現状と,今後期待される薬剤について紹介する.