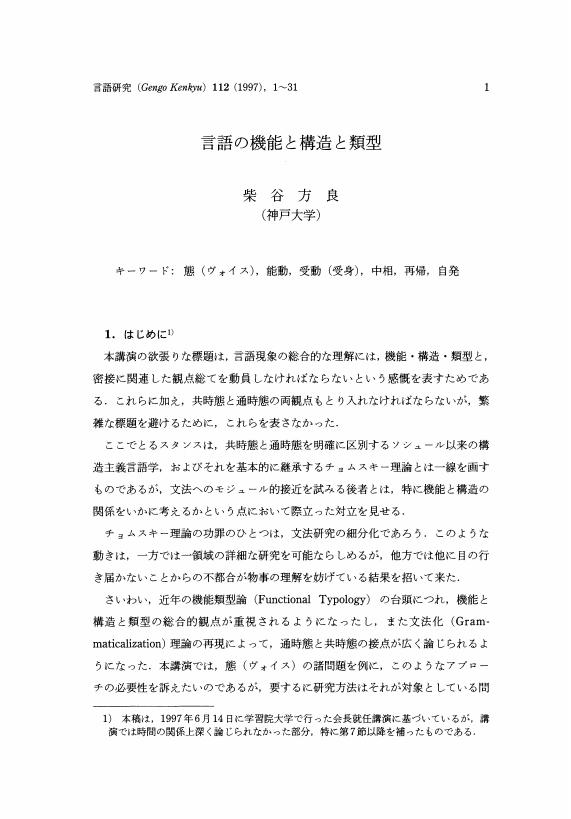5 0 0 0 OA ツツバ語の移動動詞と空間分割
- 著者
- 内藤 真帆
- 出版者
- 日本言語学会
- 雑誌
- 言語研究 (ISSN:00243914)
- 巻号頁・発行日
- vol.136, pp.153-176, 2009 (Released:2021-09-15)
- 参考文献数
- 9
本論文の目的は,ヴァヌアツ共和国のツツバ語で,移動の経路を表す三つの動詞sae「のぼる」,sivo「くだる」,vano「行く,横切る」が何に依拠して使い分けられているのかを明らかにすることである。はじめにこの三つの動詞についての説明を行い,続いてツツバ語話者がツツバ島内を移動する際の移動表現,副都心の置かれるサント島内を移動する際の移動表現,ツツバ島から他島へ移動する際の移動表現について考察する。そしてツツバ語において,移動の経路を表す三つの動詞sae「のぼる」,sivo「くだる」,vano「行く,横切る」が,①物理的な上下による対立,②心理的な上下による対立,③歴史的理由により生じた対立,という三つのカテゴリーにおいて使い分けられていることを示す。さらに,これらのカテゴリーにおける三つの動詞の関係について明らかにする。
5 0 0 0 OA チベット・ビルマ諸語と言語学
- 著者
- 西田 龍雄
- 出版者
- The Linguistic Society of Japan
- 雑誌
- 言語研究 (ISSN:00243914)
- 巻号頁・発行日
- vol.1979, no.76, pp.1-28, 1979-11-30 (Released:2010-11-26)
- 参考文献数
- 37
This paper is an enlarged version of the writer's lecture delivered at the 78th general meeting of the Linguistic Society of Japan. Two subjects are discussed: tonogenesis and ergative constructions in the TB languages. First, the sub-grouping of TB languages is mentioned briefly. With a number of examples the correspondence of cognate words in toneme dialects and tonemeless dialects within both the Chin and Tibetan groups is shown. The writer expresses his opinion concerning tonal development in the Choni dialect of Tibetan.After considering the formation of toneme patterns in the disyllabic words of Lhasa Tibetan, the writer mentions the interesting phenomena of disyllabic words reduced to monosyllables evident in the Choni dialect in China, Dzongkha in Bhutan and Lhomi in Nepal.In the second part he explains the ergative construction of Tibetan and discusses the opposition of ergative and non-ergative constructions. It is known that Tibetan originally had no passive construction as such, but in fact, when a passive meaning is called for, it is formed by the topicalization or focusization of the object of the sentence, as is clear in examples given which contrast with modern Chinese.Finally, the writer points out what were probably ergative forms of Rawang of Northern Burma, Chiang in Ssu-Chuang and Moso in Yunnan; and he assumes the development of the ergative construction in Moso.
5 0 0 0 OA 古代日本語の係り結びコソ
- 著者
- セラフィム レオンA. 新里 瑠美子
- 出版者
- The Linguistic Society of Japan
- 雑誌
- 言語研究 (ISSN:00243914)
- 巻号頁・発行日
- vol.2005, no.127, pp.1-49, 2005-03-25 (Released:2007-10-23)
- 参考文献数
- 66
古代沖縄語のス=siの係り結びと古代日本語のコ乙ソ乙=kosoの係り結びは,已然形で結ぶ強調表現であるところが類似するが,積極的に比較研究されることは少なかった.本稿においては,両者を比較し,日本祖語における原形を*ko#swo(指示詞の*コ乙+形式名詞の*ソ甲)と再構する.そして,有坂第一.法則の適用で,甲類のswoが,先行する乙類のoに母音調和した結果,古代日本語では,kosoとなったと仮説する.ソ甲の部分が甲類で,形式名詞であったとの見解は,従来の近称のコ乙+中称のソ乙との語源と相容れないが,その裏づけとして,(1)沖縄最古の辞書『混効験集』の知見,(2)西日本方言に痕跡を留める形式名詞のス・ソ,(3)機能論,文法化理論の観点からの論証を挙げる.更に,コ乙ソ乙(沖縄ス=si)とカ(沖縄ガ)の係り結びを対照させ,両者の結びがrealisとirrealis(古代日本語は多くが推量の助動詞-(a)m-)に対応する意味を認知論的に考察し,また指示詞から係助詞のようなfbcus particleへの移行は世界の言語の文法化のデータにも合致する点を指摘する.
5 0 0 0 OA タガログ語におけるthetic/categorical判断再訪――対照研究の観点から――
- 著者
- 長屋 尚典
- 出版者
- 日本言語学会
- 雑誌
- 言語研究 (ISSN:00243914)
- 巻号頁・発行日
- vol.156, pp.47-66, 2019 (Released:2020-04-14)
- 参考文献数
- 39
日本語の「は」で標示された主題名詞句とタガログ語などのフィリピン諸語のangで標示された主題名詞句(あるいは主格名詞句)の間に興味深い共通点があることはこれまでに何度も指摘されてきた(Shibatani 1988, 1991; Katagiri 2004, 2006)。その背景には,感嘆文,気候・天候文,存在文など,日本語で主題の「は」が用いられにくい環境で,angもまた使われないという観察がある。さらに近年,Santiago(2013)によって,タガログ語の主題名詞句の分布がthetic/categoricalという判断の区別(Kuroda 1972)で説明できるという説が提案された。本論文では,タガログ語の主題名詞句と日本語の主題名詞句の対照研究を行い,thetic/categoricalの区別でタガログ語と日本語の平行性を捉える仮説に異議を唱える。具体的には,先行研究で既に議論されているデータを再分析し,新しいデータを提示することによって,タガログ語において(i)theticな文における非主題標示はタガログ語に特殊な要因によって説明できること,(ii)theticな文に主題名詞句が出現することも可能であること,さらに(iii)categoricalな文のなかには主題標示が必須ではない文もあることを示す。このように,タガログ語と日本語の共通点は表面的なものであり偶然の産物である。日本語で指摘されるthetic/categoricalという判断の違いによって,タガログ語の主題名詞句の出現・非出現を予測することはできない。
5 0 0 0 OA 言語の機能と構造と類型
- 著者
- 柴谷 方良
- 出版者
- 日本言語学会
- 雑誌
- 言語研究 (ISSN:00243914)
- 巻号頁・発行日
- vol.1997, no.112, pp.1-31, 1997-11-25 (Released:2007-10-23)
- 参考文献数
- 28
5 0 0 0 OA 現代ヘブライ語における母音の長さについて
- 著者
- 栗谷川 福子
- 出版者
- 日本言語学会
- 雑誌
- 言語研究 (ISSN:00243914)
- 巻号頁・発行日
- vol.1987, no.92, pp.95-117, 1987-12-25 (Released:2010-11-26)
- 参考文献数
- 25
5 0 0 0 OA 日本語の「ている」進行形の場所格構造について
- 著者
- 松岡 幹就
- 出版者
- 日本言語学会
- 雑誌
- 言語研究 (ISSN:00243914)
- 巻号頁・発行日
- vol.155, pp.131-157, 2019 (Released:2019-10-02)
- 参考文献数
- 53
本稿は,日本語の「ている」進行形の文について,統語構造が異なる2つのタイプがあると論じる。一方では,「いる」が存在動詞として現れ,その項として主語名詞句と音形のない後置詞を主要部とする後置詞句を選択する。そして,その後置詞句内には,名詞化された節が現れ,その主語が「いる」の主語によってコントロールされるという二重節構造を成す。もう一方では,「いる」が相を表す機能範疇として現れ,単一節構造が形成される。無生名詞を主語とする「ている」進行形の文は,主語が「いる」によって選択されず,常に単一節構造を持つ。これによって,「ている」進行形の有生主語が,「ている」が付く動詞の種類に関わらず,内項の性質を示し得るのに対し,無生主語はそのような特徴を持たないという事実が説明される。さらに,ここで提案する2種類の「ている」進行形は,先行研究で分析されている,バスク語の2種類の進行形に対応すると主張する。
5 0 0 0 OA ヘジェン語の系統的位置について
- 著者
- 風間 伸次郎
- 出版者
- The Linguistic Society of Japan
- 雑誌
- 言語研究 (ISSN:00243914)
- 巻号頁・発行日
- vol.1996, no.109, pp.117-139, 1996-03-20 (Released:2007-10-23)
- 参考文献数
- 27
Hezhen is one of the Tungus-Manchu languages, spoken in China along the Amur river. It has been thought to be a dialect of Nanay. But as seen below, in some phonetic correspondences, Hezhen shows the same characteristics as Tungus-Manchu languages which belong to Ikegami's group II (This grouping is according to Ikegami 1974: Ewen, Ewenki, Solon, and Negidal belong to group I, Udehe and Orochi belong to group II, Nanay, Ulcha, and Uilta belong to group III, Manchu and Jurchen belong to group IV. This article is not referred to Hezhen). The last two correspondences show the unique character of Hezhen compared to all the other Tungus-Manchu languages.Hezhen Ewenki Orochi Nanay(group I) (group II) (group III)xakin xakin xakin paa (*p-) “liver”adi adii adi xado (*x-) “how many”inaki _??_nakin inaki inda (*-nd-) “dog”ti_??_n ti_??_n ti_??_n tu_??_g_??_n (*-_??_g-) “breast”giamsa giramna giamsa girmaksa (*-ms-) “bone”nasa nanna nasa nanta (*-ns-) “skin”xulsa xulla xukta polta (*-ls-) “quilt”x_??_r_??_n x_??_n_??_n xe_??_n p_??_i_??_n (*-r_??_-) “knee”
5 0 0 0 OA アフリカ人のコミュニケーション ―音・人・ビジュアル―
- 著者
- 梶 茂樹
- 出版者
- 日本言語学会
- 雑誌
- 言語研究 (ISSN:00243914)
- 巻号頁・発行日
- vol.142, pp.1-28, 2012 (Released:2021-09-15)
- 参考文献数
- 12
サハラ以南のアフリカは,いわゆる無文字によって特徴づけられてきた。しかし無文字社会というのは,文字のある社会から文字を除いただけの社会なのだろうか。実際に現地で調査をしてみると,そうではなく,われわれの想像もつかないようなものがコミュニケーションの手段として機能していることがわかる。本稿では,私が現地で調査したもののうち,モンゴ族の諺による挨拶法と太鼓による長距離伝達法,テンボ族の人名によるメッセージ伝達法と結縄,そしてレガ族の紐に吊るした物による諺表現法を紹介し,無文字社会が如何に豊かな形式的伝達法を持ちコミュニケーションを行っているかを明らかにする。無文字社会では,言語表現が十分定形化せず,いわば散文的になるのではないかという一般的想像とは逆に,むしろ彼らのコミュニケーションは形式的であり韻文的である。それは文字がないことへの対応様式であり,共時的に,そして世代を通して伝達をより確かなものにする努力の表れと理解できるのである。
5 0 0 0 OA 秋田県横手市方言の有核動詞に関するアクセント規則 ――弱強フットを用いた分析――
- 著者
- 菅沼 健太郎
- 出版者
- 日本言語学会
- 雑誌
- 言語研究 (ISSN:00243914)
- 巻号頁・発行日
- vol.161, pp.63-89, 2022 (Released:2022-05-20)
- 参考文献数
- 26
本論文では秋田県横手市方言の有核動詞の過去形,非過去形のアクセントパターンについて論じる。同方言の有核動詞のアクセントは,過去形におけるそのパターンが多様である点,さらにその一方で非過去形では一貫したパターンが現れる点で特徴的である。具体的には,過去形では語幹の拍数や末子音の種類などに応じて次々末拍,次末拍,末拍のいずれかに下がり目が置かれる。その一方で非過去形では一貫して次末拍に下がり目が置かれる。本論文ではこれらのアクセントパターンが弱強フットを中核とした規則群によって導かれることを示す。さらに,検討課題が残されているものもあるが,本論文で提案した規則が形容詞のアクセント,および他の動詞活用のアクセントを説明するためにも有効であることを示唆する。
5 0 0 0 OA 標準語形の計量的性格と地理的分布パターン
- 著者
- 井上 史雄
- 出版者
- 日本言語学会
- 雑誌
- 言語研究 (ISSN:00243914)
- 巻号頁・発行日
- vol.1990, no.97, pp.44-72, 1990-03-25 (Released:2010-11-26)
- 参考文献数
- 52
- 被引用文献数
- 3
In this paper, a geographical data matrix of dialectal forms which coincide with Standard Japanese forms was processed to ascertain the relation between their geographical distribution patterns and the dates of their appearance in documents. 80 Standard Japanese forms which are found in the “Linguistic Atlas of Japan” were classified by the centuries of their appearance in documents. Total values of usage for each prefecture were calculated. The resulting maps for four historical eras show that the oldest forms show a wide distribution throughout Japan, and that the newer forms show a small distribution area around Tokyo. The Kansai region where the old capital of Kyoto was situated shows less usage of standard forms.By referring to Tokugawa (1972), it was maintained that the forms had been produced continuously in the Kansai region in pre-modern ages. The forms, however, were not adopted as Standard Japanese, because the center of Japanese culture moved east to Edo (modern Tokyo). Thus a model of lexical diffusion from cultural centers was presented.Some other statistical characteristics of lexical nature were also examined, using multi-variate analyses. The time of an item's appearance in documents shows a close relation to its frequency of usage. Hayashi's quantificational theory type 3, cluster analysis and factor analysis showed that forms which are frequently used appear early in literature, and that forms which are rarely used appear later. The logical relation of historical changes in vocabulary was also discussed.
5 0 0 0 OA 第8回国際言語学者会議
- 著者
- 泉井 久之助
- 出版者
- 日本言語学会
- 雑誌
- 言語研究 (ISSN:00243914)
- 巻号頁・発行日
- vol.1957, no.32, pp.121-136, 1957-12-31 (Released:2010-11-26)
4 0 0 0 OA 認知言語学と哲学 ―言語は誰の何に対する認識の反映か―
- 著者
- 酒井 智宏
- 出版者
- 日本言語学会
- 雑誌
- 言語研究 (ISSN:00243914)
- 巻号頁・発行日
- vol.144, pp.55-81, 2013 (Released:2022-03-08)
- 参考文献数
- 41
「言語は人間の世界認識の反映である」という認知言語学的な主張(以下,主張P)は次の二つの問題を提起する。(i)人間が何を認識するのか。(ii)誰が世界を認識するのか。(i)に関して,認知言語学では,外的世界と内的世界の二元論が前提とされる。しかし,認知言語学者が外的世界に関する事実と呼ぶものは,実際にはわれわれが解釈したかぎりでの世界の記述にすぎず,同じことを一元論のもとで述べなおすことができる。それゆえ,認知言語学の二元論は十分に正当化されているとは言えない。(ii)に関して,主張Pを受け入れれば,言語間の変異はすべて話者の世界認識の違いによるという結論に至る。しかし,この結論は逆説的にも「話者の認識から独立した意味」という客観主義的意味観を帰結しうる。かくして,主張Pと対照言語学とのあいだに緊張関係が生じることになる。
- 著者
- S. I. HARADA
- 出版者
- The Linguistic Society of Japan
- 雑誌
- 言語研究 (ISSN:00243914)
- 巻号頁・発行日
- vol.1971, no.60, pp.25-38, 1971-12-25 (Released:2010-11-26)
- 参考文献数
- 8
Variations within a single dialect have often been referred to as ‘free variations’. But this terminology is quite a bit misleading, since it tends to imply that an individual speaker allows any of the variants. Recent investigations have revealed that the so-called ‘free variations’ may not in fact be free variations for an individual speaker. There are cases where an individual speaker consistently follows one variation although the dialect as a whole allows more than one variant. Variations of this sort, which cannot be accounted for in terms of geographic nor of sociological divisions, we shall henceforth refer to as ‘idiolectal variations’.The existence of idiolectal variations in this sense is not a new discovery, but systematic investigations have not been made until quite recently. For some of the results of work on idiolectat variations in English, see Carden (1970), Elliott et al.(1969), and Greenbaum and Quirk (1970). Unfortunately, however, it seems to me that there has appeared no such work on like phenomena in Japanese. The present paper will present one area of syntax of the Tokyo dialect of Japanese which clearly exhibits an idiolectal variation and will discuss how general linguistic theory could shed light on such phenomena.
4 0 0 0 OA Wh句と焦点句の共起制限について
- 著者
- ジュリアノ ボッチ ルイジ リッツィ 斎藤 衛
- 出版者
- 日本言語学会
- 雑誌
- 言語研究 (ISSN:00243914)
- 巻号頁・発行日
- vol.154, pp.29-51, 2018 (Released:2019-06-04)
- 参考文献数
- 52
イタリア語左方周縁部における焦点句とwh句の共起は,主文では文法的に不適格であるが,補文内では許容度が向上する。また,焦点句とwh句の共起制限は,焦点句の文法機能によっても左右される。例えば,焦点句が間接目的語であれば,直接目的語の場合に比べて許容度が高い。本論文では,まず,これらの一般化を,文法性判断に関する実験研究により裏付ける。次に分析を提示して,特に,主文と補文の非対称性を,統語と意味のインターフェイスにおける焦点文,wh疑問文の構造から導く提案を行う。この分析は,一般的に二重焦点が排除されることを含意するが,最後に日本語の関連する現象を取り上げて,その普遍性を検証する。具体的には,wh疑問文において観察される介在効果が,同様の分析により説明されること,また,いわゆる多重焦点分裂文がこの分析と矛盾するものではないことを示す。
4 0 0 0 OA 話題化
- 著者
- 宮川 繁
- 出版者
- The Linguistic Society of Japan
- 雑誌
- 言語研究 (ISSN:00243914)
- 巻号頁・発行日
- vol.152, pp.1-29, 2017 (Released:2017-12-29)
- 参考文献数
- 66
Chomsky(1977)は,CPの上にトピックのための特別なポジションがあると議論したが,本論文ではこの考え方をいくつかの観点から考察する。まず第1に,英語,日本語,スペイン語の3言語において,いわゆるAboutness topicがこのポジションに入ることを示す。第2に,このトピック・ポジションは主節では自由に現れるが,従属節ではHooper and Thompson(1973)によって特定されたある種の述語としか共起しないことを示す。Villalta(2008)のスペイン語の仮定法の分析に基づき,トピック・ポジションの従属節における制限を,従属節とそれを選択する述語の意味的特性から説明する。最後に,いわゆるContrastive topicとFamiliar topicの分布が言語によって異なることを示し,この言語間のバリエーションがStrong Uniformity(Miyagawa 2010, 2017)から予測できることを指摘する。
4 0 0 0 OA 日本語の量を表す形容詞の意味体系と量カテゴリーの普遍性
- 著者
- 久島 茂
- 出版者
- The Linguistic Society of Japan
- 雑誌
- 言語研究 (ISSN:00243914)
- 巻号頁・発行日
- vol.1993, no.104, pp.49-91, 1993-09-25 (Released:2007-10-23)
- 参考文献数
- 27
This paper argues that basic dimension adjectives are divided into two classes according to whether they refer to “object” or “place”. The former are systematized according to the feature of the shape of the object, and the latter the relation of the place to its surroundings.There are conceptually six dimension categories of objects. We will use the following signs analogized to phonetic signs: [A] stands for the volume of a box, [I] the length of a rod, [U] the thickness of a board, [E] the extension of a board, [O] the thickness of a rod, and [_??_] the width of a belt.The six categories have the following system and hierarchy which are based on the developement of visual perceptions and oppositions between categories: (As to the length of sides, let longest_??_intermediate_??_shortest).[P] → [Q] means that if a language contains words /Q/ (=a pair of antonyms), it must also contain words /P/. (The kernal meaning of words /p/ (/Q/) is [P] ([Q]).) Some dialects in Kyusyu have only /A/ /I/ /U/, which correspond to [A•E•0•_??_], [I], [U] respectively. Standard Japanese has /A/ / I / /U/ /0/ corresponding to [A•E], [I] [U], [O•_??_] respectively.
4 0 0 0 OA 「かきまぜ」とLFの再構成
- 著者
- 西垣内 泰介
- 出版者
- The Linguistic Society of Japan
- 雑誌
- 言語研究 (ISSN:00243914)
- 巻号頁・発行日
- vol.2002, no.121, pp.49-105, 2002-03-25 (Released:2007-10-23)
- 参考文献数
- 21
本論文は日本語で「かきまぜ」を受けた名詞句がLFでの再構成reconstructionにより文中のさまざまな位置で解釈を受ける可能性があることを主張する.まず,移動を受けた名詞句はD構造位置だけでなくCPやvPの「端」(edge)で再構成を受けることを示す.この主張の基盤となるのは束縛とスコープに関わる事実である.次に,LFでの再構成は束縛理論の制約を受けることを示す.再構成はさまざまな位置で名詞句を解釈することを許すが,その可能性の範囲は束縛条件AとCによって狭められるのである.さらに,LF再構成は指示の非透明性を引き出す動詞など,スコープに関与する要素と相互関係を持つが,このような関係も束縛条件によって制約される.
4 0 0 0 OA 音韻交替と意義分化の関係について
- 著者
- 鈴木 孝夫
- 出版者
- The Linguistic Society of Japan
- 雑誌
- 言語研究 (ISSN:00243914)
- 巻号頁・発行日
- vol.1962, no.42, pp.23-30, 1962-10-31 (Released:2013-05-23)
- 参考文献数
- 4
In the vocabulary of sound symbolism of Present-day Japanese, there are a great many examples of word-pairs such as kira-kira: gira-gira, both of which denote substantially the same thing (or event), but connote differently. The denotata of these two are the same sense-impression we obtain from looking at some light-giving object e. g. the sun, and the connotatum of the former is, broadly speaking, our appreciation of the experience, whereas that of the latter seems to be a certain sense of displeasure, if not of disgust. Here we find our emotive attitude towards the event reflected faithfully in a contrastive sound pair; k: g, thus the expressive value of sounds peculiar to Japanese is exploited to the full. The kind of naturalistic connection here illustrated between the meaning of a word and its sound, however, does not normally exist outside the sphere of onomatopoeia in a wide sense of the term. But the author points out in this article that there are a number of word-pairs, mostly of colloquial usage, which, having nothing to do with onomatopoeia, can be regarded in their semantic structure as close parallels to the example above cited. A case in point is the pair; tori: dori. Now tori here means a bird or a chicken looked on as an edible thing, and dori stands for the inedible part, i. e. lungs and intestines, of a bird. One more example; hure: bure. A bure is trembling in general. A bure for a trembling of the hand as one takes pictures. To these are found corresponding verbs as well. Discussing these and other similar pairs in some detail, the author concludes that the functioning of morphophonemic contrasts of this kind are of two levels. As for denotative meaning, the contrast t: d etc. has an associative function. As for connotative meaning the same contrast has a dissociative, i. e. distinctive function.
4 0 0 0 OA 英語の軽動詞構文について
- 著者
- 天川 豊子
- 出版者
- The Linguistic Society of Japan
- 雑誌
- 言語研究 (ISSN:00243914)
- 巻号頁・発行日
- vol.2000, no.118, pp.29-54, 2000-12-25 (Released:2007-10-23)
- 参考文献数
- 17
The aim of the present paper is to specify the type of verb which can occur in have/ take+a+V constructions in British English, particularly that spoken in Australia. Two factors are involved in the verb selection: one is the a+V, where a signifies "a" or "an" and V signifies an appropriate verb. The other factor is the construction as a whole.It is argued that since a+V in have/ take + a+V sentences defines the aspect of the verb, it is the a+V alone that determines the possible verbs appearing with it, whether the main verb is have or take. It is also argued that the two constructions have their own respective constructional constraints determined in part by the meanings of the main verbs.Jespersen (1909-49: Part VI) coined the phrase "light verbs" to refer to have and take in have l take+a+V constructions . Cattell (1984: 2) observes that these verbs signify only tense and number and so are of relatively small importance, semantically speaking. However, this paper shows that these light verbs do contribute significantly to the semantics of sentences including them.