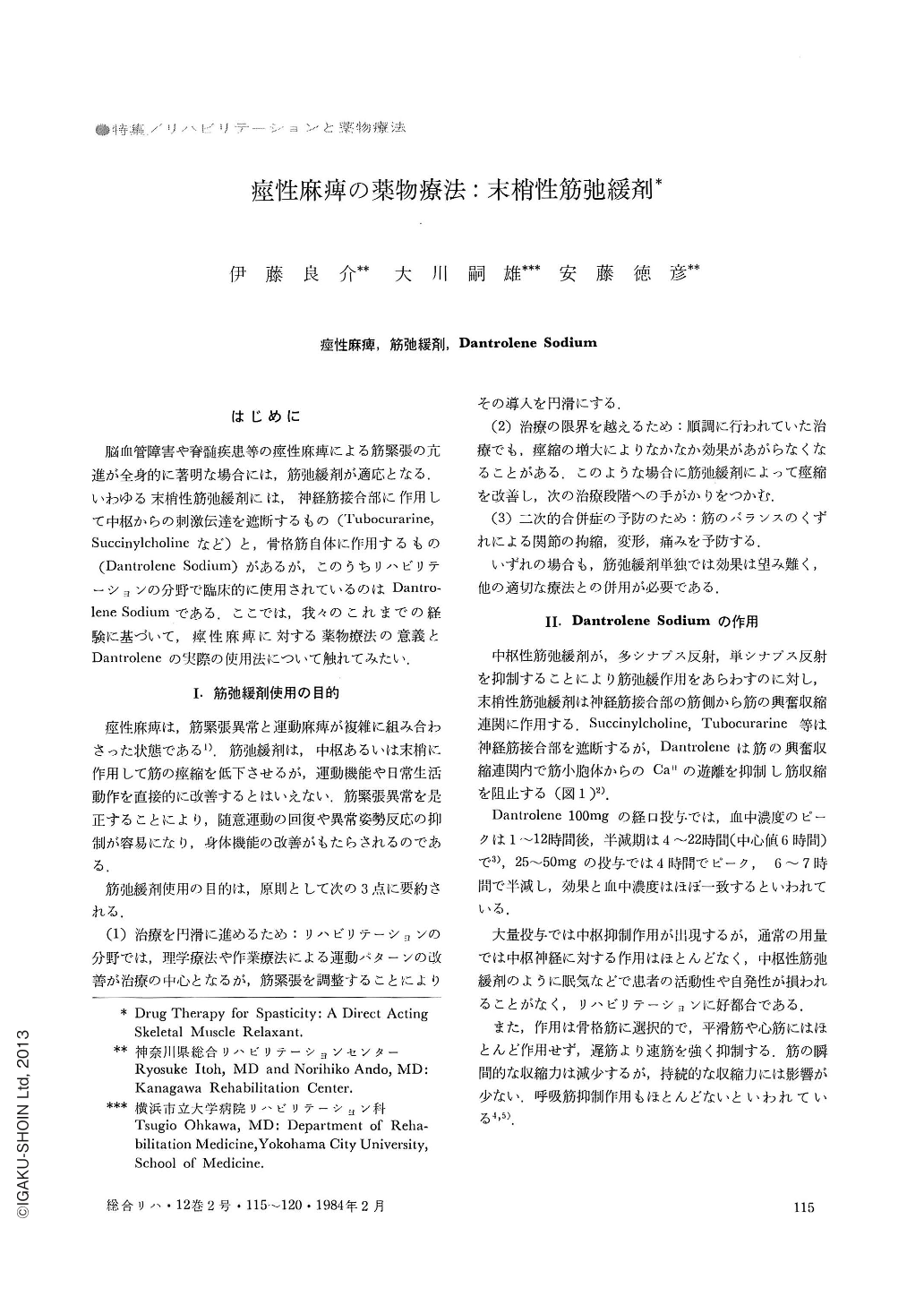1 0 0 0 OA 直観的な道徳判断における知覚・認知処理の役割
- 著者
- 白井 理沙子 小川 洋和 R. Shirai Hirokazu Ogawa
- 雑誌
- 関西学院大学心理科学研究 = Kwansei Gakuin University Bulletin of Psychological Science Research (ISSN:21876355)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, pp.15-22, 2020-03-25
1 0 0 0 ナトリウム恒常性維持中枢の神経回路構造と機能の解明
Naxナトリウムチャンネルの個体における生理機能を解析し、体液ナトリウム濃度検出中枢を特定する目的で、野生型マウスとNax遺伝子ノックアウトマウスについて塩分摂取行動を調べた。通常状態と脱水状態それぞれのマウスに水と食塩水を同時に提示し、各摂取量を調べた。複数の濃度の食塩水について検討したところ、通常状態においてはいずれのマウスも0.3Mを超えると、水に対する食塩水摂取量の割合が減少した。脱水状態においては、野生型マウスは、より低濃度の食塩水に対しても回避行動を示したが、ノックアウトマウスは絶水前と同様に0.3M付近まで水と食塩水を区別無く摂取した。次にマウスの脳室へ高張食塩水を注入し、脳室周辺部の体液Na濃度を上昇させると、野生型マウスは脱水時と同様の塩分回避行動を示した。一方、ノックアウトマウスでは脱水時の塩分回避行動が失われており、Naxによる体液Naレベル検出は、脳室周囲器官の内のいずれかの部域において行われていることが明らかとなった。そこで、Nax遺伝子を組み込んだアデノウィルス発現ベクターを作成し、ノックアウトマウスの脳室周辺へ導入し、塩分摂取行動を観察した。その結果、CVOsの内、脳弓下器官(SFO)にウィルスが感染した場合にのみ野生型と同様の、脱水時における塩分回避行動が回復した。SFOは過去の脳部分破壊実験から体液Na濃度検出への関与が指摘されており、Naxが発現する部位である。同じく第三脳室前壁に位置する終板脈管器官(OVLT)も、これまで体液Na濃度検出に関与すると考えられていたが、本実験においてNax遺伝子を導入しても行動は回復しなかった。以上より、体液Na濃度検出及び水と塩分の摂取行動制御中枢はSFOであり、その機能にNaxが必須の役割を果たしていることが初めて証明された。
平成30年度においては、治療抵抗性うつ病の患者群を対象とした集団コンパッション・フォーカスト・セラピープログラムのランダム化比較試験を継続した。加えて、Compassion Engagement and Action Scaleの日本語版についての論文化が進行中である。集団コンパッション・フォーカスト・セラピーは全12回で構成されており、コンパッション・フォーカスト・セラピー開発者であるPaul Gilbert博士からスーパービジョンを受けながら進行した。これまでに予定されている被験者数の3分の2がエントリーし、治療を受けている。また、研究成果の報告にあたっては、コンパッション・フォーカスト・セラピーに関する事例研究として、Emotion Processing and the Role of Compassion in Psychotherapy from the Perspective of Multiple Selves and the Compassionate SelfとA Case Report of Compassion Focused Therapy (CFT) for a Japanese Patient with Recurrent Depressive Disorderを公表した。さらに日本認知療法・認知行動療法学会のシンポジウムにおいてコンパッション・フォーカスト・セラピーについての発表をした。また、認知療法研究において、コンパッション・フォーカスト・セラピーに関する総説論文を掲載した。その他、マインドフルネスを医学的にゼロから解説する本においてコンパッション・フォーカスト・セラピーに関する章を執筆し、認知行動療法事典においてもコンパッション・フォーカスト・セラピーについて執筆されたものが公開予定である。
- 著者
- 巧 舟 麻耶 雄嵩
- 出版者
- 早川書房
- 雑誌
- ハヤカワミステリマガジン
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.6, pp.216-219, 2015-09
1 0 0 0 OA 明治時代に歌われた聖歌・讃美歌
- 著者
- 金谷 めぐみ 植田 浩司
- 出版者
- 西南女学院大学
- 雑誌
- 西南女学院大学紀要 (ISSN:13426354)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.59-70, 2018-03-01
キリシタン音楽、カトリックの讃美の歌声が日本から消えて200 有余年(鎖国・禁教時代)、ペリーの来航(1853)を機に、幕末・明治の開国の時代を迎えた。明治新政府は、キリスト教禁止の幕府政策を継承したが、明治6年に禁教令を廃止し、信教の自由を認めた。来日したカトリック教会と正教会、そしてプロテスタント教会の宣教師たちは、西洋文明を伝え、キリスト教の伝道と教育活動を展開し、日本の社会はキリスト教とその音楽に再会した。 日本における礼拝を執り行うために、また日本人が讃美するために、各教会は聖歌集および讃美歌集を出版した。とくにプロテスタント教会の讃美歌の編集では、日本語と英語の性質の異なる言語において、五線譜の曲に英語を翻訳した日本語の歌詞をつけて、曲と歌詞とのフレージングとアクセントを合わせることに努力が払われた。 本総説において、著者らは、明治時代に日本で歌われたカトリックの聖歌と正教会の聖歌、そしてプロテスタント教会の讃美歌について楽譜付讃美歌が出版された経緯を記し、文献的考察を行った。
1 0 0 0 OA 島崎藤村と西洋音楽 ―付 ・ 新資料藤村原稿「耳の世界」(明治学院大学図書館所蔵)紹介―
- 著者
- 岩田 ななつ
- 出版者
- 明治学院大学言語文化研究所
- 雑誌
- 言語文化 (ISSN:02881195)
- 巻号頁・発行日
- no.29, pp.30-60, 2012-03-30
【特集】近代日本と西洋音楽
1 0 0 0 OA 西南日本におけるフィリピン海プレートの沈み込みと重力異常
- 著者
- 山本 明彦
- 出版者
- 日本測地学会
- 雑誌
- 測地学会誌 (ISSN:00380830)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.2, pp.215-225, 1989-06-25 (Released:2011-03-01)
- 参考文献数
- 22
最近の深発地震の研究から,西南日本において南海・駿河トラフに沿って沈み込むリフィリピン海プレートは,東海地方と紀伊半島で南に凸の等深発地震面を持ち,これらの境界ではcuspを形成していることが明らかになってきた.一方,濃尾平野から琵琶湖にかけての広い地域でブーゲ異常が負になり,特に強い負の領域が濃尾平野と琵琶湖周辺にあることは以前より注目されてきた.本論文では稠密重力データを最新の地震学的成果と結びつけ,東海~近畿地方におけるプレートの沈み込み帯での重力異常を調べた.地下深部構造とそこから期待されるブーゲ異常について細かく考察するために堆積物や海水の影響を取り去った.濃尾平野および近江盆地では,深層ボーリングデータにより基底までの深さと堆積層の密度を推定した.琵琶湖の湖水の影響についても湖底地形をコンタで与え,三次元タルワニ法で計算した.伊勢湾から太平洋にかけての海上・海底の重力データに対しては海底地形を与えて海水の補正を行なった.得られた修正ブーゲ異常図では琵琶湖付近に依然として負の領域が残り,その値は-40mGalに達することがわかった.この量をモホ面の起伏で説明すると中部山岳と同程度となる.この残差ブーゲ異常をフィリピン海プレートの沈み込みに関連づけて説明してみた.フィリピン海プレートの海洋地殻は玄武岩質のまま沈み込み,伊勢湾から若狭湾にかけて大陸地殻に接している.この海洋性地殻を含めたプレートの三次元モデルから計算したプレートの重力効果により,琵琶湖を中心とした負のブーゲ異常をうまく説明することができた.琵琶湖付近での残差ブーゲ異常はフィリピン海プレートの上部にある比較的軽い海洋地殻の浅いもぐりこみのために,見掛け上,地殻が厚くなることによって生ずると考えられる.これにより,(見掛け上)モホ面が深くなっていることも地殻底地震の震源面がせりあっていることもうまく説明できた.
1 0 0 0 OA スイス山岳地域の「日本人劇」
- 著者
- 宮下 啓三
- 出版者
- 日本演劇学会
- 雑誌
- 演劇学論集 日本演劇学会紀要 (ISSN:13482815)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.385-406, 1999-09-30 (Released:2019-11-11)
Late in February 1863 a play called Switzerland in Japan was performed on a temporary open-air stage in the city Schwyz in Switzerland, which happened to be the first instance of the traditional performances called “the Play of the Japanese” (die Japanesenspiele). It was a kind of Fastnachtspiel (carnival play) and was not necessarily meant to be a friendly sign to Japan but, rather, a criticism to the then ongoing attempt to establish the treaty between Switzerland and the Japanese Edo Government. But it started the tradition of “the Play of the Japanese”. Its basic structure consists of the following facts: (1) the town of Schwyz is called Yeddo (Edo), (2) people of Schwyz are called Japanese, (3) on the temporary stage a play by the court poet of Japan is performed in front of the Japanese Emperor and Emperess. This paper is the result of the investigation on the tradition of this unique play.
1 0 0 0 OA 国際労働安全衛生統計の調べ方、見るべきポイント、参考になる情報ソース等について
- 著者
- 唐沢 正義
- 出版者
- 公益財団法人 産業医学振興財団
- 雑誌
- 産業医学レビュー (ISSN:13436805)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1, pp.1, 2020 (Released:2020-05-08)
国際的な及び主要な国別の労働安全衛生統計を概観し、ILOSTAT(国際労働機関統計)におけるSafetyandHealthatWork(職場における労働安全衛生統計)及びEurostat(欧州連合統計)におけるHealthandsafetyatwork(hsw)(健康安全統計)の使い方、国際的な及び国別の労働安全衛生統計(その解説等を含む。)の調べ方のコツ及び見方(見るべきポイント)、これらの著作権(copyright)等に関して解説した。また、国際的な並びに主要な国別の労働安全衛生統計の代表的なものの例及びこれらの情報ソースを紹介した。
1 0 0 0 OA エル・システマの研究(下) : 刑務所におけるオーケストラ活動の矯正教育的側面を中心に
- 著者
- 太田 和敬
- 出版者
- 文教大学
- 雑誌
- 人間科学研究 = Bulletin of Human Science (ISSN:03882152)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.39-65, 2015-03-01
El Sistema, or “the system,” is an orchestra movement financially supported by the government of Venezuela. The movement has garnered praise for the education and musical training it provides, and it has also garnered praise for protecting children who live in dangerous areas and for the music education programs it conducts in correctional facilities. The current study evaluates how joining an orchestra and playing classical music corrects the behavior of juvenile delinquents and adult offenders in prison. Findings indicate that rigorous training, cooperation, and responsibility foster self-esteem, teamwork, and social skills. Moreover, public performances and applause from friends and family encourage confidence and pride. These benefits facilitate a subsequent return to and reintegration into the community. These findings suggest that correctional education requires affirming aspects as well as rehabilitative aspects, such as encouraging reflection and/or restitution.
1 0 0 0 OA 明治期の津軽地方における讃美歌の受容 : 明治初期から三十年代前半まで
- 著者
- 安田 寛 北原 かな子
- 出版者
- 弘前大学教育学部
- 雑誌
- 弘前大学教育学部紀要 (ISSN:04391713)
- 巻号頁・発行日
- no.83, pp.77-85, 2000-03-31
学制発布後も遅々として進まなかった公立の唱歌教育に対し,キリスト教の宣教師達は,各地で日本人に讃美歌を教え続けた。したがって,日本人と洋楽受容の問題を考察する際,音楽取調掛と文部省が中心となった音楽教育のみではなく,日本各地で行われたキリスト宣教師達による讃美歌教育の影響を無視することはできないのである。筆者等は以上のような問題意識によって,早くからキリスト教布教が盛んに行われた津軽地方を対象として,洋楽受容に関する研究を重ねてきた。本稿は,津軽地方での讃美歌の受容,特に実際に歌った人々がどの様に受け止めたのか,という意識を窺わせる資料を紹介し,明治期の地方における洋楽受容の一端を明らかにしようとするものである。
1 0 0 0 OA 音楽表現と音楽教育の新しい出発点 : 鍵盤楽器調律法の問題
- 著者
- 平島 達司
- 出版者
- 松蔭女子学院大学
- 雑誌
- 研究紀要. 人文科学・自然科学篇 = Shoin review (ISSN:02886162)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.1-20, 1980-12-28
1 0 0 0 OA アメリカにおけるパフォーミングアーツの習得過程に関する比較研究
- 著者
- 西島 千尋
- 出版者
- 金沢大学人間社会研究域附属国際文化資源学研究センター = center for Kanazawa cultural resource studies / 金沢大学国際文化資源学研究センター
- 雑誌
- 金沢大学文化資源学研究 = Kanazawa cultural resource studies (ISSN:2186053X)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.106-116, 2013-01-01
1 0 0 0 東京が日本の首都になった遠因は蔚山にあり?
- 著者
- 室井 康成
- 出版者
- 韓国・朝鮮文化研究会 ; 2002-
- 雑誌
- 韓国朝鮮の文化と社会
- 巻号頁・発行日
- no.15, pp.158-160, 2016-10
1 0 0 0 OA PU Classificationによるナノデバイス出力信号からのDNA塩基パルスの抽出
- 著者
- 吉田 剛 大城 敬人 鷹合 孝之 谷口 正輝 鷲尾 隆
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第31回全国大会(2017)
- 巻号頁・発行日
- pp.2I3OS10a3, 2017 (Released:2018-07-30)
一分子計測技術に期待が高まっている.ただし計測には常にノイズ混入という問題がつきまとい,これはナノスケールにおいて非常に顕著となる.我々はPU Classificationを用いてノイズのみデータを学習することで,実測データからノイズのみを除去し試料データを適切に取得することを試みた.特に研究開発中の一分子DNAシーケンサに応用した.このノイズ除去効果の有無による識別精度の差異について報告する.
1 0 0 0 痙性麻痺の薬物療法:末梢性筋弛緩剤
はじめに 脳血管障害や脊髄疾患等の痙性麻痺による筋緊張の亢進が全身的に著明な場合は,筋弛緩剤が適応となる.いわゆる末梢性筋弛緩剤には,神経筋接合部に作用して中枢からの刺激伝達を遮断するもの(Tubocurarine,Succinylcholineなど)と,骨格筋自体に作用するもの(Dantrolene Sodium)があるが,このうちリハビリテーションの分野で臨床的に使用されているのはDantrolene Sodiumである.ここでは,我々のこれまでの経験に基づいて,痙性麻痺に対する薬物療法の意義とDantroleneの実際の使用法について触れてみたい.
1 0 0 0 IR 債権売買,債権譲渡担保における取立権能
- 著者
- 宮川 不可止 Fukashi Miyagawa 京都学園大学法学部
- 出版者
- 京都学園大学法学会
- 雑誌
- 京都学園法学 (ISSN:09164715)
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, no.1, pp.27-52, 2006
1 0 0 0 OA 日本にはなぜ Ofsted がないのか
- 著者
- 前川 喜平
- 出版者
- 日本教育政策学会
- 雑誌
- 日本教育政策学会年報 (ISSN:24241474)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.68-71, 2019 (Released:2020-06-20)
In Japan there was no education decay equivalent to what took place in Britain. Japanese schools are not independent corporations like British schools. School choice is not allowed in Japanese compulsory education. These are the reasons why there is no Ofsted in Japan.
- 著者
- 藤川 顕寛
- 出版者
- 日本白内障学会
- 雑誌
- 日本白内障学会誌 (ISSN:09154302)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.38-40, 2020 (Released:2020-07-08)
- 参考文献数
- 2