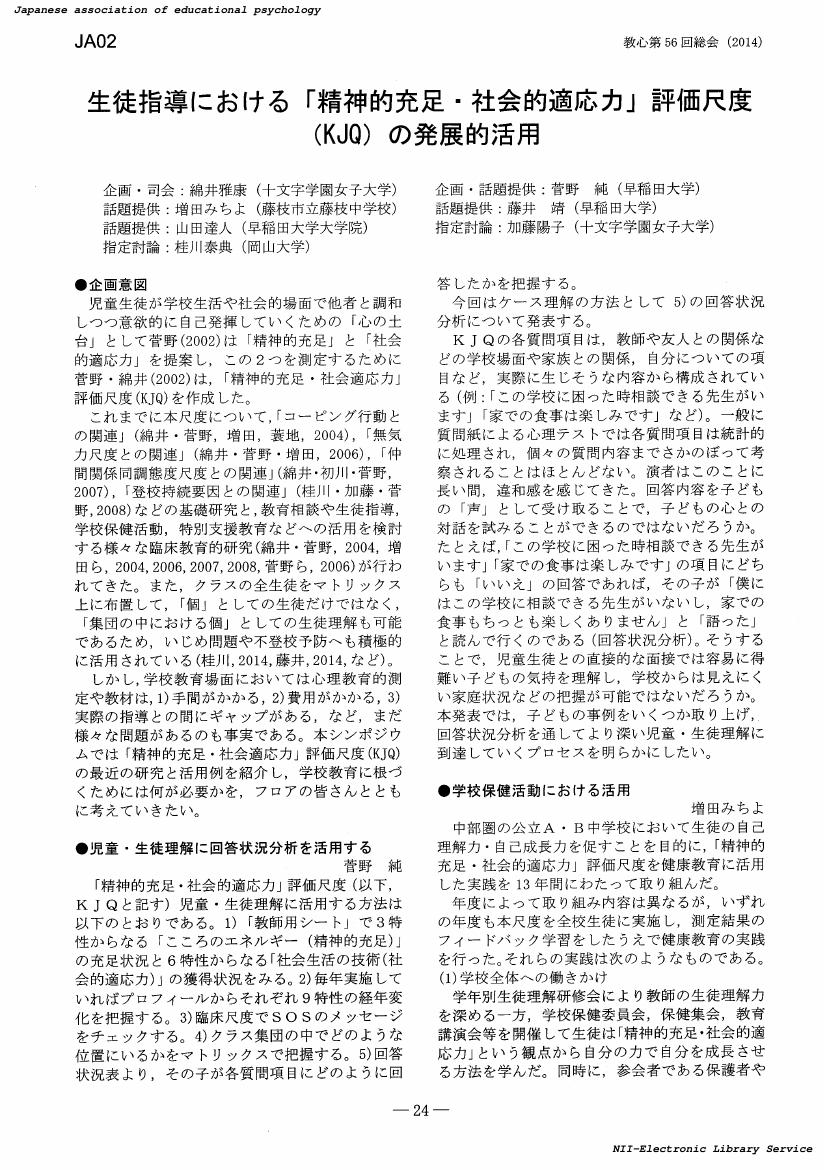1 0 0 0 職業としての新聞記者
- 著者
- 武山 泰雄
- 出版者
- 日本新聞協会
- 雑誌
- 新聞研究 (ISSN:02880652)
- 巻号頁・発行日
- no.257, pp.43-55, 1972-12
1 0 0 0 ミサイル予算と米国景気
1 0 0 0 米国経済の動向
- 著者
- 武山 泰雄
- 出版者
- 関西経済連合会
- 雑誌
- 経済人 (ISSN:09108858)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.3, 1956-01
1 0 0 0 論調に見るアメリカの景気
- 著者
- 武山 泰雄
- 出版者
- 日本評論社
- 雑誌
- 経済評論 (ISSN:02878801)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.9, 1958-07
1 0 0 0 アベグレン報告の背景
- 著者
- 武山 泰雄
- 出版者
- 中央公論社
- 雑誌
- 別冊中央公論 経営問題 (ISSN:04092465)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.4, pp.128-136, 1964-12
1 0 0 0 ヒロヒト天皇の虚実
- 著者
- 武山 泰雄
- 出版者
- 渋沢栄一記念財団
- 雑誌
- 青淵 (ISSN:09123210)
- 巻号頁・発行日
- no.663, pp.48-51, 2004-06
1 0 0 0 IR 武山泰雄著 アメリカ資本主義の構造 : 寡占経済とその社会意識
- 著者
- 原 豊
- 出版者
- 慶應義塾経済学会
- 雑誌
- 三田学会雑誌 (ISSN:00266760)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.10, pp.926(86)-931(91), 1958-10
書評及び紹介
1 0 0 0 関西国際空港の一期島と二期島におけるトノサマバッタの大発生と管理
関西国際空港において1994~97年に一期島(生息可能面積 143 ha),2007年に二期島(同 139 ha)でトノサマバッタが大発生し,群生相に特有の黒色とオレンジ色の2色の幼虫が認められた。調査は主にライントランゼクトおよびコドラート法により,管理はMEP 乳剤の散布により行った。1994~97年の推定生息個体数の最大値は1,338万個体で,天敵糸状菌<i>Entomophthora grylli </i>の発生とともに1997年に大発生が終息した。2007年の推定生息個体数の最大値は3,884万個体で,同じく<i>E. grylli </i>の発生とともに2007年7月に大発生が終息した。大発生の原因は,埋め立てにより出現した天敵不在の生物環境下に移入した成虫が数世代激しく増殖したことにあると考えられる。トノサマバッタの群生相集団は一期島,二期島とも島の北西部に偏在する傾向が認められ,この原因は6~9月の南ないし南西の風によるものと考えられる。関西国際空港においてトノサマバッタの生活史は主として年2化であり,卵だけでなく成虫,幼虫についても越冬が確認された。2007年の大発生時には効率的な調査および管理のための基本戦略を設定した。すなわち,①迅速な調査,②結果の地図化による全体把握,③高密度地点から低密度地点へと順に行う防除,④次回調査による防除効果の的確な評価(=①),⑤「①~③」の繰り返し,⑥天敵保護を目的とした低密度地点における薬剤散布の抑制,の6点とした。この戦略にしたがってMEP 乳剤により防除したところ,2007年6月9~11日に3,884万であった推定生息個体数は6月19日に14万に急減した。以上の結果,一期島,二期島におけるトノサマバッタの大発生は適切に管理され,航空機の運航に支障はなかった。
1 0 0 0 OA 教科横断的指導によるコンピテンシー育成に関する研究
- 著者
- 山田 丈美
- 出版者
- 愛知教育大学大学院・静岡大学大学院教育学研究科共同教科開発学専攻(後期3年博士課程)
- 雑誌
- 教科開発学論集 (ISSN:21877327)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.77-88, 2018-03-31
本研究では、人間理解に関わるコンピテンシー育成をめざし、教科横断的指導を手だてとする授業とカリキュラムについて検討した。具体的には、合科的指導として行った国語科と図画工作科の実践2例について、教科横断的指導としての効果検証を試みた。1例目の実践では、言語と絵画を学習教材として、二次元(面)の静的な動作から四次元(空間・時間を含む)の動的な動作化へと児童らが自発的に学習活動を発展させた。1例目をふまえ、四次元での動作化に重点を置いて授業構成した2 例目の実践では、人物の動作に関わる言語及び絵画を対応させる事前テストと事後テストの結果において有意差が見られ、授業効果が確認できた。以上の実践2 例から、国語科と図画工作科の教科横断的指導が人間理解に関わるコンピテンシー育成に効果を及ぼすことが明らかになった。その結果を基に、本稿最後に、人間理解へのアプローチをテーマとする教科横断的なカリキュラムモデルを提示した。
- 著者
- 綿井 雅康 菅野 純 増田 みちよ 藤井 靖 山田 達人 加藤 陽子 桂川 泰典
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 日本教育心理学会総会発表論文集 第56回総会発表論文集 (ISSN:21895538)
- 巻号頁・発行日
- pp.24-25, 2014-10-26 (Released:2017-03-30)
1 0 0 0 絵画の魅力を求めて-7-エル・グレコ《聖衣剥奪》
- 著者
- Clark Kenneth 高階 秀爾
- 出版者
- 鹿島出版会
- 雑誌
- SD (ISSN:05630991)
- 巻号頁・発行日
- no.131, pp.p79-86, 1975-07
- 著者
- 高砂 美樹
- 出版者
- 日本動物心理学会
- 雑誌
- 動物心理学研究 (ISSN:09168419)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.2, 2001-12-25
- 著者
- 横山 寧夫
- 出版者
- 立正大学
- 雑誌
- 立正大学文学部論叢 (ISSN:0485215X)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, pp.141-142, 1986-09-20
1 0 0 0 IR 略歴および著作目録 (高嶋教授退任記念特集号)
- 出版者
- 和歌山大学経済学会
- 雑誌
- 経済理論 (ISSN:04516222)
- 巻号頁・発行日
- no.332, pp.巻末1-13, 2006-07
1 0 0 0 IR 戦間期の町村財政と町村会--和歌山県粉河町の事例を中心に
- 著者
- 高嶋 雅明
- 出版者
- 和歌山大学経済学会
- 雑誌
- 経済理論 (ISSN:04516222)
- 巻号頁・発行日
- no.312, pp.35-57, 2003-03
1 0 0 0 輸出貿易政策と海外商品見本陳列所
- 著者
- 高嶋 雅明
- 出版者
- 和歌山大学
- 雑誌
- 経済理論 (ISSN:04516222)
- 巻号頁・発行日
- no.218, pp.p24-47, 1987-07
- 著者
- 高嶋 雅明
- 出版者
- 大阪大学
- 雑誌
- 大阪大学経済学 (ISSN:04734548)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.3, pp.p204-223, 1993-03
1 0 0 0 熊本県の経済発展と金融機関
- 著者
- 高嶋 雅明
- 出版者
- 九州産業大学
- 雑誌
- 九州産業大学商経論叢 (ISSN:02867842)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.4, pp.33-95, 1969-05
1 0 0 0 商業会議所活動と海外通商情報
- 著者
- 高嶋 雅明
- 出版者
- 和歌山大学
- 雑誌
- 経済理論 (ISSN:04516222)
- 巻号頁・発行日
- no.235, pp.p41-58, 1990-05
1 0 0 0 第百二国立銀行と外国貿易金融 : 朝鮮貿易と荷為替金融
- 著者
- 高嶋 雅明
- 出版者
- 社会経済史学会
- 雑誌
- 社会経済史学 (ISSN:00380113)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.2, pp.154-177,215-21, 1971
It is the purpose of this paper to clarify the reason why small national banks could play a role in the foreign trade finance. We would also like to show its effects on an individual bank. The attention will be focused upon the followings: (1) To re-confirm the characteristics of Korean trade by showing an example of documentary finance, (2) To clarify the characteristics of documentary finance in Korean trade, and (3) To shown the role of documentary finance in management of individual banks. First, we sill see that the existence of the 102the National Bank depended upon the documentary finance, then show the relationship between Korean trade and the finance of the bank. During the decade of the Meiji tenth, the finance of the 102th Bank did not concern with the imports of rice and beans-the important articles in Korean trade at that period-but with the exchange of the 18th National Bank of Nagasaki. In the Meiji twenties, the documentary finance of the 102th Bank expanded under the characteristic structure of Korean trade: lawns and shirtings from Nagasaki to Korea, and rice and beans from Korea to Osaka. However, Korean trade at that time was quite speculative, and the 102 Bank fell into trouble as a result of a failure in rice trade. The 18th Bank not only helped the 102th Bank financially, but also expanded its activity in Korea.