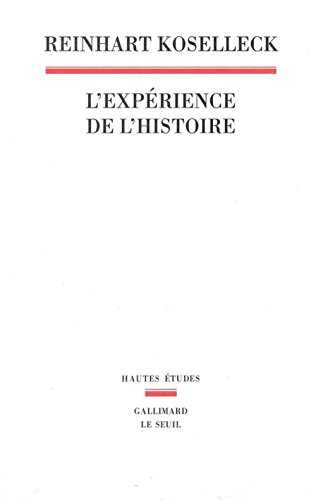1 0 0 0 OA 他者と共に「物語」を読むという行為 : 「焦点化」に着目した教室談話分析
- 著者
- 濵田 秀行
- 出版者
- University of Tokyo(東京大学)
- 巻号頁・発行日
- 2015-07-15
学位の種別: 課程博士
1 0 0 0 OA Photo Quiz : Dermatomycosis
- 著者
- 常深 祐一郎
- 出版者
- 日本医真菌学会
- 雑誌
- Medical Mycology Journal (ISSN:21856486)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.1, pp.1-2, 2013 (Released:2013-03-08)
- 参考文献数
- 1
1 0 0 0 シルクロードと奈良(3)シルクロードの音楽と雅楽
1 0 0 0 OA 農薬中毒の臨床例-31例のCase Report
- 著者
- 日本農村医学会農薬中毒研究班
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.2, pp.89-139, 1984-07-30 (Released:2011-08-11)
- 参考文献数
- 65
- 被引用文献数
- 4 2
Of clinical cases of pesticide poisoning at rural hospitals across the country, it has been requested to provide reports on 31 cases the course of which had been of interest.By type of pesticide, the number of cases is 3 for fenitrothion, 1 for DDVP, 1 for vamidothion, 2 for malathion, 1 for trichlorfon, 1 for cyanophos, 1 for phenthoate, carbaryl, and edifenphos, 1 for leptophos, 1 for ortho-dichloro-benzene and dichlorvos, 1 for fenthion anal carbamates, 2 for methomyl, 2 for nicotine sulfate, I for calcium polysulfide, 1 for blasticidin S, 1 eye injury for paraquat and chloropicrin, and 11 for paraquat.One grave factor today is a sharp rise in the prevalence of poisoning with paraquat, which in most cases is used for suicide. Of late, there have also appeared cases in which death eventually results from the spraying of paraquat.
- 著者
- 朴 紅 青柳 斉 李 英花 郭 翔宇 張 錦女
- 出版者
- 北海道大学農学部農業経済学教室
- 雑誌
- 農経論叢 (ISSN:03855961)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, pp.101-115, 2010
- 被引用文献数
- 1
中国東北地方は、近年アジアにおける有数のジャポニカ米の産地として急速な成長を示し、注目されてきた。しかし、米生産量の拡大は物流体制の未整備もあり、2003年を頂点に深刻な過剰をもたらした。その結果、東北地方内部においても激しい産地間競争が行われ、米のブランド化をめぐって品種改良や栽培技術の向上、マーケティングなどに力が入れられるようになっている。本論では、古くから良質米産地として著名である黒竜江省五常市を対象として、現段階における高級ブランド米産地の形成要因を明らかにする。まず、五常市の稲作生産と産地形成の特徴を述べた上で、第1には産地の新たな市場対応とブランド形成について分析を行う。産地の担い手が糧食局から分化・独立した精米加工企業から近年設立された農民専業合作社へと急速にシフトしていることが示される。第2には産地基盤としての農業構造の特徴を明らかにする。まず、朝鮮族の割合が高く、韓国などへの海外出稼ぎなどにより農地の賃貸借が増加し、大規模経営が形成されている点、つぎに、品種改良による優良品種の普及と臨時雇用型の有機栽培経営が行われている点が明らかにされる。
1 0 0 0 IR 中国国有農場におけるジャポニカ米の生産・加工・販売体制--北大荒米業を対象として
- 著者
- 朴 紅
- 出版者
- 北海道大学農学部農業経済学教室
- 雑誌
- 農経論叢 (ISSN:03855961)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, pp.81-91, 2011
黒竜江省は中国最大のジャポニカ米産地として知られている.水稲の作付面積は245万haであり,籾の総生産量は1,500万トンに上るが,そのうち,国有農場(農墾)のそれは103万ha (42%),840万トン(56%) であり,この地域の大きな特徴となっている(2008年現在).国有農場は,その組織改革のなかで稲作を戦略部門として位置づけ,三江平原を中心に水田開発を進めてきたが,生産に関しでは職工農家への請負制を行うとともに,それを産地として再統合し,巨大な加工・流通企業として頭角を現している.その一環として,農墾総局は傘下の優良農場を選別・統合して「北大荒農業㈱」グループを設立しているが,2001年には米穀の加工と販売のために「北大荒米業」を設立している.この企業は,グループ参加農場の産地化を図るとともに,籾保管・精米加工を行い,輪出を含む販売を行う巨大流通資本に成長し,中国における米のトップ企業に位置づけられている.以下では,米の生産・加工・販売という一連の流れのなかで,北大荒米業が果たしている機能について明らかにしていく.
1 0 0 0 OA 中国国有農場におけるジャポニカ米の生産・加工・販売体制 : 北大荒米業を対象として
- 著者
- 朴 紅
- 出版者
- 北海道大学大学院農学研究院
- 雑誌
- 北海道大学農經論叢 (ISSN:03855961)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, pp.81-91, 2011-03-31
As paddy fields were developed rapidly at the end of the Twentieth Century, Northeast China, especially Heilongjiang Province, became the main production area of japonica rice. The paddy fields, which were mainly developed by State Farms, have formed a productive base centering on the Sanjiang Plain. Beidahuang Group, which has become a huge group corporation now, provides a tremendous amount of japonica rice. It was set up on the basis of Heilongjiang Agriculture Company Limited (HACL), which is an aggregate of 16 excellent farms gathered by Heilongjiang Bureau of State Farms for japonica rice production, processing and marketing in 2002. Beidahuang Group has established a japonica rice production and processing system with the 16 farms as its foundation. Part of the rice produced by the company is sold to major cities in China by the Department of Domestic Trade, which has led to the formation of a large sales network. Another part is exported to foreign countries, including Japan, via China Oil and Foodstuffs Corporation (COFCO). Regarding the sale of paddies, it is conducted through the companyユs Department of Cereal Trade. A certain portion is purchased by the government for state reserves and the rest is sold to wholesalers as self-run provisions.Beidahuang Group possesses an enormous amount of cultivated land for japonica rice. Despite several difficulties in sales, it is undeniable that the company has already occupied an important place in the domestic market for japonica rice.
- 著者
- Kismet Anak Hong Ping
- 出版者
- 長崎大学
- 巻号頁・発行日
- 2009
博士論文
1 0 0 0 IR 超短パルスレーダによる生体イメージング
- 著者
- 竹村 素直 間瀬 淳 近木 祐一郎 北條 仁士
- 出版者
- 九州大学大学院総合理工学府
- 雑誌
- 九州大学大学院総合理工学報告 (ISSN:13467883)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.4, pp.367-370, 2007-03
Recently there are much interests in using microwave radar for monitoring and diagnostics of living subjects. In contrast to infrared and visible lights, microwave can propagate through dielectric materials, such as, concrete wall, ground, and human body. An ultra-wideband (UWB) radar is the promising method of such detection, since it gives good spatial resolution as well as good penetration characteristics for various materials. In this report, we describe the development and application of an ultrashort-pulse radar (USPR) having ultra-wideband characteristics, which frequencies are in the range of 7-15 GHz. The simulation of breast cancer detection using the USPR is performed.
1 0 0 0 OA 金利スワップ取引は単純か? -金利スワップ訴訟平成25年最高裁判決の再検討-
- 著者
- 渡辺 宏之
- 出版者
- 早稲田大学法学会
- 雑誌
- 早稻田法學 (ISSN:03890546)
- 巻号頁・発行日
- vol.90, no.3, pp.79-127, 2015-10-10
1 0 0 0 L'expérience de l'histoire
1 0 0 0 OA 造園花として櫻の景觀
- 著者
- 上原 敬二
- 出版者
- 社団法人 日本造園学会
- 雑誌
- 造園學雑誌 (ISSN:21853045)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.4, pp.292-293, 1926-04-01 (Released:2011-04-13)
1 0 0 0 OA 第八回研究大会における講述 神道について
- 著者
- 片山 文彦
- 出版者
- 未来医学研究会
- 雑誌
- 未来医学 (ISSN:09109870)
- 巻号頁・発行日
- no.11, pp.40-41, 1995-01-28
1 0 0 0 IR (未来医学を夢みて<特集>)第2部 座談会 生と死をめぐって―新しい死生観を模索する
1 0 0 0 IR 東京女子医科大学病院における病院統計 1966,1967年
- 著者
- 片山 文彦
- 出版者
- 東京女子医科大学学会
- 雑誌
- 東京女子医科大学雑誌 (ISSN:00409022)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.9, pp.688-692, 1968-09
1 0 0 0 IR 東京女子医科大学病院におけるhealth manpower
- 著者
- 片山 文彦
- 出版者
- 東京女子医科大学学会
- 雑誌
- 東京女子医科大学雑誌 (ISSN:00409022)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.1, pp.114-125, 1970-02
1 0 0 0 IR 東京女子医科大学病院の診療圏
- 著者
- 片山 文彦
- 出版者
- 東京女子医科大学学会
- 雑誌
- 東京女子医科大学雑誌 (ISSN:00409022)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.3, pp.202-220, 1971-03