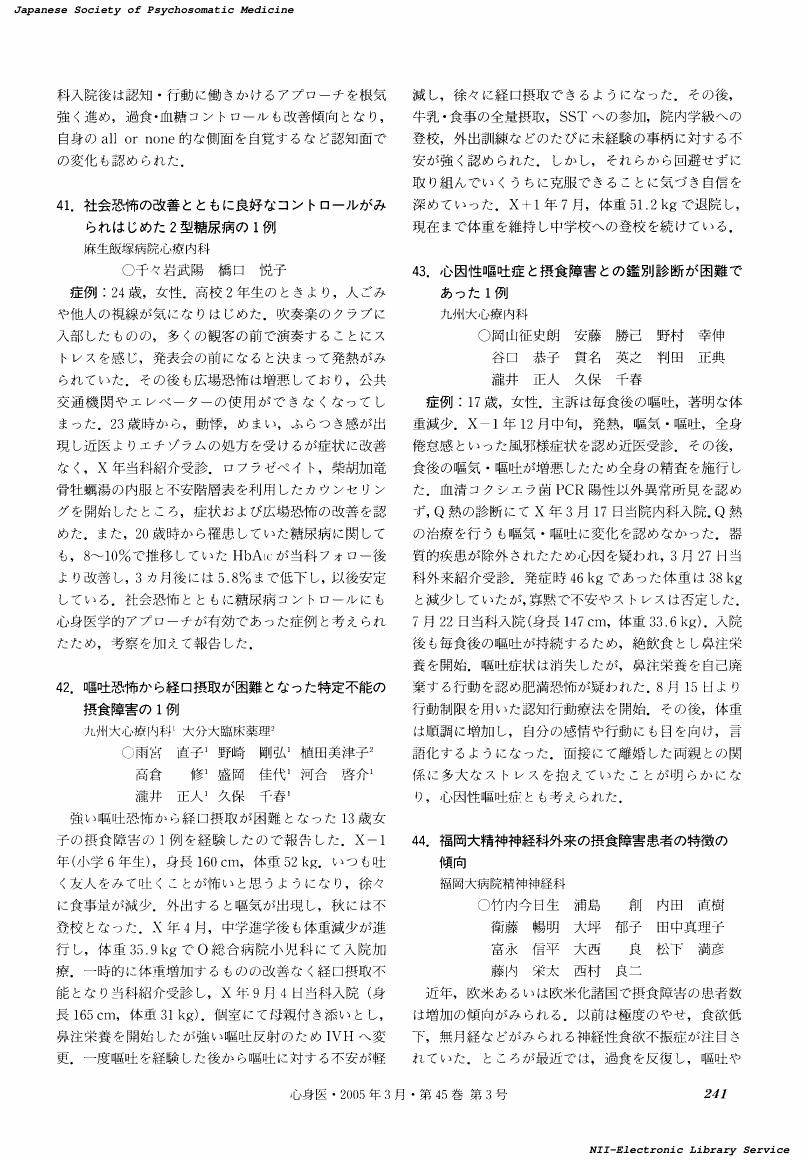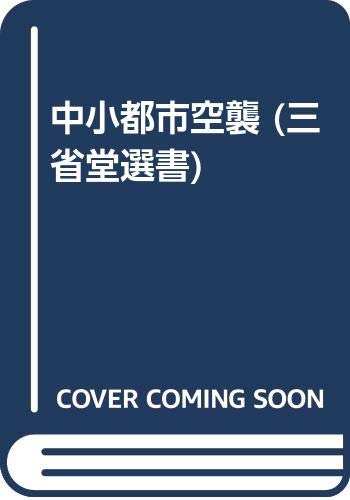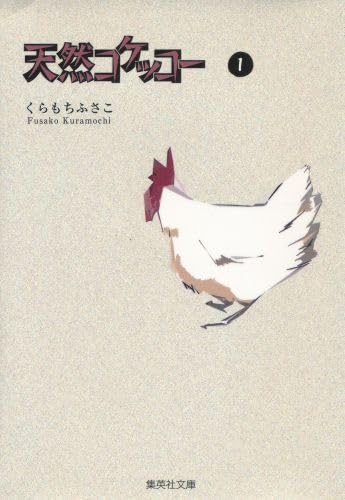1 0 0 0 西洋封建社会成立期の研究
- 著者
- 中島 涼輔 吉田 茂生
- 出版者
- 日本地球惑星科学連合
- 雑誌
- 日本地球惑星科学連合2018年大会
- 巻号頁・発行日
- 2018-03-14
We investigated waves in a stably stratified thin layer in a rotating sphere with an imposed magnetic field. This represents the stably stratified outermost Earth's core or the tachocline of the Sun. Recently, many geophysicists focus on the stratification of the outermost outer core evidenced through seismological studies (e.g. Helffrich and Kaneshima, 2010) and an interpretation of the 60-year geomagnetic secular variations with Magnetic-Archimedes-Coriolis (MAC) waves (Buffett, 2014).Márquez-Artavia et al.(2017) studied the effect of a toroidal magnetic field on shallow water waves over a rotating sphere as the model of this stratified layer. On the other hand, MAC waves are strongly affected by a radial field (e.g. Knezek and Buffett, 2018). We added a non-zero radial magnetic perturbation and magnetic diffusion to Márquez-Artavia et al.(2017)'s equations. Unlike their paper's formulation, we applied velocity potential and stream function for both fluid motion and magnetic perturbation, which is similar to the first method of Longuet-Higgins(1968).In the non-diffusive case, the dispersion relation obtained with the azimuthal equatorially symmetric field (Bφ(θ) ∝ sinθ, where θ is colatitude) is almost the same as Márquez-Artavia et al.(2017)'s result, which includes magneto-inertia gravity (MIG) waves, fast magnetic Rossby waves, slow MC Rossby waves and an unexpected instability. In particular, we replicate the transition of the propagation direcition of zonal wavenumber m=1 slow MC Rossby waves from eastward to westward with increasing Lamb parameter (ε=4Ω2a2/gh, where Ω, a, g and h is the rotation rate, the sphere radius, the acceleration of gravity and a equivalent depth, respectively) and Lehnert number (α=vA/2Ωa, where vA is Alfvén wave speed). As a consequence, fast magnetic Rossby waves and slow MC Rossby waves interact, and the non-diffusive instability occur.Next, we are examining the case with an equatorially antisymmetric background field, which is more realistic in the Earth's core. In this case, if the magnetic diffusion is ignored, the continuous spectrums appear owing to Alfvén waves resonance (similar to the continuous spectrums in inviscid shear flow, e.g. Balmforth and Morrison, 1995). To solve this difficulty, our numerical model includes the magnetic diffusion term.
1 0 0 0 OA 朝陽館漫筆抄 20巻 文化5-8
- 著者
- [高野武貞] [編]
- 巻号頁・発行日
- vol.[2], 1000
- 著者
- 鈴木 芳次
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 精神医学 (ISSN:04881281)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.10, pp.p1109-1120, 1976-10
1 0 0 0 OA 出水一件
- 巻号頁・発行日
- vol.第102冊, 1000
- 著者
- 渡辺 徹也 戸田 常紀 梶 龍児 木村 淳
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.7, pp.611-616, 1996-10-01 (Released:2017-08-01)
- 参考文献数
- 20
今回我々は, 阪神大震災被災による心的外傷から, 重度の脱水, 高Na血症を来したPTSDの1例を経験した。本例はclomipramine hydrochlorideの点滴静注とbromazepam投与を行ったところ著しい改善を認めたので, 若干の考察を加えて報告する。
1 0 0 0 OA 武者鑑 一名人相合 南伝二
1 0 0 0 好ましい肌色の研究 : 記憶色選択法による評価
- 著者
- 小林 裕幸 鈴木 正和 青木 直和
- 出版者
- 一般社団法人映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会技術報告 (ISSN:13426893)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.33, pp.21-24, 2002-05-24
- 参考文献数
- 2
- 被引用文献数
- 4
好ましい肌色が人の記憶色に基づくとの考え方が一般的に受け入れられている。本研究は肌色の記憶色そのものについて、CRTディスプレー上に示した無地、女性、男性のイラスト画、写真画像といった画像に各自が肌色として記憶している色を塗ってもらうことによって調べた。その結果、人が肌の色としてイメージするのは女性の肌の色で、しかも実際の肌の色よりもかなり明るいこと、また、好ましい肌の色の要因である記憶色とは決まった一つの色ではなく、それぞれの画像ごとにあり、色の違いに一定の傾向がある。その傾向にも年齢、性別によって差があることがわかった。
1 0 0 0 OA Javaへの限定された継続の実装と、その応用
- 著者
- 川口 耕介
- 雑誌
- 第47回プログラミング・シンポジウム予稿集
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, pp.91-100, 2006-01-10
「継続」は、関数型言語で良く見られる一風変わった言語機能である。継続には色々と面白い用途があるが、残念なことにJavaなどの手続き型汎用言語では使うことができなかった。本稿では、まず、Java言語上のライブラリとして継続をエミュレートし、アプリケーションから利用できるようにするjavaflowプロジェクトを紹介する。次に、このライブラリのテストベッドとして開発しているdalmaプロジェクトを紹介する。
1 0 0 0 大阪大空襲 : 大阪が壊滅した日
1 0 0 0 戦前戦後 : 大河内演習の二十五年
1 0 0 0 OA 本草綱目52卷圖3卷脈學1卷奇經八脈1卷
- 著者
- 三枝 幹生
- 出版者
- JAPANESE PHYSICAL THERAPY ASSOCIATION
- 雑誌
- 日本理学療法学術大会
- 巻号頁・発行日
- vol.2008, pp.B3P1335-B3P1335, 2009
【はじめに】「純粋無動症とは歩行に際してすくみ足と加速現象を特徴とするが、振戦や筋固縮を認めず、L-DOPAが無効である神経症候である.…中略…、純粋無動症の経過観察中に進行性核上性麻痺と同一の症候が出現した症例や神経病理学的に進行性核上性麻痺と診断された症例が報告され、純粋無動症は進行性核上性麻痺の非定型例または病初期の症候の可能性がある(南山堂 医学大辞典第19版より抜粋).」この診断名のもとに週1回の通所リハビリテーションを利用される利用者に対して、理学療法士ができたこと、そして考えられた今後の地域課題について報告する.<BR><BR>【症例】72歳・男性.退職後は、多趣味であり幅広く活動していたが、平成16年頃から「身体が思うように動かない」ことを自覚.徐々に右足の引きずり、両足のすくみ足が著明となり、平成20年1月に純粋無動症と診断される.同年3月より短時間の通所リハビリテーションを週1回で利用開始となる.現在、週1回は変更なく、通常時間での利用をされている.介護度は要支援1、通院は投薬調整の目的で3週ごとに通われている.<BR><BR>【経過】通所開始時、FIM124点.歩行・階段の項目のみ各6点.すくみ足著明だがT字杖で身辺ADL自立.右遊脚時に下垂足みられ足部の引きずりが認められるが、靴着用で減少する.感覚障害は右足外側に軽度の痺れ訴えあり.住環境の整備・筋力および全身持久力の維持・すくみ足の緩和を目標に個別メニューを作成し実施した.現在、自宅内は早期に生活導線へ手すりを設置したこともありADLは自立、FIMは一部修正自立で121点.筋力・全身持久力は良好に維持されているが、すくみ足の増強が認められ歩行速度・TUGなど低下傾向にある.これに伴い自宅での外出は減少傾向となっている.<BR><BR>【考察】その都度の運動指導は、本人の理解や認識にも左右されるものの週1回の通所リハビリテーションでも十分行える.筋力そのものの維持は可能であったが、すくみ足の症状について改善は得られなかった.パーキンソン病などと異なり純粋無動症は内服の効果が期待できないとされていることからも今後は易転倒の増加が考えられる.また疾患が特異的であるため情報が少なく、利用者本人と家族、介護現場のスタッフの不安も非常に大きい.「医療から介護へ」・「病院から自宅へ」のシフトが進められている昨今、医療機関主体で連携パスが進められているが、医師不足で常勤医不在も珍しくはない.医療主体で動き出しにくい場面がある.今後の経過をどのように診ていくのか、自治体の枠、医療・介護の枠、それらを超えた取り組みが必要である.<BR><BR>【倫理的配慮】本報告は本人が特定されないよう配慮するとともに、本人とご家族への説明・承諾を得て報告した.