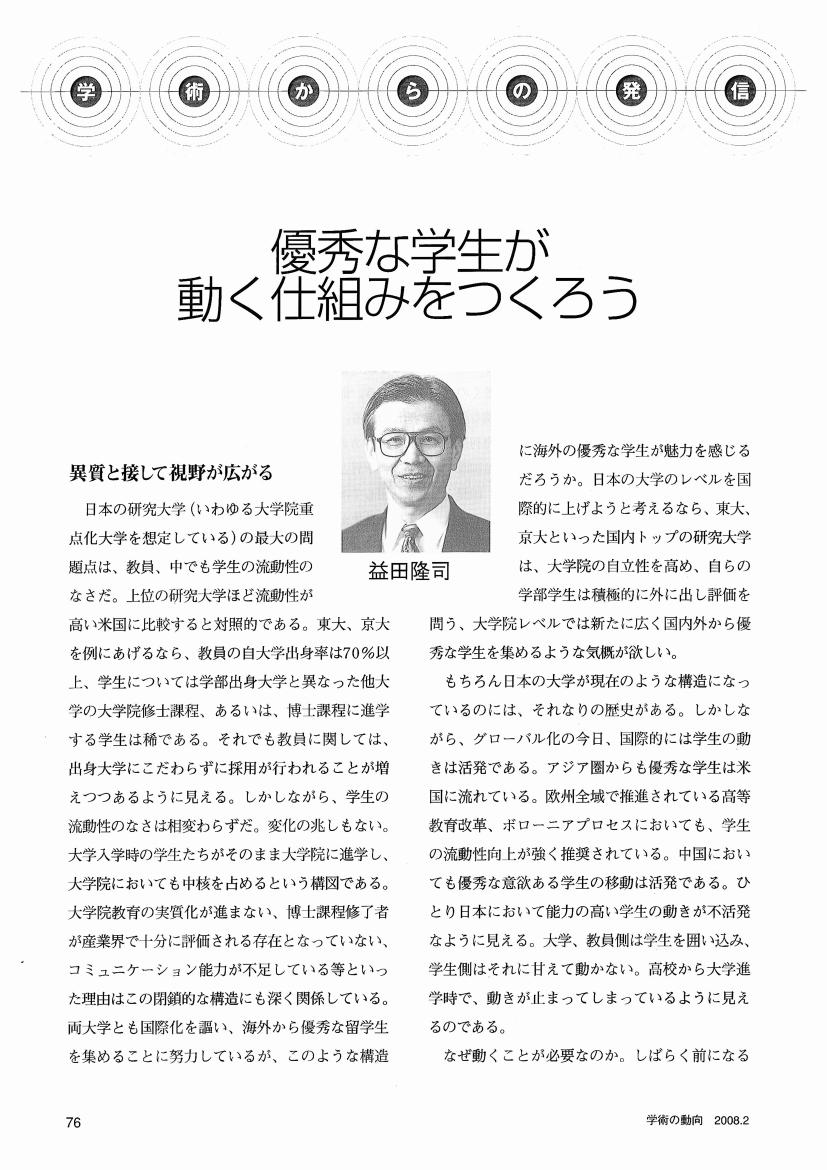1 0 0 0 OA 天地人脚色正本 2編8巻
1 0 0 0 OA 優秀な学生が動く仕組みをつくろう
- 著者
- 益田 隆司
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.2, pp.76-80, 2008-02-01 (Released:2012-02-15)
- 著者
- 王 平 江上 知就 林 岩 談 潔 佐原 寛二
- 出版者
- 一般社団法人 経営情報学会
- 雑誌
- 経営情報学会 全国研究発表大会要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2009, pp.19-19, 2009
ミクシィで代表されるSNSが日本で拡大して数年が経過した。最近になって同じような現象が中国でも発生している。我々の発表は日本のコンビニ等日本ビジネスが中国でどのように受け止められているかを、中国のSNSを利用して若者の意見を知ろうという試みである。文献調査とあわせて中国のマーケットの動向を知る。同時にネットコミュニティ発展の視点から中国のSNSと日本のSNSとの比較も行っていく。
1 0 0 0 OA [P06] デジタルアーカイブに対するDOI活用の可能性
- 著者
- 住本 研一 余頃 祐介
- 出版者
- デジタルアーカイブ学会
- 雑誌
- デジタルアーカイブ学会誌 (ISSN:24329762)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.2, pp.152-153, 2018-09-03 (Released:2018-05-18)
- 参考文献数
- 5
科学技術基本計画[1]にもオープンサイエンスの重要性が明記され、論文のオープンアクセス化、研究データのオープン化への動きが活発になっている。また、オープンサイエンスの基盤としてのデジタルアーカイブの重要性も増している。このように多くの情報が行き交うようになると、コンテンツの特定や識別が重要になる。今回ジャーナル論文では一般的になった国際的永続識別子DOIを紹介する。DOIは、論文だけで無く登録対象コンテンツを最近増やしており、今回国内での古典籍への適用事例や海外でのデジタルコンテンツへの適用事例等を紹介したい。当日はそれらの事例を踏まえて、デジタルアーカイブに搭載されたコンテンツへのDOI適用の可能性を議論させて頂きたいと考えている。
- 著者
- 大西 亘
- 出版者
- デジタルアーカイブ学会
- 雑誌
- デジタルアーカイブ学会誌 (ISSN:24329762)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.2, pp.71-74, 2018-03-09 (Released:2018-05-18)
- 参考文献数
- 9
自然史博物館に収蔵される自然史標本は、研究成果の証拠標本として引用明示されることで、自然科学研究の再検証可能性を担保する。近年、自然科学研究の文献情報は、その引用・被引用関係も含め、インターネットを通じて広く閲覧・参照可能となっている。また、自然史博物館の収蔵標本についても、目録や標本画像のインターネット公開が進み、参照・引用への障壁が取り除かれつつある。こうした状況下において、「博物館資料」×「引用先文献情報」間のクロスリファレンスシステムは、博物館における学術情報の流通と博物館資料の利活用を推進する仕組みとして期待される。この仕組みの現状と課題について、自然史標本のうち、生物のタイプ(基準標本)の事例に着目すると、国際的な情報基盤が整いつつある一方で、国内の博物館における、進行途上のデジタル・アーカイブについての課題と、従来からある資料管理上の課題が浮かび上がる。
1 0 0 0 OA 英国奴隷貿易廃止の物語(その4) : ゾング号事件
- 著者
- 児島 秀樹
- 出版者
- 明星大学経済学部経済学科研究室
- 雑誌
- 明星大学経済学研究紀要 (ISSN:03855678)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.2, pp.[21]-30, 2013-03-10
1 0 0 0 OA 英国奴隷貿易廃止の物語(その2)
- 著者
- 児島 秀樹
- 出版者
- 明星大学経済学部経済学科研究室
- 雑誌
- 明星大学経済学研究紀要 (ISSN:03855678)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.2, pp.[103]-114, 2008-03-25
1 0 0 0 OA [関東を主とする酒造関係資料雑纂]
- 出版者
- [ ]
- 巻号頁・発行日
- vol.[70], 1000
1 0 0 0 2次元アレイ上における一斉射撃アルゴリズムについて
- 著者
- 久岡 雅也 前田 雅史 梅尾 博司
- 出版者
- 日本ソフトウェア科学会
- 雑誌
- 日本ソフトウェア科学会大会講演論文集 (ISSN:13493515)
- 巻号頁・発行日
- vol.2003, pp.54-54, 2003
従来から数多くの研究がされている一斉射撃問題は, 主として1次元格子点上にセルを配列した1次元アレイを考察の対象とし, そのための同期アルゴリズムが考案されてきた. また2次元アレイに対しては, 正方形, 長方形など単純な形状を持つ2次元アレイ上では, 比較的容易に同期アルゴリズムの設計が可能であるが, 任意の形状を持つ2次元連結アレイに対しては,(1) 長方形などと同様なアルゴリズム設計が可能か?(2) 同期アルゴリズムの実現に必要な状態数は?(3) 同期に必要なステップ数は?など, 考察すべき問題が多く残されている. そこで本研究の目的は, 1次元アレイにおけるアルゴリズムを新しい埋め込み手法に基づいて設計することで, 2次元アレイ上において動作可能なセルの連結が任意の状態においても同期を実現でき, 初期状態において将軍位置が任意であることも示すことである.
1 0 0 0 OA 竜昇殿鉱山
- 著者
- 西出 喜義
- 出版者
- 一般社団法人 資源・素材学会
- 雑誌
- 日本鉱業会誌 (ISSN:03694194)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.956, pp.1719-1720, 1967-12-25 (Released:2011-07-13)
1 0 0 0 OA 蕭山漁臨華氏宗譜6卷
1 0 0 0 OA ARPS Simulations of Convection during TOMACS
- 著者
- Augusto José PEREIRA FILHO Felipe VEMADO Kazuo SAITO Hiromu SEKO José Luis FLORES ROJAS Hugo Abi KARAM
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- vol.96A, pp.247-263, 2018 (Released:2018-05-17)
- 参考文献数
- 54
- 被引用文献数
- 5
The Tokyo Metropolitan Area Convection Study (TOMACS) for extreme-weather-resilient cities is a research and development project (RDP) of the World Weather Research Programme (WWRP). TOMACS provided a multiplatform and high spatiotemporal resolution dataset for the present research on three episodes of deep convection in the Tokyo Metropolitan Area (TMA) under its heat island effect and sea breeze circulations. Heavy rainfall episodes of August 26, 2011, and July 23 and August 12, 2013, were simulated with (and without) the tropical town energy budget (T-TEB) model coupled with the advanced regional prediction system (ARPS). The T-TEB/ARPS system used initial and boundary conditions from the Japan Meteorological Agency (JMA) mesoscale analysis data for 24-hour integration runs at 5-km resolution over Japan and at 1-km resolution over TOMACS area. The 1-km resolution hourly rainfall field simulations were verified against the respective automated meteorological data acquisition system (AMeDAS) rain gauge network measurements. Statistics of the Contingency tables were obtained to estimate the critical success index (CSI), probability of detection (POD), and false alarm rate (FAR) as well as the root mean square error (RMSE). The T-TEB/ARPS simulations improved the south and east sea breeze circulations of TMA and its urban heat island effect. The time evolution of CSI scores improved within the advective time scale, whereas dissipation (phase) errors on precipitation RMSE increased with the integration time and were larger than the dispersion (amplitude) errors. The initial and boundary conditions of JMA greatly improved the simulations as compared to the previous ones performed with the outputs of NCEP's global forecast system as indicated by the TOMACS datasets. Thus, the results represent the temporal and spatial evolutions of the atmospheric conditions leading to the development of a deep convection within TOMACS region. Furthermore, TMA is a good testbed to evaluate the urban surface schemes, such as T-TEB in this study.
1 0 0 0 OA 野菜ジュースの嚥下時の舌と硬口蓋の接触に及ぼすピューレの影響
- 著者
- 森髙 初惠 小林 誠 卯川 裕一 提坂 裕子 不破 眞佐子 佐川 敦子 小野 高裕
- 出版者
- 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 平成26年度(一社)日本調理科学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.191, 2014 (Released:2014-10-02)
【目的】食塊の粘性率や密度などの物理的性質は、口腔から胃への安全な食塊の移送に影響を与えるため、嚥下機能低下者の安全な嚥下のためには重要である。水溶性あるいは不溶性の食物繊維は添加する食品のレオロジー特性やテクスチャー特性を変化させるため、安全な嚥下を確保するために他の食品と共に用いられている。本報告では、野菜ジュースの嚥下時の舌と硬口蓋の接触様相に及ぼすニンジンピューレの影響について検討した。【方法】ニンジン搾汁とリンゴ搾汁の同量混合ジュースにおいて、ニンジン搾汁部分を加熱後粉砕したニンジンピューレで0~30%置換して試料とした。被験者は21~23歳の女子学生20名とし、硬口蓋に5個の感圧点を配列した極薄型センサシートを貼付した。感圧点の位置は、硬口蓋正中部前方部・中央部・後方部と2点の硬口蓋後方周辺部とした。野菜ジュースの嚥下時の接触開始時間、ピーク出現時間、舌と硬口蓋の接触最大圧などを求めた。【結果】舌と硬口蓋の接触開始は硬口蓋正中部前方部が最も早く、次いで硬口蓋正中部中央部であり、硬口蓋正中部後方部および後方周辺部が最も遅く、この傾向は20%および30%ジュースで明確であった。舌と硬口蓋の最大接触圧の出現時間は、舌と硬口蓋の接触開始の順位と同じ傾向であった。硬口蓋正中部後方部および硬口蓋後方周辺部においては、30%ニンジンピューレ添加野菜ジュースの最大接触圧は0%ニンジンピューレ添加野菜ジュースよりも有意に大きかった。すべてのチャンネルの平均最大接触圧は、30%ニンジンピューレ添加野菜ジュースで最も大きく、次いで10%と20%ニンジンピューレ添加野菜ジュースであり、0%ニンジンピューレ添加野菜ジュースでは最も小さかった。
1 0 0 0 OA 大衆人事録
- 著者
- 帝国秘密探偵社 編
- 出版者
- 帝国秘密探偵社[ほか]
- 巻号頁・発行日
- vol.第3版 ア-ソ之部, 1930
1 0 0 0 OA ドイツの観光街道にさぐる〈線型ツーリズム〉の可能性(1)
- 著者
- 河野 眞
- 出版者
- 愛知大学国際問題研究所
- 雑誌
- 愛知大学国際問題研究所紀要 = Journal of international affairs (ISSN:05157781)
- 巻号頁・発行日
- no.142, pp.1-49, 2013-12-25
- 著者
- 岡本 亮輔
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, no.4, pp.1345-1346, 2012-03-30 (Released:2017-07-14)
1 0 0 0 大野俶嵩素描集 : 花
- 出版者
- 京都書院
- 巻号頁・発行日
- 1977