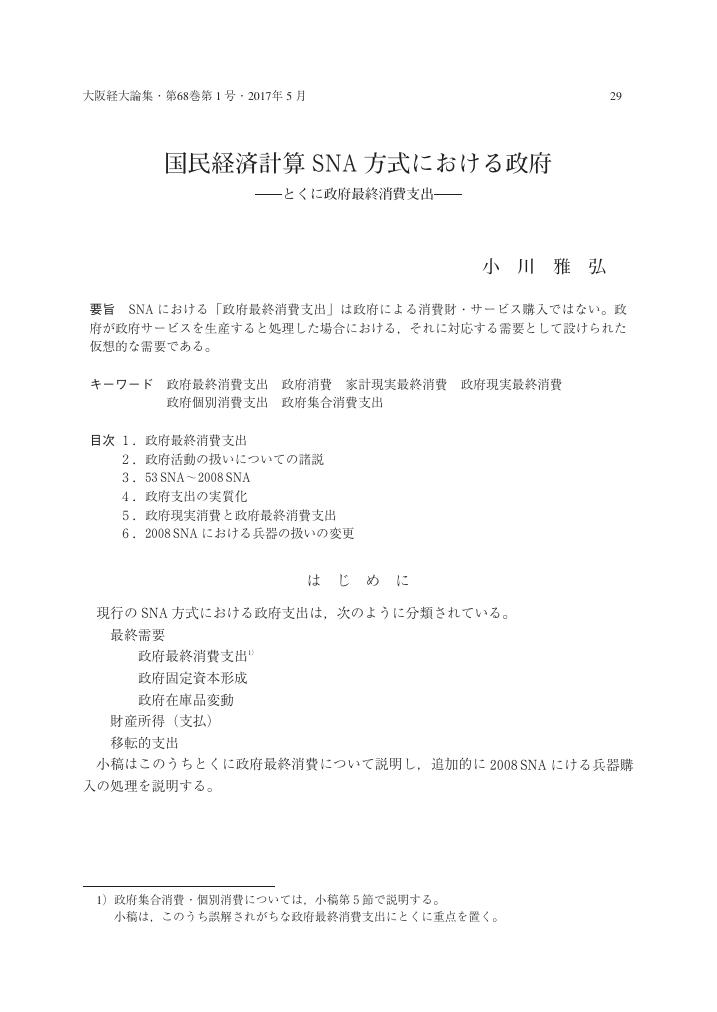5 0 0 0 OA 第二次世界大戦来と我国防
5 0 0 0 OA ゲエテとの対話
- 著者
- ヨオハン・ペエテル・エツケルマン 著
- 出版者
- 春陽堂
- 巻号頁・発行日
- vol.第1, 1924
5 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1939年08月30日, 1939-08-30
5 0 0 0 OA 第三回普選総選挙大観
- 出版者
- 朝日新聞社
- 巻号頁・発行日
- 1932
5 0 0 0 OA 腹腔鏡下に摘出した後腹膜原発粘液嚢胞腺腫の1例
- 著者
- 藤幡 士郎 坂本 宣弘 松尾 洋一 佐藤 幹則 木村 昌弘 竹山 廣光
- 出版者
- 日本臨床外科学会
- 雑誌
- 日本臨床外科学会雑誌 (ISSN:13452843)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.3, pp.617-621, 2015 (Released:2015-10-01)
- 参考文献数
- 8
患者は24歳,女性.食後の悪心を主訴に近医を受診し,腹部CT検査にて左傍結腸溝付近に45×24mm大の嚢胞性腫瘍を指摘され,当院消化器外科を紹介された.腹部は平坦・軟であり腫瘤は触知されず,圧痛も認めなかった.紹介後に当院施行の腹部造影CTにて60×20mm大の嚢胞性病変が指摘され,MRI T2強調画像では50×32mm大の高信号域が前述の部位に指摘された.内部に結節等の充実性病変は認められなかったが,徐々に増大する良性嚢胞性疾患の診断の下予防的切除に同意され手術を施行した.腹腔鏡下に手術を施行,下行結腸外側の後腹膜に境界明瞭な嚢胞性の腫瘤を確認し被膜を損傷することなく摘出した.嚢胞内容物は粘液様で細胞診は陰性であったが,生化学検査ではCEA・CA125が高値であった.病理組織学検査の結果,粘液嚢胞腺腫の診断を得た.術後9カ月の現在,再発の兆候を認めていない.
- 著者
- 小林 琢 岩崎 孝俊 倉田 裕子 二階堂 暁 幡 芳樹
- 出版者
- 一般社団法人日本理学療法学会連合
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- pp.12196, (Released:2022-08-09)
- 参考文献数
- 36
【目的】後期高齢心疾患患者の基本チェックリスト(以下,KCL)によるフレイル評価と30-Second Chair Stand Test(以下,CS30)の関連性を明らかにする。【方法】対象は当院の生活習慣病外来を受診した75歳以上の心疾患患者141名(男104例,79.6±3.4歳)とした。KCL総合点と体組成,身体機能(握力,CS30),片脚立位保持時間),運動習慣,運動耐容能を測定して,その関連性を解析した。【結果】KCL総合点による分類では,対象者のうち約2割がフレイルを有していた。また,CS30とフレイルは有意に関連していた(オッズ比:0.795, 95%信頼区間:0.663–0.952, p=0.013)。【結論】後期高齢心疾患患者におけるCS30の低値は,フレイル患者の特徴を表す重要な指標のひとつである。
5 0 0 0 OA ぺた語義:著作権法35条と32条の微妙な関係
5 0 0 0 OA 私の歩んだ道
- 著者
- 古川 董
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.4, pp.294-295, 1977-04-15 (Released:2011-11-04)
5 0 0 0 OA 台南神学校『校友会雑誌』(1928年-)にみる「台湾人」意識
- 著者
- 三野 和恵
- 出版者
- 教育史学会
- 雑誌
- 日本の教育史学 (ISSN:03868982)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, pp.71-83, 2013-10-01 (Released:2017-06-01)
This paper explores how Taiwanese Christians around 1930 perceived and expressed their own identity of being Taiwanese and Christian, particularly when facing contemporary social circumstances. In order to do so, this paper analyzes The Bulletin of Tainan Theological College Alumni (BTTCA), an annual magazine published by Alumni members of Tainan Theological College (established in 1877), and discusses the following three points. First it is the significance that BTTCA was published both in Japanese and Chinese, despite the constraint of colonial policies that established Japanese as the national language. Alumni members managed to employ Chinese in many BTTCA articles, and operated the periodical autonomously to a significant degree. Second, through an examination of BTTCA articles, I will discuss that Alumni members, due to their varied educational experiences, faced a significant generation gap in terms of command of language. Alumni members were distinctly divided into the younger generation, who received a Japanese education and/or studied in Japan proper, and the older generation of Christians, who grew up during the late-Qing era, thereby mastering Chinese rather than Japanese. Third, this paper argues that despite the intergenerational gap regarding command of language, many Alumni members collectively sought to articulate the significance of their identity as both Taiwanese and Christian, in the face of contemporary social circumstances. This was especially true of the Alumni members who formed and affirmed their Taiwanese consciousness in BTTCA, through the expression of their peculiar mission of evangelizing 'Four Million Fellow Countrymen', that is, all of Taiwanese society.
5 0 0 0 OA 【論文翻訳】 大人と子供の間の言葉の混乱 - やさしさの言葉と情熱の言葉 -
- 著者
- フェレンツィ シャーンドル 森 茂起 Sandor Ferenczi Shigeyuki MORI
- 出版者
- 甲南大学大学院 人文科学研究科人間科学専攻, 学術フロンティア研究室
- 雑誌
- 心の危機と臨床の知
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.163-172, 2000-07-20
5 0 0 0 OA 伏見城 (I) 武家地の建築 : 近世都市図屏風の建築的研究 : 洛中洛外図・その 3
- 著者
- 内藤 昌 大野 耕嗣 高橋 宏之
- 出版者
- 一般社団法人 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会論文報告集 (ISSN:03871185)
- 巻号頁・発行日
- vol.181, pp.75-82,86, 1971-03-30 (Released:2017-08-22)
This paper deals with the particulars of the Fushimi-castle that met with the rise and fall by the men then in power. And the writer devides this term into five parts by the use of new historical materials. That is; The Ist period ; The residence at Shigetsu for the retreat of Hideyoshi Toyotomi. The 2nd period; From the construction of the castle at Shigetsu by Hedeyoshi Toyotomi to the collapse by the earthquake. The 3rd period ; From the reconstruction of the castle at Mt. Kohata by Hideyoshi Toyotomi to the fall of the castle. The 4th period ; The construction of the castle at Mt. Kohata by Iyeyasu Tokugawa. The 5th period ; From the repair of the castle by Hidetada Tokugawa to the destruction of it by Iyemitsu Tokugawa.
5 0 0 0 OA 口腔乾燥症の基本的な診査・診断と治療
- 著者
- 伊藤 加代子 井上 誠
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年歯科医学会
- 雑誌
- 老年歯科医学 (ISSN:09143866)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.3, pp.305-310, 2017-12-31 (Released:2018-01-25)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 2
5 0 0 0 OA イギリス 2021年家庭内虐待法
- 著者
- 田村祐子
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説 (ISSN:13492071)
- 巻号頁・発行日
- vol.(月刊版. 290-1), 2022-01
5 0 0 0 OA サブスクリプション・サービス利用と顧客満足の特性
- 著者
- 太宰 潮
- 出版者
- 日本マーケティング学会
- 雑誌
- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.3, pp.18-29, 2022-01-07 (Released:2022-01-07)
- 参考文献数
- 19
本論は近年影響力を増している,サブスクリプション・サービスにおける顧客満足の特性を知ることを目的とし,オリコン社の顧客満足度調査から利用の程度と満足度の関係を探索的に調査した研究である。利用が少ないにもかかわらず契約を続けてしまう現象などを踏まえて,利用の程度と満足との関係が線形であるか,満足度が大きく減る,もしくは増える閾値と思われる点などを調査した。その結果,日次・週次といった習慣的な利用に満足度が動く閾値があること,週1回といったラインを下回ると満足度に与える影響が大きいことなどが判明した。その他にもサービスタイプによって理想の利用にも閾値があること,長期的継続は満足に強く影響していないこと,単価と満足度が関係しないことを示し,日次・週次の習慣的利用の重要性や閾値の存在という利用の特性を明らかにした。
5 0 0 0 OA 百鬼夜行 3巻拾遺3巻
5 0 0 0 OA 戦時下の軍国主義教育における『竹取物語』の教材化とその影響
- 著者
- 斉藤 みか
- 雑誌
- 国際基督教大学学報 3-A, アジア文化研究 = Internaitonal Christian University Publications 3-A (ISSN:04542150)
- 巻号頁・発行日
- no.48, pp.75-94, 2022-03-30
5 0 0 0 OA 国民経済計算SNA方式における政府 --とくに政府最終消費支出--
- 著者
- 小川 雅弘
- 出版者
- 大阪経大学会
- 雑誌
- 大阪経大論集 (ISSN:04747909)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.1, pp.29, 2017 (Released:2018-02-15)
5 0 0 0 OA 1910年代朝鮮総督府機関紙と徳富蘇峰
- 著者
- 咸 苔英
- 雑誌
- 国際基督教大学学報 3-A,アジア文化研究 = International Christian University Publications 3-A,Asian Cultural Studies
- 巻号頁・発行日
- no.37, pp.95-119, 2011-03-30
5 0 0 0 OA 理工系大学・学部への女性の入学状況に関する考察 : 「男女別大学入学者数調査」から
- 著者
- 河野 銀子
- 出版者
- 山形大学地域教育文化学部附属教職研究総合センター
- 雑誌
- 山形大学教職・教育実践研究 = Bulletin of the Teacher Training Research Center attached to the Faculty of Education, Art and Science, Yamagata University (ISSN:18819176)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.7-16, 2013-03-12
本稿は,理工系学部を専攻する女性が少ない一因を考察するため大学入試に着目してその実態を把握し,先行研究に新たな知見を与えることを目的としている。全国の理工系大学・学部(394)を対象とした調査(「男女別大学入学者調査」) を実施したところ,その入学者数が男女別に判明したのは299学部(国立110,公立31,私立158)であった。そのうち,女性学生比率が30パーセント以上の理工系大学・学部を「高比率群」として,大学特性を分析した。しかし,該当する学部が65しかなく,それらの所在地や女性教員比率の特性を一般化するにはサンプルが少ないと思われた。一方で,入試状況の分析からは「高比率群」に該当する学部に関する知見が得られた。「低比率群」(女性学生比率10%以下)が,受験機会が多く,入試科目が少なく,合格が難しくない理工系学部であったのに対し「高比率群」は,受験機会が少なく,入試科目が多く,超難関に次く守合格難易度の理工系であった。つまり,理工系学部を希望する女子高校生たちは,合格しやすい学部を選択しない傾向があることが明らかになった。理工系学部に女性の学生が少ない一因として「積極的選択層」のみが入学していることを挙げた。 キーワード:男女共同参画基本計画, 科学技術基本計画, 理工系人材, 進路選択, ジェンダー, 大学入試