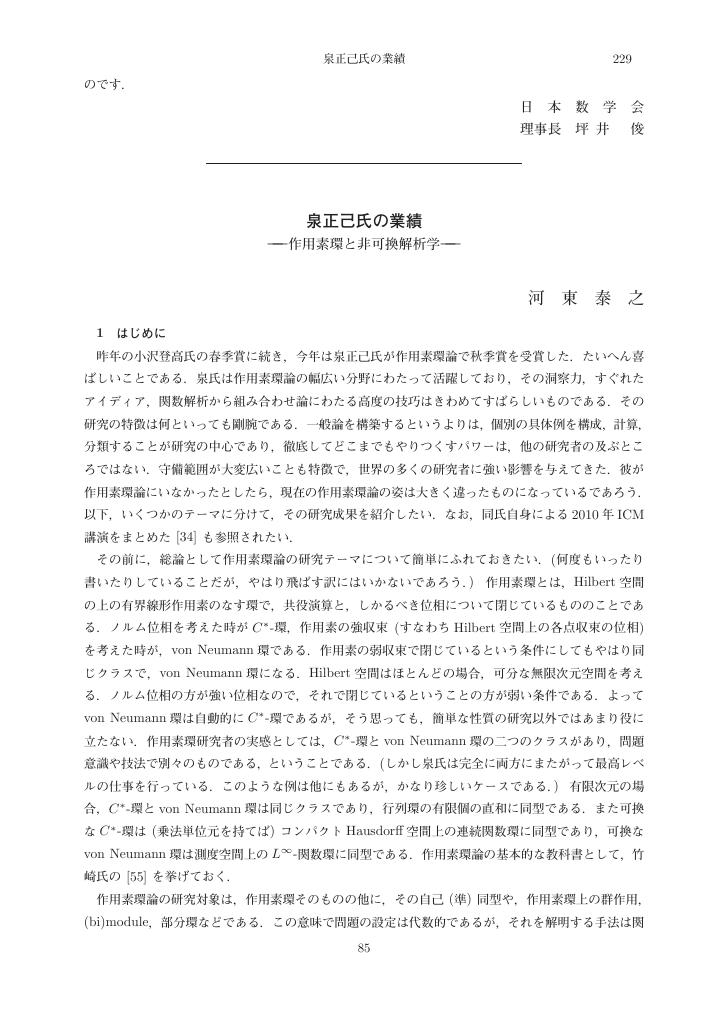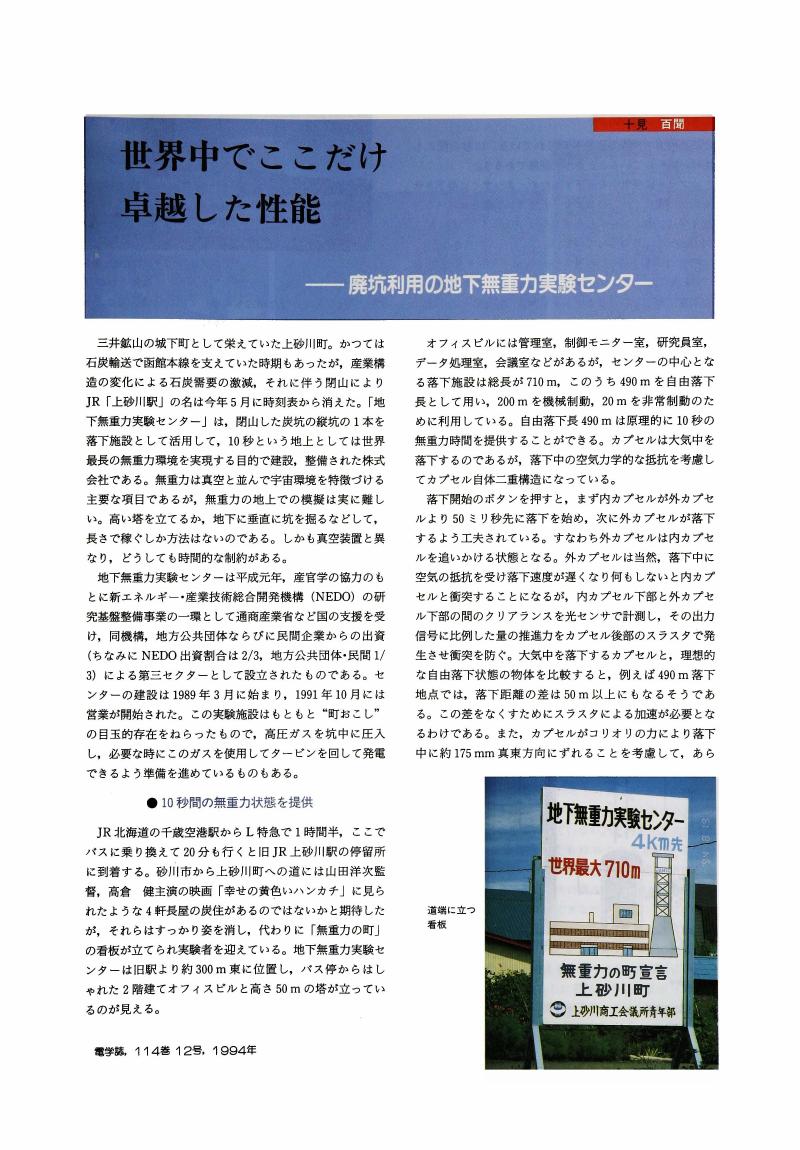5 0 0 0 OA 竹の成長過程での滲出水の元素分析と生成機構の考察
- 著者
- 和仁 宗憲 東 學 梨子木 久恒 安長 たかみ 高尾 征治
- 出版者
- 公益社団法人 化学工学会
- 雑誌
- 化学工学会 研究発表講演要旨集 化学工学会第70年会
- 巻号頁・発行日
- pp.316, 2005 (Released:2005-08-30)
5 0 0 0 OA ゴルフ場の半自然草原を活用した生物多様性の保全
歴史の長いゴルフ場の植生を調査した結果,全国版・地域版のレッドデータブックに掲載の絶滅危惧種および多くの草原生植物の生育を確認した.つまり,これらの場所は草原生植物の逃避場所や種子供給源として機能する可能性がある.管理方法と種多様性との関係では,草刈り頻度および草刈高が種多様性に大きく影響を与えており,草刈り頻度が低く,草刈高が高い地点においては種多様性が高く,逆の地点では種多様性が低かった.また,ゴルフ場関係者の意向を把握する質問紙調査からは,ゴルファーの多くは野草の生育に対して好意的であることが示された.
5 0 0 0 OA 泉正己氏の業績 ——作用素環と非可換解析学——
- 著者
- 河東 泰之
- 出版者
- 一般社団法人 日本数学会
- 雑誌
- 数学 (ISSN:0039470X)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.2, pp.229-235, 2011 (Released:2013-11-01)
- 参考文献数
- 58
5 0 0 0 OA 共同売店から見えてくる沖縄村落の現在
- 著者
- 宮城 能彦
- 出版者
- 日本村落研究学会
- 雑誌
- 村落社会研究 (ISSN:13408240)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.1, pp.13-24, 2004 (Released:2013-09-28)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 2
The Community Stores which exist even now in Okinawa have been established by the residents in the rural community(buraku). But, because of the development and the subsequent changes in the community, a lot of Community Stores have been closed during the last 20 years. At present, there are some Community Stores whose management is stable, but many others with the difficulties in management. It is thought that the rural community can be well understood by studying Community Stores. How the rural communities have been able to continue to manage these stores in spite of the difficulties in management is the question to be raised in this paper. My argument is that by addressing this question 1) we can understand how the Okinawan communities are wavering between the urbanization of their life and their consciousness of maintaining the spirit of community, and 2) we can develop a new theory of policies matching to the circumstances.
5 0 0 0 OA 世界中でここだけ卓越した性能
- 著者
- 工藤 勲
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会誌 (ISSN:13405551)
- 巻号頁・発行日
- vol.114, no.12, pp.781-784, 1994-11-20 (Released:2008-04-17)
- 被引用文献数
- 2
5 0 0 0 OA 種苗法の沿革と知的財産保護
- 著者
- 小林正
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- レファレンス (ISSN:1349208X)
- 巻号頁・発行日
- no.655, 2005-08
5 0 0 0 OA 電気接触現象
- 著者
- 玉井 輝雄
- 出版者
- The Japan Institute of Electronics Packaging
- 雑誌
- エレクトロニクス実装学会誌 (ISSN:13439677)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.3, pp.256-262, 2000-05-01 (Released:2010-03-18)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1 1
5 0 0 0 IR 有史以来の地震活動よりみたる我国各地の地震危険度及び最高震度の期待値〔英文〕
- 著者
- 河角 広
- 出版者
- 東京大学地震研究所
- 雑誌
- 東京大学地震研究所彙報 (ISSN:00408972)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.3, pp.469-482, 1951-09
- 被引用文献数
- 6
- 著者
- 江藤 裕之
- 出版者
- 長野県看護大学紀要委員会
- 雑誌
- 長野県看護大学紀要 (ISSN:13451782)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.1-8, 2007-03-31
5 0 0 0 英人の見た海軍兵学校
- 著者
- セシル・ブロック 著
- 出版者
- 内外書房
- 巻号頁・発行日
- 1943
- 著者
- 酒井 克彦
- 出版者
- 中央ロー・ジャーナル編集委員会
- 雑誌
- 中央ロー・ジャーナル (ISSN:13496239)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.3, pp.99-124, 2015-12-20
いわゆる馬券訴訟においては、納税者が勝ち馬券から得られた所得の所得区分が争われている。最高裁判決は刑事訴訟において、かかる所得を雑所得であると判断した。そもそも、所得税基本通達はかような所得を一時所得に該当するものとして通達しており、課税実務においては勝ち馬券に係る所得は一貫して一時所得と取り扱ってきた。しかしながら、およそ日本中のほぼすべての競馬レースの馬券を継続して購入しているような極めて異例のケースについてまでをも果たして一時所得と判断することが妥当であるのかという点は議論の余地がある。そもそも、一時所得に区分されると、直接要した費用の額のみしか控除できないという問題があり、負け馬券の購入代金を所得金額の算定上引くことができないことになる。そこで、上記最高裁判決とは、納税者は一時所得ではなく雑所得に該当すると主張したという事例であった。さらに、東京地裁では類似の事例において一時所得と判断されたことから、注目を集めている。本稿は、上記最高裁の判断を検討し、その判断枠組みの妥当性を論証した上で、さらにその射程範囲について検討を行ったものである。
5 0 0 0 OA EM菌の抗酸化作用的確認
- 著者
- 秦 斐斐 李 鳳蘭 徐 会連
- 出版者
- 日本作物学会
- 雑誌
- 日本作物学会講演会要旨集 第235回日本作物学会講演会
- 巻号頁・発行日
- pp.436, 2013 (Released:2013-03-26)
5 0 0 0 OA 明清期の瘟神と医神
- 著者
- 二階堂 善弘
- 出版者
- 関西大学東西学術研究所
- 雑誌
- 関西大学東西学術研究所紀要 (ISSN:02878151)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, pp.A27-A42, 2021-04-01
This article explores the gods of plague and medicine in the Ming and Qing dynasties. With regard to the gods of plague, many are known throughout China, including Wangye (王爺) in Fujian and Taiwan, Yanguang Niangniang (眼光娘娘) in the north, as well as Banchen Niangniang (斑疹娘娘), Tainhua Niangniang (天花娘娘), and other niangniang who drive disease. The numerous Yaowang temples across mainland China attest to the belief in these gods. Concerning rituals, the sending off of the royal ship (送王船) is performed to expel epidemics. With regard to the gods of medicine, the kings of medicine (藥王) include famous doctors such as Bian Que (扁鵲), Sun Simiao (孫思邈), Wei Cicang (韋慈藏), and Hua Tuo (華陀). Emperor Baosheng of Fujian was, for example, a well-known doctor who later became a god of medicine. Fictional characters also display traits of gods, such as Lu Yue (呂岳), who appears in the novel Fengshen Yanyi [封神演義] and resembles a plague god, as well as Marshal Gao (高元帥) and Marshal Zhang (張元帥) of Marshal God, who resemble the gods of medicine.
5 0 0 0 OA 『もう一つの眠り』から『幻を追う人』へ : 両次大戦間のジュリアン・グリーン(2)
- 著者
- 原田 武
- 出版者
- 大阪外国語大学
- 雑誌
- Etudes francaises (ISSN:0285984X)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.19-44, 1987-03-30
- 著者
- 衆議院憲法調査会事務局
- 出版者
- 衆議院
- 巻号頁・発行日
- 2003-02
5 0 0 0 OA アメリカの大統領行政府と大統領補佐官
- 著者
- 廣瀬淳子
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- レファレンス (ISSN:1349208X)
- 巻号頁・発行日
- no.676, 2007-05
5 0 0 0 OA 北原白秋と「赤い鳥」 : 童心への傾斜とその軌道修正
- 著者
- 小沢 聰
- 出版者
- 信州豊南女子短期大学
- 雑誌
- 信州豊南女子短期大学紀要 = Bulletin of Shinshu Honan Women's Junior College (ISSN:02897644)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.179-208, 1989-03-01