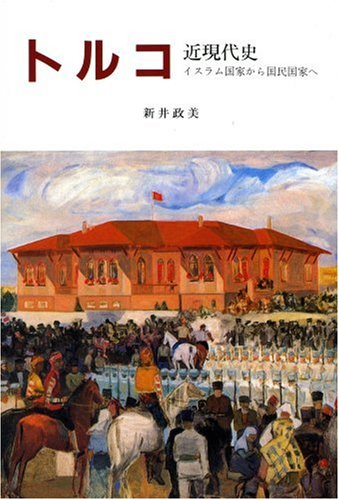1 0 0 0 OA アミノ酸添加による炭酸カルシウム結晶のモルフォロジー制御
- 著者
- 中川 究也 北川 輝幸 北村 光孝
- 出版者
- 公益社団法人 化学工学会
- 雑誌
- 化学工学会 研究発表講演要旨集 化学工学会第39回秋季大会
- 巻号頁・発行日
- pp.216, 2007 (Released:2008-03-17)
1 0 0 0 OA 官能基置換によるBPT誘導体結晶の析出挙動ならびに結晶構造への影響
- 著者
- 原 崇行 足立 浩介 北村 光孝
- 出版者
- 公益社団法人 化学工学会
- 雑誌
- 化学工学会 研究発表講演要旨集 化学工学会第39回秋季大会
- 巻号頁・発行日
- pp.210, 2007 (Released:2008-03-17)
1 0 0 0 OA トリアシルグリセロールの結晶化に及ぼす圧力の影響
- 著者
- 山本 英二 石本 裕一 安部 伸宏 松井 岐美 村田 哲章 高橋 俊介
- 出版者
- 公益社団法人 化学工学会
- 雑誌
- 化学工学会 研究発表講演要旨集 化学工学会第39回秋季大会
- 巻号頁・発行日
- pp.202, 2007 (Released:2008-03-17)
1 0 0 0 トルコ近現代史 : イスラム国家から国民国家へ
1 0 0 0 OA 分岐鎖アミノ酸の晶析時における類似構造アミノ酸の相互間取り込み機構
- 著者
- 亀井 利道 長谷川 和宏 冨家 一郎 永井 秀忠 横田 政晶 清水 健司 土岐 規仁
- 出版者
- 公益社団法人 化学工学会
- 雑誌
- 化学工学会 研究発表講演要旨集 化学工学会第39回秋季大会
- 巻号頁・発行日
- pp.225-226, 2007 (Released:2008-03-17)
1 0 0 0 OA 除草剤ビアラホスの開発
- 著者
- 橘 邦隆 金子 邦夫
- 出版者
- 日本農薬学会
- 雑誌
- 日本農薬学会誌 (ISSN:03851559)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.2, pp.297-304, 1986-05-20
- 被引用文献数
- 1 3
Bialaphos, L-2-amino-4-[(hydroxy)(methyl) phosphinoyl] butyryl-L-alanyl-L-alanine, is a metabolite of Streptomyces hygroscopicus and the first herbicide produced by fermentation. Bialaphos acted on foliage and was effective against a wide range of weeds including perennials. Bialaphos was slower acting than paraquat, but faster than glyphosate. It controlled the regrowth of weeds longer than paraquat but shorter than glyphosate. Translocation of radioactivity in Rumex obtusifolius treated with ^<14>C-bialaphos was observed autoradiographically. Bialaphos did not affect emergence nor growth of crops through soil. Therefore, bialaphos is expected to be used widely for arable land including nontillage cultivation. Growth inhibition of pollen tube of Camellia japonica was recovered by the addition of glutamine. The result suggested that glutamine synthetase (L-glutamine : ammonia ligase (ADP), EC 6.3.1.2, GS) was inhibited in the pollen. Decrease of GS activity was observed in shoots of Echinochloa utilis OHWI treated with bialaphos. Decrease in glutamine content was observed in plant leaf treated with bialaphos, but it did not appear that the decrease was a main factor for the herbicidal activity. Ammonia content in plant leaf was observed to increase in four hr after the treatment and reached about 30 to 100 times higher than the control in 24 to 48 hr. The accumulation was not momentary, but maintained until the death of the plant. The high correlation between free ammonia content and herbicidal activity indicated that the toxicity of accumulated ammonia is the primary factor of herbicidal activity of bialaphos. The ammonia accumulation is considered to be a particular action of bialaphos in plants. More extensive use of microbial metabolites is expected by the fact that bialaphos was developed as a herbicide.
1 0 0 0 OA ライフストーリー・インタビューの世代間学習としての可能性
- 著者
- 中川 恵里子
- 出版者
- 東京大学大学院教育学研究科生涯学習基盤経営コース内『生涯学習基盤経営研究』編集委員会
- 雑誌
- 生涯学習基盤経営研究 (ISSN:1342193X)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, pp.99-112, 2010-03-30
研究ノート/Notes
- 著者
- Jessop Bob 中谷 義和[訳]
- 出版者
- 立命館大学
- 雑誌
- 立命館大学人文科学研究所紀要 (ISSN:02873303)
- 巻号頁・発行日
- vol.99, pp.3-32, 2013-03
1 0 0 0 OA ウォーレス・スティーヴンズの「ものそのもの」について
- 著者
- 岩瀬 悉有 Shitsuu Iwase
- 雑誌
- 人文論究 (ISSN:02866773)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.4, pp.14-32, 1994-02-20
- 著者
- 古谷 遼 森山 剛
- 出版者
- 電気学会
- 雑誌
- 電気学会研究会資料. PI = The papers of Technical Meeting on "Perception Information", IEE Japan,
- 巻号頁・発行日
- vol.2015, no.43, pp.43-46, 2015-04-24
- 著者
- 原岡 文子
- 出版者
- 学灯社
- 雑誌
- 国文学 解釈と教材の研究 (ISSN:04523016)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.5, pp.76-81, 2001-04
1 0 0 0 6p-KT-6 陽光柱プラズマ中のイオン音波の振幅振動
- 著者
- 山本 巧 間瀬 淳 築島 隆繁
- 出版者
- 一般社団法人日本物理学会
- 雑誌
- 春の分科会予稿集
- 巻号頁・発行日
- vol.1974, no.4, 1974-03-20
1 0 0 0 OA 335 道路交通に対する関心についての一研究
- 著者
- 田中 敬二
- 出版者
- 日本教育心理学会
- 雑誌
- 日本教育心理学会総会発表論文集
- 巻号頁・発行日
- no.7, pp.106-107, 1965-10
1 0 0 0 OA 道路のネットワーク構造の下での課徴金賦課の問題
- 著者
- 藤岡 明房
- 出版者
- 立正大学
- 雑誌
- 経済学季報 (ISSN:02883457)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.3, pp.79-114, 2007-03
本論文は,道路のネットワークの構造が与えられている場合の交通の問題を,混雑現象が生じている場合を中心に検討する.はじめに,道路がネットワーク構造を持つ場合の交通移動の市場均衡の解を求める.その際,混雑現象が生じていることから,市場均衡は最適状態を達成していない.そこで,最適状態を達成させるためには,外部不経済の内部化を行う必要がある.その内部化のために課徴金を用いるとして,その課徴金の額を決定しなければならないという新たな課題が登場する.その課徴金の額の決定のために,社会的限界費用と私的限界費用の差を求める必要がある.従来は,一本の道路しか考えていなかったので,単純に課徴金の額が決定できた.しかし,道路がネットワーク構造を形成している場合は,その影響を受けることになる.そこで,ネットワーク構造を踏まえたうえで,複数道路での課徴金の額の決定というより複雑な問題について検討している.
1 0 0 0 OA 中国の白酒 (鳳香型白酒) の製造方法 (1)
- 著者
- 高山 卓美
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)
- 巻号頁・発行日
- vol.97, no.6, pp.398-410, 2002-06-15 (Released:2011-09-20)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1
中国では少なくみても約300種の酒が造られている。このうちコウリャンや麦などの穀類を原料として, これを糖化, 発酵して蒸留したものが白酒であり, 日本の焼酎にあたる。中国の白酒は, 世界で唯一固体発酵を利用した蒸留酒であり, その製造方法は大変に複雑である。筆者は中国の酒事情に詳しく, そこで代表的な白酒の1つである鳳香型白酒について2回にわたって解説していただく。第1回目は, 鳳香型白酒の製造方法を詳述していただいた。
1 0 0 0 OA 次数2のユリタリ群上の尖点形式に付随するL-関数の解析的性質について
- 著者
- 門田 智則
- 出版者
- 京都産業大学
- 雑誌
- 京都産業大学論集. 自然科学系列 (ISSN:09165916)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, pp.105-176, 2006-03
1 0 0 0 パーマロイ薄膜磁化異方性の電顕による測定 : 表面物理・薄膜
- 著者
- 前田 宏 日比野 倫夫 丸勢 進
- 出版者
- 一般社団法人日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会春季分科会講演予稿集
- 巻号頁・発行日
- vol.1965, no.1, 1965-04-06
- 著者
- 岡部 昌生
- 出版者
- 札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部
- 雑誌
- 札幌大谷短期大学紀要 (ISSN:02865238)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, 1989-03-20
- 著者
- 高橋 武雄
- 出版者
- 一般社団法人日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築學會研究報告
- 巻号頁・発行日
- no.54, pp.251-257, 1960
- 著者
- 小室 信喜 待井 一樹 六田 智之 白石 剛大 上田 裕巳 河西 宏之 坪井 利憲
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会総合大会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2009, no.2, 2009-03-04