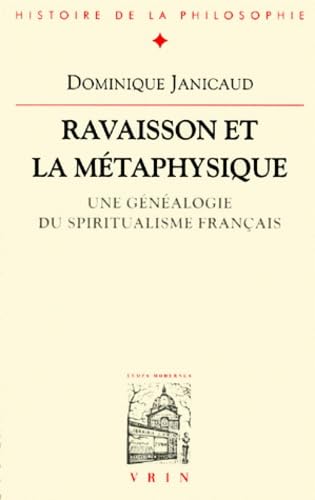1 0 0 0 「寄付」の政治社会学考--慣習化すれば日本国の形を変える効用も
1 0 0 0 OA 「岡山県立大学」のビジュアルアイデンティティ
- 著者
- 野宮 謙吾 齋藤 美絵子 西田 麻希子 西垣 浩行
- 出版者
- 一般社団法人 日本デザイン学会
- 雑誌
- 日本デザイン学会研究発表大会概要集 日本デザイン学会 第55回研究発表大会
- 巻号頁・発行日
- pp.183, 2008 (Released:2008-06-16)
近年の実践事例にも見られるように国公立大学においては、独立行政法人化以降の「新たなイメージづくり」が大きな課題となっている。本研究チームでは、まず国公立大学を中心に大学におけるVI(ビジュアルアイデンティティ)に関する研究を行い、大学の理念がどのような手法によって視覚造形化されているかについて調査分析を行った。また、大学のイメージとVI及び広報・広告の関係について他大学の事例調査を行うとともに、岡山県立大学(以下、本大学)のイメージについてアンケート調査を実施した。本研究では、これらの分析結果を参考に、本大学VIの整備に取り組んだ。まず、シンボルマーク及びロゴタイプ等ベーシックデザインを策定し、次に名刺、封筒他アプリケーションデザインへの展開を試みた。
- 著者
- par Dominique Janicaud
- 出版者
- J. Vrin
- 巻号頁・発行日
- 1997
1 0 0 0 OA 教育病院におけるノロウイルス胃腸炎アウトブレイクへの対応
- 著者
- 大西 司 足立 満
- 出版者
- 社団法人 日本感染症学会
- 雑誌
- 感染症学雑誌 (ISSN:03875911)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.6, pp.689-694, 2007-11-20 (Released:2011-02-07)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 1 1
平成16年1月昭和大学東病院でノロウイルスによる感染性胃腸炎のアウトブレイクを経験し, 12日間で患者20名, 職員19名が発症した. 流行曲線からヒトーヒト感染例と考え, 標準予防策を行ったが, 感染はフロア全体に広がった. 感染対策は保健所の指導を仰ぎ実践した. 手洗い, 消毒手袋-マスク-防護衣着用の徹底移動制限, 隔離部屋をつくるなどの厳密な院内感染対策により, 感染を1フロアに留めることができた. また同3月, 病院食堂に端を発したノロウイルスによる食中毒事例が発生し54名の職員および患者家族1名が発症したが, 早期に発症者を把握し出勤停止をかけることで二次感染を防止できた. 早期の感染対策すなわちアウトブレイクの発生を知り周知させること, 健常者と患者を分けること, そして感染防御を行うことは, 感染症のコントロールを行う上で重要と思われた.
1 0 0 0 OA ノロウイルスによる感染性胃腸炎アウトブレイクの経験
- 著者
- 志田 泰世 野口 久美子 金子 潤子 金沢 宏 吉川 博子
- 出版者
- Japanese Society of Environmental Infections
- 雑誌
- 環境感染 (ISSN:09183337)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.3, pp.184-187, 2005-09-30 (Released:2010-07-21)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 5
平成15年12月30日, 新潟市民病院の神経内科と整形外科の混合病棟の入院患者47名中13名に下痢, 嘔吐の症状が出現した. 準夜勤務者 (3名) にも同様の症状が認められた. 病棟発生調査とおよび脱水症状の患者への治療が開始された. 出勤していないスタッフにも同様の症状が多いことがわかった. 緊急対策会議を開催し, 患者隔離・スタンダードプリコーションの徹底及び厳重な接触感染予防策が実施された. 胃腸炎の原因はノロウイルスであることが判明した. 1月8日には有症状患者は0となり, 10日患者の隔離解除・平常業務体制となった. ノロウイルス感染の症状は, 嘔吐69%, 下痢66%といわれ, 成人では下痢, 小児では嘔吐が多いとされている. そのため, ノロウイルスの主要感染ルートは, 糞口感染で, 高齢者ではおむつ交換時, 汚染された水や貝 (二枚貝) で, 時に飛沫による感染が推定されることから, 注意が必要である.
- 著者
- Hidetada KOMATSU Masami KOJIMA Naoyuki TSUTSUMI Shuichiro HAMANO Hiroshi KUSAMA Arao UJIIE Shigeru IKEDA Masayuki NAKAZAWA
- 出版者
- (社)日本薬理学会
- 雑誌
- The Japanese Journal of Pharmacology (ISSN:00215198)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.1, pp.43-51, 1988 (Released:2006-08-25)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 42 39 53
We investigated the mechanism of inhibitory action of tranilast on chemical mediator release by antigen-antibody reactions. Tranilast (10-5-10-3 M) inhibited antigen (DNP-Ascaris)-induced histamine release from sensitized purified rat mast cells (PMC), but did not show an obvious influence on intracellular cyclic AMP. 45Ca uptake into PMC induced by antigen (300 μg/ml) was obviously suppressed by tranilast (10-6-10-3 M). Tranilast (10-4 M) inhibited antigeninduced histamine release from and 45Ca uptake into PMC independently of the presence or absence of glucose in the medium. On the other hand, 2-deoxyglucose (10-2 M) markedly inhibited both responses in the absence but not in the presence of glucose. Tranilast slightly inhibited Ca-induced contraction of guinea pig taenia coli, but had no influence on aggregation of rabbit platelets. Verapamil (10-6-10-4 M) had no effect on antigen-induced histamine release, but it markedly suppressed Ca-induced contraction and platelet aggregation. From these results, we suggest that the mechanism of inhibitory action of tranilast on the release of antigen-induced chemical mediator from mast cells involves the suppression of Ca uptake, but that its mode of action is apparently different from those of 2-deoxyglucose and verapamil.
1 0 0 0 OA 初期の映画理論とその受容についての一考察 -K・ランゲとH・ミュンスターバーグ
- 著者
- 篠木 涼
- 出版者
- 立命館大学大学院先端総合学術研究科
- 雑誌
- Core ethics : コア・エシックス
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.213-221, 2007
1 0 0 0 OA 岩手県赤金鉱山産新鉱物赤金鉱(β-FeOOH)について
- 著者
- 南部 松夫
- 出版者
- Japan Association of Mineralogical Sciences
- 雑誌
- 岩石鉱物鉱床学会誌 (ISSN:00214825)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.4, pp.143-151, 1968-04-05 (Released:2008-08-07)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 5 7
The new mineral akaganeite is beta-ferric oxyhydroxide from the weathered outcrop of the Akagane pyrometasomatic copper-iron deposit in Carboniferous green rock, Iwate Prefecture, Japan. The mineral is the supergene oxidation product of massive pyrrhotite and intimately associated with goethite, melantilite and two kinds of ferric sulfates. The mineral occurs in powdery aggregates of very fine orange to brownish-yellow crystals, elongated [001] and flattened (100) up to 0.3×0.03μ in size under the electron microscope. Two chemical analyses carried out in 1956 and 1959, respectively: Fe2O3 78.23, 80.98; FeO 0.82, 0.23; SiO2 3.10, 3, 57; A12O3 1.21, 1.40; Na2O 0.62, 0.82; K2O 0.19, 0.29; H2O+ 10.20, 9.71; H2O- 4.96, 2.55, sum 99.33, 99.55%. These data correspond closely to FeOOH. Chlorine was detected qualitatively, but material was in sufficient for a quantitative analysis. X-ray powder data are indexed on a tetragonal cell with a=10.50, c=3.03A. The strongest lines are 7.45 (98) (110), 5.31 (48) (200), 3.71 (21) (220), 3.34 (100) (310), 2.361 (33) (400), 2.553 (95) (211), 2.340 (8) (420), 2.300 (43) (301), 2.103 (31) (321), 1.954 ((39) (411), 1.750 (42) (600), 1.720 (12) (501, 431), 1.646 (52) (521), 1.520 (21) (002), 1.456 (28) (640), 1.441 (30d) (1.438), 1.381 (40d) (730, 312). These data agree very closely with the data obtained by Macky (1960), who showed the synthetic β-FeOOH is tetragonal, 14/m, a=10.48, c=3.023A. A DTA curve showed a slight endothermal reaction at about 300°C and a marked exothermal peak at 375°C. The mineral loss 11% in weight to 350°C, nearly all between 250 and 350°C. The name is for the mine. The mineral and name were aproved before publication by the Commission on New Minerals and Mineral Names, IMA. Two short communications on akaganeite have been described in Japanese by the present author (1957, 1960).
1 0 0 0 注意のマネジメント ―ミュンスターバーグ、産業心理学、映画理論
- 著者
- 篠木 涼
- 出版者
- 立命館大学生存学研究センター
- 雑誌
- 生存学 : 生きて存るを学ぶ
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.374-389, 2010-03
1 0 0 0 OA PRの心理学,心理学のPR : エドワード・バーネイズと心理学の大衆化
- 著者
- 篠木 涼
- 出版者
- 立命館大学人間科学研究所
- 雑誌
- 立命館人間科学研究
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.75-89, 2013-07
- 著者
- 吉田 めぐ美
- 出版者
- 東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻
- 雑誌
- 超域文化科学紀要 (ISSN:13492403)
- 巻号頁・発行日
- no.10, pp.105-119, 2005
- 著者
- 斉藤 勝司
- 出版者
- 誠文堂新光社
- 雑誌
- 農耕と園芸 (ISSN:13458833)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.10, pp.18-23, 2014-10
- 著者
- 浅井 隆彦
- 出版者
- フレグランスジャーナル社
- 雑誌
- フレグランスジャーナル (ISSN:02889803)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.9, pp.63-68, 2009-09
1 0 0 0 第31回医学情報サービス研究大会(MIS31)
- 出版者
- 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.7, pp.501-503, 2014-10
1 0 0 0 イノベーションとは 科学技術の視点から
- 著者
- 山下 恭範
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.7, pp.504-509, 2014
1 0 0 0 イノベーションとは 科学技術の視点から
- 著者
- 山下 恭範
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.7, pp.504-509, 2014
1 0 0 0 著作物の公正使用 おとぎ話同然?
- 著者
- 名和 小太郎
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.7, pp.497-500, 2014
1 0 0 0 つながれインフォプロ 第13回
- 著者
- 迫田 けい子
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.7, pp.494-496, 2014
- 著者
- 上野 佳恵
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.7, pp.484-489, 2014