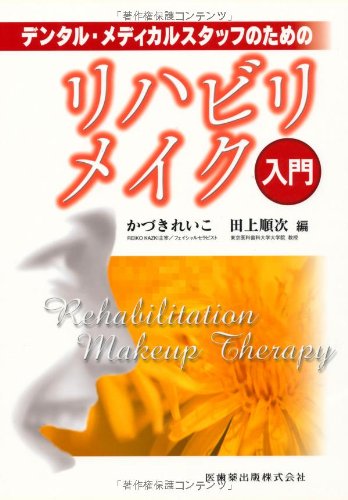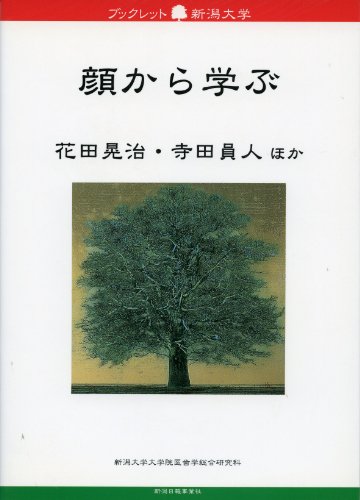1 0 0 0 OA 配電盤劣化診断及び余寿命推定手法に関する研究
1 0 0 0 デンタル・メディカルスタッフのためのリハビリメイク入門
- 著者
- かづきれいこ 田上順次編
- 出版者
- 医歯薬出版
- 巻号頁・発行日
- 2004
1 0 0 0 顔から学ぶ
- 著者
- 花田晃治 [ほか] 著 新潟大学大学院医歯学総合研究科ブックレット新潟大学編集委員会編
- 出版者
- 新潟日報事業社
- 巻号頁・発行日
- 2004
1 0 0 0 岩手県関係大正刊行書目
1 0 0 0 岩手県関係明治刊行書目
- 著者
- 籔内 佐斗司
- 出版者
- 新潮社
- 雑誌
- 芸術新潮 (ISSN:04351657)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.2, pp.p47-49, 1988-02
- 著者
- 楊 舒洪 進士 五十八
- 出版者
- 社団法人日本造園学会
- 雑誌
- ランドスケープ研究 : 日本造園学会誌 : journal of the Japanese Institute of Landscape Architecture (ISSN:13408984)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.5, pp.465-470, 1997-03-28
- 被引用文献数
- 2
中国杭州の「西湖十景」は,南宋時代(1127〜1278)に南宋画院の画家らに画題として描かれることによって成立した風景地である。本研究は,「西湖十景」が成立するまでの背景や形成要因ならびにその発展と変化を史実から明らかにすると共に,このような人文的景勝地(名所)の発展条件について考察した。その結果「西湖十景」は,(1)南宋の都としての杭州の発展(2)杭州と西湖の風土(3)西湖らしさというイメージの固定化と定着(4)権力者の芸術愛好による風景画の興隆と需要増(5)南宋画院における山水画の構図の改変などを背景として成立し,そして媒体の宣伝によって景名が保存されたり,時代とともに見直され,現在にいたっていることが判明した。
1 0 0 0 OA 逓信省塔上ヨリ東京市中展望ノ景
1 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1916年02月08日, 1916-02-08
1 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1932年07月14日, 1932-07-14
1 0 0 0 脳活動の非対称性と吉田法の関連性 : 音刺激による生体反応評価
- 著者
- 陳 曦 高橋 勲 沖田 義光 平田 寿 杉浦 敏文
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. MBE, MEとバイオサイバネティックス (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.111, no.423, pp.77-82, 2012-01-20
音刺激(怖い音と快適な音)に対する心理反応を脳波前頭葉非対称性モデル(anterior asymmetry and emotion model, AAE model)と吉田法によって評価,検討し,両方法の信頼性と関連性を検討した.被験者は21〜25歳までの大学院生13名(22.9±1.3歳)であり,実験中はゆったりとした椅子に座って目を閉じてもらった(前安静10分,音呈示5分,後安静10分).AAEモデルによって消極的な反応を示したと判断された被験者は吉田法による評価では不快度が増加しており,積極的な反応を示したと判断された被験者は快適度が変わらないか,少し快な状態へと変化していた.本研究の結果,AAEモデルと吉田法は心理評価法として信頼できる方法であるとともに両者の間に一定の関係があることが分かった.
1 0 0 0 Partial Marking GC
- 著者
- 田中良夫 松井 祥悟 前田 敦司 中西 正和
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会記号処理研究会報告
- 巻号頁・発行日
- vol.94, no.49, pp.17-24, 1994
- 被引用文献数
- 1
通常ガーベッジコレクション(GC)はリスト処理を中断して行なわれる.GCをリスト処理と並列に行なう(並列GC)ことにより,GCによる中断時間をなくし,リスト処理の実時間化が可能となる.並列GCではGCの処理中にリスト処理によってデータが書き換えられるので,GCの正当性を保証するために特殊な処理が必要となる.そのため並列GCは停止型GCに比べてあまり効率が上がらず,実用化されているものもほとんどない.mark and sweep方式の並列GCにおいては,ゴミセルの回収効率が停止型GCに比べて約1/2になってしまうことが知られている.これらの欠点の改善は,並列GCの実用化へ向けての重要な研究テーマである.本論文では,mark and sweep方式の並列GCの欠点を改善したGCである,Partial Marking GC(PMGC)の提案,実装および評価に関する報告を行なう. PMGCはmark and sweep型の並列GCに世代別GCの概念を導入したGCである.PMGCを実装し様々な実験を行なった結果,PMGCによってゴミセルの回収効率は従来の並列GCに比べ最大で2倍に改善されることが確認された.PMGCは並列GCの実用化に向けての有効なGCである.
1 0 0 0 月刊美術
- 出版者
- 実業之日本社(発売)
- 巻号頁・発行日
- 1975
1 0 0 0 帰納論理プログラミングによる数値データからの学習
帰納論理プログラミングは事例集合と背景知識から第一階節を導出する枠組みであり,GOLEM,FOIL,PROGOL[2]などの高速な学習システムが開発され,様々な実問題への適用も行われている.しかしながら,この枠組みは実数等の数値データからの学習には適していないため,我々は制約論理から出発した枠組みを提案した.本稿ではこの枠組みを実現する数値データからの学習方法を提案する.この方法は仮説空間を探索する際に特徴があり,リテラルの追加による仮説の特殊化と数値データから制約への一般化の2つの操作を組み合わせている.以下では,この方法を例に従って述べる.
- 著者
- Ryozo Nagai Koichiro Kinugawa Hiroshi Inoue Hirotsugu Atarashi Yoshihiko Seino Takeshi Yamashita Wataru Shimizu Takeshi Aiba Masafumi Kitakaze Atsuhiro Sakamoto Takanori Ikeda Yasushi Imai Takashi Daimon Katsuhiro Fujino Tetsuji Nagano Tatsuaki Okamura Masatsugu Hori the J-Land Investigators
- 出版者
- 日本循環器学会
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- pp.CJ-12-1618, (Released:2013-03-15)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 21 93
Background: A rapid heart rate (HR) during atrial fibrillation (AF) and atrial flutter (AFL) in left ventricular (LV) dysfunction often impairs cardiac performance. The J-Land study was conducted to compare the efficacy and safety of landiolol, an ultra-short-acting β-blocker, with those of digoxin for swift control of tachycardia in AF/AFL in patients with LV dysfunction. Methods and Results: The 200 patients with AF/AFL, HR ≥120beats/min, and LV ejection fraction 25–50% were randomized to receive either landiolol (n=93) or digoxin (n=107). Successful HR control was defined as ≥20% reduction in HR together with HR <110beats/min at 2h after starting intravenous administration of landiolol or digoxin. The dose of landiolol was adjusted in the range of 1–10μg·kg–1·min–1 according to the patient’s condition. The mean HR at baseline was 138.2±15.7 and 138.0±15.0beats/min in the landiolol and digoxin groups, respectively. Successful HR control was achieved in 48.0% of patients treated with landiolol and in 13.9% of patients treated with digoxin (P<0.0001). Serious adverse events were reported in 2 and 3 patients in each group, respectively. Conclusions: Landiolol was more effective for controlling rapid HR than digoxin in AF/AFL patients with LV dysfunction, and could be considered as a therapeutic option in this clinical setting.
- 著者
- Makoto OTANI Tatsuya HIRAHARA
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences (ISSN:09168508)
- 巻号頁・発行日
- vol.E94-A, no.9, pp.1779-1785, 2011-09-01
A non-audible murmur (NAM), a very weak whisper sound produced without vocal fold vibration, has been researched in the development of a silent-speech communication tool for functional speech disorders as well as human-to-human/machine interfaces with inaudible voice input. The NAM can be detected using a specially designed microphone, called a NAM microphone, attached to the neck. However, the detected NAM signal has a low signal-to-noise ratio and severely suppressed high-frequency component. To improve NAM clarity, the mechanism of a NAM production must be clarified. In this work, an air flow through a glottis in the vocal tract was numerically simulated using computational fluid dynamics and vocal tract shape models that are obtained by a magnetic resonance imaging (MRI) scan for whispered voice production with various strengths, i.e. strong, weak, and very weak. For a very weak whispering during the MRI scan, subjects were trained, just before the scanning, to produce the very weak whispered voice, or the NAM. The numerical results show that a weak vorticity flow occurs in the supraglottal region even during a very weak whisper production; such vorticity flow provide aeroacoustic sources for a very weak whispering, i.e. NAM, as in an ordinary whispering.