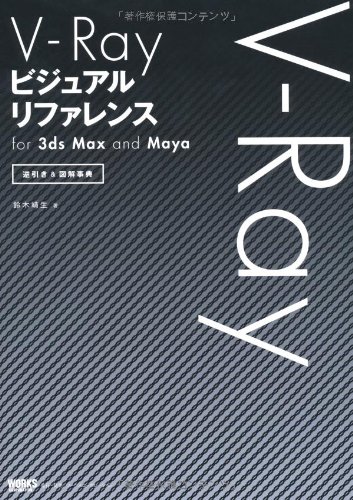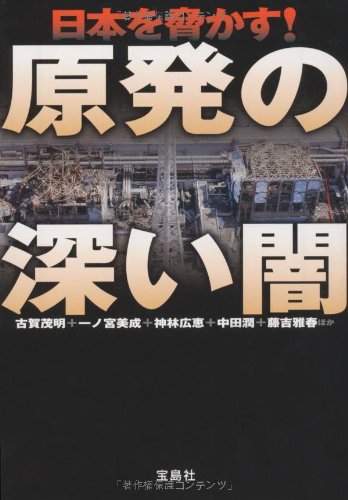1 0 0 0 伊達政宗
- 出版者
- デアゴスティーニ・ジャパン
- 巻号頁・発行日
- 2012
1 0 0 0 OA <資料>パフォーマンス空間の生成 : サン・フェルミン祭を事例として
- 著者
- 水谷 由美子
- 出版者
- 山口県立大学
- 雑誌
- 山口県立大学生活科学部研究報告 (ISSN:13444999)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.43-51, 2000-03-25
パンプローナ市で毎年7月6日から7月14日まで実施されるサン・フェルミン祭は,守護聖人を敬う地域的な祝祭儀礼である。現代では世界的に有名になり,伝統的なものばかりでなく,現代的なプログラムも増えている。こうした中で祭りの本質と言えるものが,エンシエロ(牛追い),祝日の行列そしてヒガンテスとその仲間のパフォーマンスであり,そこにはこの都市固有の伝統的な文化が表されている。特に,サン・フェルミン祭では老若男女が皆,全身白い服装をして首に赤いスカーフを巻くという戦後から定着してきた仮装に特徴がある。本論は1999年に筆者がフィールドワークした成果を報告する中で,この固有の仮装と伝統的な祝祭儀礼という文化的なパフォーマンスについて記述し,そこで生成されるパフォーマンス空間の意味と機能について検討したもの。
1 0 0 0 IR C.バーニーのイタリア音楽紀行
- 著者
- 今井 民子
- 出版者
- 弘前大学
- 雑誌
- 弘前大学教育学部紀要 (ISSN:04391713)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, pp.65-71, 1997-10
イギリスの音楽史家,Cノヤーニーの『ヨーロッパ音楽紀行』は,主著である『音楽通史』執筆の資料収集を目的に企てた大陸旅行の見聞録である。本稿では,この旅行記に基づき,彼が見聞した教会,劇場,私的コンサートにおける音楽活動の実態と,その他,大道の音楽,楽器,楽譜について,主にイタリアを中心に検討する。まず,イタリアの教会音楽では,世俗化の著しい祝日の音楽と,平日の素朴で古風な聖歌との対照が指摘される。オペラ劇場では,貴族と一般市民からなる聴衆,音楽家の生活支援のための劇場コンサートが,また,私的コンサートでは,教養豊かなディレッタントによる良質のコンサート(アッカデーミア)の様子が言及される。バロックの教会,劇場,室内という音楽様式の3つの区分はあいまい化し,相互の融合,類似化が窺える。その他,野趣に富む大道の民謡,後年,『音楽通史』に結実する楽器や楽譜の資料収集に関する記述がある。
1 0 0 0 作って覚えるExcel カレンダー(第3回)祝日を赤く表示させる
- 著者
- 岡村 秀昭
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経パソコン (ISSN:02879506)
- 巻号頁・発行日
- no.451, pp.135-138, 2004-02-16
ダブルクリックで見出しを付ける/祝日はWebで確認して確実に/条件付き書式の優先順位に注意/ゴールデンウィークで確認
- 著者
- 鈴木靖生著
- 出版者
- ワークスコーポレーション
- 巻号頁・発行日
- 2013
1 0 0 0 IR <政策科学会2008秋季公開講演会> 彦根城下町の挑戦 : ゆるキャラの活用
- 著者
- 安達 昇
- 出版者
- 立命館大学
- 雑誌
- 政策科学 (ISSN:09194851)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.151-158, 2009-10
1 0 0 0 追悼 ジャン=ジャック・オリガス教授
- 出版者
- すずさわ書店
- 雑誌
- 比較文學研究 (ISSN:0437455X)
- 巻号頁・発行日
- no.83, pp.105-116,1〜7, 2004-03
1 0 0 0 <研究動向:分野別研究動向(労働)>産業・労働社会学の現状と課題
- 著者
- 小川 慎一
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.4, pp.964-981, 2006-03-31
- 被引用文献数
- 2
- 著者
- 有本 真紀
- 出版者
- 立教大学
- 雑誌
- 立教大学教育学科研究年報 (ISSN:03876780)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, pp.5-20, 2007
1 0 0 0 モーフィング付きスケルトントゥイーニング
コンピュータグラフィックス(CG)アニメーションは、最近のTVや映画等で盛んに用いられているが、一般に人達にはまだまだ遠い存在である。もっとより多くの人が簡単に使用できて、できる限り制限の少ない、リアリスティックなアニメーションシステムは作成できないだろうか。現在のCGアニメーションは、作り手が描いた絵(グラフィック)を何枚もコマ撮りしていくものや、予め撮影された動画像(ムービー)をデジタル入力したものが代表的な手法である。しかし、グラフィックの場合は、作り手の絵心の有無によって随分と違ったものとなるし、リアリスティックな動きを表現するのに特殊な技法を用いる事や、短編のアニメーションであっても、必要な絵の枚数は膨大な量である。また、ムービーの場合も、大規模なセットやアクター等が必要であり、多くの人が簡単に用いることはできない。だからといって、アニメーションはある特定の人達でないと作成できないものなのであろうか。その間題を解決することが今回のテーマである。そのために写真のようなムービーでいないものでもイメージとしてスキャニングを行い、そのイメージをスケルトンモデルに貼り付けて大まかな動きの表現を実現し、また、こと細かい動きの表現に関しては、モーフィングを使う事により実現する、簡単で、リアリスティックで、柔軟なアニメーションシステムを提案する。
1 0 0 0 OA DLAの成長特性とフラクタル次元
- 著者
- 太田 正之輔
- 出版者
- 物性研究刊行会
- 雑誌
- 物性研究 (ISSN:07272997)
- 巻号頁・発行日
- vol.93, no.1, pp.33-69, 2009-10-05
この論文は国立情報学研究所の電子図書館事業により電子化されました。
- 著者
- 安部 素実 田原 志浩 大和田 哲
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. MW, マイクロ波 (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.111, no.313, pp.25-29, 2011-11-17
マイクロストリップ結合線路で構成されるカプラは、ストリップ導体の間隔と幅の製造限界により、一定以上の密結合度を得るのが困難、また偶・奇モードの位相速度が異なることから、方向性が劣化しやすい問題がある。これらの課題に対し、マイクロストリップ結合線路で構成される多段カプラにおいて、最も密結合となる1/4波長結合線路の幅を一部狭くするとともに、幅を狭めていない部分にズリットを設ける構造で密結合かつ高方向性を得る手法を提案する。ここでは、本1/4波長結合線路を用いた多段カプラを検討し、カプラとしての所望結合度を実現するために、最密結合段の特性インピーダンスを他段より高くする手法も用いている。提案構成を適用した多段マイクロストリップ結合線路型カプラの試作評価を行った結果、比帯域162%にわたり良好な特性が実現し、本構成の有効性が確認された。
- 著者
- 西村 貴裕
- 出版者
- 大阪教育大学
- 雑誌
- 大阪教育大学紀要 第II部門 社会科学・生活科学 (ISSN:03893456)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.2, pp.1-18, 2012-02-29
本稿は,自然保護をめぐる議論が戦前・戦中にどのようなイデオロギーと結びつき得たかを分析するものである。国立公園制度の意義について,雑誌『国立公園』(1929~44年,1943年からは『国土と健民』と改称)誌上に掲載された論考を追い,国立公園が「国民精神」の涵養のため,あるいは戦争に耐え得る心身を作る「鍛錬」のため利用されるべきだと主張されるに至った経緯を分析する。さらに,こうした日本の言説に対応するドイツでの郷土保護・自然保護をめぐる言説を紹介し,その対比を若干試みる。In diesem Artikel analysiere ich die Entwicklung des Diskurses über die Bedeutung des Nationalparks in Japan während der Kriegszeit anhand der Zeitschrift "Nationalpark" (1929-1944). Hier wird gezeigt, daß genau der Diskurs, den Thomas Lekan als "Militalisierung von Natur und Heimat" bezeichnete, gab es auch in Japan. Darüber hinaus war der Diskurs in Japan gut vergleichbar mit dem in Deutschland während der Nazi Zeit. Diese Tatsache zeigt, daß wir über die Bedeutung des Naturschutzes tief reflektieren müssen.
1 0 0 0 日本を脅かす!原発の深い闇
- 著者
- 古賀茂明 [ほか] 著
- 出版者
- 宝島社
- 巻号頁・発行日
- 2012
1 0 0 0 IR 慢性関節リウマチを合併し抗ゴルジ抗体陽性を示した自己免疫性肝炎の1例
- 著者
- 谷合 麻紀子 穐和 信子 稲葉 博之 風間 吉彦 小林 潔正 松島 昭三 小松 達司 進藤 仁 高橋 陽 林 直諒 成田 洋一 宮地 清光
- 出版者
- 東京女子医科大学学会
- 雑誌
- 東京女子医科大学雑誌 (ISSN:00409022)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.6, pp.601-602, 1994-07-25
第25回消化器病センター例会 1994年1月22日‐23日 東京女子医科大学弥生記念講堂
1 0 0 0 用水空間における水辺の変貌について : 都市計画
- 著者
- 中岡 義介
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 学術講演梗概集. 計画系
- 巻号頁・発行日
- no.53, pp.1621-1622, 1978-09