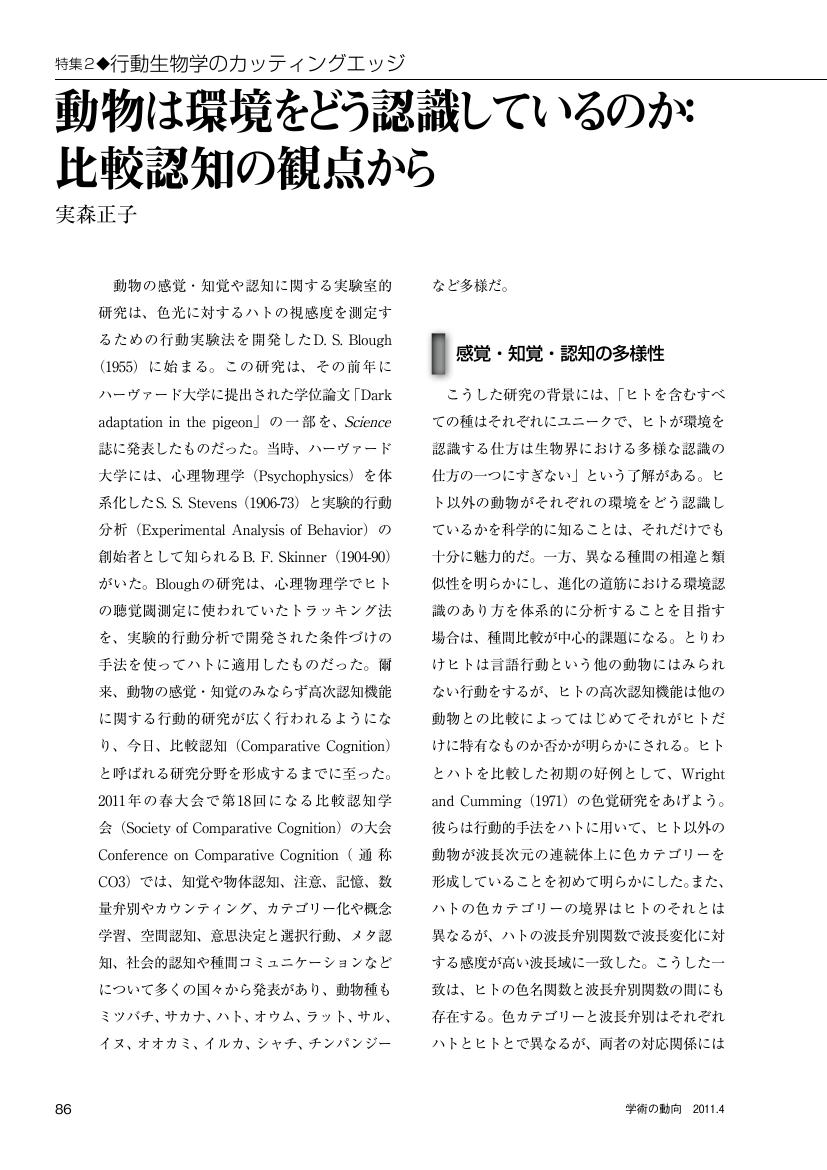3 0 0 0 知識の構造化俯瞰表現に関する研究
- 著者
- 大槻 明 岡田 謙一
- 出版者
- Japan Society of Information and Knowledge
- 雑誌
- 情報知識学会誌 (ISSN:09171436)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.3, pp.350-361, 2011-09-27
本研究では,筆者らが提案している知識を構造的に俯瞰表現する「構造化俯瞰図」をさらに発展し,同図を構成する各知識に属性情報や叙述を付与し,それら属性情報等を含めた知識同士の関係性を意味付けしたうえで俯瞰マップを作成するCosut(Concept Support Tool)について提案する.Cosutを使用することにより,当該知識群のさらなる整理や分析を実現することが可能となる.つまり,企業における新商品開発や課題解決時,さらには研究機関における新理論の検討時など,様々な場面における知識の有効活用に資することができるものと考える.評価実験では,構造化俯瞰図を使用した場合に比べた定量的分析及び概念構造の変化を分析した.その結果,仮説をまとめるためのアイディアの量的な増加傾向が確認され,さらには,Cosutが被験者の概念構造に直接影響を与えた部分を把握することが可能になるなどの発想支援的な効果が認められた.
3 0 0 0 OA GIS と言語研究 (GIS 特集)
- 著者
- 池田 潤
- 出版者
- 筑波一般言語学研究会
- 雑誌
- 一般言語学論叢 (ISSN:13443046)
- 巻号頁・発行日
- no.9, pp.1-10, 2006-12-31 (Released:2013-12-25)
3 0 0 0 IR アニメ・マンガの日本語--ジャンル用語の特徴をめぐって
- 著者
- 熊野 七絵
- 出版者
- 広島大学国際センター国際教育部門
- 雑誌
- 広島大学国際センター紀要 (ISSN:21862028)
- 巻号頁・発行日
- no.1, pp.35-49, 2011-03
表7(p.49)を修正: 2011.5.12.
- 著者
- 市丸 道人 石丸 寅之助 JOSEPH L. BELSKY
- 出版者
- Journal of Radiation Research 編集委員会
- 雑誌
- Journal of Radiation Research (ISSN:04493060)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.3, pp.262-282, 1978-09-15 (Released:2006-07-14)
- 参考文献数
- 38
- 被引用文献数
- 35 57
The leukemogenic effect of atomic radiation was examined in relation to age at the time of the bomb (ATB), calendar time, and type of leukemia over the period 1950-71. Confirmed cases of leukemia in the Leukemia Registry, a fixed cohort of 109, 000 subjects and the T65 dose calculations provided the basis for the analysis. Calendar time was divided into three periods, 5-10, 10-15, and 15-26 years after the bombs. The larger the exposure dose and the younger the age ATB, the greater was the effect in the early period and the more rapid was the decline in risk in subsequent years. In the oldest group, aged 45 or over ATB, the increase in risk appeared later and was sustained in the period 1960-71. Chronic granulocytic leukemia contributed substantially to the total leukemogenic effect initially but made little contribution after 1955. Sensitivity to the leukemogenic effect of atomic radiation not only depended on age ATB but its expression varied by type of leukemia and with time after exposure. Although the effect of atomic radiation on the incidence of leukemia in the atomic survivors is now greatly reduced and apparently on the wane, in the period 1966-71 the incidence was still greater than expected, especially in Hiroshima. In the Nagasaki sample, no case of leukemia was observed among the high-dose subjects from July 1966 to the end of 1971.
3 0 0 0 ODAコンバータの機能仕様の検討
我々はこれまでマルチメディア文書交換形式(ODA)の処理系の研究開発を行なって来た。その一環として、ODA実装規約AE.1136準拠のPDAの処理系を既存のDTPシステムとのコンバータ方式により試作し、その実装および評価について先に報告した。今回、その際に課題として残った点に対応した実用的なODAコンバータの実現を目指し、その実現目標となる機能仕様について検討を行なった。処理対象はODA実装規約AE.1126準拠のODA文書とした。本稿では、検討したODAコンバータの機能仕様について述べる。
3 0 0 0 OA 近世大名屋敷における食生活 : 港区郵政省飯倉分館構内遺跡出土の動物依存体を中心に
- 著者
- 桜井 準也
- 出版者
- 慶應義塾大学
- 雑誌
- 史学 (ISSN:03869334)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.1, pp.79-97, 1987-05
論文I はじめにII 港区麻布台一丁目郵政省飯倉分館構内遺跡出土の動物遺存体 一 麻布台一丁目郵政省飯倉分館構内遺跡 二 出土した動物遺存体の内容III 遺跡出土の動物遺存体からみた大名屋敷における食生活 一 大名屋敷の居住者 二 出土した動物遺存体の性格 三 食物嗜好の変化 四 出土した動物遺存体と贈答品IV 食事の献立からみた大名と下級武士の食生活 一 大名の日常食 二 下級武士の日常食 三 栄養状態からみた大名と下級武士V まとめNumerous faunal remains have been excavated from many modern age sites in Tokyo With the increased excavation activity, several aspects of dietary patterns in the Edo era have been identified At the Azabudai site in Minato-ku, Tokyo, many fish bones and shells have been excavated from refuse pits These are the remains of food consumed by residents of the site, on which had stood the official residences of two daimyo, the Uesugi and Inaba, in the Edo era. The remains are of two main types one is exemplified by red sea-bream bones and abalone shells, traditionally exchanged as gifts among the daimyo and other members of the upper classes, the other is mainly sardine bones and corbicula shells, which were widely consumed among the inhabitants of Edo. This shows that the residents of the site represented all social classes, from daimyo to servant. Servants were chosen from among farmers and city people to provide domestic services. The backbones of tuna at the site were excavated only from pits dating form the latter half of the eighteenth century Historical sources from the Edo era suggest that tuna was note a major seafood before the middle of the eighteenth century. However, wth the development of fishing technology and the expansion of the city population in the latter half of the eighteenth century, tuna became an important source of protein among the inhabitants of the city. This coincidence of archaeological and historical evidence is a good example of how one can reconstruct cultural history with the co-operation of archaeology and history
3 0 0 0 COMETS搭載移動体衛星通信用機器(MCE)の軌道上性能
- 著者
- 斉藤 春夫 三浦 周 小原 徳昭 岡本 英二 山本 伸一 森川 栄久 小園 晋一 若菜 弘充
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会論文誌. B, 通信 (ISSN:13444697)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.4, pp.731-740, 2001-04-01
通信放送技術衛星(COMETS)は, 平成10年2月21日に打ち上げられたが, H-IIロケット第2段エンジンの故障により静止トランスファー軌道への投入に失敗した.その後, アポジエンジンによる7回の軌道変更により, 遠地点高度17,711km, 近地点高度473kmの2日9周回の準回帰軌道にのせることに成功し, 1日当り最長90分間の通信実験が行えることになった.平成10年8月末から通信・放送実験が開始され, 平成11年1月に定常運用段階を終了し, 2月からは後期利用段階に移行した.しかし, 残念ながら平成11年8月6日に, 予定された運用期間のほぼ半分でCOMETSの運用は終了した.本論文では, 軌道変更直後に衛星のテレメトリのみを用いて実施された軌道上における移動体衛星通信用機器(MCE)の初期機能確認試験と, その後, 地球局から実際に通波して行われた軌道上機能評価実験の結果ついて述べる.周回化により懸念されていた放射線の影響による特性の劣化はごく一部に限られ, ほとんどのMCE機器が軌道上においてもほぼ良好に機能していることが判明した.
3 0 0 0 樹木構造接近法と最近の発展
- 著者
- 杉本 知之 下川 敏雄 後藤 昌司
- 出版者
- 日本計算機統計学会
- 雑誌
- 計算機統計学 (ISSN:09148930)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.2, pp.123-164, 2007-02-28
- 被引用文献数
- 7
本稿では,樹木構造接近法とその発展の主要な流れを総合的に省察する.CARTの方法論は諸種の樹木構造接近法の理解と発展において避けることのできない基礎をなしている.MARS法はCART法の連続型への有意義な拡張である.最近の発展において,アンサンブル学習法と融合し組み立てられた接近法は,より強い予測性能をもち,より魅力的な変数重要度の結果を与える.ここでは,広範な応用への示唆を提供するために,これらの諸種の方法における適用例と簡単なシミュレーション結果を与える.最後に,各方法の特微を要約し,今後において関心のある研究を与える.
3 0 0 0 OA 芸術受容の近代的パラダイム : 日本における見る欲望と価値観の形成
3 0 0 0 OA 動物は環境をどう認識しているのか: 比較認知の観点から
- 著者
- 実森 正子
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.4, pp.4_86-4_88, 2011-04-01 (Released:2011-08-18)
- 参考文献数
- 6
前年度に引き続き、写真言説の中でとりわけ重要と思われる、カルティエ=ブレッソン受容文脈の変遷について、研究・調査を行った。昨年度、新型インフルエンザ流行と、海外での資料開示状況が思わしくなかったために見合わせていた出張を積極的に行った。まず六月にニューヨーク近代美術館のアーカイヴへの出張を行った。これはアメリカにおけるカルティエ=ブレッソン受容の状況を掘りこす意味で重要な調査であり、一部、公開審査を停止している資料があったものの、二十世紀後半の状況について、調査を行うことできた。また、八月には国際比較文学会(ICLA)の大会(於韓国ソウル、中央大学校)に参加し、研究発表を行った。これは、前述ニューヨーク出張の成果を踏まえたものである。またこの研究発表に関連して、国際比較文学会のProceedings(研究発表記録集)も英文原稿を投稿し(本年一月)、掲載可否の査読を待っているところである。なお、本研究に関連して博士論文の執筆中であるため、これ以外の途中段階の研究報告は行わなかった。本研究の二年間の採用年度の間に、次々と新しい題材が見つかり、研究対象の範囲を拡げてきたが、写真関連の一次資料(写真集ど)および二次資料(研究文献)は、国内の所蔵が極めて少なく、基本的な文献でも国内の図書館に全く所蔵されていない物も少ななかった。また、これらについて海外の図書館から複写取り寄せを試みたが、いずれも新しい時代の題材であるために,複写許可がりない物がほとんどであった。したがって、必要最低限のものは独自に購入せざるを得ず、本年度も昨年度に引き続き、洋文献購入特別研究員奨励費の多くを使った。その結果、本研究に関わる題材の、海外における研究状況の概略が明らかになったほか、従来の真研究の通説とは違った構図も徐々に発掘でき、現在執筆中の博士論文にも大きな前進が見られた。
3 0 0 0 OA 近世仏教説話の研究 : 唱導と文芸
- 著者
- 堤邦彦 [著]
- 巻号頁・発行日
- 1995
- 著者
- 植野 真澄
- 出版者
- 東京社会福祉史研究会
- 雑誌
- 東京社会福祉史研究 (ISSN:18819869)
- 巻号頁・発行日
- no.4, pp.71-86, 2010-05
3 0 0 0 OA 作業療法臨床実習における信念対立解明アプローチの応用可能性
- 著者
- 京極 真
- 出版者
- 吉備国際大学
- 雑誌
- 吉備国際大学研究紀要. 医療・自然科学系 (ISSN:21867410)
- 巻号頁・発行日
- no.22, pp.37-45, 2012-03-31
- 著者
- John HOWARD Frank HEARL
- 出版者
- National Institute of Occupational Safety and Health
- 雑誌
- Industrial Health (ISSN:00198366)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.2, pp.80-83, 2012 (Released:2012-04-13)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 4 7
In the USA, national worker protection legislation was enacted in 1970. The legislation required that research, recommendations and guidance be developed to aid employers and workers, that workplace health and safety standards be adopted, that employer comply with those rules and that the government police employer compliance, and that assistance be offered to employers and workers to help them maintain a safe and healthful workplace. In the 40 yr since passage of the Occupational Safety and Health Act of 1970, worker injury, illness and fatalities have declined but not been eliminated. Efforts to accelerate the standards adoption process are much discussed in the USA along with how to protect workers from emerging hazards like nanotechnology. New strategies which seek to eliminate not only the causes of work-related injury and illness, but also more broadly, worker injury and illness, are on the horizon.
- 著者
- 中村 恭子
- 出版者
- 日本農学図書館協議会
- 雑誌
- 日本農学図書館協議会誌 (ISSN:13421905)
- 巻号頁・発行日
- no.162, pp.1-6, 2011-06