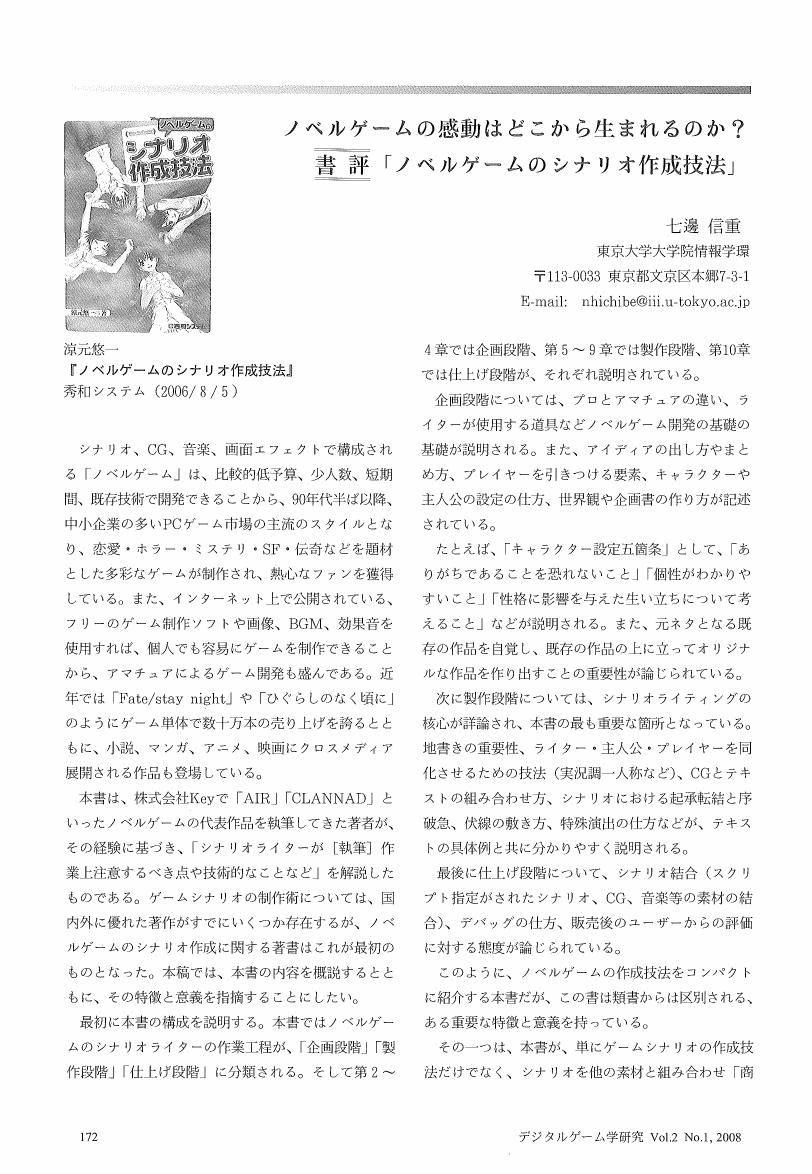2 0 0 0 OA ブレイクとスウェーデンボルグ (出渕敬子教授記念論文集)
- 著者
- 新見 肇子 ニイミハツコ Hatsuko Niimi
- 雑誌
- 日本女子大学英米文学研究
- 巻号頁・発行日
- vol.41, pp.181-192, 2006-03
2 0 0 0 OA お遍路における巡回セールスマン問題
- 著者
- 鳥居 鉱太郎 Koutaro Torii
- 雑誌
- 松山大学論集 = Matsuyama University review (ISSN:09163298)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.3, pp.89-101, 2011-08-01
2 0 0 0 OA 有翼飛翔体計画: HIMES
- 著者
- 稲谷 芳文
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測と制御 (ISSN:04534662)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.6, pp.499-502, 1987-06-10 (Released:2009-11-26)
2 0 0 0 OA 強まる反インフォーマリティの規範――マニラ首都圏スラムの「盗電」を事例に――
- 著者
- 宮川 慎司
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- アジア経済 (ISSN:00022942)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.3, pp.28-60, 2020-09-15 (Released:2020-10-14)
- 参考文献数
- 50
途上国の貧困層は,生活の上で当局に認められないインフォーマルな活動を行うことが少なくない。本稿は,互いの苦境を理解するマニラ首都圏の貧困層自身が,なぜ2010年代半ばになって反インフォーマリティの規範をもつようになったかについて,スラム地域の「盗電」に関する調査から考察する。盗電を行う住民と行わない住民双方の論理から,盗電を許容しない規範が生じる理由を明らかにする。もとよりスラム住民は火災発生の恐れがある盗電に対して批判的な規範をもつ一方で,電力正規契約を得る障壁の高さから盗電を正当化していた。しかし近年の2つの法執行強化により,盗電は許容されなくなりつつある。第1に,技術的な取締りの導入により,盗電を取締られた住民が金銭的負担の不公平から盗電に対して批判を強めた。第2に,ドゥテルテ政権下における公的機関の行政手続き改善を背景に,正規契約を得る障壁低下の可能性が示され,盗電の正当化が難しくなった。
2 0 0 0 OA 田辺聖子の少女時代の作品 : 『伸びゆく者』を中心に
- 著者
- 中 周子
- 出版者
- 大阪樟蔭女子大学
- 雑誌
- 樟蔭国文学 (ISSN:03898792)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, pp.1-16, 2021-03-01
2 0 0 0 OA 3.心臓リハビリ代替法としての神経筋電気刺激療法: 現況と将来展望
2 0 0 0 OA ミョウバンとその代替化合物の添加がパンケーキの膨張と構成タンパク質に与える影響
- 著者
- 齊藤 紅 簑島 良一 椎葉 究
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.4, pp.170-175, 2016-04-15 (Released:2016-05-31)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1 1
ミョウバン中の硫酸アルミニウムカリウム(PAS)やグルコノ-δ-ラクトン(GDL)がパンケーキなど膨張剤として使用されているが,それらのタンパク質への影響について,オズボーン分画変法によりタンパク質を分画しその構成比の違いから評価した.その結果,PASやGDLの添加量を増やすと,パンケーキ中の水溶性タンパク質(アルブミン区分)の比率が減少し,代わって水不溶性の区分,特に70 %エタノール可溶性タンパク質(グリアジン区分)や酸可溶性タンパク質(可溶性グルテニン)および不溶性グルテニン区分が増加する傾向にあり,全体的にタンパク質の水不溶性が増加する傾向があった.このタンパク質の構成の変化の原因を探るため,いろいろな化合物を添加して効果を比較した中で,過酸化水素水の添加は,パンケーキの膨張にたいへん効果的であり,PASやGDL添加時と同様なタンパク質の水不溶化傾向を生じた.一方,増粘多糖類であるアルギン酸ナトリウム(SAA)の添加は,そのような効果が認められなかった.
2 0 0 0 OA ノベルゲームの感動はどこから生まれるのか? 書評「ノベルゲームのシナリオ作成技法」
- 著者
- 七邊 信重
- 出版者
- 日本デジタルゲーム学会
- 雑誌
- デジタルゲーム学研究 (ISSN:18820913)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.172-173, 2008 (Released:2021-07-01)
2 0 0 0 IR 映画「天城越え」についてのインタビュー記録羽方義昌篇
- 著者
- 鶴田 武志
- 雑誌
- 文化科学研究 = CULTURAL SCIENCES
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.17-42, 2015-03-15
- 著者
- 福永 幹彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.12, pp.1104-1111, 2013-12-01 (Released:2017-08-01)
近年,確認できる機能性の異常に比して,強い身体症状を訴える患者を総称して「機能性身体症候群」と呼ぶことがある.これに含まれる患者は,一般外来患者の中にかなりの比率でいる.過敏性腸症候群,機能性ディスペプシア,線維筋痛症,慢性疲労症候群がその代表的なものだ.しかし,すでに機能性疾患として確立したものが多く含まれており,統合的な概念の必要性については疑問も多い.本稿では統合的な概念の意義につき,患者が重なり合う概念の,medically unexplained symptom,身体表現性障害,心身症などとの概念の違いを明らかにすることから検討した.統合的に考えることで,治療に関係するプライマリ・ケア医,各科専門医,精神科医,心療内科医に対して,症候群に共通する治療法を検討するため共通の土台を提供するということが最も大きいのではと考える.
2 0 0 0 OA ASD 児者の感覚の特性(過敏と鈍麻)に関する国内研究の動向
- 著者
- 長南 幸恵
- 出版者
- NPO法人 日本自閉症スペクトラム支援協会 日本自閉症スペクトラム学会
- 雑誌
- 自閉症スペクトラム研究 (ISSN:13475932)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.1, pp.29-39, 2014-11-30 (Released:2019-04-25)
- 参考文献数
- 54
- 被引用文献数
- 1
自閉症スペクトラム児者の感覚の特性に対する支援を検討するために、過去30 年間の国内研究のレビューを行った。医中誌Web 版にて「自閉症スペクトラム(Autism Spectrum Disorder: 以下ASD)」と「感覚」を検索キーワードとし、対象や内容が関連のないものを除外した結果、52 件であった。これまで医学的診断基準に感覚の特性(過敏や鈍麻:以下特性)が盛り込まれていなかったことが影響していると思われたが、今後は増加していくと予測される。感覚の特性に関する研究では、文献数および扱っている感覚数共に最多であった作業療法分野がその中心を担っていると思われた。ASD 児の半数以上に感覚の特性が生じ、生活の困難と結びつき、その程度や種類も個別性が高い。したがって、個々にアセスメントする必要があるが、誰がいつどのようにアセスメントしていくのかは、今後の課題の1 つである。さらにASD 児の母親は、早期から感覚の特性に気がついていることが多く、それが母親の感じる育てにくさにつながっている可能性がある。したがって、母親の感じる育てにくさから支援を開始することがASD 児の早期診断、早期支援に繋がる可能性があるだろう。
- 著者
- Hiroko Takumi Kazuko Kato Hiroki Nakanishi Maiko Tamura Takayo Ohto-N Saeko Nagao Junko Hirose
- 出版者
- Japan Oil Chemists' Society
- 雑誌
- Journal of Oleo Science (ISSN:13458957)
- 巻号頁・発行日
- pp.ess21449, (Released:2022-06-10)
- 被引用文献数
- 10
Precision nutrition, also referred to as personalized nutrition, focuses on the individual to determine the individual’s most effective eating plan to prevent or treat disease. A precision nutrition for infants requires the determination of the profile of human milk. We compared the lipid profiles of the foremilk (i.e., the initial milk of a breastfeed) and hindmilk (the last milk) of six Japanese subjects and evaluated whether a human milk lipid profile is useful for precision nutrition even though the fat concentration fluctuates during lactation. We detected and quantified 527 species with a lipidome analysis by liquid chromatography-tandem mass spectrometry. The fat concentration in hindmilk (120.6 ± 66.7 μmol/mL) was significantly higher than that in foremilk (68.6 ± 33.3 μmol/mL). While the total carbon number of fatty acids in triglyceride (TG) was highest in C52 for all subjects, the second or third number differed among the subjects. Both the distribution of total carbon number of fatty acids included in TG and the distribution of fatty acids in TG classified by the number of double bonds were almost the same in the foremilk and hindmilk in each subject. The lipids levels containing docosahexaenoic acid and arachidonic acid in total lipids of the foremilk and the hindmilk were almost the same in each subject. Among the sphingolipids and glycerophospholipids, the level of sphingomyelin was the highest in four subjects’ milk, and phosphatidylcholine was the highest in the other two subjects’ milk. The order of their major species was the same in each foremilk and hindmilk. A clustering heatmap revealed the differences between foremilk and hindmilk in the same subject were smaller than the differences among individuals. Our analyses indicate that a human-milk lipid profile reflects individual characteristics and is a worthwhile focus for precision nutrition.
- 著者
- Kakui Keiichi Shiraki Shoki
- 出版者
- The Crustacean Society
- 雑誌
- Journal of Crustacean Biology (ISSN:02780372)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.2, pp.ruab026, 2021-06
- 被引用文献数
- 1
Morphological diversity of sound-producing structures has not been well investigated among members of superorder Peracarida. Presumptive stridulatory sound-producing organs have been reported in some amphipods and tanaidaceans, and sound production by these organs has been documented in two isopod species in Oniscidea and Sphaeromatidea. Here we describe three presumptive stridulatory organs in the paranthurid isopod Paranthura cf. japonica Richardson, 1909, the first case known in Cymothoida. One type, consisting of a scale-bearing knob on the posterolateral corner of a pereonite and the scale-bearing anterolateral corner of the succeeding pereonite, was found between two pairs of pereonites (1, 2 and 2, 3). A second type involves a serrated structure in the sub-posterolateral region of pereonites 1 and 2, with the sharp anterolateral margins of pereonites 2 and 3 appearing to provide corresponding plectra. The third type involves an extension bearing a pair of serrated structures on the posteroventral margin of pereonites 1 and 2; the anterior-ventrolateral edges of pereonites 2 and 3 appear to provide corresponding plectra. All three organs occurred in both sexes of P. cf. japonica. Our discovery of novel, presumptive stridulatory organs in an intertidal isopod indicates that much remains to be learned about the biology of even common peracarid species.
2 0 0 0 OA 日立化成における半導体用CMPスラリーの開発
- 出版者
- 公益社団法人 精密工学会
- 雑誌
- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.7, pp.655-656, 2017-07-05 (Released:2017-07-05)
- 著者
- Ogasawara Masatoyo Yashiro Tomonari
- 出版者
- ARCHITECTURAL INSTITUTE OF JAPAN (AIJ), ARCHITECTURAL INSTITUTE OF KOREA (AIK), ARCHITECTURAL SOCIETY OF CHINA (ASC)
- 雑誌
- Journal of Asian Architecture and Building Engineering (ISSN:13467581)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.31-38, 2018-01-15 (Released:2018-01-15)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 2
This paper aims to illustrate the design review process of ″General Construction Companies″ (GCCs) and ″Design Firms″ (DFs) in Japan. It then quantitatively evaluates the time duration for the production of ″design and supportive documents″ which is required to go through a design review. The research is divided into three stages. First, the constraints in the design process in both GCCs and DFs are illustrated. Second, the duration of each design phase is measured to assess the allocation of resources for design coordination required by the constraints. Third, the most commonly shared building types in the survey were evaluated based on the ″designed floor area per month.″The survey statistically confirms the characteristics of the front-loaded design process by GCCs in the Preliminary Design phase to the Detailed Design Phase. GCCs have more cost and time constraints than DFs, through the involvement of the Cost Estimation and Procurement division in the construction department. It requires the production of ″design and supportive documents″ throughout the design process. On the contrary, DFs tend to spend more time and resources in the later part of the design process. This grants DFs more flexibility in cost and time throughout the design process as they have less strict constraints than GCCs.
2 0 0 0 OA オランウータンを殺したのは誰?-野生オランウータンの頭骨を対象とした法医学的研究-
- 著者
- 久世 濃子 河野 礼子 蔦谷 匠 金森 朝子 井上 陽一 石和田 研二 坂上 和弘
- 出版者
- 日本霊長類学会
- 雑誌
- 霊長類研究 Supplement 第34回日本霊長類学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.52, 2018 (Released:2018-11-22)
オランウータン(Pongo属)は,大きな体(雄:80kg,雌40kg)で樹上から下りることがほとんどないので,他の霊長類に比べて捕食のリスクが小さいと考えられている(Wich et al. 2004)。本研究では,野生オランウータンの頭骨を対象に,法医学的手法を用いて,中大型哺乳類に攻撃された可能性を検証した。対象の頭骨(頭蓋冠のみ:顎骨と歯は消失)は,ボルネオ島北部マレーシア領サバ州のダナムバレイ保護区内の熱帯雨林の林床で,2016年発見された。頭骨には側頭部に複数の損傷(貫通穴)が見られ,動物による咬傷の可能性が考えられた。主要な2つの穴の穴間距離(A)および,アタッカー候補である4種の上顎犬歯間距離(B)を測定した。アタッカー候補として,同所的に生息している中大型の肉食もしくは雑食(動物性食物を摂取した報告がある種)の哺乳類,ウンピョウ(Neofelis diardii),ヒゲイノシシ(Sus barbatus),マレーグマ(Helarctos malayanus),ボルネオオランウータン(Pongo pygmaeus)の頭骨標本(博物館等に所蔵)を用いて,Bを測定した。穴間距離A:35mmに最も近似していたのはウンピョウ(B:27.9-33.0, n=3)だった。ヒゲイノシシ(74.5-163.5 n=13),マレーグマ(64.7-76.1, n=2),ボルネオオランウータン(69.1-74.2 n=3)はAに対して大きすぎ,犬歯2本で同時に噛むことで,陥没穴を形成する可能性は非常に低いと考えられた。さらに飼育下のウンピョウに,オランウータンの頭蓋とほぼ同じ大きさの樹脂性のボールを与えて,噛むことができるかを確認する実験を行った。また,損傷のあるオランウータン頭骨のサイズと,蝶後頭軟骨結合の状態を,他のオランウータンと比較し,性別と年齢クラスを推定した。その結果,高齢のオトナ雌である可能性が最も高いと考えられた。さらに他の調査地でも,オトナがウンピョウに襲われたと推定される事例が2例あることも判明した。今まで,ウンピョウはオランウータンの未成熟個体しか襲わないと考えられていたが,成熟個体も襲われる可能性があることが明らかになった。
2 0 0 0 OA 編集後記
- 著者
- 亀山 晶子
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.138-1, 2021 (Released:2022-01-23)