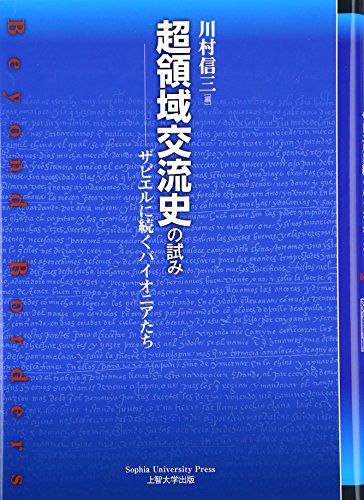- 著者
- 川崎 真弘
- 出版者
- 筑波大学
- 雑誌
- 新学術領域研究(研究領域提案型)
- 巻号頁・発行日
- 2015-04-01
発達障害者はコミュニケーションが苦手であることが知られているが、その原因については不明な点が多い。本研究では京都大学医学部と共同研究することで、定型発達との比較脳波研究を行った。これまでに計測した協調コミュニケーション課題時の脳波解析より、発達障害者は他者との協調で前頭葉に認知負荷がかかることを示し、論文発表した(Kawasaki, Funabiki, et al., Cogn. Neurodyn. 2014)。これらの脳活動は発達障害の特徴の中でも特に「こだわり傾向」と関係することがわかった。さらにこれまでに定型発達者を対象として交互発話中に発話リズムが同期する2者間では脳波リズムが同期することを示してきた(Kawasaki, et al., Sci. Rep. 2013)。この解析方法を用いて、定型発達者と発達障害者の2者間の脳波リズム同期を比較した結果、発達障害者は脳波リズムが同期が少ないことがわかった。さらに位相振動子モデルおよび情報理論を用いて2者間の関係性を推定する研究を行っている。この成果について現在論文執筆中である。また発達障害者と定型発達者に対して、運動模倣課題を行った結果、発達障害者の多くは心的回転を、定型発達者の多くは視点取得の戦略を用いることが分かった。さらに発展研究として、視覚・聴覚記憶課題時の脳波、fMRI実験を実施し、発達障害者の注意の偏りに起因した脳活動や、うつ病患者の脳ネットワークの障害の検証を行っている。上記の研究は将来的に脳メカニズムから精神疾患を判断する診断法の開発に貢献する。
2 0 0 0 IR セラミック・デザインの研究と制作/フィンランドと日本の陶磁器の比較研究
- 著者
- 市野 元和 Motokazu ICHINO
- 出版者
- 神戸芸術工科大学
- 雑誌
- 芸術工学2014
- 巻号頁・発行日
- 2014-11-25
陶磁器はその地域や文化、生活様式によってそれぞれの特色をもっている。特に素材の特性を生かしたもの作りという事を目的とし、実際に現地(フィンランド)の素材で自らの作品を制作した。そして、日本のクラフト工芸とフィンランドのセラミック技 術とを比較研究する中で、アアルト大学の学生に制作を通じて、日本の陶芸の伝統技術を紹介したり、ワークショップを行う事でクリエイターとしてアプローチしながら、陶磁器デザインの研究と制作を実施した。また、アアルト大学・セラミック・ガラス学科の実習、演習授業に参加し、セラミック・ガラス素材とデザイン研究における総合プロジェクトに加わり、窯の焼成方法や釉薬の研究を行った。
2 0 0 0 IR 書評に応えて : フィジオクラットの統治論補遺
- 著者
- 安藤 裕介 アンドウ ユウスケ Yusuke Ando
- 出版者
- 立教法学会
- 雑誌
- 立教法学 (ISSN:04851250)
- 巻号頁・発行日
- no.90, pp.282-291, 2014
2 0 0 0 「コンクリート甲子園」を通しての人材育成について
- 著者
- 尾嵜 秀典
- 出版者
- 公益社団法人土木学会
- 雑誌
- 令和元年度土木学会全国大会第74回年次学術講演会
- 巻号頁・発行日
- 2019-06-25
2 0 0 0 トンネル覆工コンクリートの養生効果の評価法に関する検討
- 著者
- 高石 地晴 林 和彦 長谷川 雄基 岡崎 慎一郎 宇野 洋志城 阿部 浩之
- 出版者
- 公益社団法人土木学会
- 雑誌
- 令和元年度土木学会全国大会第74回年次学術講演会
- 巻号頁・発行日
- 2019-06-25
2 0 0 0 赤外線熱画像による橋梁コンクリートの温度差領域と密実性の関係
- 著者
- 橋爪 謙治 林 和彦 橋本 和明 松田 靖博
- 出版者
- 公益社団法人土木学会
- 雑誌
- 令和元年度土木学会全国大会第74回年次学術講演会
- 巻号頁・発行日
- 2019-06-25
2 0 0 0 OA ソーシャル世論の傾向 : ツイッター分析を基に〔論文〕
- 著者
- 佐藤 航 大隈 慎吾
- 出版者
- 埼玉大学社会調査研究センター
- 雑誌
- 政策と調査 (ISSN:2186411X)
- 巻号頁・発行日
- no.9, pp.35-50, 2015
既存の世論調査は対象者に回答を依頼し質問に答えてもらう「応答型」で実施されるが,近年この手法の回収率が低下しつつあると言われている.それに対し,人々が自発的に発言した中から研究課題に関連する部分を抽出して分析する「観測型」の調査が提案されている.そこで,本稿ではツイッター上で観測型の世論調査が可能かどうかを検討した.独自に開発したシステムによって投稿を取得し分析した結果,日本語ユーザーが最も多くつぶやく話題は友人募集や「自分語り」であることがわかった.他方,政治の話題に触れた投稿者はユーザー全体の1%にも満たず,世論調査のサンプルとするには不可能なほど僅少であった.とはいえ,マスメディアの報道に呼応する形で投稿者が急増する現象が確認されたので,これを応用し,報道の中で質問を発し回答ツイートを観測・収集するような「中間型」の調査であれば可能であるかもしれない.Our established poll was carried out using a procedure where respondents answered a number of questions, what we call the Questioning method. This method may have recently faced a decrease in response rate. While, on the other hand, the Observation method analyzes messages that are extracted from voluntary speech that refers to the subject of the survey. In this article, we confirmed the feasibility of a poll on Twitter using the Observation method. Using the tweet data acquisition system that we have developed, we discovered that the most common Japanese tweet is “Let's be friends” and self-conscious mention. Less than 1% of active Twitter users brought up politics, they are too little to poll. During the analysis process, we discovered what the media news accelerate increase of tweets. This suggests that collecting responses via tweets from questions by the media is feasible. We call this the Hybrid method.
2 0 0 0 OA 片脚着地動作における失敗パターンの解析
- 著者
- 三浦 雅史 川口 徹
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.41 Suppl. No.2 (第49回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.1306, 2014 (Released:2014-05-09)
【目的】着地動作はスポーツ外傷の受傷機転として多い動作の一つである。これまで我々は,この着地動作に注目し,前後左右4方向への片脚着地動作について解析してきた。過去の報告では着地動作の成功例についてのみ解析してきたが,失敗例については解析されていなかった。実際のスポーツ場面での受傷状況を考えると,失敗例にその原因を突き止める鍵があるかもしれない。そこで,4方向への片脚着地動作について,どの方向で失敗しやすいのか,またどのようなパターンで失敗しているのかについて検討した。【方法】対象は健常な女子大学生38名とした。対象を女性と限定したのは膝外傷の特にACL損傷は女性に多いとされているためである。片脚着地動作の解析にはデジタルビデオカメラを用い,台から5m前方に設置した。測定した着地動作は高さ30cmの台から前方・後方・右側方・左側方へ片脚着地することとし,測定肢は全て右とした。着地動作時には視線は前方に保ち,上肢によるバランス保持の影響を少なくするために両上肢を胸の前で組むように指示した。まず,対象者は台上で足部を肩幅に広げた立位から片脚となり,片脚立位が安定してから検査者の合図により落下し,着地した。着地方向は前方,後方,右側方,左側方に10回ずつ実施した。着地成功・失敗の判定基準は2秒以内に静止できた施行を成功例,2秒以内に静止できなかった施行や着地後に足部の接地位置が変化した施行,遊脚側である左下肢を床につけてしまった施行を失敗例とした。各着地方向での失敗回数をカウントし,失敗動作を足底接地後2秒以内に静止できなかった施行(静止失敗群),着地後右足底の接地位置が変化した施行(足底離床群),遊脚側である左下肢を床につけてしまった施行(両脚接地群)の3パターンに分類した。【倫理的配慮,説明と同意】本研究は演者が所属する大学の倫理委員会の承認を得て実施した。研究内容について書面で説明し,同意を得た上で研究に参加頂いた。【結果】解析対象とした施行回数は1520回であった(4方向×10回×38名)。このうち,成功回数は775回(全試行の51.0%),失敗回数は745回(全試行の49.0%)であった。着地の方向別の失敗回数は左側方が最も多く210回,次いで右側方200回,後方182回,前方153回の順であった。パターン別では全方向とも足底離床群が最も多く,合計586回(失敗回数の78.7%),前方119回,後方144回,右側方150回,左側方173回であった。次いで多かったのが静止失敗群で合計118回(失敗回数の15.8%),前方25回,後方23回,右側方38回,左側方32回となった。両脚接地群は最も少なく合計41回(失敗回数の5.5%)であった。【考察】これまで我々が検討してきた先行研究では成功例のみを解析対象とし,失敗例は解析対象から除外してきた。しかし,今回の研究結果からも示された通り,片脚着地動作は約半数近くの施行で失敗する動作であることが明らかとなった。このことは片脚着地動作がスポーツ外傷の受傷原因となり得る動作であることを改めて説明する結果ではないかと考えている。また,今回の結果から,前後方向に比べ左右側方への着地動作で失敗していることが分かる。着地動作,特にドロップジャンプに関する先行研究では,前方への着地動作に関する解析がほとんどであり,本研究結果を踏まえると,今後は側方への着地動作に関する解析が重要と考える。失敗パターンでは足底離床群が約80%を占めており,体勢を保持または立て直すための動作が実施されており,スポーツ外傷の発生に関連する可能性が示唆された。【理学療法学研究としての意義】従来の動作分析では,解析にそぐわない条件,すなわち失敗例をデータ対象から除外する傾向があった。今回,改めて失敗例にスポットを当てたことで,今後の研究課題のヒントを得た点は非常な重要な意味を持つと考える。
2 0 0 0 OA 得点の分布と科目間の調整
2 0 0 0 OA 日本結晶学会講習会「粉末X線解析の実際」を開催して
- 著者
- 中井 泉 植草 秀裕
- 出版者
- 日本結晶学会
- 雑誌
- 日本結晶学会誌 (ISSN:03694585)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.3, pp.187-188, 2019-08-31 (Released:2019-08-31)
- 著者
- アツミ マサズミ
- 出版者
- ピープルズ・プラン研究所 ; 2001-
- 雑誌
- ピープルズ・プラン = People's plan
- 巻号頁・発行日
- no.76, pp.63-71, 2017
2 0 0 0 翻訳 N・クリスティーエ「理想的な被害者」
- 著者
- Christie Nils 齋藤 哲
- 出版者
- 東北学院大学学術研究会
- 雑誌
- 東北学院大学論集 法律学 (ISSN:03854094)
- 巻号頁・発行日
- no.63, pp.274-256, 2004-12
- 著者
- 進藤,務子
- 出版者
- 久留米信愛女学院短期大学
- 雑誌
- 久留米信愛女学院短期大学研究紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.30, 2007-07
What was the beginning of the education of Western music in Japan? As numerous results of studies which many scholars have gained show, we may say that, the answer would be that the missionaries from the Society of Jesus came to Japan in the middle of 16^<th> century in order to preach Christianity and taught the Japanese converts how to sing great number of Gregorian chants and how to play various kinds of musical instruments, such as the previous-type of the viola and the organ. In fact, when we read historical materials written by those padres, it is not difficult to find the facts that 400 distant years ago, the Japanese at the time adored Western music quite, whether they loved the Christian ideas/doctrines or not, and also the high quality of musical education was provided in the educational, religious institutions (especially, the schools called seminario and collegio) which those Jesuit missionaries established, although people today tend to think that the flourish of the education of Western music emerged after the Meiji restoration. The first contact between the Japanese and the Westerners stretches back to 1543, when the Japanese old-type firearms was first brought to Japan by shipwrecked Portuguese merchants. Soon after that, their commercial contacts were developed into the Nan-ban trade, and this was soon followed by the missionary work towards the Japanese, since at that time, the Iberian countries enjoyed the great age of exploration with their economic and political ambitions. On the other hand, Japanese feudal lords, who were in pursuit of their own economic motives, were fairly attracted by the trade income as well. Thus, the Nan-ban trade and the expansion of the churches in Japan were inseparable for their financial reasons. However, the religious music appealed to inhabitants' hearts as a cultural aspect of Christianity. An Italian Padre, A. Valignano, who endeavoured to spread the Christian faith and religious education in Japan, attached a huge importance to this effective, spiritual exchange, in teaching at church-related schools. I shall examine his efforts and the outcome of such education of religious music in Japan, taking the following examples of seminario timetable and the despatch of Tensho boy-missions to Rome, 'Manvale ad Sacramenta' and 'uta-oratio', one of crypto-Christian's heritage, from various points of view ; political, social and cultural backgrounds in Japan in this essay.
2 0 0 0 超領域交流史の試み : ザビエルに続くパイオニアたち
- 著者
- 川村信三編
- 出版者
- ぎょうせい (発売)
- 巻号頁・発行日
- 2009
2 0 0 0 OA 高温超伝導の発見から現在まで
- 著者
- 北澤 宏一
- 出版者
- 公益社団法人 応用物理学会
- 雑誌
- 応用物理 (ISSN:03698009)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.8, pp.929-931, 1998-08-10 (Released:2009-02-05)
- 参考文献数
- 4
- 著者
- 樫田 美雄
- 出版者
- 日本質的心理学会
- 雑誌
- 質的心理学フォーラム = Qualitative psychology forum (ISSN:18842348)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.54-61, 2018
- 著者
- 青木 大也
- 出版者
- 民事法研究会
- 雑誌
- Law & technology (ISSN:1346812X)
- 巻号頁・発行日
- no.84, pp.56-65, 2019-07
2 0 0 0 Sapio = サピオ
- 出版者
- 小学館
- 巻号頁・発行日
- vol.4(21), no.83, 1992-11
2 0 0 0 朝日新聞社メディアラボの人工知能研究の取り組み
- 著者
- 田森 秀明 人見 雄太 田口 雄哉
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.12, pp.591-595, 2018-12-01 (Released:2018-12-01)
朝日新聞社メディアラボは,新規ビジネスの開発や出資・投資,研究開発などを主なミッションとし,2013年9月に発足した新しい部署だ。発足当初より研究開発(R&D)がスコープにあり,新技術を積極的に取り入れ,将来のビジネスにいかす活動を進めている。近年では自然言語処理への取り組みは新聞社には必要な技術分野として,メディアラボのみならず社内のIT部門である情報技術本部,更には社外のベンチャー企業などとともに取り組みを広げている。本稿では,メディアラボの人工知能,特に機械学習や自然言語処理の取り組みについて発足当初の取り組みや,最近の成果を紹介する。