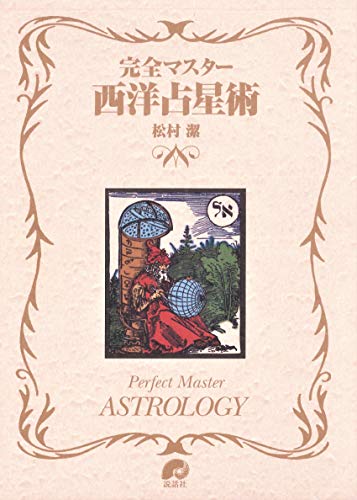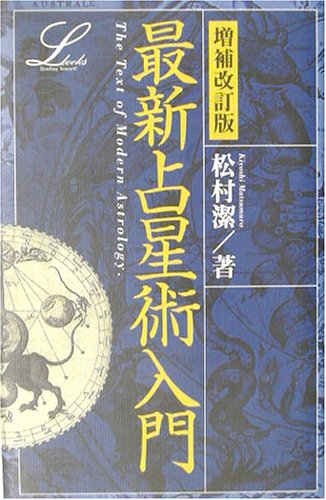1 0 0 0 学習ノウハウの共有を支援するコミュニティ指向型図書館システム
- 著者
- 常川 真央 小野 永貴 松村 敦
- 出版者
- 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 (ISSN:13479881)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.1-4, 2010
- 著者
- 松村 一男
- 出版者
- 大修館書店
- 雑誌
- 言語 (ISSN:02871696)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.12, pp.26-33, 2000-12
1 0 0 0 完全マスター西洋占星術
1 0 0 0 棒針編み困ったときに開く本 : 誰も教えてくれなかった基礎のキソ
- 著者
- 斎藤 勝 籔 晴夫 山崎 昌弘 松村 阜子 加藤 日出男
- 出版者
- The Pharmaceutical Society of Japan
- 雑誌
- Chemical and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:00092363)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.2, pp.652-658, 1982-02-25 (Released:2008-03-31)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 3 5
The existence of four crystalline forms (forms I, II and III, and a hydrate) and an amorphous form of tulobuterol hydrochloride was confirmed by X-ray powder diffraction, infrared spectroscopy and thermal analyses (DSC and TG). The hydrate was found to be the monohydrate by elemental analysis and measurement of water content. From the DSC measurement, it was found that forms I and II melted at 163°C and 170°C, and their heats of fusion were 5.15 kcal/mol and 4.76 kcal/mol, respectively. Form III, the amorphous form and the hydrate transformed into form II at 135°C, 90°C and 75°C, respectively. Activation energy for the dehydration of the hydrate determined by Kissinger's method was 56.1 kcal/mol. No crystal changes were observed in the four crystalline forms when they were ground in a mortar or compressed at high pressure ; however, after such mechanical treatments form I transformed into form II on being heated. The investigation of phase transitions of the four crystals showed that form II was the most stable among them.
1 0 0 0 興味あるCT所見を呈した松果体部原発類上皮腫の1例
- 著者
- 山内 康雄 高原 街彦 河村 悌夫 松村 浩
- 出版者
- 日本脳神経外科学会
- 雑誌
- Neurologia medico-chirurgica (ISSN:04708105)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.2, pp.136-142, 1985
- 被引用文献数
- 2 4
A 69-year-old male was admitted complaining of gait disturbances and diplopia, 2.5 years after an episode of serous meningitis. Neurological examination on admission disclosed Parinaud's sign, unsteady gait and dysdiadochokinesis on the left side. A striking finding on the computerized tomography (CT) was the left to right shift of the posterior portion of the third ventricle without visualization of the quadrigeminal and ambient cisterns, which were almost completely occupied by an isodense mass accompanied by high dense flecks and a low dense part. Enhanced CT showed positive enhancement in the vicinity of the pineal calcification. By the suboccipital supracerebellar approach, an encapsulated mass containing brownish yellow fluid was subtotally removed and a histological examination of it revealed epidermoid tissue and hemosiderin deposits in the solid portion. Few reports of isodense epidermoid cysts have so far been found in the literature giving a full explanation for this unusual CT attenuation value. Based on the clinical course and histology of this case, the pathogenesis of the unusual density is discussed along the following lines: The mixture of the low dense factor due to cholesterin and the high dense factor due to prior bleeding is believed to result in the isodense attenuation value in the liquid portion. Also, in the solid part, a microscopically mixed texture of deposited hemosiderin and cholesterin clefts in the inflammatory granulomatous tissue could explain its density on the CT scan.
- 著者
- 開田 翔一 松村 健太 加藤 祐次 清水 孝一
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告 = IEICE technical report : 信学技報 (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.114, no.514, pp.29-33, 2015-03-16
手指や手のひらの血管像による個人認証はすでに一般的に行われているが,手首血管の光透視像による個人認証を実現した例は知られていない.手首は,近年出現している腕時計タイプのウェアラブル機器の装着が容易であり,これに認証機能を付加できれば有用と考えられる.そこで我々の開発してきた光透視像技術を応用し,腕時計型デバイスで手首血管透視像による個人認証を行うことを考えた.成人手首部で得られた血管透視像に対して,ウェアラブルデバイスでも実装可能な簡易なアルゴリズムで画像処理を施し,画像相関による個人認証を行った.その結果,腕時計型デバイスでも,有効な個人認証が行える可能性を実証した.
- 著者
- 渡辺 皓太 松村 將宏 宮坂 勇輝 深谷 拓己 飯田 達也 沖本 憲昭 井元 浩二
- 出版者
- 公益社団法人 自動車技術会
- 雑誌
- 自動車技術会論文集 (ISSN:02878321)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.2, pp.421-426, 2011 (Released:2011-07-14)
- 参考文献数
- 5
直噴式ディーゼル機関の低公害、低燃費化のために、コモンレール式燃料噴射系、高圧縮比のもとで、吸気スワール比、アフター噴射特性を理論的、実験的に追求した。その結果、NOx-燃費のトレードオフの点で、低吸気スワール比での燃料噴射時期遅延、アフター噴射時期を早め、少量にすると有効であることを見い出した。
1 0 0 0 OA 2014年8月20日に広島市で発生した集中豪雨に伴う土砂災害
- 著者
- 松村 弓彦
- 出版者
- ぎょうせい
- 雑誌
- 法律のひろば (ISSN:09169806)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.6, pp.74-80, 2000-06
1 0 0 0 IR 川端康成「古都」における西洋と日本 : パウル・クレーを視座として
川端康成は自身が旅した土地や住んでいた都市を舞台とした作品を数多く残した作家である。伊豆を舞台とした「伊豆の踊子」、浅草を舞台とした「浅草紅団」、新潟を舞台とした「雪国」、鎌倉を舞台とした「山の音」などが挙げられる。その中でも、一九六一年十月から一九六二年一月まで朝日新聞にて連載された「古都」は、京都を舞台としており、作中には京都の風物や名所、年中行事がふんだんに盛り込まれている。文庫版の山本健吉の解説には「この美しい一卵双生児の姉妹の交わりがたい運命を描くのに、京都の風土が必要だったのか。あるいは逆に、京都の風土、風物の引立て役としてこの二人の姉妹はあるのか。私の考えは、どちらかというと、後者の方に傾いている」とあり、これに川端自身の「古都」に関する言説も踏まえて、どちらが主となっているのかという論がこれまで先行研究にて繰り広げられてきた。実際にある京都の行事と作中に登場する行事のずれを指摘した三谷憲正の研究や、同じ時期に書かれた「美しさと哀しみと」と「古都」を比較した蔵田敏明四の研究など、山本の意見を支えるような研究も多々されており、今のところ、山本が言う後者つまり京都の風土がこの作品の主題となっているという意見が優勢である。そこで、京都の風土が主題であるという点を踏まえて重要となってくるのが、色彩である。桜やすみれといった花や木などの自然物が作品を彩る中で、話の筋に関わってくるのがパウル・クレーの画集である。作中で太吉郎がクレーの画集を参考に帯の下絵を描く場面がある。日本の美、京都の美を描く作品の参照項として、なぜクレーの絵が取り上げられているのであろうか。山田吉郎五は「川端康成『古都』論―遡行の構造―」において、川端とクレーについて左記のように述べている。近藤不二氏も『現代世界美術全集一〇 クレー、カンディンスキー、ミロ』(河出書房新社刊)のクレエの解説の中で、「事物の中に霊的根源を認める神秘主義」がクレエの絵画に流れていることを指摘している。こうした霊界の人クレエを、『古都』執筆中の川端が強く意識したであろうことが推測される。なぜなら、小説『古都』は先に栗原雅直氏が指摘したごとく、「人間がどのように世の中にあらわれるか、生前の我がいかようであったかということ」を追いもとめる、つまりは未生の我をさがしもとめる作品だからである。このような霊的雰囲気は北山杉の村に色濃く漂っており、クレエの絵画世界とは色彩も構図も異質ながら、一脈の共通性を示している。このように先行論ではクレーについて言及はされてはいるものの、当時の日本のクレー受容の中で、川端がどういった意図でクレーを「古都」で利用したのかは未だ明らかではない。川端はどのように考え、日本の美を描く上で、クレーを作中に登場させたのか。また、「古都」は「ノーベル賞審査委員会がその決定をするに当って参考にした」作品であると言われている。本稿では、川端のクレー受容や国際的な活動も視野に入れて「古都」を再考し、本作のノーベル文学賞受賞との関わりの新たな観点を示したい。
- 著者
- 松村 卓朗 吉村 浩一
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経情報ストラテジ- (ISSN:09175342)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.7, pp.188-191, 2008-08
組織の運営において「チーム」の重要性が高まってきているが、複数の人が集まっただけでは「グループ」にすぎない。メンバーの力の総和を超えた成果を生み出すには、グループがチームに進化する必要がある。さらに「ハイパフォーマンス・チーム」へと進化することで、継続的に大きな成果を生み出すことが可能となる。「チームEビルディング」とはこうした進化を促すプロセスである。
1 0 0 0 OA 実用化が始まった磁気軸受
- 著者
- 松村 文夫
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電氣學會雜誌 (ISSN:00202878)
- 巻号頁・発行日
- vol.111, no.3, pp.219-222, 1991-03-20 (Released:2008-11-20)
- 参考文献数
- 3
- 著者
- 松村 昌信
- 出版者
- 公益社団法人 腐食防食学会
- 雑誌
- Zairyo-to-Kankyo (ISSN:09170480)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.5, pp.187-195, 2007-05-15 (Released:2007-10-30)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 1 1
本稿では,高温の純水を輸送する炭素鋼配管に生じる異常減肉の特徴を述べる.典型的な事例として,美浜原子力発電所の事例を取り上げる.これは,この事例については原子力安全・保安院の調査委員会が行った詳細な調査結果が既にウェブサイトに公開されているので,残留肉厚分布や減肉箇所の鮮明な写真などが容易に得られるからである.その発生機構を説明するための二つのモデル,すなわち FAC(流れ加速腐食) モデルとマクロセル腐食モデルが検討された.後者はその発生メカニズムを合理的に説明したので,このモデルに基づいて管壁減肉の発生防止法が述べられた.また,減肉の進行を検出する方法も述べられた.
- 著者
- 松村 清
- 出版者
- じほう
- 雑誌
- ファーマネクスト (ISSN:1348897X)
- 巻号頁・発行日
- no.2, pp.50-53, 2004-02-10
1 0 0 0 携帯電話リサイクルに関する大学生の行動と意識に関する一考察
- 著者
- 黒木 翔吾 真鳥 晃一 松村 隆
- 出版者
- 一般社団法人環境情報科学センター
- 雑誌
- 環境情報科学論文集 (ISSN:03896633)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.455-460, 2011
大学生を対象に携帯電話リサイクルに関する意識調査を行った。携帯電話端末にレアメタル等が使用されていることを知っている学生は約64%であった。機種変更時に使用済み携帯電話端末を返却・リサイクルしたものは約25%で,約67%の学生はそのまま所持していた。返却・リサイクルしなかった理由は,電話機能以外の目的で所持(約27%),思い出として手元に保管(約28%),処理が面倒(約19%),リサイクルできることを知らなかった(約11%),個人情報流出への懸念(約10%)であった。返却・リサイクルをしなかった学生約90 名を対象に携帯電話リサイクルに関する経済的なインセンティブに関する調査も行った。
1 0 0 0 損害賠償に対する一般人の態度
- 著者
- 松村 良之
- 出版者
- JAPAN ASSOCIATION FOR PHILOSOPHY OF SCIENCE
- 雑誌
- 科学基礎論研究 (ISSN:00227668)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.1, pp.21-25, 1972
1 0 0 0 IR 1950年代西カリマンタン華人社会における学校教育
- 著者
- 松村 智雄
- 出版者
- 早稲田大学アジア太平洋研究センター
- 雑誌
- アジア太平洋討究 (ISSN:1347149X)
- 巻号頁・発行日
- no.27, pp.213-229, 2016-10