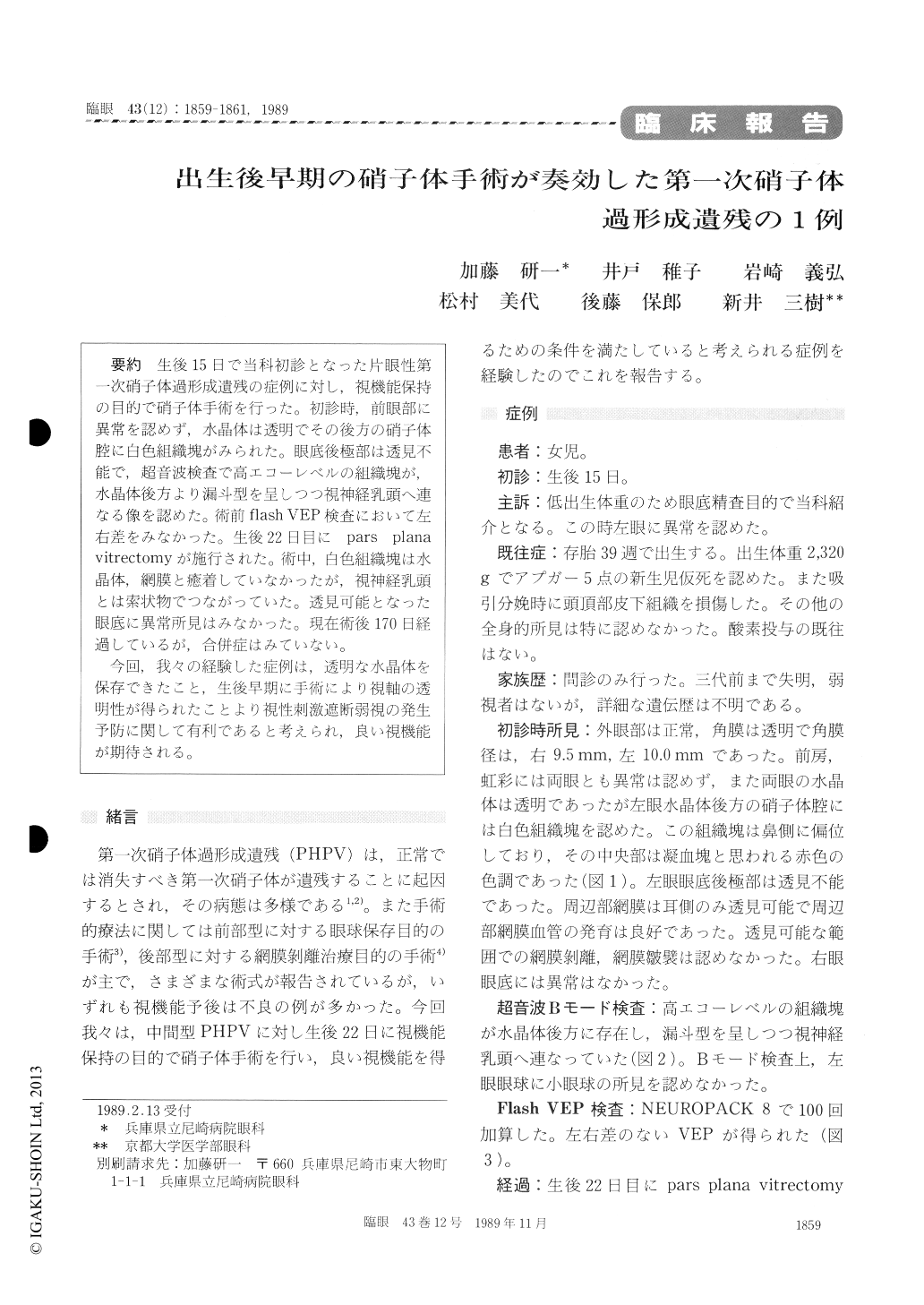- 著者
- 功刀 正行 阿部 幸子 鶴川 正寛 松村 千里 藤森 一男 中野 武
- 出版者
- 公益社団法人 日本分析化学会
- 雑誌
- 分析化学 = Japan analyst (ISSN:05251931)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.11, pp.967-984, 2010-11-05
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 1 2
残留性有機汚染物質による地球規模の海洋汚染の時空間変動及び化学動態を把握するため,商船を篤志観測船として用い,この目的のために開発した海洋汚染観測システムを搭載し,太平洋及び南シナ海における広域観測を実施した.日本-オーストラリア間は鉱石運搬船を,南太平洋(含む南極近海)はクルーズ船を,北太平洋(東アジア-北米間)及び南シナ海はコンテナ船を,それぞれ篤志観測船として用いた.鉱石運搬船,クルーズ船には専用の海洋汚染観測システムを開発し搭載し,コンテナ船にはユニット化した小型の海洋汚染観測システムを開発して搭載し,試料採取及び観測を実施した.海水中の残留性有機汚染物質の捕集は,固相抽出法を用い,船上で100 Lの海水を濃縮捕集し,採取試料は直ちに船上で冷凍保存し,日本に持ち帰った.持ち帰った試料は冷凍庫で保存し,分析直前に前処理後HRGC/HRMS-SIM法で分析した.すべての試料から残留性有機汚染物質が検出された.低緯度海域では,HCHsの濃度は低く,かつその異性体のうちβ-HCHが最も高い,一方高緯度海域では中央から北米沿岸域ほどα-HCHが高い傾向にあるなどその濃度や異性体存在比などは極めて特徴的であり,発生源及び輸送過程を推定する上で貴重な情報を与えることが明らかとなった.
- 著者
- 松村 剛志 大場 美恵 山田 順志 楯 人士 青田 安史
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2013, 2014
【はじめに,目的】介護保険制度においてリハビリテーション(リハ)専門職は,生活機能全般,特に活動の向上に働きかける役割を求められている。役割にはこうした社会や制度の中で付与される集団的役割だけでなく,関係的地位の相手方の期待に基づく関係的役割も存在する。外来理学療法では患者の期待と理学療法士(PT)の役割認識にズレが生じていることが明らかとされているが,介護保険サービスにおいて要介護者が抱くPTへの役割期待は十分に解明されておらず,その変化を捉えようとする試みも見当たらない。そこで今回,通所リハ利用者の抱くPTへの役割期待の変化を質的研究手法を用いて明確にすることを試みた。【方法】対象者は静岡県中部地域にある2カ所の通所リハ事業所にてPTによる通所リハ・サービスを受けており,重度の記憶障害がなく言語によるコミュニケーションが可能で,かつ同意が得られた14名の要介護高齢者であった(男性10名,女性4名,平均年齢76.9±4.1歳)。主要疾患は脳血管障害9名,パーキンソン病3名,その他2名である。2012年9月に11名,追加調査として2013年3月に3名の対面調査を行った。面接は録音の許可を取った後に,通所リハ利用の目的,PTへの期待とその変化等について半構成的インタビューを行った。20~40分の面接終了後に,録音内容の逐語録を作成し,Steps for Coding And Theorization(SCAT)を用いて分析した。SCATによる分析では,まずSCATフォームの手順に沿って文字データから構成概念の生成を進めた。同時に,データに潜在する研究テーマに関する意味や意義を,得られた構成概念を用いてストーリーライン(SL)として記述した。次に,個々の対象者においてSLを断片化することで個別的・限定的な理論記述を行った。得られた理論記述の内容をサブカテゴリーと位置づけ,その関係性を検討した上でカテゴリーを構築した。最後に集約されたカテゴリーを分析テーマに沿って配列し直し,研究対象領域に関するSLを再構築した。対象者14名にて理論的飽和の判断が可能かどうかは,シュナーベル法を用いて構成概念の捕獲率を求め,捕獲率90%以上にて理論的飽和に達していると判断した。【倫理的配慮,説明と同意】本研究は平成24年度浜松大学研究倫理委員会の承認を受けており,対象者に対して書面ならびに口頭での説明を行った後に同意書への署名を得た。【結果】本研究では,76種類154個の構成概念が構築され,14例目における捕獲率は93.54%であった。また,全対象者から37個の理論記述が生成され,6つのカテゴリーに分類された。これらのカテゴリーから構築されたSLは以下の通りである。通所リハ利用者は,サービス開始当初,PTに対して身体機能や歩行能力の回復に対する働きかけを期待していた。ただし,脳血管障害の対象者にその傾向が強く,慢性進行性疾患の場合は悪化防止に焦点が当てられていた。リハ効果は,自己による自己評価と他者による自己評価の認知によって確認されており,息切れや歩行といったモニタリング指標を各自が持っていた。リハ効果が期待通り或いは期待以上であれば,PTへの信頼感に基づく全面的委任や担当者の固定による現状の継続が希望され,PTには得られた効果の維持が期待されるようになった。一方,転倒のような失敗体験の反復は,自己信頼感を低下させ,リハ効果が期待外れや不十分と認識される要因となっていた。この場合,サービスへのアクセスそのもの(回数増加や治療時間の延長)が期待されるようになり,治療効果を生み出すことは期待されなくなっていた。さらに,利用者に回復の限界に関する気づきがみられると,利用者は通所リハをピアと会える新たなコミュニティと位置づけていた。【考察】本研究においては,利用者のPTに対する役割期待に変化が認められ,その変化にはモニタリングされたリハ効果をどのように自己評価しているかが大きく影響しているものと考えられた。通所リハにおける利用者の満足感に関する背景要因には,(1)設備や雰囲気といった場,(2)サービス担当者の知識・技術・言動,(3)プログラムの多様性や治療機会,(4)心身の治療効果が挙げられている。利用者がPTから満足感を得ようとする場合,これら要因を組み合わせてPTへの役割期待を作り上げているものと考えられ,モニタリングの結果によって役割期待を能動的に変更している可能性も示唆された。【理学療法学研究としての意義】本結果は一地域の通所リハ利用者に限定されるものではあるが,通所リハ利用者の抱くPTへの役割期待の変化をSLとして明らかにし,PTが利用者理解を深めるためのモデルケースを提示できたものと考えられる。
1 0 0 0 所有と分配の力学 : エチオピア西南部・農村社会の事例から
- 著者
- 松村 圭一郎
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 民族學研究 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.2, pp.141-164, 2007
本稿は、エチオピア西南部の多様な民族が居住する農村社会を対象に、土地から生み出される作物などの富がどのような手続きをへて、誰の手に渡っていくのか、富の所有と分配という問いを考察する。とくに「分け与えること」と「与えずに自分のものにすること」をめぐる人びとの相互行為から、所有や分配を支えている力学を浮き彫りにしたい。IIでは、農作物の分配行動に注目する。作物が収穫されたとき、雨季で食糧が不足するとき、持つ者は持たざる者から乞われたり、自発的に与えたりしている。じっさいに農民たちが誰にどのようなものを与えているか、具体的事例を分析することで、身近な親族から見知らぬ物乞いまで、さまざまな相手に対して富が分配されている実態を明らかにする。IIIでは、与える相手ごとの分配行動の差異に注目する。相手との社会関係が違うことで、分け与える背景にどのような違いがでるのか。「親族」と「よそ者」という対照的な相手に対する分配の事例から、それぞれに異なる動機が分配を促すきっかけとなっている可能性を示す。IVでは、人びとの分配をめぐる意識や葛藤について分析する。分配を定める宗教的な規律がある一方で、人びとは与えすぎると自分が困るというジレンマを抱えている。貧しい者が分配を受けるために行う働きかけのあり方と、与え手が分配を回避する事例から、与え手と受け手との相互行為において「分け与えること」と「与えずに自分のものにすること」が交渉されている点を指摘する。そして、Vで互酬性の議論を再検討しながら、「分け与える」という行為を支える相互的な「働きかけ」の重要性を提起する。
1 0 0 0 OA 豆状骨単独骨折の2症例
- 著者
- 安部 淳 樋口 理 松村 利昭
- 出版者
- West-Japanese Society of Orthopedics & Traumatology
- 雑誌
- 整形外科と災害外科 (ISSN:00371033)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.4, pp.1377-1382, 1990-03-25 (Released:2010-02-25)
- 参考文献数
- 15
Isolated fractures of the pisiform bone are uncommon. We reported two cases of isolated fracture of the pisiform bone. The first case was a 40-year-old male, and the second case was a 24-year-old female. The second case showed the Guyon canal syndrome. Both cases were treated by open reduction and fixation with microscrew. Bony unions were otained in both cases. A few months after the operation both patients were asymptomatic.
1 0 0 0 OA プロバイオティクス細菌による膵リパーゼ阻害作用
- 著者
- 松村 敦
- 出版者
- 公益財団法人 日本ビフィズス菌センター
- 雑誌
- 腸内細菌学雑誌 (ISSN:13430882)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.4, pp.287-292, 2010 (Released:2010-11-25)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 3
当研究所保有乳酸菌293株の膵リパーゼ阻害作用を検討した結果,60株が10%以上の膵リパーゼ阻害作用を示した.また,特に強いリパーゼ阻害作用を示した7菌株について,脂肪負荷ラットにおける中性脂肪濃度の上昇抑制作用を検討した結果, Lactobacillus gasseri NLB367が有意な作用を示した. 膵リパーゼ阻害作用の機能を有し,脂肪負荷ラットの中性脂肪上昇抑制作用を示したことから,乳酸菌はメタボリックシンドロームを予防・解消する可能性が示唆された.
- 著者
- 松村 茂樹
- 出版者
- 大妻女子大学人間生活文化研究所
- 雑誌
- 人間生活文化研究
- 巻号頁・発行日
- vol.2017, no.27, pp.603-609, 2017
<p>ボストン美術館東洋美術展示場に掛けられている呉昌碩「与古為徒」扁額は,同美術館中国・日本美術部長であった岡倉天心が呉昌碩に依頼したものと考えられて来たが,実は,天心の友人で,当時上海在住の漢学者・長尾雨山が,隣人関係にあった呉昌碩に揮毫を依頼し,黒漆木額に仕立ててボストンの天心宛に送ったものである.この頃,雨山は,天心より,ボストン美術館鑑査委員を委嘱されており,その就任記念に,この扁額を贈ったと筆者は考えている.天心のボストン美術館における活動は高く評価されているが,その背景に呉昌碩と交流した雨山という中国の正統的学問を受け継ぐ学者の協力があったことは,これまでほとんど指摘されていない.本稿は,これを分析し,近代において画期的成果を収めた日・中・米文化交流の意義を明らかにすることを目的とする.</p>
1 0 0 0 <近世ドイツ文学> K.Ph.モーリッツと聾唖者の言語
- 著者
- 松村 朋彦
- 出版者
- 学術雑誌目次速報データベース由来
- 雑誌
- 獨逸文學 (ISSN:03872831)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, pp.111-119, 1987
1 0 0 0 OA <原著論文>高齢者スポーツへの「構造的」アプローチ : 過疎山村のゲートボールをめぐって
- 著者
- 松村 和則 佐藤 大介
- 出版者
- 筑波大学体育科学系
- 雑誌
- 体育科学系紀要 (ISSN:03867129)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.83-95, 1994-03
- 著者
- 松村 芳明
- 雑誌
- 聖学院大学論叢 = The Journal of Seigakuin University (ISSN:09152539)
- 巻号頁・発行日
- vol.第24巻, no.第2号, pp.193-206, 2012-03
The youth-protection ordinance of Fukushima Prefecture includes articles which punish a person for putting materials (including books, videotapes, DVDs, etc.) harmful to youth in automatic vending machines. The Supreme Court of Japan upheld this regulation in a case on March 9, 2009. The automatic vending machine in which the defendant in this case put a DVD had a remote control system. This case note aims to examine this decision, including relevant precedent cases, in view of constitutional law. This case note concludes that the defendant in this case should have been found not guilty.
1 0 0 0 口唇形成術後に上唇に生じた断端神経腫の1例
- 著者
- 松村 香織 笹栗 正明 光安 岳志 新井 伸作 前野 亜実 中村 誠司
- 出版者
- 一般社団法人 日本口蓋裂学会
- 雑誌
- 日口蓋誌 (ISSN:03865185)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.3, pp.212-216, 2016
断端神経腫は,末梢神経切断後に神経の中枢側断端に生ずる腫瘤である。口腔領域における報告はオトガイ孔部や下唇が主で,上唇の報告例は1例のみであった。今回,われわれは口唇形成術後に上唇に発生した断端神経腫の1例を経験したのでその概要を報告する。
1 0 0 0 IR 弾を斬り裂いた日本刀
- 著者
- 永田正樹 磯部千裕 安原裕子 古畑智博 高田重利 松村宣顕 山崎國弘 長谷川孝博 井上春樹
- 出版者
- 国立大学法人 情報系センター協議会
- 雑誌
- 学術情報処理研究 (ISSN:13432915)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1, pp.12-22, 2018-09-19 (Released:2018-09-10)
- 参考文献数
- 17
静岡大学は,2018年3月にトラフィック分散型eduroam無線LAN基盤「静大IoTE」を構築した.静岡大学では,アクティブラーニング,反転授業,大学動画配信Webサイトなど,多様な教育ICTサービスを提供しており,年々利用者が増加している.これらサービス利用の環境として,これまでも学内無線LANを整備していたが,サービス多様化にともない利用者の増加およびトラフィック量が増加した.そこで,学内のインターネット通信を分散して,複数回線にバイパスするデータオフロードの仕組みをeduroam基盤にて構築した.これまで,学内ネットワークの最終出口はSINETを介していたが,これに複数の商用回線を追加することでトラフィック負荷を軽減した.また,eduroam基盤には普及品の機器やオープンソースソフトウェアを用いることで,構築費用を軽減できた.
1 0 0 0 出生後早期の硝子体手術が奏効した第一次硝子体過形成遺残の1例
- 著者
- 加藤 研一 井戸 稚子 岩崎 義弘 松村 美代 後藤 保郎 新井 三樹
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 臨床眼科 (ISSN:03705579)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.12, pp.1859-1861, 1989-11-15
生後15日で当科初診となった片眼性第一次硝子体過形成遺残の症例に対し,視機能保持の目的で硝子体手術を行った。初診時,前眼部に異常を認めず,水晶体は透明でその後方の硝子体腔に白色組織塊がみられた。眼底後極部は透見不能で,超音波検査で高エコーレベルの組織塊が,水晶体後方より漏斗型を呈しつつ視神経乳頭へ連なる像を認めた。術前flash VEP検査において左右差をみなかった。生後22日目にpars planavitrectomyが施行された。術中,白色組織塊は水晶体,網膜と癒着していなかったが,視神経乳頭とは索状物でつながっていた。透見可能となった眼底に異常所見はみなかった。現在術後170日経過しているが,合併症はみていない。 今回,我々の経験した症例は,透明な水晶体を保存できたこと,生後早期に手術により視軸の透明性が得られたことより視性刺激遮断弱視の発生予防に関して有利であると考えられ,良い視機能が期待される。
1 0 0 0 IR 阿波おどりの囃子における笛の役割に関する研究
- 著者
- 松村 美穂 岩井 正浩
- 出版者
- 神戸大学
- 雑誌
- 神戸大学発達科学部研究紀要 (ISSN:09197419)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.1, pp.109-127, 2003-09
- 著者
- 本内 直樹 松村 高夫
- 出版者
- 社会経済史学会 ; 1931-
- 雑誌
- 社会経済史学 = Socio-economic history (ISSN:00380113)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.4, pp.357-376, 2017
1 0 0 0 OA 15歳以下の孤立性僧帽弁疾患における僧帽弁手術の遠隔期成績
- 著者
- 久米 悠太 平松 健司 長嶋 光樹 松村 剛毅 山崎 健二
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本心臓血管外科学会
- 雑誌
- 日本心臓血管外科学会雑誌 (ISSN:02851474)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.4, pp.154-160, 2016-07-15 (Released:2016-08-19)
- 参考文献数
- 23
[背景]小児期の人工弁置換術には術後の脳関連合併症や血栓弁,成長に伴うサイズミスマッチなどの懸念があり可及的に弁形成術を行うことが望ましいが,やむを得ず弁置換術となる症例が存在する.15歳以下の孤立性僧帽弁疾患(孤立性僧帽弁閉鎖不全症,孤立性僧帽弁狭窄症)に対する僧帽弁形成術,僧帽弁置換術の遠隔期成績を検討した.[対象]1981年1月から2010年12月までに当院で僧帽弁形成術を行った30例(P群:男児21例,平均年齢4.6±4.6歳,平均体重13.4±8.9 kg),および機械弁による僧帽弁置換術を行った26例(R群:男児9例,6.2±4.6歳,平均体重16.4±11.2 kg)の計56例を対象とした.平均追跡期間9.3±7.8年,最長27.7年であった.また,孤立性僧帽弁閉鎖不全症(iMR)群と孤立性僧帽弁狭窄症(iMS)群とに分けて追加検討を行った.[結果]P群,R群ともに周術期死亡例はなく,遠隔期にR群で4例を失った.再手術はP群で6例,R群で5例に認めた.脳関連合併症は両群とも遠隔期に1例ずつ認めたのみで,人工弁感染は認めなかった.10年時および20年時での生存率はP群100%,100%,R群88.0%,80.0%であり有意差が見られた(p=0.043).10年時および20年時での再手術回避率はP群77.6%,77.6%,R群77.0%,70.0%,10年時における脳関連合併症回避率はともに100%であり有意差は見られなかった.iMR群とiMS群の10年時における生存率は100%と53.3%であり有意差がみられた(p=0.001).iMR群とiMS群の10年時における再手術回避率は77.1%と64.3%,20年時では72.0%と64.3%であり有意差は見られなかった.[結語]15歳以下の孤立性僧帽弁疾患に対する僧帽弁形成術,僧帽弁置換術の遠隔期成績は,懸念していた機械弁置換術後の脳関連合併症回避率や再手術回避率も僧帽弁形成術と有意差なく,小児期の僧帽弁手術として許容されるものであった.特に孤立性僧帽弁閉鎖不全症に対する僧帽弁手術の遠隔期成績は良好であった.孤立性僧帽弁狭窄症においては孤立性僧帽弁閉鎖不全症に劣らない再手術回避率であったが生存率には懸念が残る結果となった.
- 著者
- 齋藤 洋平 安永 正浩 黒田 順一郎 古賀 宣勝 松村 保広
- 雑誌
- Drug delivery system (ISSN:09135006)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.3, 2009-06-09
1 0 0 0 OA 聴秋閣試論
- 著者
- 松村 耕
- 出版者
- 湘南工科大学
- 雑誌
- 湘南工科大学紀要 = Memoirs of Shonan Institute of Technology (ISSN:09192549)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.1, pp.87-102, 2018-02-01
本稿は、原富太郎によって三渓園に移築された国の重要文化財建造物である聴秋閣について、その既存研究を整理した上で、実測調査を行い考察を加えたものである。
1 0 0 0 OA 機械構造の非線形性を考慮した自励びびり振動のシミュレーション解析(第1報)
- 著者
- 臼井 英治 松本 英樹 松村 隆
- 出版者
- 公益社団法人 精密工学会
- 雑誌
- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.12, pp.1968-1973, 2000-12-05 (Released:2009-04-10)
- 参考文献数
- 12
The paper presents a structure model with single degree of freedom which may represent the non-linear characteristics of actual machine tool structure. By using an experimental set-up for orthogonal turning which utilizes the proposed structure model, it is shown that the non-linear variations of vibration parameters m, k, c with applied load can be measured with a special impulsive excitation technigic during the actual turning. Th obtained variations are proved to be quite similar to those obtained for usual turning lathe. Computer simulations of chatter on-set process are then carried out with taking both the variable m, k, c obtained and the non-linearity of cutting process reported in the previous papers into account. The predicted stability thresholds of chatter vibration through the simulation are in good quantitative agreement with the experimental results which include the well-known non-linear phenomena such as high feed and high speed stabilities of chatter and the finite amplitude chatter vibration.
1 0 0 0 OA 金属アレルギーと口腔内修復物の成分組成に関する調査
- 著者
- 濱野 英也 魚島 勝美 苗 維平 益田 高行 松村 光明 埴 英郎 北崎 祐之 井上 昌幸
- 出版者
- 口腔病学会
- 雑誌
- 口腔病学会雑誌 (ISSN:03009149)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.1, pp.93-99, 1998-03-31 (Released:2010-10-08)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 7 11
Allergies caused by metals have been increasing. The number of patients visiting dentists with the chief complaint of metal allergy has also been increasing. From March 1994 to February 1997, 263 patients who complained of various symptoms visited our allergy clinic. Among them, 184 patients were suspected to have allergy caused by metals in dental restoration materials and were referred to the patch test. Among 165 patients', 128 were positives for metal allergy. Constituent elements of intraoral metals were analyzed in 107 of these 128 positive patients. The findings were as follows:1. The most common five elements acting on the patients were Hg, Co, Ni, Cr, and Pd.2. The most frequently used elements of dental restoration metal materials were Zn, Ag, Cu, Au, and Pd, and the alloy was Au-Ag-Pd alloy.3. The highest tendency of coincidence between allergen and intraoral metals were observed among Co-Cr-Ni alloys and Pd, Ni, and Cr elements.4. In case of palmoplantar pustulosis, allergen metals tended to be the same as intraoral metal elements.